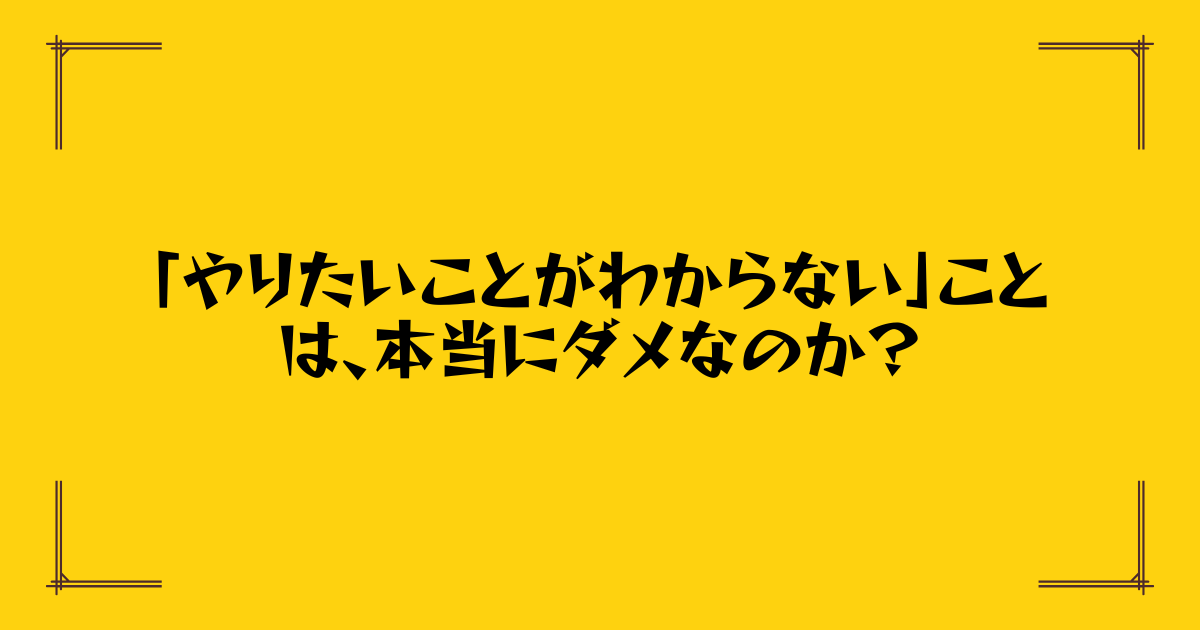就活が本格化しても“軸”が見えない焦り
「周りは志望業界が決まっているのに、自分は…」という劣等感
就活が本格化してくると、自己分析のワークシート、業界研究セミナー、インターン選考……あらゆる情報が「自分の志望を明確にしていること」を前提に動いていく。その中で、「何がやりたいかわからない」「どの業界にもピンとこない」という感覚を抱えている学生は、焦りと置いていかれるような孤独を感じる。
就活サイトでは「やりたいことを明確にして企業に伝えよう」と繰り返されるし、まわりの友人たちも「ベンチャー志望」「総合商社に絞った」「マスコミ一本」などと口にし始める。そんな中で、なんとなくエントリーしている自分がすごく不安になる。
でも実際には、最初から明確に「やりたいこと」が決まっている学生の方が少数派だ。声に出せているか、出せていないかの違いでしかない。むしろ、“やりたいことがわからない”と素直に思えている人ほど、自分をちゃんと見つめようとしている証拠でもある。
無理やり「やりたいこと」を作ろうとすると、迷子になる
「やりたいことがないのはダメだから、就活っぽく見える目標を設定しよう」としてしまうと、本来の自分とズレた方向へどんどん進んでしまう。たとえば、「人と話すのが嫌いじゃないから営業にしよう」「人気企業に入れたらかっこいいから総合職を目指そう」など、外からのイメージで自分のキャリアを作ってしまうと、面接で話すことも空虚になるし、選考に進んでもしっくりこない。
それに、就活では「こういう人になりたい」という目標よりも、「どういう価値観で働きたいか」「どんな環境なら頑張れるか」という軸の方が、企業とのマッチングにおいて重要になる。無理やり“志望理由”をつくるより、自分の中にある本音や違和感に向き合った方が、結果的に納得のいく選択につながる。
まずは「選び方を決める」ところから始めればいい
自分が企業をどう見るかの「モノサシ」を持つ
業界ではなく「環境」「スタンス」から掘り下げてみる
やりたい仕事が明確でないなら、選び方を変えればいい。たとえば、「会社の規模が大きい方が安心できる」「顔が見える距離で働ける方がいい」「上下関係が厳しすぎるのは無理」など、自分が働く上で大事にしたい“スタンス”を考えることで、業界を横断して見られるようになる。
この視点を持つだけで、たとえば広告業界だけでなく、ITベンチャーのマーケティング部門や、メーカーの広報など、「仕事内容は違っても、自分の価値観に近い企業」に出会えるようになる。業界名や知名度ではなく、「この会社の働き方、自分に合ってそう」という基準で探せるようになると、就活の選び方がガラリと変わる。
「興味はあるけど不安」な業界から動いてみる
よくある思考のパターンが、「この業界、ちょっと興味あるけど…向いてるかわからない」「興味あるけど、自分なんかが行けるのか不安」というものだ。しかしこの“不安”は、実はチャンスでもある。何の関心もない分野には不安すら湧かないのだから。
この段階では、完璧な自己理解は求めなくていい。「興味はあるけど、知らないことが多い」という状態であれば、まずは説明会やOB訪問など、軽い接点を増やしていくことで、自分の感覚を確かめることができる。情報に触れていく中で、「なんか居心地が悪い」「意外と面白そう」という“肌感覚”を蓄積していくことが、軸の手がかりになる。
「やりたいことがない」就活生が選考で見られているポイント
本音で語る姿勢が、“背伸び就活”より刺さる
作られた志望動機より「何を考えてるか」が伝わる方が強い
企業は、就活生が「やりたいことが明確であるか」だけを見ているわけではない。むしろ、「ちゃんと考えてきたか」「自分の言葉で語れているか」を見ている。だから、取り繕った志望動機よりも、「やりたいことはまだ明確ではないが、こういう観点で企業を見ている」「こんな価値観を大切にして仕事を選びたい」という語り方の方が、信頼される。
特に、“正解を探してきた感”のあるESや面接の受け答えは、採用担当にはすぐに見抜かれる。表面的にうまく話せていても、「その言葉に本人の感情が乗っていない」と感じた瞬間、評価は一気に落ちてしまう。一方で、「まだ模索中だけど、自分なりに仮説を持って動いている」という姿勢は、伸びしろとして評価されることもある。
“キャリア迷子”を隠す必要はないが、放置はNG
就活がうまく進んでいない学生の中には、自分が何をしたいのかわからないこと自体を「恥ずかしい」「隠したい」と感じてしまう人もいる。しかし、正直に向き合っていること自体が、社会人としてのスタートラインに立っている証拠だ。
ただし、「わからない」ままで動かないのは危険だ。何もせずに時間だけが過ぎると、エントリーや説明会の枠もなくなり、チャンスが減ってしまう。だからこそ、「やりたいことがわからない」から動けないのではなく、「わからないからこそ、動いてみる」というスタンスが重要になる。
「動き出したくても動けない」理由とその突破口
情報に飲まれて、逆にフリーズしてしまう就活
自己分析も業界研究も、深くやりすぎると迷子になる
「とりあえず動こう」と思って自己分析に手をつけたはずなのに、やればやるほど自分がよくわからなくなる。そうして「やりたいことも向いていることも、結局わからない」と言って立ち止まってしまう。就活ではよくあることだ。
問題は、真面目に取り組む人ほど「完璧な自己理解」「矛盾のない志望動機」を目指してしまうこと。だが、自己分析は“解答”を出す作業ではなく、自分の中にあるモヤモヤに輪郭を与えるプロセスだ。「自分はこうかもしれない」という仮説をもとに、企業を見て、話を聞いて、少しずつ確かめていく。それでいい。
何も動かないまま、自分の中だけで完結させようとするから、堂々巡りになる。就活は、考えながら動き、動きながら考える“往復運動”で進めるものだ。
「情報を集めれば安心できる」は幻想にすぎない
「まだ就活のことがよくわからないから、もう少し情報を集めてから…」という思考も、実は行動を止めてしまう原因になる。今の時代、ネットやSNSには就活情報が溢れていて、検索すればするほど「自分がやるべきことが足りない」ように思えてくる。
「インターンに出遅れてる」「OB訪問もやってない」「ガクチカが弱い」…焦りだけが蓄積して、結局何も動けなくなる。でも本当に大事なのは、情報を持っていることではなく、それを自分の判断材料に変える視点だ。自分の判断軸がなければ、どんな情報もただのノイズになる。
だからこそ、就活が進まないときほど、「もう十分情報はある。あとは自分で確かめよう」と腹をくくって、手を動かすフェーズに入ることが大事だ。
「仮置き」で動くという選択肢
100点満点の答えが出るまで待ってはいけない
「この企業に行きたい」は後から湧いてくるもの
就活初期にありがちなのが、「行きたい企業が見つかってから動く」という考え方。だが、実際には最初から“志望企業”が決まっている人は少ない。むしろ、「なんとなく面白そう」「説明会の雰囲気が良かった」という偶然の出会いが、その企業に惹かれるきっかけになる。
何が向いているか、どんな仕事が合うかなんて、やってみないとわからない部分も多い。だからこそ、最初から答えを求めるのではなく、「まずはこの業界を仮に見てみよう」「この仕事なら少し興味があるかも」という仮置きで十分だ。
その仮置きが外れてもいい。むしろ、ミスマッチの経験からわかることの方が多い。「これは違った」という発見が、次の判断の精度を高めてくれる。
「動いたら失敗しそう」という不安を乗り越えるために
仮置きで行動することに対して、「動いて失敗したら怖い」「やっぱり違ったらどうしよう」と躊躇する人も多い。でも実際、説明会に参加した、OB訪問をしてみた、エントリーしてみた――この程度で取り返しのつかない失敗なんて、起きない。
就活の本当の失敗とは、「何もしなかった半年後」に訪れるものだ。気づけば周囲は選考が進み、自分だけエントリーも出せていない。その状況に追い詰められて、焦って適当に応募して、さらに失敗するという悪循環に陥る。
だからこそ、仮でもいいから“試す”ことが重要だ。気になる説明会があれば予約してみる、選考の雰囲気を知るために1社エントリーしてみる。それだけで、就活は大きく進み出す。
“やりたいこと探し”から“試す就活”への切り替え
正しいスタートラインは「興味のある順」に動くこと
就活の入口は「熱量」より「好奇心」でいい
「この会社で絶対働きたい!」という強い動機がないと選考に進めないと思い込んでしまう学生も多いが、それは一部の人気業界だけの話だ。多くの企業は、「この業界についてちゃんと調べているか」「その中でも当社に関心があるか」を見ている。
だからこそ、最初は“熱量”よりも“好奇心”で動けばいい。「知らないけど、知ってみたい」「話を聞いてみたい」「中の人のリアルを知りたい」――それで十分エントリーする理由になる。
そして、その中で「ちょっと面白そう」「思ったより自分に向いてるかも」という手応えがあれば、そこから志望理由をつくればいい。就活は、出会ってから好きになるプロセスでもある。
“合いそうな企業”と“自分が無理しない企業”は違う
学生がよく言う「この会社、なんか合いそう」は、雰囲気や社員の話から感じる相性であることが多い。それ自体は悪くないが、「無理して合わせている自分」に気づかないこともある。
本当に相性がいい企業とは、「無理にテンションを上げなくても会話ができる」「変に取り繕わなくても受け入れてくれる」と感じられるところだ。説明会や面談での違和感は、意外と後々まで引きずる。だからこそ、「気を遣わずにいられたか」「自分らしく話せたか」という視点で企業を見ることも大切だ。
動きながら「自分なりの軸」を育てる方法
最初から“志望動機”を固めようとするのは逆効果
曖昧でも行動してみると、言葉が後からついてくる
就活において、志望動機が書けないから動けない、という学生は多い。だが実際には、動いた人ほど「志望動機が自然に言語化される」経験をしている。最初は“よくわからないけど面白そう”という曖昧な理由で説明会に出ても、社員の話や会社の雰囲気に触れる中で「なぜこの会社に惹かれたのか」が自分の中に生まれてくる。
つまり、動かないと何も始まらないし、動けば少しずつ形になっていく。“興味”という漠然とした感情を、自分なりに言語化していくプロセスこそが、就活の軸をつくるための実践なのだ。
「思いついたことを、仮に信じてみる」ことの効用
本音を言えば、多くの学生は「自分が何に向いているか」なんて本当はわかっていない。だが就活では、自分なりに“仮説”を立てて動かなければ、何も進まない。たとえば、「人と話すのは好きだから営業かな」「モノづくりは面白そうだからメーカー見てみよう」といった程度でいい。
それが合っているかどうかは、後でいくらでも修正できる。大事なのは、「この方向性を一旦信じて動いてみる」という勇気だ。そうやって一歩踏み出した先に、初めて“現実との対話”が生まれる。そしてその体験を通してこそ、自分の中に“納得できる軸”が芽生えてくる。
「自分の言葉で話せない」を乗り越えるために
就活がうまくいかない理由の多くは“他人の言葉”のまま話しているから
模範解答に見える言葉では面接官は納得しない
多くの学生が志望動機や自己PRでつまずくのは、「正解っぽい言葉」を並べてしまうからだ。「御社の理念に共感しました」「チームで協力して成果を上げました」といった、どこかで見たような言葉では、面接官の心には響かない。
企業は、“その人のリアル”を見たい。表面的にきれいな話よりも、「なぜそれを選んだのか」「どんなときに迷ったのか」「どう考えを変えたのか」といった、過程の中にある等身大のストーリーに価値を感じている。だからこそ、“自分の言葉”を見つけていくことが重要なのだ。
本当の強みは“自分が当たり前にやっていること”の中にある
自分の強みがわからない、という人は少なくない。だが実は、他人から見れば“すごい”ことでも、自分にとっては当たり前すぎて気づけないことが多い。たとえば、「頼まれたら断れない」「提出期限は絶対に守る」「人の話をちゃんと聞く」など、些細なことでも、それが一貫して行動に出ているなら立派な強みだ。
それを強みとして認識するためには、自分の過去を掘り起こして「それをどんな場面でやっていたか」「なぜそうしたのか」を思い出していくことが大切だ。エピソードが曖昧なままだと、自信を持って語ることはできない。逆に、些細な行動にも背景を与えて言語化できれば、それは立派な“武器”になる。
本音と建前のバランスをどう取るか
就活だからこそ“嘘のない言葉”が一番強い
背伸びしたエピソードはすぐに見抜かれる
「面接でウケがよさそうな話をしよう」と思って、実際よりも盛ったり、無理にかっこよく話したりすると、不自然さはすぐに伝わる。採用担当者は何百人、何千人と学生を見ている。話の内容が立派でも、語り口や表情に違和感があれば、すぐに「この人、本当のことを言ってないな」と察知されてしまう。
だからこそ、自分にとって“本当に大切だった経験”を、言葉にして話すことが何より大切だ。例え話のスケールが小さくても、自分の感情や考えが詰まった言葉は、人の心に届く。
正直に話すためには「就活で無理しない」ことが前提
就活では、「こう見られたい」という意識が強くなりすぎて、自分を作り込みすぎてしまうことがある。でも、それは非常に疲れるし、長くは続かない。どこかで限界がきて、「もう無理」と就活自体を止めてしまうケースもある。
だからこそ、最初から「自分らしくいられる場所を探そう」という前提で企業を見ていくことが大切だ。それができれば、話す内容にも嘘がなくなり、自然体の自分で就活を進められるようになる。
“納得感”のある内定に近づくための行動戦略
「就活の成功」は“自分の物差し”で決めるもの
周囲と比べて焦るほど、就活は迷走する
「友達はもう最終選考まで行ってる」「あの子はもう内定もらったらしい」――こうした情報に触れるたびに、心がざわついてくるのは当然だ。でも、他人の就活と自分の就活は全く違うゲームだ。スタート地点も違えば、得意なことも志望する企業も違う。何より“就活に何を求めているか”も人によってバラバラだ。
誰かより早く内定をもらうこと、倍率の高い企業に受かることが「勝ち」ではない。むしろ、自分が納得できる選択肢を手に入れたかどうかが、就活における“本当の成功”だ。焦りそうなときほど、自分の就活の軸に立ち返る必要がある。
納得感は“自己理解×企業理解×行動量”で決まる
どの企業に内定してもモヤモヤが残る人には、「自己理解が浅い」「企業を表面的にしか見ていない」「行動量が少ない」という共通点がある。逆に、最終的に納得して就活を終えられる人は、この3つを地道に積み重ねている。
自己理解は完璧でなくてもいい。行動しながら“なんとなくこっちの方向性が合ってるかも”とつかめればそれで十分。企業理解も、インターンに出ていなくても、説明会や面談、OB訪問を通じてリアルに感じることはできる。そして何より、「まずはやってみる」行動量が、すべての土台になる。
“やりたいことがない”人が企業選びで見るべき視点
仕事内容よりも「働く環境の相性」を重視する
やりたいことは入社後に見つかることもある
学生時代に「これが一生の仕事だ」と確信を持って就職する人は稀だ。実際、多くの人は入社後に「自分はこういうことが向いているんだ」と気づく。つまり、“やりたいことがない”という状態は、必ずしも不利ではない。むしろ、自分の強みに気づいてから進路を決めるほうが、現実的で幸せな選択になることが多い。
だからこそ、企業選びのときには「仕事内容がピンとこないから対象外にする」のではなく、「ここでなら、やりたいことが見つかりそうか」という視点で見ることが大事だ。
一緒に働きたいと思える人がいるかどうかを重視する
就職後、最もストレスの原因になりやすいのが“人間関係”だ。逆に言えば、「この人たちとなら一緒に働けそう」「自分のペースを尊重してくれそう」と感じられる会社は、長く続けやすい。
説明会や選考、面談などの場で出会う社員の雰囲気を観察することは、実は企業選びにおいて非常に重要だ。企業理念よりも、給与よりも、「この会社の人たち、なんかいいな」と思える直感の方が、結果的に納得できる選択につながることが多い。
「自分に自信がないまま」でも内定を得るために必要な考え方
自信よりも“自分を出せるか”がカギになる
自信満々じゃなくても、素直な姿勢が評価されることは多い
「自信がなくてうまく話せない」「すごい経験もない」――そんな人でも、採用されることはある。面接官が見ているのは、「この人と一緒に働きたいか」「成長しそうか」という点であって、今の完成度ではない。
むしろ、自分の弱さを自覚していて、それを乗り越えようと努力している人の方が、成長の余地があると判断されることが多い。大事なのは、“取り繕わない姿勢”と、“自分なりに頑張ってきたことを伝える勇気”だ。
「特別じゃない自分」を言語化できれば十分戦える
多くの学生が就活で悩むのは、「語れるエピソードがない」「すごい成果を出してない」という点だ。だが、就活において特別なエピソードは必須ではない。
むしろ、「自分はこういうタイプで、こういう場面で力を発揮しやすい」という自己理解があれば、それを伝えるだけでいい。たとえば、「縁の下の力持ちタイプ」「目立たないけど粘り強く続けられる」など、等身大の自分を言葉にできる人は、企業にとってもリアルで採用しやすい存在だ。
まとめ:正解探しをやめたとき、内定は近づく
“やりたいことがわからない”という状態は、決して恥ずべきことでも、就活の敗因でもない。それは、今の自分が「まだ社会を知らない」だけのこと。
本当に大事なのは、わからないなりに仮置きして動くこと、失敗してもそこから学ぶこと、そしてその経験から“自分なりの判断軸”を育てていくことだ。
誰かの理想像をなぞるのではなく、自分にとって居心地のよい環境、素直に話せる相手、自分のままで働ける場所を探していけばいい。
やりたいことは、働く中で見つかっていくものだし、その第一歩を踏み出せた人から、内定という結果に近づいていく。
「わからない」を言い訳にせず、まずは試してみる。その小さな行動が、あなたの就活を動かし、未来を変える。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます