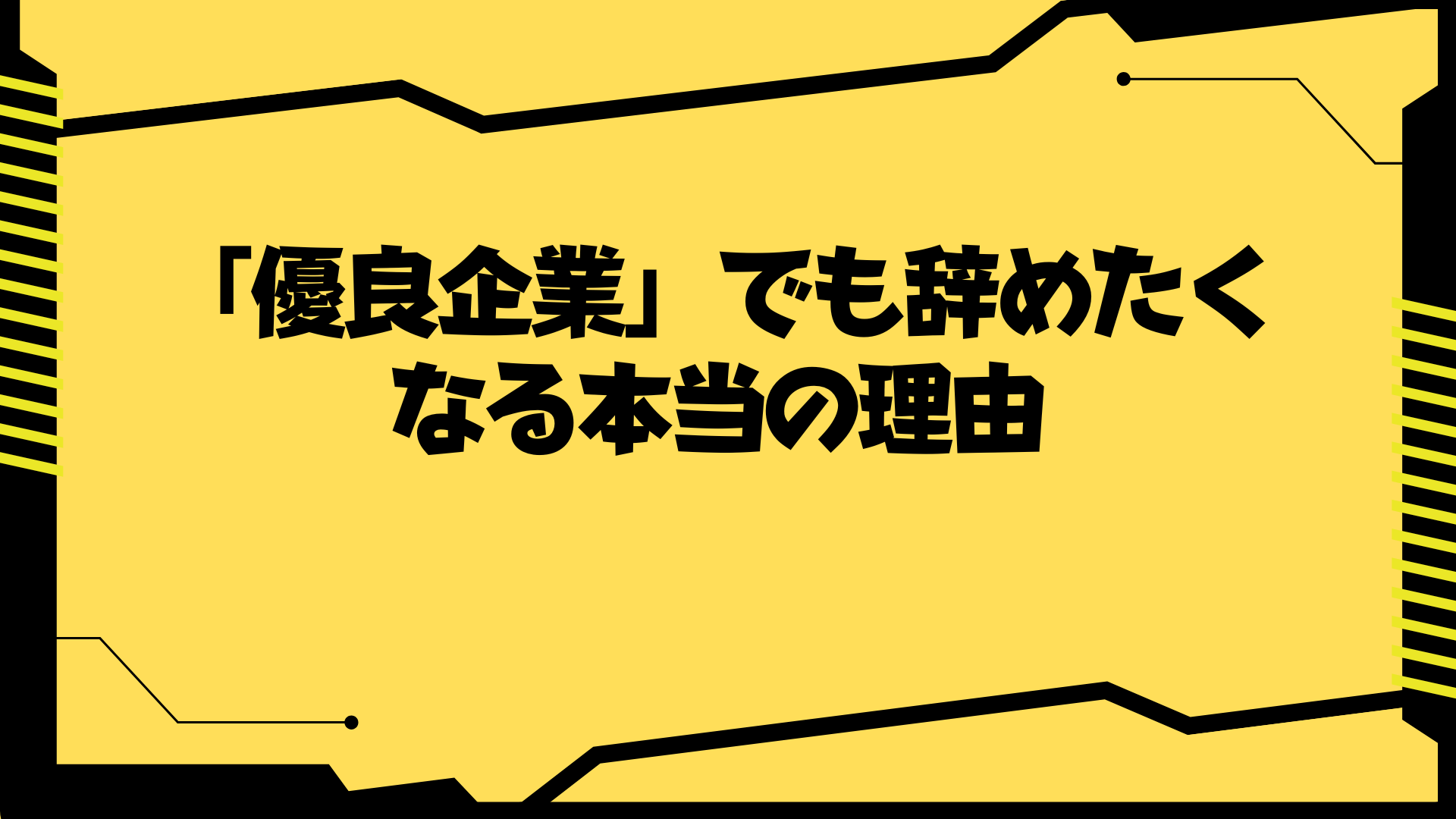就活で語られない“入社後の違和感”
見えないギャップがモチベーションを削る
就活中、多くの学生は「ホワイト企業」「福利厚生が充実している」「残業が少ない」といった条件に目を向ける。実際、それらは働きやすさの基準として重要であり、企業側も積極的にアピールする。しかし、条件が整っている=働き続けたいと思える環境とは限らないという現実がある。
「上場企業で安定している」「研修制度がしっかりしている」など、いわゆる“優良企業”に入社したにもかかわらず、3年以内に辞めてしまう人は少なくない。理由の多くは、「想像していた仕事と違った」「人間関係がしんどかった」「成長実感が得られなかった」といった定量化できない不一致にある。
業務内容よりも“文化”に馴染めない
働きやすさには、「職場の文化」や「価値観の相性」が大きく関わっている。たとえば、
「風通しが良い」と聞いていたが、実際は上司の顔色をうかがう文化
「若手が活躍」とあったが、裁量はなく、指示通りの作業ばかり
「自由な社風」だが、ミスに対しては厳しく責任追及される
こうした企業文化とのズレは、入社前の情報収集だけではなかなか気づけない。そして、一度“合わない”と感じてしまうと、どんなに待遇がよくても心理的な負担は増していく。
就活の情報は「良い部分」に偏っている
選考過程ではマイナス面は見えにくい
説明会や面接で語られる内容は、基本的にポジティブな情報に限られる。「実は離職率が高い」「実際は残業が多い」「年功序列が強くて昇進が遅い」といったネガティブな情報は企業側も口にしない。
だからこそ、就活生は「企業が発信する情報」をうのみにせず、“現場の実態”を把握する努力が必要になる。その努力を怠ると、入社してから「こんなはずじゃなかった」と感じる可能性が高まる。
「成長できるかどうか」は自分の基準で測る
就活では、「この会社で自分は成長できるのか?」という視点も重要だ。しかし、“成長”の定義は人によって異なる。たとえば、
厳しい環境で鍛えられることが成長だと考える人もいれば、
じっくりと経験を積み重ねることが成長だと考える人もいる。
つまり、企業側が語る「成長できる環境」が、必ずしも自分に合っているとは限らない。にもかかわらず、「成長できると言っていたから入ったのに…」と後悔するケースは少なくない。
「辞める人」の本音を探る
定量データより定性的な理由に注目
転職サイトなどで企業の離職率や平均勤続年数は確認できるが、辞めた理由の内実までは見えてこない。実際に辞めた人の声には、次のような定性的な理由が多い。
「上司との相性が悪くてメンタルを崩した」
「単純作業ばかりで、やりがいを感じられなかった」
「チームワークよりも個人主義が強く、孤立感があった」
こうした声は、数値や制度には表れない“職場のリアル”である。
OB・OG訪問やSNSから実態を知る
辞めた理由を直接聞くのは難しいが、OB・OG訪問では「辞めた先輩に話を聞く」ことも選択肢の一つになる。退職済みの先輩であれば、より本音を語ってくれる可能性が高い。また、X(旧Twitter)やnote、WantedlyなどのSNS・ブログにも、企業の内情や職場文化について発信している社会人が多い。
「辞めた理由」を集める行為は、ネガティブに見えるかもしれないが、“自分にとって何が合わないのか”を逆に理解する手がかりになる。
“最初の会社選び”の重要性は想像以上に大きい
第二新卒枠での再チャレンジも容易ではない
「合わなかったら辞めればいい」と軽く考える人もいるが、実際に辞めた後のキャリア形成は簡単ではない。特に、第二新卒として再就職する場合には、
キャリアの一貫性が求められる
前職で何を得たかを問われる
一部業界では“早期離職”がマイナス評価になる
という壁が待っている。つまり、最初の選択がその後の選択肢を狭めるリスクもある。
「辞めたいと思わない会社」の探し方を学ぶ
離職率が低い会社が正解なのではなく、「自分にとって辞めたいと思わない会社」を見つけることが大事である。そのためには、
働き方より働く人に注目する
社風や価値観の一致を見る
キャリアの展望と重ねて考える
といった視点が必要になる。ただ条件を比較するのではなく、「この会社で5年後どうなっていたいか」を想像できるかが重要だ。
「やりがい」の正体を勘違いすると危ない
仕事に求める“やりがい”は人それぞれ
理想と現実のギャップが“辞めたい”に変わる
就活の自己PRや志望動機では「やりがいを感じられる仕事がしたい」と語る学生は多い。しかし、この“やりがい”という言葉ほど曖昧で、誤解されやすい言葉もない。たとえば、「人の役に立ちたい」と思って営業職に就いた人が、実際には数字ばかり追い、断られ続ける日々に嫌気が差すこともある。
「社会貢献がしたい」と入社した医療・福祉系企業で、現場の過酷な人手不足や精神的負担に直面し、「理想と違った」と辞めていく人もいる。“やりがい”を抽象的に捉えてしまうと、現場での違和感に耐えきれなくなる。
「誰かの役に立つ」ことは結果論である
「誰かに感謝されたい」「価値を提供したい」といったやりがい志向の人ほど、最初のギャップに苦しみやすい。現実の仕事は、すぐに感謝されたり、社会的価値が見えるわけではない。
特に新卒1年目はルーティン業務や事務処理、雑務に近い業務が多く、華やかさやインパクトを感じにくい。にもかかわらず、「やりがいを感じられない」と感じてしまい、早期退職を選んでしまう人もいる。やりがいは「積み重ねた後に見えるもの」であり、入社直後から満たされるものではない。
入社前に「仕事のリアル」をどう知るか
会社説明会では仕事の“断面”しか見えない
説明会やHPで紹介される社員インタビューには「活躍している先輩社員」の話が多い。しかし、それらは例外的な成功例であり、全体の姿ではない。実際には「8割は補助業務や事務作業が中心」「1年目は電話当番や庶務がメイン」という現実も多い。
つまり、“主役”ではなく“助演”としての役割を求められる期間が長いというのが新人社員のリアルだ。そこに強いギャップを感じ、「想像していたキャリアじゃない」と離職する人が出るのは自然な流れといえる。
「仕事の1日」を具体的に聞くべき
現場でのミスマッチを避けるためには、「この職種の人は1日の中で何をどのくらいの時間やっているのか」を具体的に把握することが鍵になる。OB・OG訪問で聞くべきは、「やりがい」や「雰囲気」ではなく、
朝出社してからどんな業務が続くのか
会議、メール対応、実作業などの配分
ルーティンか創造的か
残業の発生要因と頻度
といった行動レベルの具体性を持った情報である。これを押さえることで、自分がその業務に適応できるかをよりリアルに想像できる。
「好きなことを仕事に」はリスクが大きい
好きだからこそつらくなることもある
就活では、「好きなことを仕事にしたい」と考える人も少なくない。しかし、“好き”が“仕事”になったとき、プレッシャーやルール、ノルマがつきまとうようになる。好きで始めたことが、「成果を出さないと給料が出ない」「納期に追われる」「他人の指示で進める」状態になると、途端につらさを感じるようになる。
たとえば、「文章を書くのが好き」で編集職に就いた人が、実際は企画会議や校正作業、広告主との調整ばかりで、「思っていた仕事と違う」と感じてしまうように、“好き”と“職業としての適性”は一致しないケースも多い。
「やれること」を伸ばす方が長く続く
やりがいを重視するあまり、“好き”や“興味”ばかりにこだわると、実際に自分が得意なこと・成果が出ることを見逃す可能性がある。結果として、評価も得られず、自己肯定感を失って辞めたくなるリスクが高まる。
重要なのは、「自分が継続的に成果を出せそうな領域はどこか?」を冷静に見極めることだ。“やりたいこと”だけでなく、“やれそうなこと”にも目を向けた企業選びをすることが、長く働く上では重要な視点になる。
情報収集の不足が“辞める理由”になる
「調べ方がわからない」まま選ぶ怖さ
就活生の多くは、インターンや説明会、企業パンフレットの情報をベースに企業選びを進める。しかし、それらの情報はすべて企業発信のものであり、“都合の良い情報”に偏っている。OB・OG訪問をした経験がないまま内定をもらい、「雰囲気が合わなかった」「仕事がきつかった」と辞める人も多い。
情報収集の質=キャリア初期の満足度を決めると言っても過言ではない。ネットに書いてあることを鵜呑みにせず、自分の手で1次情報を取ることが、ミスマッチを防ぐ一番の武器になる。
選考対策ばかりに目が向く就活の落とし穴
就活生の多くは「選考に通る」ことをゴールにしてしまう。だからこそ、面接対策やESのテクニックに集中し、「この会社が自分に合っているか?」という視点が薄くなりがちだ。その結果、“内定をもらった企業に入社したが、すぐ辞めた”というパターンに陥る。
内定はスタートラインであってゴールではない。選考を突破することより、自分に合った職場に出会うことの方が、何倍も大事だという認識が必要になる。
離職理由の本音No.1は「人間関係」
働く環境の快適さを決める“人”
「仕事内容より人間関係」が辞める原因
就活中、企業を選ぶ際の軸として「仕事内容」や「企業理念」を重視する学生は多いが、実際に退職理由として最も多いのは「人間関係のストレス」である。どれほど待遇が良くても、やりがいがあっても、職場の上司や同僚との関係が悪ければ、仕事へのモチベーションは著しく下がる。
特に新卒で入社した社員は、上司の一言やチームの雰囲気に大きく影響を受けやすい。まだ社会人経験が浅いため、自分を主張したり、適切な距離をとるスキルが十分でなく、精神的に追い詰められやすい。
職場の“空気感”は入社しないと見えない
採用ページや説明会で語られる「風通しの良い職場」「若手も活躍できる文化」といった言葉は、実態とは異なる場合がある。言葉ではポジティブに見えても、実際は体育会的な上下関係や“忖度文化”が根強く残っているケースもある。
さらに、異動や配属ガチャにより、社内でもまったく違う環境に置かれる可能性がある。例えばある部署では穏やかな先輩が多く働きやすいが、別部署ではパワハラまがいのマネジメントが横行している――ということも珍しくない。
上司や先輩との相性が“すべて”になる初年度
上司との関係性でキャリアが左右される
新卒1〜2年目は、業務知識もスキルも未熟であるため、上司や先輩社員からどのような指導を受けるかがキャリア形成に直結する。そのため、直属の上司との相性が悪いだけで「辞めたい」と思うようになる人も多い。
たとえば「報連相をしたのに無視される」「怒鳴られるが何が悪いのかは説明してくれない」「常に“自分で考えろ”と言われて放置される」など、成長の妨げとなる指導や“ブラックな放任”も見られる。
こうした中で「自分には社会人は無理なのかも」と自己否定に陥り、早期離職に至るケースが多発している。
優秀な上司=良い上司とは限らない
注意すべきは、“優秀な人”が必ずしも“部下育成に長けた人”ではないという点だ。プレイヤーとして優秀でも、他人に教えるのが苦手だったり、忙しすぎて時間を割けなかったりするケースは多い。
さらに、「自分はできたんだからお前もできるはずだ」という無言のプレッシャーをかけるタイプの上司に当たると、精神的負荷が大きくなる。直属の人間の影響が絶対的な新卒時代は、組織全体の雰囲気以上に“上司運”がすべてを左右する。
チーム構造と評価制度の“隠れた罠”
“競争させる文化”がストレスになる
一見、活気があるように見えるベンチャー企業や営業職では、個人の成果が数字で厳密に評価される仕組みが多い。このような組織では、表面上はチームと謳いつつ、実際には「個人のパフォーマンス次第で立場が決まる」という、ピリピリとした競争環境が存在している。
競争の中で自分だけ成果が出ないと、「チームの足を引っ張っている」「期待に応えられない」と自己否定感が強まりやすい。他人と比較される構造そのものが、精神的にきついと感じる人にとっては大きなストレス源になる。
評価される人・されない人の“見えない分かれ道”
どれほど頑張っても、評価されるかどうかは「見える業務」に携われるかどうかで大きく異なることがある。たとえば裏方業務や調整作業などは重要であっても目立たない。そんな中で、上司からのフィードバックが少ないと、「自分は認められていない」と感じてしまう。
また、「仕事はできるが、媚びない人」が評価されにくい文化、「仲良しグループ」のような雰囲気を重視する職場など、組織独特の“暗黙ルール”が存在する企業では、適応できない人が離脱していく傾向がある。
面接や説明会では見抜けない“リアルな人間関係”
面接で話す人は「人間関係が良い側」の人
面接官や人事担当者は、基本的に会社の「顔」として機能しているため、当然ながら人当たりが良く、社内でも信頼されている“優秀で穏やかな人”が多い。つまり、説明会や面接で接する社員が優しかったからといって、それが全社員の平均値ではない。
一方で、実際に配属される現場のマネージャーやリーダーは、まったく違う人格であることも多い。本当に見るべきは「自分がどんな上司に付くか」なのに、その情報にはアクセスできない就活構造自体が、ミスマッチの温床になっている。
OB訪問は“現場の空気感”を確かめる場にすべき
本質的なミスマッチを防ぐためには、「一緒に働く上司や同僚のキャラや価値観」が自分と合いそうかを見極める必要がある。そのために有効なのが、現場社員とのOB訪問だ。ただし、表面的な質問だけでは意味がない。
たとえば以下のような点を深掘ると、組織の空気感が見えてくる。
上司は部下にどんな接し方をしているか?
成果を出せない人にどう対応しているか?
雰囲気が重たいと感じる瞬間はあるか?
離職する人の理由として多いのは何か?
「人間関係が合わなかったら辞めたくなる」ことを前提に情報収集する視点を持つことで、就活の判断軸は大きく変わるはずだ。
表面上の“働きやすさ”が現実とズレる理由
「有給消化率100%」の裏にある“空気”
「自由に休める」は建前であることも多い
就活中に耳にする「有給取得率90%以上」や「ワークライフバランスを重視」などの謳い文句。これらの数字や表現は一見、安心材料に思える。しかし、実際に入社した後に多くの若手社員が感じるのは、「数字と現実は別物」というギャップである。
たとえば、「取得率100%」というのは“全員が1年に1回強制的に取らされる夏季休暇や年末年始に計上された結果”であったり、あるいは上司に“言われたタイミングでまとめて取る”仕組みだったりする場合がある。つまり、自分が必要なときに自由に休めるわけではないのだ。
有給取得に“申請の心理的ハードル”がある現場
制度としては整っていても、実際に休むとなると「周囲に申し訳ない」「忙しいのに抜けにくい」という空気が存在する職場も多い。特に新卒1〜2年目の若手にとっては、有給取得が「わがまま」や「逃げ」と受け取られないか不安で、結果として休みを取らない=“取れない”状態に陥る。
そのため、「うちはちゃんと有給使えるから安心してね」という人事の言葉を鵜呑みにするのではなく、現場の実態(誰が、いつ、どんな理由で取っているか)を知る視点が欠かせない。
テレワークやフレックス制の“見えない拘束”
自由に見える制度にも“運用次第”の落とし穴
近年多くの企業が導入しているテレワークやフレックス制度。これらは本来、社員の柔軟な働き方を支える仕組みだが、制度と現場の運用が乖離していると、むしろ逆に“常に働いている”ような状況を生む。
たとえば「フレックスだから朝はゆっくり出社でいいよ」と言われても、実際には「メールは朝9時までに返すのが暗黙のルール」「夜もSlackが常に動いている」という状況では、名ばかりの柔軟性に過ぎない。
テレワークによる“成果主義プレッシャー”の増加
オフィスにいない環境では、「どれだけ頑張っているか」が可視化されにくくなるため、成果やスピードで評価されやすい構造になる。その結果、人によっては「常に成果を出さなきゃ」と思いつめ、働きすぎてしまうケースもある。
実際、「テレワークで通勤はなくなったけど、その分夜遅くまで仕事をしている」「誰かがオンラインにいると、自分もログインしていないと不安」という声は多い。就活生が想像する“自由な働き方”と、社会人が感じている“プレッシャー付きの自由”は、大きく乖離しているのだ。
“働き方改革”の副作用を受ける若手社員
時間外労働の減少=育成機会の減少
残業削減が進むこと自体は歓迎すべきだが、その影響として、若手への教育や丁寧な引き継ぎの時間が減少している実態がある。先輩社員も「定時で帰る」ことを優先するため、結果として「自分で調べて」「自走して」が強調される現場が増加している。
つまり、働きやすさが表面上整ったことで、“放置されやすい新人”が増えているという副作用が起きている。教育制度があっても、実際に現場で丁寧に教わる時間が確保されているかは別問題である。
“成長機会がない”と感じて離職する若手
そのような環境では、「このままでは何も成長できない」「任される仕事が単調すぎる」という不満が溜まりやすくなる。かといって異動や改善の要望を出せるほどの関係性や経験もないため、「環境のせいにするのは甘えかもしれないけど…」という迷いの中で離職を選ぶ若手も多い。
就活生が抱く「長く働けそうな会社=働きやすい会社」というイメージは、必ずしも正解ではない。「働きやすいけど、物足りない」「制度はあるけど使えない」というリアルなギャップを知っておくことが大切だ。
「自分らしく働ける環境」は探せば見つかるのか?
どの企業も“合う人”と“合わない人”がいる
企業の制度や文化に完璧なものはない。どれだけ「働きやすい」「自由な社風」と言われる企業であっても、そこにフィットする人・しない人がいる。そのため、情報を収集する際は「どんな制度があるか」だけでなく、「自分がその制度を使えるタイプか」を判断することが不可欠だ。
たとえば「自分で判断して動ける人」には向いている自由な会社も、「指示がないと不安になる人」にはつらいだけの環境になり得る。制度や文化の説明を“他人事”で聞くのではなく、“自分だったらどう感じるか”という目線で考える姿勢が必要だ。
まとめ:就活生が知っておくべき「働くリアル」
学生時代の情報だけで見えている“働きやすさ”や“ホワイト企業”のイメージは、実際に働いてみると大きく異なることがある。制度や待遇の良さは、それを使える空気感や人間関係、マネジメントの質が伴ってこそ意味がある。
本記事で紹介したように、人間関係、評価構造、制度運用などの“見えない部分”が離職に直結しているという事実を踏まえれば、就活生は「企業を見る目」をアップデートする必要がある。
「いい会社に入る」ではなく、「自分が無理なく、成長を実感しながら続けられる会社に入る」という視点が、これからの就職活動におけるリアルな成功指標になる。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます