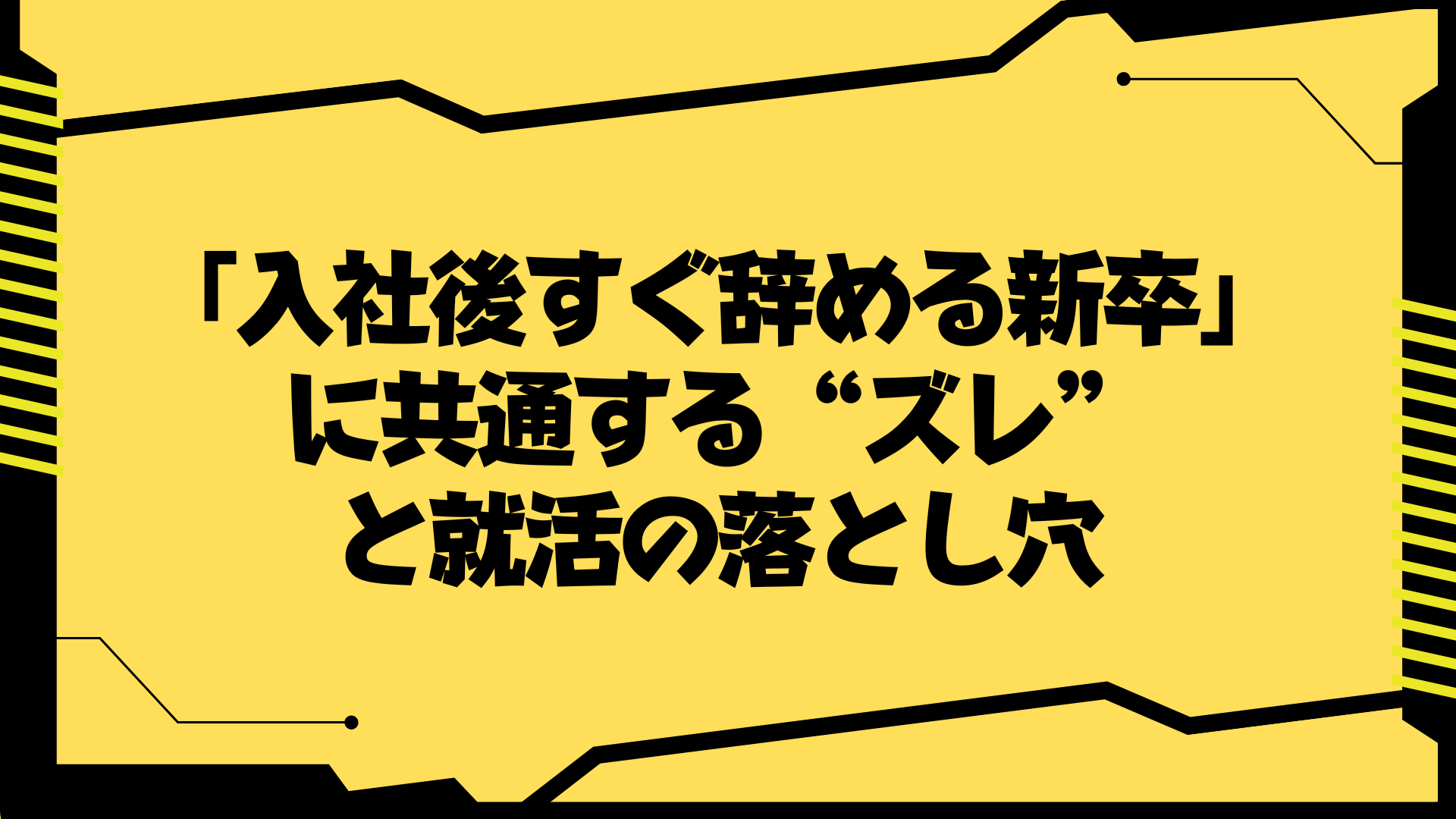なぜ「3年以内に辞める新卒」が後を絶たないのか
離職率30%という“数字の裏”にあるリアル
新卒入社者の約3人に1人が、3年以内に離職しているという厚生労働省のデータは、もはや毎年のように取り上げられる定番の話題となっている。この数値に「若者は根性がない」といった批判を向ける声もあれば、「企業側のミスマッチが原因」とする論調もある。しかし、この離職率の高さには、単純な“甘え”や“合わなかった”という理由だけでは片づけられない構造的な問題が横たわっている。
就活生の多くは、「社会人になる」という実感が乏しいまま、就職活動をスタートする。企業説明会やナビサイトの情報をもとに企業選びを行い、「なんとなく雰囲気がよかった」「説明が丁寧だった」「有名だから安心そう」といった曖昧な理由でエントリーする企業を絞っていく。このプロセスには一見問題がないように見えるが、実は“自分と企業の価値観のズレ”が生まれる大きな要因が隠されている。
就活生が見る情報は、企業が発信したい内容に限定される。「風通しがよい」「若手が活躍」「メリハリのある働き方」など、どの企業も似たようなワードを並べる中で、本質的な職場のリアルは見えにくい。こうして「理想の社会人生活像」が膨らむ一方で、入社後に待ち受けている現実とのギャップが、若手の離職を加速させている。
よくある“ギャップ離職”のパターン
「思っていた仕事と違った」系のズレ
最も多いのは、「想像していた仕事内容と違っていた」という声だ。営業職であれば「もっと顧客と向き合う仕事だと思っていたのに、数字やノルマばかりで辛い」、事務職なら「ルーティン作業ばかりで成長を感じられない」など、事前のイメージと実務内容との乖離が離職理由になることがある。
だが、こうしたズレの多くは、企業側が嘘をついていたわけではない。むしろ「受け取る側の想像力と問いの浅さ」が原因であることも多い。説明会で話された内容やインターンで体験した業務の一部を、「この会社はこんな働き方なんだ」と全体像に拡張してしまう傾向が、現実との落差を生んでいる。
「雰囲気がよさそう」が裏目に出るケース
企業選びで「人のよさ」や「雰囲気のよさ」を重視する学生も多い。実際、説明会での社員の対応や、面接官の印象が好感触だと、それだけで安心感を抱いてしまう。
しかし、就職は“人生の契約”ともいえる選択である。一時的な印象に左右され、深く企業文化や価値観を検証しないまま選ぶと、「いい人が多いけれど仕事の内容は合わない」「雰囲気はよかったが制度面で厳しかった」といったギャップが生じる。人柄や雰囲気は大事だが、それが自分のやりたいことや働き方と一致しているかを見極める視点が必要だ。
「社会人としてのリアル」を想像できていない問題
「成長できる環境」は“しんどい”ことが前提
就活生が好んで使うフレーズのひとつに「成長できる環境で働きたい」がある。だが、この言葉の裏には「教えてくれる人がいて、スキルが身につき、やりがいもある」といった“受け身の成長”が前提になっていることが多い。
現実の「成長できる環境」は、責任やプレッシャー、厳しいフィードバックを受ける日々の中で自力で考え、もがきながら前に進む過程にある。その過程は楽ではないし、周囲が常に支えてくれるわけでもない。
「想像していた成長」と「現実の成長」が異なることで、入社後に「こんなに苦しいとは思わなかった」となるケースが多発する。これは本人が悪いわけではない。ただ、就活時点で“美化された成長像”だけを信じていると、現場のリアルに耐えられなくなってしまうのだ。
「とにかく大手を目指す」ことの落とし穴
企業規模=安心という幻想
「大手に行けば将来は安泰」と考えて、知名度や規模だけで企業を選ぶ学生も少なくない。親や周囲の期待、知名度への憧れなども影響して、大手企業への志望が集中する傾向は年々強まっている。
しかし、企業規模が大きいことは、個人にとって必ずしも「働きやすい」「成長できる」「自分らしくいられる」こととは一致しない。大手ゆえの分業制や年功序列、意思決定の遅さにストレスを感じることもある。むしろベンチャーや中堅企業の方が、若手の裁量や柔軟な働き方を実現できる場合も多い。
「大手だから安心」という発想は、“知っている企業=いい企業”というバイアスに過ぎない。本当に見るべきは、「自分の価値観や働き方とその企業が一致しているかどうか」だ。
「就職活動=正解探し」という誤解
内定=ゴールではない
就活を通して、「早く内定を取ること」「どこかに決まること」が目的になってしまう学生は多い。とくに周囲がどんどん内定を獲得していく時期になると、焦りから「どこでもいいから決まりたい」と考えてしまいがちだ。
しかし、就職活動の本質は「自分と相手の価値観のすり合わせ」である。マッチしていない企業に“とりあえず”で入社すれば、早期離職のリスクが高まるのは当然だ。むしろ「内定が出たけれど辞退する」という選択をした学生の方が、自分の働き方と真剣に向き合っているとも言える。
ゴールは「就職すること」ではなく、「自分が納得して働ける場所に進むこと」。その意識を持っていないと、“どこかに決まればいい”という短期的な判断が、将来的な後悔を生む結果となってしまう。
入社前に見抜ける“ミスマッチのサイン”とは何か
企業説明会や面接で“都合のいい情報”しか出てこない会社
「うちはアットホーム」が危ない理由
就職活動中、企業説明会で「アットホームな職場です」「風通しの良い組織です」といった言葉を聞いたことがある学生は多いだろう。だが、こうした言葉には要注意だ。なぜなら、これらは非常に抽象的であり、誰にでも好意的に受け止められる一方で、実態がまるで見えないからである。
例えば、「アットホーム」と言いながら実際は業務の線引きが曖昧で、上司からの指示も雑然と飛んでくる、“馴れ合い”の職場であるケースもある。また、「風通しが良い」と言われて入った会社が、ただ単に上司が何でも話してくるだけで、自分の意見が反映されるような“本当の意味での双方向性”が存在しない、という場合もある。
こうした曖昧な言葉を並べる企業は、実態を語れない、もしくは語りたくない何かがある可能性がある。学生にとって“耳障りのいいワード”を並べて、企業側が優位に立ちたいという心理が背景にある。情報の出し方が一方向的すぎる場合は、見極めの目を持つ必要がある。
「若手が活躍」と「若手に押し付け」問題
本当に裁量があるのか、それとも丸投げなのか
「若手にチャンスがある」「入社1年目から活躍できます」——これも多くの就活生が惹かれるポイントだ。しかし、ここには大きな落とし穴がある。企業によっては「人手不足で任せざるを得ない」ことを“裁量”として包装しているケースも存在する。
実際に起こりうるのは、現場に経験豊富な社員が少なく、マネジメントも教育体制も不十分なまま、新卒がフロントに立たされてしまうという事態だ。営業数字やクライアント対応を“とにかくやってみろ”というスタンスで放り出され、「学びのある環境」どころか「孤立と疲弊の環境」に変わっていく。
このように、“若手が活躍”は非常に魅力的に聞こえるが、その実態が「教育不足の現場での丸投げ」なのか、「本当に段階的な成長支援と機会提供がある体制」なのかを見極めるには、面接やOB訪問で具体的な制度や経験談を聞く必要がある。
入社前に「働く価値観」のすり合わせを怠ると起こること
「仕事に求めるもの」がズレていると長続きしない
新卒が短期離職してしまう根本的な理由のひとつに、「仕事に求める価値」が企業と本人で噛み合っていないことが挙げられる。たとえば、「安定して働きたい」と思っている人が、変化とスピード感を重視するスタートアップに入ってしまえば、毎日の急な変更や曖昧なルールに疲弊してしまうだろう。
逆に、「成長したい」「チャレンジしたい」と思っている学生が、年功序列で昇進の機会も限定された安定志向の企業に入社すれば、数年後には“何もできていない焦り”に苛まれる。
この「求めるもののズレ」は、説明会や求人票ではなかなか見抜きにくい。重要なのは、「あなたが仕事に何を求めているか」「企業は社員にどんな働き方をしてほしいのか」という価値観を、自分から突っ込んで聞くことである。企業が大切にしている“行動指針”や“評価基準”を把握することで、自分との価値観の相性をある程度見定めることができる。
就活時点での「違和感」を放置するな
内定承諾前に冷静になる“時間”を作る
多くの学生が、内定が出るとすぐに承諾してしまう傾向にある。特に第一志望の企業から内定をもらった時には、舞い上がってしまい冷静さを欠きがちだ。しかし、そのタイミングこそが冷静に「本当にここでいいのか」と考えるラストチャンスである。
もしも説明会や面接中に、「なんとなく違和感があった」「社員の言葉に一貫性がなかった」「職場の雰囲気に息苦しさを感じた」といった引っかかりがあったのなら、それを無視してはいけない。違和感は直感ではなく、情報の非対称性や本音と建前のギャップに無意識が反応している可能性がある。
また、企業によっては、内定後のフォローイベントで“囲い込み”を強く行うこともある。たとえば、「他社の選考は断ってください」と遠回しに伝えるケースや、「○日までに承諾してください」と急かしてくるパターンだ。そのようなときほど、「この会社は本当に自分に合っているのか」を見直す冷静な時間が必要だ。
入社前に「リアル」をつかむためにすべき行動
OB訪問や口コミに頼りすぎず、自分の目で見る工夫
インターネット上の口コミサイトや、OB訪問の話などを頼りに企業研究を進める学生は多い。しかし、ここにもリスクがある。口コミはあくまで個人の主観であり、過去の一時点の体験にすぎない。OB訪問も、企業が選んだ“話してほしい人”が登場することが多く、客観性に欠ける場合がある。
そこで重要なのが、「自分の視点で現場を確認すること」だ。たとえば、職場見学ができる企業なら、社員の様子や社内の雰囲気をよく観察してみる。誰が挨拶していて、誰が黙々とPCに向かっているのか。雑談の空気があるのか、全体に張り詰めたムードなのか。そうした“空気感”の情報は、表面の言葉よりも多くの真実を語ってくれる。
また、質問する際は「何年目でどんな仕事を任されるのか」「どう評価されるのか」「失敗したときの対応はどうか」など、具体的でリアルな場面に関する問いを用意することで、企業の本質に近づける可能性が高まる。
「辞めたい」と思った瞬間に見える“現実”
入社直後のギャップがもたらす精神的ショック
理想と現実の落差は誰にでも起こる
新卒として入社した直後、多くの人が一度は感じるのが「こんなはずじゃなかった」という感情だ。これは決して“甘え”ではない。どれだけ丁寧に企業研究をしても、実際の現場のリアルや人間関係、日々の業務の積み重ねは、予想と違って当然の側面を持っている。
特に、就活時に「社員が仲良さそう」「自分のやりたいことができそう」と期待して入社した企業で、最初の配属が希望外だったり、研修で“管理的な作業ばかり”を求められたりすると、落差は大きくなる。このギャップが一気に感情を揺さぶり、「ここで働き続ける意味がわからない」となってしまう。
「辞めたい」と思う人が取りがちな典型行動
① 無断欠勤や体調不良を理由に距離を置く
ストレスや疲労が限界に近づくと、人は「その場から逃げたい」という本能に支配される。実際に多くの“早期退職者”が経験しているのが、「朝起きられない」「頭痛や腹痛が続く」といった身体症状である。これはメンタル面の疲弊が体に現れているサインであり、放置すれば本格的な体調不良につながる。
無断欠勤をしてしまったり、連絡を入れるのが億劫でズルズル出社できない状態が続くと、職場との距離は一気に広がる。上司からの連絡がプレッシャーに感じられ、ますます辞めたくなる。この段階では、「辞めたい」よりも「もう戻れないかも」という感情が強まる。
② SNSやネットで同じ境遇の人を探す
孤独感から抜け出そうと、X(旧Twitter)やInstagramで「#新卒辞めたい」などのタグを検索し、同じ気持ちの人を見つけて安心感を得ようとするケースも多い。実際、そこには同じように苦しんでいる人がいて、「辞めた」「逃げて正解だった」という言葉も並んでいる。
だが、ここで問題なのは、“共感”が“思考停止”を引き起こす点である。似た境遇の人の体験を読むことで一時的に安心できても、自分の職場、自分の状況とは違う可能性がある。「あの人が辞めたなら、自分も辞めよう」となってしまえば、判断基準が外部依存になるリスクがある。
誰にも相談せず決断してしまう危険性
「自分だけが苦しんでいる」という思い込み
早期離職に至る人の多くが、「周りはうまくやっているのに、自分だけがつらい」と思い込んでしまう傾向がある。だが、実際には入社1年目というのは誰しも多かれ少なかれ“仕事のストレス”を抱えるものだ。表には出さずとも、同期や先輩も陰で悩んでいる。
この“自分だけ感”が強くなると、相談できず、孤立し、判断を自分の中だけで閉じてしまう。結果として、上司や人事に改善を求めることなく、退職という選択肢しか見えなくなるのだ。
相談すべき相手は誰か?
まずは信頼できる同期や先輩社員がいれば、素直に「しんどい」「ついていけない」と伝えてみることで、自分の悩みが特別なものではないと気づけることもある。次に、社内の人事やキャリア相談窓口があれば、配属変更や仕事の進め方についての相談が可能だ。
また、外部のキャリアカウンセラーや大学のキャリアセンターも選択肢のひとつとなる。辞める・辞めないの前に、「今の状況を整理する」ことが極めて重要であり、他者との対話を通してしか見えてこない視点が必ずある。
「辞めたい」の本質を自分で深掘りする
何が“イヤ”で、何が“足りていない”のか
「辞めたい」と思ったとき、最も避けたいのが“感情だけで辞める”ことだ。衝動的な退職は、次のキャリアに必ず影を落とす。「やりたいことが見つかっていない」「人間関係がうまくいかない」「自信がない」など、理由を突き止めることで、その解決策が社内にあるのか、あるいは別の環境を探すべきかが明確になる。
たとえば、「自分に合わない仕事ばかり振られている」と感じていたとしても、それが“単なる研修の一時的なもの”なのか、“会社の方針として続いていくもの”なのかでは判断が変わる。感情の奥にある“事実”と“構造”を見極めようとすることが、次の一手を誤らないための鍵となる。
「辞めてもいい」のだが、考えずに辞めるのは危ない
キャリアに“負債”を残さないための準備
もちろん、職場が明らかにブラックである、パワハラがある、精神的に限界が近いなどの状況であれば、早期退職は正当な選択だ。しかし、「何となく」「向いてない気がする」といった曖昧な理由で辞めてしまうと、次の就職活動でも“すぐ辞めそうな人”という印象を持たれやすい。
退職する際は、「なぜ辞めるのか」「次はどんな環境を求めているのか」「何があれば続けられるのか」など、自分の判断を論理的に説明できる状態を整えておく必要がある。これをせずに辞めてしまえば、「結局どこに行っても同じことの繰り返し」になりかねない。
すぐに辞めなかった人たちがしていたこと
逃げずに踏みとどまる人が持つ“視点”とは
「このままではダメだ」ではなく「ここからどうするか」
入社後のギャップや辛さは、多くの新卒が直面する現実だ。しかし、すべての人が退職に至るわけではない。辞めなかった人たちは、目の前の違和感や不満を「改善可能な課題」として捉えなおす視点を持っていた。たとえば、「この業務は本当に自分に向いていないのか」「この部署以外ではどうなのか」と一段階視座を上げて状況を見直している。
このような視点を持てる人は、感情に支配されず、環境のせいにしすぎず、主体的な判断ができている。苦しい中でも「どうすれば良くなるか」「どこに相談すれば改善するか」を考える思考が、結果として離職を防いでいるのだ。
信頼できる人を見つけることが環境を変える
「職場内に味方がいるか」が大きな分岐点
どんなに仕事が合っていても、人間関係がストレスであれば継続は難しい。逆に、仕事内容に多少の不満があっても、「この人と働けるなら頑張れる」と思える存在がいれば、それが支えになる。入社後すぐに辞めなかった人たちの多くは、“一人の味方”を見つけていた。
上司でなくても構わない。隣のデスクの先輩や、同期の一人でもいい。「本音で話せる」「わかってくれる」と感じられる相手の存在が、出社する理由になる。人間関係が“苦しさ”の根源になりやすいなら、逆に“居場所”をつくれるかが残留の鍵になる。
「どうせ辞めるなら、まず戦ってから」が選択肢になる
言いたいことを言ってから辞めるか
納得感のない退職は、次のキャリアに尾を引く。だからこそ、「どうせ辞めるなら、一度ちゃんと会社に伝える」「改善を求めてみる」という“行動”を挟むことが重要だ。伝えた上で変わらなければ、それは辞める理由として合理的になる。
「相談したら評価が下がるのでは」「余計に気まずくなるのでは」と恐れる気持ちは当然だが、何も伝えずに辞めた結果、「自分は結局、何も変えられなかった」という無力感が残るリスクの方が高い。辞める/辞めないの二択ではなく、「伝える」という中間の選択肢を挟むことで、視野は大きく広がる。
就活時にどこを見直すべきだったのか
見ていたのは“表面的なイメージ”ではなかったか
「社員の雰囲気」や「企業のカラー」に惑わされる罠
学生が就活で重視しがちな要素の中に、「若手が活躍している」「風通しがよさそう」「オフィスが綺麗」といった表層的な情報がある。だが、こうした要素は配属や職種によってまったく意味をなさないことが多い。「会社全体の印象がよかったから」と言って入社しても、自分が実際に関わるのは“自分の部署の人と仕事”でしかない。
実際に入社してから「雰囲気が違った」「想像と違った」と感じる理由は、この“見ていた対象”が広すぎたことに起因する。企業研究において、“会社全体”ではなく“自分が関わる可能性の高い業務・部署・上司像”を具体的に想定する力が必要だ。
“自分”が見えていないまま選んでいたリスク
軸が曖昧だと、会社とのズレに気づけない
「働く上で何を大事にしたいか」「どういう環境なら自分は頑張れるか」などの軸がないまま企業選びをしていた人ほど、入社後に違和感を抱きやすい。特に「大手だから安心」「知名度があるから将来安泰」という理由で入社すると、“仕事内容”や“働き方”が合っていなくても無理をしてしまう。
この“合っていない”ことに早く気づける人は辞める選択をするし、気づかない人は我慢を続けてメンタルを崩すことになる。だからこそ、就活段階で「自分はどういう価値観のもとで仕事をしたいのか」「どんな条件が揃えば納得感をもって働けるのか」を自覚しておくことが不可欠になる。
入社前に「辞めたくなったらどうするか」まで想定する
最悪の事態を想像しておく
意外に思われるかもしれないが、“最悪の状況”を想定しておくことは、就活で極めて重要な準備である。「もしパワハラがあったら誰に相談するか」「どこまで我慢したら辞める判断をするか」といったシミュレーションを就活中にしておけば、入社後の行動に迷いが生じにくい。
これをしておかないと、いざ「辞めたい」と思ったときに、自分の中での基準が曖昧で、行動が後手に回る。理想だけではなく、現実の厳しさも織り込んだ上で、「それでもこの企業でチャレンジしたい」と思えた会社こそ、本当に自分に合った会社だと言える。
まとめ
入社後すぐに辞めたくなる新卒が増えている背景には、就活段階での“企業選びの甘さ”や、“理想と現実のギャップ”がある。だが、すべての新卒が辞めるわけではない。辞めずに踏みとどまった人たちは、「感情に支配されない視点」「信頼できる人の存在」「改善に向けた対話」を通じて乗り越えていた。
就活生は、企業選びの際に“会社のイメージ”ではなく“自分に合う環境かどうか”を具体的に想定し、自分なりの「働く価値観」や「続けられる条件」を明確にしておく必要がある。そして、最悪の事態も想定したうえで、それでも挑戦したいと思える企業に出会えたとき、それは初めて“納得感のある入社”になる。
早期離職は誰にでも起こり得る。だが、起こったときにどう行動するかが、その後のキャリアを決定づける。感情に振り回されず、視座を上げて、長く働ける環境を自ら作っていくことが、真に後悔しない選択と言えるだろう。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます