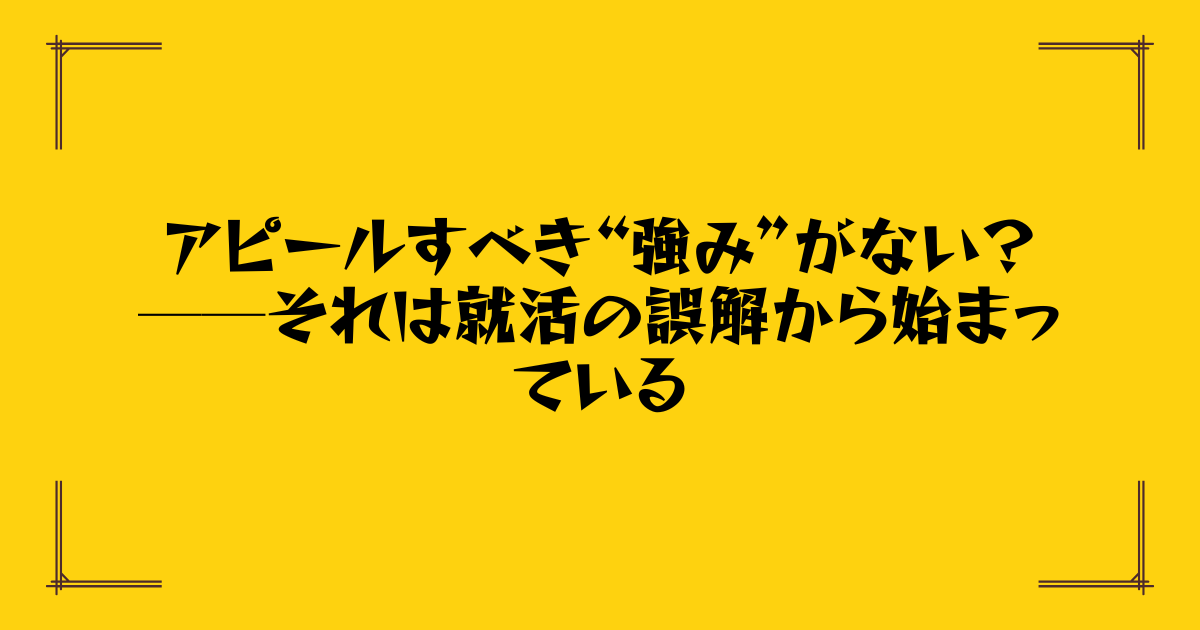自己PRは“特別な人”だけのものではない
「何かすごい経験を話さなきゃいけない」という呪縛
就活の自己PRという言葉には、どこか“特別な実績を持っている人だけがするもの”という誤解がつきまとっている。全国大会出場、留学、ベンチャーでの長期インターン、大規模なプロジェクトを主導──SNSや就活体験談で目にする“成功ストーリー”が、自己PRに対するハードルをどんどん上げている。
だが、ほとんどの学生がそういった“話のネタになる武器”を持っているわけではない。アルバイトは普通、サークルでは目立たなかった、ゼミも淡々とこなしただけ。そんな自分が“話すことがない”と感じるのは当然かもしれない。
けれど、企業が本当に知りたいのは、“すごい成果”ではない。採用したいと思える人かどうかを見極めるために、あなた自身が「どんな人で」「どう行動するか」を知ろうとしている。それは、派手な経歴の有無とはまったく別の話だ。
自己PR=自慢話だと思っていると、就活が苦しくなる
「自分をよく見せよう」とするあまり、嘘ではないけれど誇張気味のエピソードを作ってしまう。あるいは、周囲に負けじと“それっぽい話”をテンプレート通りに並べてみる。結果、どこか自分らしくない文章や話し方になり、面接でもうまく言葉が出てこない──そうやって就活が苦しくなる人は少なくない。
自己PRは「自分はこんなにすごいです」と言う場ではない。本来は、「こんな自分なんですが、こんな考え方で動いてきました」「こういう価値観を大事にしてます」という“自己紹介”に近いものだ。事実をありのままに、でも丁寧に伝える。それだけでいい。
企業が見ているのは「スキル」ではなく「姿勢」
“未経験者”を採用する理由に目を向ける
新卒採用=“ポテンシャル採用”の本質を理解する
新卒採用の場で、企業が学生に“完成された能力”を求めているケースはほとんどない。なぜなら、新卒で入る人材にはいずれ社内で育成していく前提があるからだ。つまり、スキルや知識よりも「この人は育ちそうか」「一緒に働けそうか」を見ている。
ここで問われるのは、「今何ができるか」ではなく、「どんな姿勢で物事に取り組んできたか」。もっと言えば、「この人が社会に出たらどんなふうに動いてくれそうか」という“想像の余地”があるかどうかだ。
「私はまだ何もできない」という自覚がある人こそ、自分の思考や行動の背景を言語化して伝えることが大切になる。それが相手に「この人は成長していきそうだ」という印象を与える鍵になる。
「どんな状況でもちゃんと向き合っていたか」がPRになる
「強みがない」と感じている人でも、「あのとき、こんなふうに考えて動いた」という過去の行動は必ずある。たとえば、アルバイトでクレーム対応に困ったときに、自分なりにどう対応したか。ゼミで意見が食い違ったときに、どうやって関係を保とうとしたか。そうした“当たり前の経験”にこそ、企業はその人らしさを見出す。
就活では、他人と比べて「目立つ経験をしていない」と落ち込むよりも、自分が経験してきた中で「どんな姿勢で動いたか」「どう向き合ったか」に目を向けた方が、自分だけの言葉が見つかる。
自己PRは“選ばれる”ためじゃなく“伝える”ためにある
企業に合わせて作ると「中身のない自己PR」になる
評価されそうなことを並べるのは、逆に逆効果
就活が進まない人ほど、「この会社にはこれを言った方がいいかな」とか「協調性って入れとけば無難だよな」と、“企業受け”を意識しすぎるあまり、どこか抽象的で芯のないPRになりがちだ。
だが、企業の面接官はそれを見抜く。どこかで聞いたような話、自分の言葉じゃないエピソードは、伝わりにくいし記憶にも残らない。
本当に印象に残るのは、「この人はちゃんと自分のことを分かっていて、それを自分の言葉で伝えてくれているな」と感じさせるPRだ。だからこそ、無理に「受かりそうなこと」を探すのではなく、自分の等身大の言葉で伝える覚悟が必要になる。
「伝えよう」としている人は、実はそれだけで魅力的
たとえ話すのが下手でも、文章がうまくまとまっていなくても、自分を“理解してもらおう”という姿勢がにじみ出ていれば、それだけで伝わるものがある。これは面接官の立場になればわかるが、テンプレで上手に作った自己PRよりも、少しつたなくても“気持ちが伝わる”PRの方が印象に残る。
自己PRは、完璧さを競うものではない。むしろ「自分はこれまでこんなふうに考えて動いてきました」「こういう人間なんです」と、真剣に伝えようとする人こそ、採用したくなる。
自己PRが書けない・話せないのは“素材”がないのではなく“視点”が違うだけ
自分の言葉で話せるようになる土台は「自分の過去の納得」
“小さな行動”に注目するだけで、見えるものが変わる
「何もアピールできる経験がない」と感じてしまうとき、人はつい“目立つ成果”や“変化”ばかりを探してしまう。だが、実は企業が知りたいのは“派手な結果”ではない。
「なぜその行動をしたのか」「そのとき何を感じたのか」「どう改善しようと思ったのか」──つまり、行動の“理由”と“プロセス”にこそ、人柄や考え方が表れる。
だからこそ、自分の過去の中から「自分なりに頑張ったこと」「工夫したこと」「悩んだこと」を思い出し、それを“なぜやったか”という視点で振り返ると、自分の中に確かにある“PRすべき素材”が見えてくる。
“できること”ではなく“見せたい自分”を選ぶ
就活は、スキルのプレゼンではない。たとえば「プレゼンが得意」「統率力がある」などの能力をアピールすることも大事だが、それ以上に「私はこういう人でありたい」「こういう姿勢で仕事に向き合いたい」という意思を伝えることの方が大切になる。
それは、どんな仕事をしていても根っこに残る“人としての土台”だ。だからこそ、PRするのは“何ができるか”より“どんな自分でありたいか”であっていい。
エピソードが弱い?──“行動の中身”で勝負する思考法
大事なのは「何をしたか」ではなく「どう考えて動いたか」
結果ではなく“過程”にこそ、その人らしさが出る
就活において自己PRのネタ探しに悩む学生は、「成果」や「結果」に注目しがちだ。けれど企業が注目しているのは、そうした“結果”そのものではない。むしろ、「どう考えて動いたか」「そこにどんな姿勢があったか」といった“行動の中身”の方が、遥かに価値があると判断される。
たとえば、アルバイトで月間売上1位を取ったという実績は確かに目立つ。だが、仮に売上が平均的だったとしても、「なぜその仕事を選び、どう工夫して取り組んだか」「困難があったときどう乗り越えようとしたか」などのエピソードには、等身大の人間性が表れる。これは、「企業が一緒に働きたいと思うかどうか」を判断するうえで、最も重要な部分でもある。
ありふれた経験でも、視点を変えれば立派な自己PRになる
「誰でもやっていることだから自己PRにならない」と思っている経験こそ、実は最も共感を呼ぶ材料になる。たとえば、コンビニのレジ業務やカフェの接客、学園祭の運営など、特別ではない行動でも、「そのとき自分は何を意識して動いたか」を丁寧に振り返ると、その人らしさが浮かび上がってくる。
エピソードの価値は、経験の“派手さ”ではなく、そこに込められた“考え方”や“姿勢”によって決まる。だからこそ、自分だけのリアルな体験に誇りを持ち、他人と比べずに語ることが、選考で生き残る自己PRへの第一歩となる。
自分の中の「小さな違和感」こそ、伝える価値がある
何を問題だと感じ、どう変えようとしたか
自分の中で“ひっかかった経験”にこそ、成長の種がある
人は何かに違和感を覚えたとき、それをスルーするか、向き合うかで大きな差が生まれる。自己PRでは、その「違和感と向き合った経験」が伝わると、企業は「この人は自分の頭で考える力がある」と感じる。
たとえば、「先輩のやり方に疑問を感じて、少しずつ自分なりの方法に変えていった」「バイト先の非効率なルールに気付き、店長に相談して改善を提案した」──こうした経験は、どれも派手ではない。しかし、自分の頭で考え、自分なりに動いた“人間としての反応”がある。それこそが、企業が評価するポイントだ。
変化は小さくても、その人の“意思”は十分伝わる
自分の行動によって劇的に何かが変わった──そんなストーリーがなくてもいい。むしろ、現実的な小さな工夫や変化の積み重ねにこそ、その人がどんな価値観で動いているのかが表れる。
たとえば、「お客様の言い方がきつくても、相手の立場を想像して怒りを抑えるようになった」とか、「ゼミの議論で発言できなかった自分が、事前にメモを準備するようになった」など、小さな行動の変化でも、それを“自分で気づいて選択した”という姿勢が伝わるだけで、自己PRになる。
他人と比べて“弱く”感じるのは、語り方のせい
自分だけの軸を見つけることで「比較」の呪縛から抜け出す
「この人には勝てない」と思った時点で負けているわけではない
就活中、どうしても他人の経験やエピソードが自分より“強く”見えてしまう瞬間がある。長期インターンで大きな成果を出した人、サークルで代表を務めた人、TOEICの点数が高い人。そうした情報に触れるたび、「自分には勝ち目がない」と思ってしまうのも無理はない。
だが、選考というのは“能力の高い人が勝つ”という単純な話ではない。企業は「この人と一緒に働きたいか」「チームに合いそうか」「誠実に仕事に取り組みそうか」といった多面的な視点で判断する。だからこそ、他人の土俵で勝負するのではなく、自分なりの“伝え方の軸”を持つことが大切になる。
自分の“スタンス”を決めるだけで、語れる言葉が変わる
たとえば、「とにかく結果を出すことより、人との信頼関係を大事にしてきた」とか、「誰よりも目立つのではなく、周囲を支える役割に徹してきた」というスタンスも、十分にアピールポイントになる。
この“スタンス”があるだけで、同じエピソードでも語り方が変わる。曖昧だった行動の意味が言葉として整理され、自信を持って語れるようになる。PRするのは“成果”ではなく、“選んできた価値観”だという意識が持てると、自分のエピソードに対しての納得感が格段に上がる。
自分だけのエピソードをPRに昇華させる視点
「自分なりに工夫したこと」を軸に掘り下げる
行動の中で「自分が考えたこと」を丁寧に描く
自己PRが弱いと感じる場合、エピソードに“自分の思考”が入っていないケースが多い。たとえば、「バイトで接客を頑張った」「ゼミで発表を経験した」といった説明にとどまっていると、聞き手は「それで、あなたはどう考えたの?」と感じてしまう。
このとき有効なのが、「行動 → 気づき → 工夫 → 結果」というシンプルな流れで整理してみることだ。接客バイトで「お客様が不機嫌に見えたときに、先回りして声をかけてみた」とか、「発表のときに緊張で話せなかったので、スライドを減らして要点だけ話すようにした」など、自分が“なぜそうしたか”を明確にするだけで、エピソードが一気にPRになる。
正直に語ることが“説得力”につながる
作り込んだような話よりも、等身大で語られる言葉の方が、聞き手には伝わりやすい。たとえば「最初は失敗ばかりだったけど」「自信がなかったけど、少しずつ変わっていった」といった“過程”にこそ、リアリティと信頼感が宿る。
完璧なストーリーを目指す必要はない。むしろ、「ありのままの自分をどう伝えるか」という視点を持つことが、結果的に強いPRにつながっていく。
話すのが苦手?──緊張しながらでも伝わる“構造と順序”
面接で緊張して話せないのは「話し方」より「考え方」の問題
緊張するのは当たり前。その上でどう話すかが分かれ道
「面接が苦手」「話そうと思っても言葉が出てこない」と悩む学生は非常に多い。特に、自分に自信がなかったり、自己PRに納得感がない場合、面接の場ではさらにその不安が大きくなってしまう。
だが実際のところ、「緊張しないこと」ではなく「緊張しても話せること」の方が大切だ。採用側は、完璧なプレゼンテーション能力を求めているわけではない。むしろ、言葉に詰まりながらも真剣に伝えようとしている姿勢から、その人の誠実さや思考力を感じ取っている。
面接が怖いのは、「何を話すか」を自分の中で整理しきれていないからだ。話す順番が頭に入っていないまま臨んでしまうと、思考が混乱し、余計に緊張が増す。「話すのが苦手」な人ほど、“順番”を明確にして臨むだけで、大きく変わる。
伝える内容は「3段構成」にすると整理しやすい
もっともシンプルで効果的な話の構成は、以下のような3つの流れである。
何を話すのか(結論)
なぜそう考えるのか(理由)
実際にどう行動したのか(エピソード)
この型を使うだけで、話が論理的かつ簡潔になる。そして「順番が決まっている」と思えるだけで、不安感が減り、落ち着いて話しやすくなる。自信があるかどうかではなく、「言う順番が決まっているかどうか」が勝負の分かれ目になる。
伝わる自己PRは「うまさ」ではなく「わかりやすさ」で決まる
話が上手い=伝わる、ではない
印象に残るのは“整った話”ではなく“伝わる話”
「もっと上手く話せれば内定が出るのに…」と思いがちだが、それは少し違う。人を惹きつける話し方は必ずしも“話のうまさ”ではない。むしろ、「この人は本当にそう思っているんだな」と感じさせる“納得感のある話”の方が、採用担当者の印象に残る。
たとえば、少し言い間違えたり、言い直したりしても、「なぜそれを伝えたいのか」「その人にとってなぜ大事な経験なのか」が伝わっていれば、それは面接として十分に合格ラインを超えている。
「話すのが得意じゃない」と悩むよりも、「自分の言葉で、わかりやすく伝える」ことに集中する方が、ずっと実践的で成果が出やすい。
「わかりやすい話」には“具体性”が必須
話がぼんやりしてしまう学生の多くは、抽象的な言葉で自己PRをまとめてしまっている。
たとえば「主体的に取り組みました」「粘り強く努力しました」といったフレーズは、聞こえはいいが、内容が伝わりづらい。これを「毎日売上ランキングを確認して、次の日の接客を変えてみた」などのように、実際の行動にまで落とし込むと、一気にリアルな印象になる。
「具体的に言うとどういうこと?」と自問しながら準備することで、面接でも伝わる話に近づいていく。
話す内容を整理する「準備」が自信につながる
「構造」で話す練習が、緊張に勝つ最短ルート
ストーリーではなく「要素の順番」を決めておく
プレゼンのように話を組み立てようとする学生が多いが、話し方に慣れていない人ほど、物語風に話すのは難しい。流れが前後したり、余計な情報が入って話が伝わらなくなるリスクがある。
そこで大事なのは、ストーリーではなく「順番」。たとえば「バイト先でのエピソードを、困った状況 → 自分が考えたこと → 工夫した行動 → 小さな変化」の順で話す、というように、順序を決めておくと、それだけで話が整理される。
「流れるように話そう」とせず、むしろ「順番どおりに話すこと」に集中するだけで、頭が混乱せず落ち着いて話せるようになる。
反復練習よりも「整理した言葉」で話す方が効果的
何度も繰り返して練習すれば上手くなる、と思っている人もいるかもしれないが、実際にはそう単純ではない。むしろ、何度も同じ話を練習するほど、余計に言葉がぎこちなくなったり、「うまく言おう」として逆に混乱してしまうことも多い。
大切なのは、「整理した言葉を持つ」こと。話すたびに少し言い回しが違っても、「何を伝えるのか」「どの順番で言うのか」が決まっていれば、軸はぶれない。自分の中で“伝えたい意味”が固まっていれば、どんな場面でも対応できるようになる。
面接で評価されるのは「伝えようとする姿勢」
完成度より“真剣さと納得感”を重視する企業の視点
緊張していても「伝えたい」という意志があれば評価される
多くの学生が誤解しているのが、「うまく話せなかったから落ちた」という思い込みだ。もちろん、あまりに言葉にならない場合は不利になることもあるが、多くの企業は“その人の意志”や“伝えようとする姿勢”を見ている。
言葉に詰まっても、「自分にとってこれは大切な経験でした」と目を見て伝える人には、企業も耳を傾けてくれる。面接はスピーチ大会ではなく、「人柄を見る場」だということを忘れてはいけない。
うまく話せない=採用されない、ではない
話すのが得意ではない学生でも、採用されている例は非常に多い。重要なのは、「言いたいことがあるかどうか」。その言いたいことが自分の中に明確にあれば、話し方がぎこちなくても、必要なメッセージはちゃんと伝わる。
逆に、話し方は流暢でも、何を伝えたいのかが見えない話は、印象に残らない。だからこそ、「伝えたいこと」と「伝える順番」を整理することが、面接対策の本質になる。
“自分の言葉”で語れる人が最後に内定を取る理由
就活は「言葉の巧さ」より「言葉の納得度」が問われている
流暢な話より“腹落ちしている”話が印象に残る
自己PRが苦手な学生は、「どう言えばうまく聞こえるか」にとらわれすぎていることが多い。しかし、面接で評価されるのは“話のうまさ”ではなく、“言葉の重み”だ。
たとえば、「自分の言葉で語っているな」と感じさせる人は、多少拙い表現でも面接官の記憶に残る。逆に、どれだけ洗練されたフレーズを並べても、それがテンプレート的で本人の実感が伴っていないと、採用担当者の心には届かない。
「自分の言葉」とは、誰かから借りてきたような表現ではなく、自分の中で咀嚼し、自分の経験と結びついたもの。それがある人は、質問に対する答えも自然で、説得力がある。
言葉を磨くより、思考を掘る方が先
「言葉が出てこない」「何を言えばいいか分からない」と悩んでいるとき、その多くは“思考が浅い”ことが原因だ。つまり、話そうとしている内容を、まだ深く理解できていないということ。
だからこそ大切なのは、「どう言うか」ではなく「何を考えたか」を深掘りすること。自分が経験した出来事に対して、「なぜその選択をしたのか」「その時どんな気持ちだったのか」「結果として何を学んだのか」と掘り下げていくことで、自ずと“自分の言葉”が出てくるようになる。
面接官は“完成された人”ではなく“考えている人”を採る
結果よりも「変化の兆し」を見ている企業の視点
企業が重視するのは「育つ可能性」
就活では「完成された自己PRを披露しなければ」と思い込む学生が多いが、企業が本当に見ているのは「この人は入社後に育ちそうかどうか」だ。すでに完璧な人材を求めているわけではない。
むしろ、現時点では未熟でも、自分の考えを持ち、それを言葉にして人と共有できる学生に対して、企業は“将来性”を感じる。「この人なら、入社後も悩みながら成長していけそうだ」と思わせることができれば、それが何よりの自己PRになる。
「考える力」は、言葉の端々ににじみ出る
「自分の考えを持っているかどうか」は、話の中のキーワードや姿勢から自然と伝わる。「自分はこう思いました」「この時、自分なりにこう工夫しました」と語れる人は、表面的な言葉でごまかす必要がない。
一方、「周囲がこうだったから」「特に意識していなかった」と答えてしまう学生は、考える習慣がないと判断されやすい。企業が求めるのは「今の時点で完璧な答え」ではなく、「考えようとしている姿勢」だということを意識しておきたい。
自己PRで大事なのは「武器」ではなく「意味づけ」
すごい経験ではなく、“自分にとって意味があった経験”を語る
自己PRに必要なのは“実績”よりも“意味”
自己PRができないと感じる人は、「自分にはすごい経験がない」と思いがちだ。しかし、面接官が知りたいのは、何を成し遂げたかではなく、「その経験を自分がどう受け止めたか」だ。
たとえば、飲食バイトで皿洗いを頑張った経験でも、それに対して「自分なりに工夫して効率化しようとした」「先輩にどう相談するか考えた」といった視点があれば、立派な自己PRになる。
重要なのは、「その経験が自分にとってどんな意味を持ったのか」を語れること。“すごさ”ではなく、“深さ”が問われている。
他人と比べない自己PRをつくる発想法
「他の人と比べて、自分の経験は見劣りする」と感じたときは、比べる基準を間違えている。他人と比べて“すごいかどうか”ではなく、自分にとって“どれだけ重要だったか”が自己PRの軸になる。
同じサークル活動でも、「ただ楽しかった」ではなく、「その中で何を感じ、どう行動したのか」を言語化することが、本当の意味での差別化になる。自分の経験の中にしかない価値を掘り出すことが、“自分らしいPR”につながっていく。
就活のゴールは“話せること”ではなく“伝わること”
話すのが得意ではない人が、内定を勝ち取るには
伝わる自己PRの本質は「共感」と「納得」
話すことが得意でなくても、伝わる話はできる。そのためには、「自分がその話に納得しているか」「その言葉に自分らしさがにじんでいるか」が大切だ。
採用担当者は、話の内容よりも、その人がどんな人間かを見ようとしている。「等身大の考え」を見せることができれば、それだけで印象は大きく変わる。
「話す練習」よりも「言葉の整理」から始めよう
言葉に自信がないなら、話す練習よりもまず「自分の言葉を整理する」ことから始めてみてほしい。自分が何を伝えたいのかを紙に書き出してみる、誰かに説明してみる、音声で録音して聞き返してみる──そんな小さな準備の積み重ねが、“伝わる自己PR”をつくっていく。
話すことが苦手な人ほど、「完璧に話そう」と思わないこと。伝えるべき中身が整っていれば、言葉は自然に伴ってくる。
まとめ:自分の言葉を見つけた人から、内定は近づいてくる
就活における自己PRとは、派手な成果を語る場ではない。うまく話す技術でもない。大事なのは、「自分の経験を、自分の考えで語れること」。
誰かにすごいと思われるかどうかではなく、自分自身が「これは自分にとって大事な経験だった」と思えるかどうか。そこに納得できていれば、言葉が自然と強くなる。
自信がなくても、実績がなくても、自分の言葉を整理し、少しずつ伝える準備をすること。それが、「話せない」状態から脱却し、「伝わる」人材になるための、もっともリアルな第一歩だ。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます