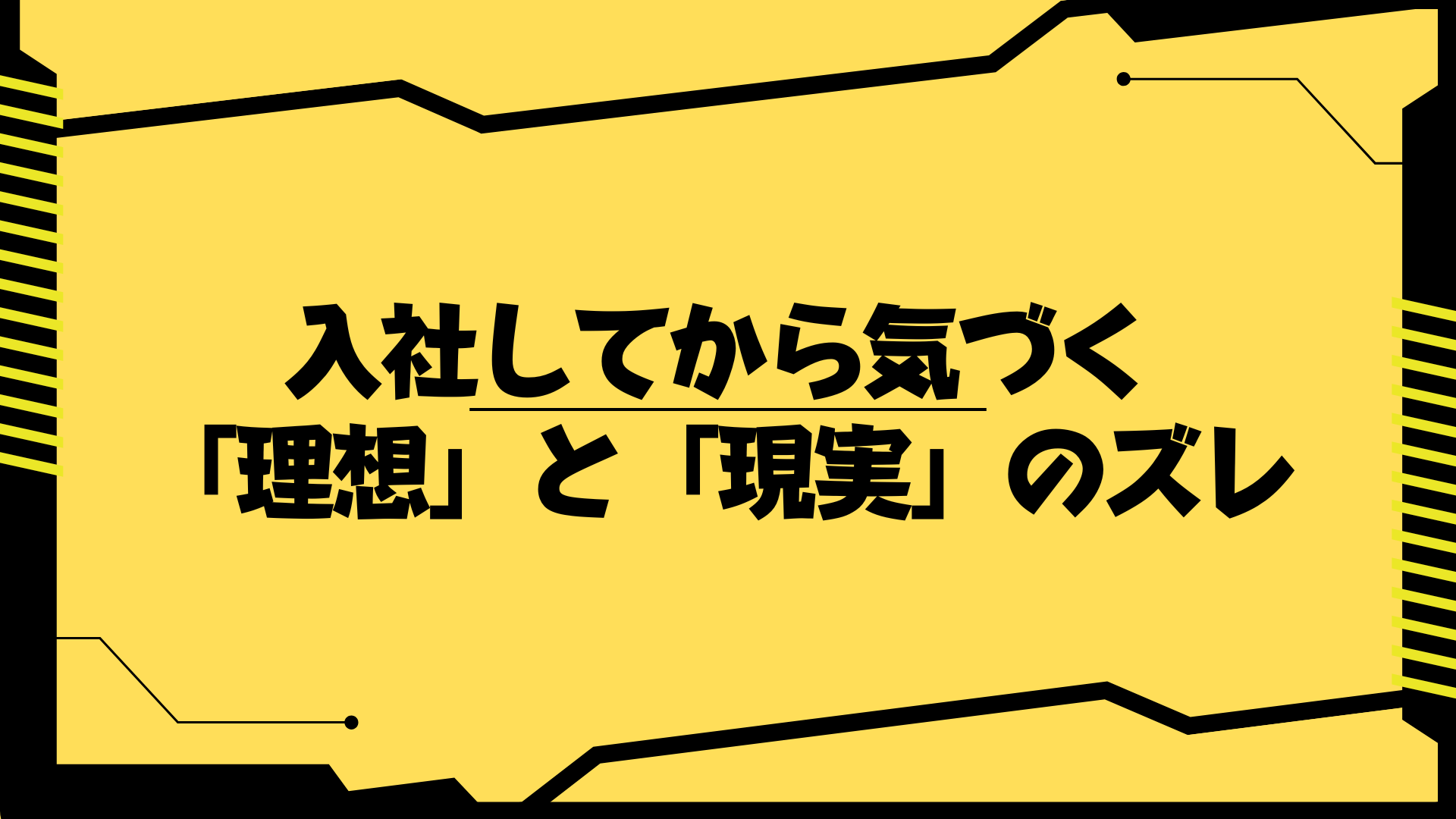企業研究では見えない“職場の空気”
なぜ“働きやすい”と言われる企業で退職者が出るのか
就活中、多くの学生が企業サイトや口コミ、説明会などで「働きやすい」「離職率が低い」「風通しの良い社風」といったワードを頻繁に目にする。しかし実際に入社してみると、「あれ、なんか思っていたのと違う」と感じる人は少なくない。
その違和感の原因の多くは、就活中に見聞きできる情報が“企業が外部向けに発信するイメージ”に限定されているからである。オフィスが綺麗で福利厚生も整っている。しかし配属先の上司が高圧的だったり、チーム内の空気がギスギスしていたりすることは、内定を得る前の段階ではなかなか想像しにくい。
先輩社員インタビューの“落とし穴”
「入社の決め手は人の良さです」――どの会社の先輩社員紹介ページを見ても、こうしたコメントが並んでいる。しかし、これは必ずしも嘘ではないにせよ、すべての部署・社員に当てはまるわけではない。配属先の文化、上司の価値観、取引先との関係など、職場の居心地を左右する要素は数多くある。
また、紹介されている先輩社員が“会社の中でも優秀かつ発信力のある一部の人材”である可能性が高く、自分が配属される環境と一致するとは限らない。就活で見える情報は、会社の“平均”や“実情”ではなく、“例外的に成功しているケース”であることもある。
就活生に伝わらない「人間関係」のリアル
働く上で“上司との相性”は避けられない現実
評価は「成果」だけではなく「人間関係」で決まることもある
新卒就活では、どうしても企業規模や待遇、ブランドに目が行きがちだ。しかし、実際に働き始めると、評価や働きやすさに大きく影響するのは“人間関係”であることに気づく。たとえば、真面目に仕事をしても上司と価値観が合わなければ正当な評価を受けられなかったり、逆に多少仕事が粗くても気に入られている社員が昇進していくこともある。
これは理不尽のように感じられるが、現実の職場では“仕事の成果”と“社内での立ち位置”が一致しないことは珍しくない。人間関係が評価に影響する職場では、上司や先輩との関係構築能力が問われる。
チームの“色”に馴染めないと孤立する危険も
どんなにスキルや学歴が高くても、職場の空気や文化に適応できなければ孤立してしまう。たとえば、「雑談が多い職場」が苦手な人が配属されれば、それだけで居心地の悪さを感じる可能性がある。また、体育会系のノリが強い部署では、意見を控えがちなタイプの人が評価されづらい場合もある。
就活生の多くは“職場に馴染めるか”という観点を見落としがちだが、実際にはそれが職場での充実感や継続性に直結する要素になっている。
新卒ブランドは“入社した瞬間”に消える
「新卒だから許される」期間は驚くほど短い
入社1ヶ月で“即戦力”を求められる現場もある
多くの学生は「新卒は育ててもらえる存在」と思っている。しかし実際には、企業によっては入社直後から即戦力としての動きを期待されるケースもある。特に中小企業やベンチャーでは、新人教育に十分なリソースを割けないため、「見て覚えて」「自分から聞いて」というスタンスが求められる。
そのような環境では、“質問することすら怖くなる”という心理的な壁が生まれ、ミスを繰り返して自信を失ってしまう人も少なくない。
さらに「できないやつ」とレッテルを貼られると、その印象が半年〜1年と長く影響するため、最初のスタートダッシュが重要になる。
配属ガチャによる“格差”も見過ごせない
同じ会社に入っても、部署によって業務内容も評価基準も大きく異なる。「人気部署」に配属された同期はやりがいとチャンスに恵まれる一方、「不人気部署」に配属された社員はルーチン業務に追われ、モチベーションを保てないまま働くことになるケースも多い。
この“配属ガチャ”は、会社側も完全にはコントロールできず、ある意味で運に左右される側面がある。しかもその配属結果は、最初のキャリア形成や将来の異動可能性にも大きく影響を与える。
入社後に直面する「仕事のリアル」とそのギャップ
毎日が“やりがい”で満たされるわけではない
やりがいは“感じられる瞬間”であって“常にあるもの”ではない
就活のエントリーシートや面接で、「やりがいを重視しています」と答える学生は多い。実際に企業も「社会貢献性の高い仕事」や「お客様の感謝がやりがいに直結する仕事」など、魅力的な言葉を並べることが多い。だが現実には、やりがいのある瞬間が毎日続くわけではない。
会議資料の作成、データ入力、上司からの修正対応、同じ問い合わせへの繰り返し対応など、地味で目立たない作業の割合が想像以上に多く、そうした業務が「やりがい」からは遠く感じることもある。それを経験したとき、就活時に思い描いた「やりがいのある社会人生活」とのギャップに戸惑う新卒は多い。
感情労働と「納得できない」評価の現実
サービス業や営業職など、人と関わる仕事では“感情労働”が避けられない。たとえば、理不尽なクレームや無理な要望に冷静に対応し続ける必要がある一方で、それを乗り越えても「当たり前」とされ、評価には直結しないこともある。
また、営業成績などが数字として明確に現れる職種であっても、その数字の背景にある努力や過程を見てもらえないこともある。「あの人は結果を出しているから」という理由だけで昇進が決まる一方で、下支えしているメンバーが軽視されるような状況も起こりうる。就活時に想定していた「正当な評価がある会社」と、現場での評価のされ方が異なる現実に直面することも少なくない。
新卒に求められる“見えない期待”とプレッシャー
「育てる前提」で見てくれるとは限らない
経験がないからこそ、空気を読めと言われる
新卒には「右も左もわからないはず」という前提があるように思えるが、実際の職場では、「新人でも最低限の空気は読め」という無言のプレッシャーがかかる。会議中に発言しないと「意欲がない」と受け取られ、積極的に発言すれば「空気が読めない」と指摘される。
教育係がいたとしても、他の業務で多忙で十分に時間を割いてもらえないケースも多く、「わからないことをそのままにするな」と言われる一方で、質問のタイミングが悪いと嫌な顔をされるなど、曖昧な期待値に振り回される場面は多い。
“新卒だから失敗しても許される”は幻想
確かに、入社当初は多少のミスには寛容な空気があるかもしれない。だがそれは“軽微なミス”に限られる。業務の根幹に関わる重大なミスや、顧客トラブル、納期遅延などは、新卒であっても容赦なく責任を問われることがある。また、「何度も同じ失敗をする」「指摘されたことを改善しない」と見なされると、一気に信頼を失い、フォローの手も遠のく。
つまり、「育成される側」として守られる期間は非常に短く、実質的には“早期から自立”を求められる文化が一般的になりつつある。学生から社会人へと切り替えるための猶予期間は、思っているよりずっと短い。
理想のキャリアと現実のキャリアのギャップ
入社時点の夢が“現実”に押しつぶされることもある
「数年でリーダーに」と思っていたが現場から離れられない
就活中には、「若手でも裁量がある」「早期にマネジメントに関われる」などの言葉に魅力を感じた人も多いはずだ。だが、いざ入社してみると、「新人にはまず現場経験を積んでもらう」「マネジメント層は限られたポストしかない」という会社側の実態に直面する。
本来であれば経験を積んでからの昇格が望ましいのは当然だが、「短期間でキャリアアップできる」という就活中のイメージと、現実の昇格スピードには明確なズレがある。特に大企業では、年功的な昇進が根強く残っており、思っていた以上に「待たされる」ことが多い。
望まない異動や転勤に左右されるキャリア
キャリアを自分の意志で積み重ねていけると考えていた学生にとって、配属後に望まない異動や地方への転勤が発生することは大きなストレスとなる。「この部署でこの仕事がしたい」と考えていたとしても、企業の人員配置や経営判断の前では個人の希望は優先されないことが多い。
特に総合職として採用された場合は、会社都合での異動や転勤が前提となるケースが多く、勤務地や業務内容を選べないこともある。自分が思い描いたキャリアとの方向性の違いに葛藤し、モチベーションが下がってしまう人も少なくない。
理想の職場に裏切られたと感じる理由
入社後すぐに「この会社は違った」と思ってしまう構造
働く環境は“配属部署”によってまるで別物
就職活動の段階で、企業研究や説明会などを通じて「この会社なら安心して働けそう」と判断したとしても、実際に入社してみるとまったく違う印象を受けることがある。その最も大きな原因の一つが「部署間の格差」である。
たとえば同じ企業内でも、ある部署は風通しが良く和やかな雰囲気である一方、別の部署は上下関係が厳しく緊張感に満ちている、といった具合に、文化や人間関係が全く異なるケースが少なくない。配属された部署が「自分が想像していた会社」と乖離していれば、その時点で“会社に裏切られたような感覚”を抱いてしまうのは自然な反応である。
企業文化よりも“現場の空気”の方が強い
多くの企業は「チャレンジ精神を大切にする」「意見を自由に言える環境」などの企業理念を掲げている。しかし、現場ではそうした理念が形骸化しており、実際には「黙って言われたことをやるのが正解」という空気が支配していることもある。
企業文化と現場文化のギャップは非常に大きく、就活生はどうしても「企業全体の方針」に目が向きがちだが、実際に自分が属するのは“部署”という小さな単位だ。つまり、どれだけ理念が魅力的でも、自分が働く場所の現場空気に馴染めなければ、働くこと自体が苦痛になってしまう。
思っていた仕事と違う現実
「希望職種」と「現実の業務内容」のギャップ
営業志望だったのに内勤へ、開発がしたいのにテスト業務ばかり
配属におけるミスマッチは想像以上に多い。「営業志望だったが配属は経理だった」「マーケティング職を希望したのに実際の業務はデータ入力がメインだった」など、本人の希望と会社の人員配置とのズレが現実に起きる。企業によっては“まずは一通りの部署を経験してもらう”という方針があるため、希望外の配属が“教育の一環”として扱われることもある。
その場合でも、会社としては「今後のキャリアにプラスになる」と考えての配属かもしれないが、本人にとっては「やりたいことができない」というフラストレーションが溜まりやすい。
説明会の業務内容と実務の解像度の違い
企業の説明会やパンフレットでは、「○○の提案業務」「プロジェクト推進」など、抽象度の高い言葉で職種を説明することが多い。しかし、実際の業務は細かな日程調整や議事録作成、既存資料の修正、上司の指示通りの段取り業務といった裏方の仕事が大半であることも多い。
学生時代に「プロジェクトリーダー」「企画職」に憧れていた人ほど、業務の“地味さ”に失望しやすい。また、「裁量がある」と説明されたポジションでも、実際には上司の承認なしでは何も動かせないという制限の多い環境も少なくない。
入社後に悩まされる“会社とのズレ”
価値観の違いがモチベーションを削る
成長よりも安定を優先する社風に戸惑う若手社員
就活時に「成長できる環境」を求めていた学生が入社後にぶつかる壁の一つが、社風との価値観の違いである。たとえば、変化を好むタイプの人が、保守的で変化を嫌う組織に入ると、「なぜ改善しようとしないのか」「どうして効率化を考えないのか」といった疑問が蓄積する。
こうした違和感が蓄積すると、いくら待遇がよくても日々の業務がつまらなく感じられたり、自分の存在意義を見失ってしまうことにつながる。逆に、安定を求めて入社した人がスピード感を求められる環境に置かれて疲弊するパターンもある。
社内評価の軸と自分の努力が噛み合わない
新卒の多くは「頑張れば評価される」と信じている。しかし、実際の評価基準が「目に見える数字」や「上司との関係性」に偏っている場合、自分の努力や工夫が見過ごされることもある。
たとえば、顧客対応で粘り強く課題解決に取り組んだとしても、評価の指標が「新規契約数」であれば、その努力は数字に反映されない限り評価されない。また、論理的に正しい提案をしても、上司の方針に逆らったという理由で印象が悪くなることもある。
このように、何を重視して評価されるのかという“社内ルール”と、自分の働き方や価値観が一致しないと、頑張ること自体に意味を感じられなくなってしまう。
新卒一年目で直面する「辞めたい」の正体
理由は一つではなく、いくつもの“違和感”の積み重ね
明確な原因よりも“漠然とした不満”がしんどい
社会人としての生活が始まると、多くの新卒が心のどこかで「本当にこの会社でよかったのか?」「この仕事は自分に合っているのか?」という迷いを抱くようになる。決定的な出来事があったわけではなくても、職場の雰囲気、上司との距離感、業務内容の単調さ、成長実感の薄さなど、様々な小さな違和感が積み重なり、気づけば「辞めたい」という感情に変わっている。
特に真面目な人ほど、「自分が悪いのでは」「もっと頑張るべきでは」と自責的になりやすく、誰にも相談できないままストレスを溜め込んでしまうことも多い。
SNSや他人との比較で“今の自分”が苦しくなる
働き始めてしばらく経つと、学生時代の友人たちがそれぞれ異なるキャリアを歩んでいることに気づくようになる。「あいつはベンチャーでやりがいのある仕事をしているらしい」「同期がもう転職して年収を上げている」といった情報が耳に入るたびに、自分の現状に対して焦燥感が募る。
しかし、それらはあくまで表面的な情報にすぎず、他人の“見える部分”と自分の“現実”を比べても意味はない。にもかかわらず、SNSや口コミによって「今の自分は遅れているのでは」という感情が増幅され、冷静にキャリアを見直す余裕を失ってしまう人も多い。
社会人一年目に知っておきたい“現実との付き合い方”
不満は“今すぐ辞めるべき理由”にはならない
自分の違和感を「言語化」することが第一歩
「なんとなく違和感がある」「自分には向いていない気がする」というモヤモヤは、すぐに転職を決断する理由にはなり得ない。まずはその違和感を言語化することが重要だ。たとえば、「人間関係が辛い」のか「業務内容が合わない」のか、「自分の能力が活かせない」のか、「会社の価値観とズレている」のかなど、具体的な原因を見極めることで、今後どうすべきかの選択肢が明確になる。
言語化のプロセスには、日記をつけたり、信頼できる第三者に相談したり、キャリア相談を受けたりする方法がある。自分の気持ちを言葉にできるようになると、感情ではなく論理で次の行動を考えられるようになる。
「とりあえず3年」ではなく「なぜ続けるか」を明確に
よく言われる「石の上にも三年」という言葉に従って、「とにかく辞めずに続けるべき」と思い込む人もいるが、大切なのは「続ける理由」を自分で納得して持っているかどうかである。成長を実感しているのか、今の経験が将来にどうつながるのか、何かスキルが身についているのか――これらを自覚できていれば、「続ける価値」はある。
一方で、「ただ辞めたくないから」「転職は怖いから」といったネガティブな動機で留まり続けることは、モチベーションを下げ、精神的にも身体的にも疲弊する可能性が高い。大切なのは、“続ける”か“辞める”かという二択ではなく、“自分のキャリアにとってどうするのが最善か”を考える視点である。
新卒就活を通じて得られなかった視点
“合う会社”より“合う働き方”を探す発想
就活では「自分に合う会社を探す」が、現実には合わない環境に飛び込むこともある
就活のゴールは「内定獲得」ではなく、「自分らしく働ける環境に出会うこと」であるはずだが、実際の選考では“会社に選ばれること”ばかりを意識してしまい、自分にとっての「働き方の相性」を後回しにしがちである。
働き始めてから、「朝型の方が向いていた」「オフィスよりリモートが快適だった」「指示されるよりも自分で動ける方が楽だった」など、自分の“仕事のスタイル”に気づくケースは多い。こうした気づきを得てから、改めて自分に合う環境を探す方が、納得のいくキャリアを築ける可能性は高まる。
「どこで働くか」より「どう働くか」を重視する視点
企業ブランドや知名度、待遇条件といった要素は就活では大きく取り上げられるが、入社後にその価値が薄れることは多い。結局は、日々の仕事内容や人間関係、自分がやりたいことに近づける感覚こそが、満足度に直結する。
そのためには、「どの会社か」だけではなく、「その会社でどう働くか」「どんな役割で力を発揮できるか」を意識する必要がある。自分に合った“働き方の型”を知ることが、キャリアの選択肢を広げる鍵となる。
まとめ:就活の延長にある“現実”と向き合うために
新卒就活は、多くの学生にとって「人生で最も努力した経験」となる。しかし、内定がゴールではなく、入社後の現実こそが本当のスタートであるという事実を受け止めることが重要である。
どれだけ慎重に企業研究をしても、実際に働いてみなければわからないことが多く、「入社して初めて見える真実」に戸惑うのは当然のことだ。
だが、違和感や葛藤に直面したときこそ、自分の価値観やキャリアの軸を再確認するチャンスでもある。配属や人間関係、業務内容、評価制度――すべてが思い通りにいくことはないが、「どう感じたか」「どう動くか」を自分の手で選び続けることで、納得感のあるキャリアは作れる。
就活という限られた期間では見えなかった“仕事のホンネ”と向き合い、自分自身の働き方を見つめ直す視点を持てるかどうかが、社会人一年目を充実させる鍵となる。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます