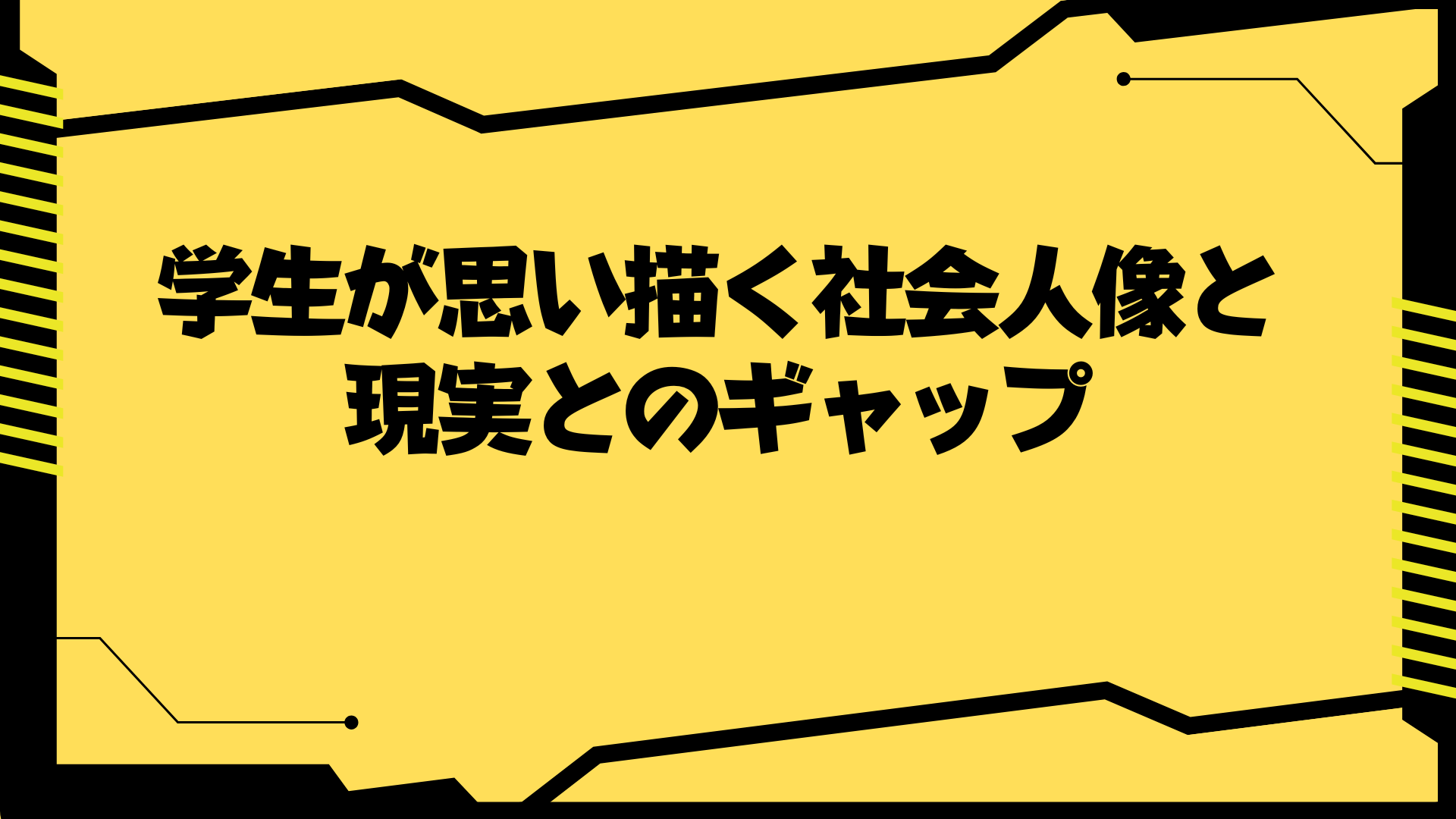「社会人ってなんとなく忙しそう」では就活に活かせない
抽象的なイメージだけで仕事を選ぶ危険
多くの学生は、社会人の生活を具体的に想像できないまま就活を始めている。「スーツを着て出社して、なんとなく忙しく働いている」「土日は休めるっぽい」「会社の飲み会って大変そう」──その程度の印象で企業を選び、面接を受け、内定を得てしまう人も少なくない。
だが、就活において最も重要なのは、自分が納得して入社できる企業を選ぶことだ。納得するには、仕事内容や待遇だけでなく、「働き方」や「日常の風景」をある程度理解しておく必要がある。たとえば、出社時間や退勤時間、昼休みの過ごし方、会議の頻度、上司との距離感、チームでの動き方など、リアルな労働環境を知らないと、本当の意味で「この会社に行きたい」とは言えない。
社会人の実態を知らずに就職先を決めることは、住んだことのない街に引っ越すのに、現地を一度も見に行かないようなものだ。自分に合うかどうか判断しないまま決めてしまえば、後悔につながるリスクが高い。
実際に働いている人たちの声は貴重な情報源
では、どうすればリアルを知ることができるのか。それは、実際に働いている社会人に話を聞くことに尽きる。企業の採用ページやパンフレットには、「やりがい」「成長」「働きやすさ」などの前向きな表現ばかりが並んでいるが、それだけでは本当の姿は見えない。
たとえば、パンフレットに「若手が活躍中!」と書かれていても、実際は「新人でも責任が重く、プレッシャーが大きい」という意味かもしれないし、「チームで支え合う社風」と言われても、実態は「個人に任される比重が大きい」というケースもある。実際の社員がどんな1日を過ごし、何に悩み、何を喜びとして働いているか──こうした一次情報が、判断の軸になる。
OB訪問やオンラインインタビュー、SNS上での交流、社員登壇イベントなど、学生と社会人をつなぐ場は少なくない。表面的な言葉ではなく、実態を知るための問いをぶつけることが、就活の質を上げるための第一歩となる。
社会人の“1日”を知ると見えてくるもの
「定時退社」は職種と業務内容で大きく異なる
たとえば「定時退社が可能な会社かどうか」は、就活生が気にする項目のひとつだが、この「定時」という言葉は職種によってまったく意味が異なる。営業職なら、外回りのあとに事務処理があることも多く、帰社後に提案資料をまとめているうちに19時、20時になることもある。一方で、開発職や事務職では、タスクが明確に分かれており、ルーティン化されている業務も多いため、比較的定時退社がしやすい傾向もある。
重要なのは、「会社が定時退社をうたっているか」ではなく、その職種・部門で定時に帰ることができる体制や文化があるかどうかである。また、「定時退社できる=楽」ではなく、「仕事の密度が高く、短時間で成果を求められる」パターンもある。単に早く帰れるかどうかではなく、「どのような働き方が自分に合っているか」を見極める視点が必要だ。
上司との関係性や人間関係は“見えないけど大きな影響”
就活生が見落としがちな要素の一つが、「社内の人間関係のリアル」だ。説明会では「風通しのよい職場」「上下関係がフラット」などの言葉が飛び交うが、実態は千差万別である。上司との距離感、年功序列の有無、年次を超えた相談のしやすさなど、その職場の空気感や文化は、外から見てもなかなか分からない。
だが、実際に働き始めてからストレスになるのは、「業務量」よりも「人間関係」が多いというのが現実だ。自分の意見を言える雰囲気があるのか、理不尽な叱責があるのか、同僚と協力しやすい風土なのか──。こうしたリアルを把握するには、社員インタビュー記事や口コミサイトの信頼できる投稿、社員が匿名で語るSNSなどを総合的に見ていくしかない。
「思っていた社会人と違う」による早期離職の実態
入社前の期待と、入社後の現実に悩む若手社員
多くの若手社会人が共通して語るのが、「想像していた社会人生活と、実際の毎日が違っていた」という感覚だ。仕事の裁量が大きく自由な働き方ができると思っていたら、細かい指示に従わなければならないケースもある。逆に、指示待ちでは仕事が進まない環境に戸惑うこともある。
また、チームで支え合う職場を期待していたのに、実際は個人での成果を強く求められ、孤独感を感じることもある。これらのギャップは、事前の情報収集が不十分で、企業のリアルな姿を知らなかったことに起因している。
結果として、3年以内に離職する新卒社員は3割を超えており、その多くが「人間関係」「仕事のイメージとのズレ」「評価制度に対する不満」など、リアルに起因した理由で退職している。
就活で「社会人のリアル」に近づくための情報源とは?
就活における情報の“偏り”を自覚しよう
企業が発信する情報は“広報的”である
企業説明会や公式サイト、パンフレットなどで得られる情報は、基本的に「魅力を伝えるためのもの」である。これは当然のことであり、悪いことではない。だが、その情報が企業の本質すべてを語っているわけではないという視点を持たなければならない。
たとえば、「自由な社風」と謳っていても、上司の許可なしではメール一通も送れない職場もあるし、「若手が活躍」と言いながら、実際には経験者ばかりが評価される環境である可能性もある。情報発信の多くは企業のブランディングであり、学生の目にどう映るかを計算して作られている。
したがって、就活生側は「これは広報的表現かもしれない」という疑いの視点を持ち、それを裏付ける一次情報を集めていく必要がある。広報情報は“入口”として活用し、本質に近づく努力を重ねることが不可欠だ。
「リアル」を得るには多面的なアプローチが必要
真の企業理解に近づくには、一つの情報源だけに頼るのではなく、複数のチャネルから集める必要がある。以下に、その代表的な情報源を挙げてみる:
社員インタビュー記事(メディア・公式noteなど)
YouTubeやTikTokにある社員の日常紹介動画
Twitter(X)やInstagramでの社員の投稿
口コミサイト(Vorkers、OpenWorkなど)
OB・OG訪問やリファラル面談
オンラインイベントでの社員との交流
重要なのは、「どの立場の人が」「どんな意図で」「どの媒体で語っているか」を見極めることだ。匿名性が高い情報ほど本音が出やすいが、その分偏っているリスクもある。逆に、公の場で語られている話はポジティブに寄りやすいが、企業文化の方向性をつかむ手がかりにもなる。
SNSや口コミは“使い方”次第で武器になる
SNSは「会社ではなく人」を見るためのツール
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでは、社員が日々の仕事についてポロッとつぶやいていることがある。たとえば、「今日は会議3本、資料づくり4本、終電で帰宅…」といった投稿からは、その部署の忙しさや雰囲気がにじみ出る。
また、「#社会人1年目」「#営業職の日常」「#今日のランチ」などのタグで検索すると、業種別・職種別にリアルな働き方を垣間見ることができる。企業アカウントではなく“人のアカウント”を探しにいくことがコツだ。
もちろん、SNSには個人の主観が大きく反映されているため、信頼性やバイアスには注意が必要だが、「どんな環境でどんなテンションで働いているか」という雰囲気を知るには非常に有効な手段である。
口コミサイトを見るときの3つのポイント
OpenWorkや転職会議などの口コミサイトには、在職者・退職者の率直な評価が多く寄せられている。すべてを鵜呑みにするのは危険だが、「どこに不満を持っている社員が多いか」「評価されている制度は何か」といった傾向を読み取るには非常に有効である。
閲覧時のポイントは以下の3点:
時期を見る:3年前と直近では、体制や人事制度が変わっている場合がある。
職種・部署を見る:同じ企業でも、営業と開発、現場と本社では働き方が全く異なる。
ポジティブ・ネガティブの両面を見る:どちらかに偏った印象ではなく、複数の角度から読む。
口コミサイトを通じて“社員目線のリアル”を知ることで、自分の価値観と合うかどうかの判断材料にすることができる。
OB・OG訪問や社員登壇イベントの“聞き方”が重要
表面的な質問では深い答えは得られない
OB・OG訪問や就活イベントで現役社員と話す機会があっても、「その会社を志望した理由は?」「やりがいは何ですか?」という“テンプレ質問”では、得られる情報もまたテンプレになってしまう。
リアルを知るためには、より具体的で、答えに個人差が出るような質問が必要になる。たとえば:
「今週の1日で一番しんどかった時間帯って、どんなときでしたか?」
「実際に入ってみて、“これは予想外だったな”と思ったことは?」
「3年目の社員が多く辞めてると聞いたのですが、社内でどう捉えられてますか?」
こうした質問は、一見すると失礼にも思えるかもしれないが、「企業選びで後悔しないために、どうしてもリアルを知っておきたい」という姿勢で伝えれば、誠実な受け止め方をしてもらえることが多い。むしろ、その本音をぶつけられることが、面接官や社員の記憶に残ることすらある。
「1人の意見」として受け止め、複数人から集める
注意点としては、1人の社会人の話を“すべて”だと誤解しないこと。その人の配属先、上司、タイミングによって感じることは全く異なるからだ。理想は、同じ会社でも複数人から話を聞くこと。可能であれば異なる職種や年次の社員にアプローチし、「立場の違いによる見え方の差」を把握することが、企業の実態を立体的にとらえる手がかりになる。
社会人になってから気づく“就活で見落としていた視点”
就活で評価された強みが、必ずしも武器になるとは限らない
「コミュニケーション力」は万能ではない
就活では「コミュニケーション力」が重宝される。面接でもグループディスカッションでも、明るく話せる人が評価されがちだ。だが、実際の社会人生活では、“話せること”と“仕事ができること”はイコールではない。むしろ、的確に報告・相談・連絡ができるか、顧客や上司のニーズを正確に理解し資料に反映できるかといった、目的に基づいた伝達力が問われる。
面接で「明るく元気」で通った学生が、入社後に“雑談はできるけど実務が抜けている”と指摘されるケースは珍しくない。逆に、「話し下手でもロジックが整理できる人」は評価されていく。就活で通用する「人当たりの良さ」は、社会人では“最低限の土台”にすぎないこともあるのだ。
「チームで頑張った経験」より“結果責任”の重み
学生時代のチーム経験では、仲間と協力したこと、達成感を得たことなどが重視される。一方、社会人では「最終的に誰が責任を持つのか」がはっきりしている。チームでの成功でも、結果の責任をどこまで引き受けたかが問われる。
入社後に「先輩と一緒にやったプロジェクトなのに、自分だけが顧客から怒られた」と驚く新人は多い。仕事では“誰がやったか”より“誰の名前で出しているか”が重視される。これは就活のガクチカで重視される「過程」ではなく、ビジネスにおける「責任構造」の違いだ。
就活時に「見せかけの良さ」に惹かれてしまう理由
表面的な“福利厚生の充実”に惑わされやすい
「在宅制度あり」「カフェスペース完備」「年間休日125日」など、福利厚生の言葉は魅力的に映る。だが、制度が“ある”ことと“使える”ことはまったく別の話だ。
たとえば、「有給取得率90%」と記載があっても、実態は“特定部署だけが取得しやすい”ケースもあるし、「在宅制度あり」と書かれていても“上司の許可制で実質使えない”企業もある。制度の文字面に惹かれるのではなく、誰が、どういう環境で活用しているのかまで確認しなければならない。
学生目線では、「制度=安心」と思ってしまいがちだが、その制度が活きるかどうかは、風土と運用次第であることを見落としてはいけない。
「かっこよさ」や「大手ブランド」に引っ張られる心理
「業界大手」「知名度がある」「親や友人に言いやすい」などの理由で企業を選ぶ学生も多い。だが、入社後に感じるのは、「どんなブランドでも、自分がやるのは地味な作業の連続だった」という現実だ。
ブランドや社名は、学生のうちしか効果を発揮しない。社会人になると、どの部署で何をやっているか、誰と仕事しているか、どれだけ自分が成長できているかといった要素のほうが、幸福感や納得感を左右するようになる。
つまり、他人がうらやむ就職先=自分にとって良い職場とは限らない。このギャップは、多くの若手社員が「就活時に見落としていた」と振り返るポイントである。
「働き方の自由」や「裁量」は、年次や職種で異なる
自由度のある働き方は“即座に得られる”わけではない
「裁量が大きい」「自由な働き方」などに惹かれて企業を選んだものの、入社1年目は電話対応と資料整理ばかり…という現実に戸惑う新卒は少なくない。
実際、自由な働き方は信用と経験を積んだ先にあるものであり、最初から全ての新人に与えられるわけではない。もちろん、社風や部署によって差はあるが、「新卒1年目から大きな裁量で自由に働ける」会社はごく一部である。
誤解してはいけないのは、「裁量がある会社=放任主義」ではないこと。むしろ、きちんとした育成やフォロー体制があったうえで、徐々に裁量が渡されていくのが理想だ。“自由”という言葉の裏に、どれだけの責任と準備があるのかを読み解く視点が必要だ。
同じ企業でも、職種ごとに全く異なる世界
総合職と一般職、営業と技術、現場と本社。こうした違いで、同じ企業に属していても、働く環境・評価基準・キャリアパスは大きく異なる。
たとえば、「若手が活躍」と書かれていても、それは営業職に限った話で、開発部門はベテランしか意思決定できない場合もある。就活では「企業単位」で見てしまいがちだが、実際のリアルは「職種単位」「部署単位」でまったく異なる世界が広がっていることを忘れてはならない。
情報収集では、「自分が希望する職種・勤務地・配属先」にフォーカスして話を聞くことが、現実とのズレを防ぐ鍵となる。
理想と現実を埋める“選び方と心構え”
「完璧な企業」を探すのではなく「許容できる欠点」を探す視点
ミスマッチの原因は「理想像の固定化」にある
多くの学生が「成長できる」「人間関係が良い」「働きやすい」「やりがいがある」など、ポジティブな条件ばかりを挙げて企業を探そうとする。だが、現実にはそれら全てを兼ね備えた企業はほとんど存在しない。「どこに重きを置くか」「何を妥協できるか」のバランスこそが、納得のいく選択に直結する。
たとえば、スピード感ある成長を望めば、厳しい評価や成果主義の文化と向き合う必要があるかもしれない。福利厚生や制度が整った企業に入れば、挑戦機会が限定されることもある。就活とは“自分が納得できる不完全さ”を受け入れるプロセスでもある。
「自分にとっての理想とは何か?」だけでなく、「自分が許容できる現実とは何か?」を軸にした選び方にシフトすることで、就職後の満足度や定着率は確実に高まる。
「嫌なことを避ける」視点のほうがリアルを見抜ける
理想を追い求めるより、むしろ「自分が耐えられない環境はどんなものか」を明確にしたほうが選択の精度は高まる。たとえば、「体育会系ノリが苦手」「細かいマニュアル仕事がストレス」「一人で黙々と作業するのは退屈」といった感覚は、就活ではあまり表に出されないが、実際に入社後の離職理由として頻出する要素でもある。
「絶対に嫌だと感じる環境」を先に潰しておけば、残る選択肢には一定の納得感が生まれる。自分の弱さや苦手さを直視することは勇気がいるが、それこそが現実に向き合う第一歩となる。
就活を「ゴール」ではなく「社会人準備のスタート」と捉える
内定獲得は“勝ち負け”ではない
就活中はどうしても「内定の数」や「企業の知名度」で比較されがちになる。だが、入社後に待っているのは誰もがゼロからのスタートラインであり、過去の肩書きや選考の成績は意味をなさない。
入社後に急速に成長する人もいれば、内定時点で目立っていた人が苦しむこともある。「就活で勝ったからといって、社会人でも活躍できる保証はない」。これは多くの若手社員が実感しているリアルな真実だ。
本当に大事なのは「自分がどんな状態でスタートするか」よりも、「スタートしてからどう進むか」である。その観点を持つだけで、就活のプレッシャーや周囲との比較から、少しずつ自分を解放できる。
「選ばれること」より「選ぶ力」を育てる
就活ではどうしても企業から“選ばれる”ことばかりに意識が向きがちだが、本質的には「自分がどんな環境を選ぶか」がキャリア形成においてはるかに重要だ。
目の前の選考に一喜一憂するのではなく、「この企業の環境で自分は成長できるか」「この会社の価値観は、自分に合っているか」という視点で考える習慣を身につけよう。企業を“評価される相手”ではなく、“共に働く相手”として見る姿勢が、ミスマッチを減らす最大のカギになる。
そのためには、自己分析の質も重要だ。自己理解が浅いと、企業との比較軸があいまいになり、ただなんとなく内定を目指す就活になってしまう。自分の価値観や行動パターンを深掘りすることで、“選べる人材”へと近づいていく。
リアルに向き合ったからこそ得られる「長期視点の安心感」
自分の選択に納得できる人は、多少の困難にも折れない
「企業を知った上で選んだ」「リスクも理解して入社した」人と、「ブランドやイメージだけで決めた」人では、入社後の耐性や行動力に明確な差が出る。
たとえば、新人時代に上司とそりが合わなかったり、希望通りの業務に就けなかったとしても、自分の意思で選んだ実感がある人は、粘り強く乗り越えようとする傾向がある。反対に、他人基準で選んだ人は、「こんなはずじゃなかった」と早期に離職してしまうケースが多い。
リアルを受け止めたうえで納得して決めた選択は、たとえ理想通りにいかなくても、後悔の少ないキャリアを築く基盤となる。
「どこで働くか」より「どう働くか」へと軸が変わる
社会人になると、徐々に「会社がすべてではない」と感じるようになる。重要なのは、その会社で自分がどんな役割を担い、どう成長していくかという“自分軸”だ。
これは、どの会社を選んでも当てはまる普遍的な真実である。つまり、どんなに有名企業に入っても、自分の意志や行動が弱ければ成長は鈍るし、逆に無名企業であっても、自分なりに価値を見出せれば確かなキャリアにつながっていく。
だからこそ、「理想の企業を探す就活」ではなく、「どんな状況でも前を向ける力を育てる就活」に変えていくことが、最終的に納得できるキャリア選択へとつながるのだ。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます