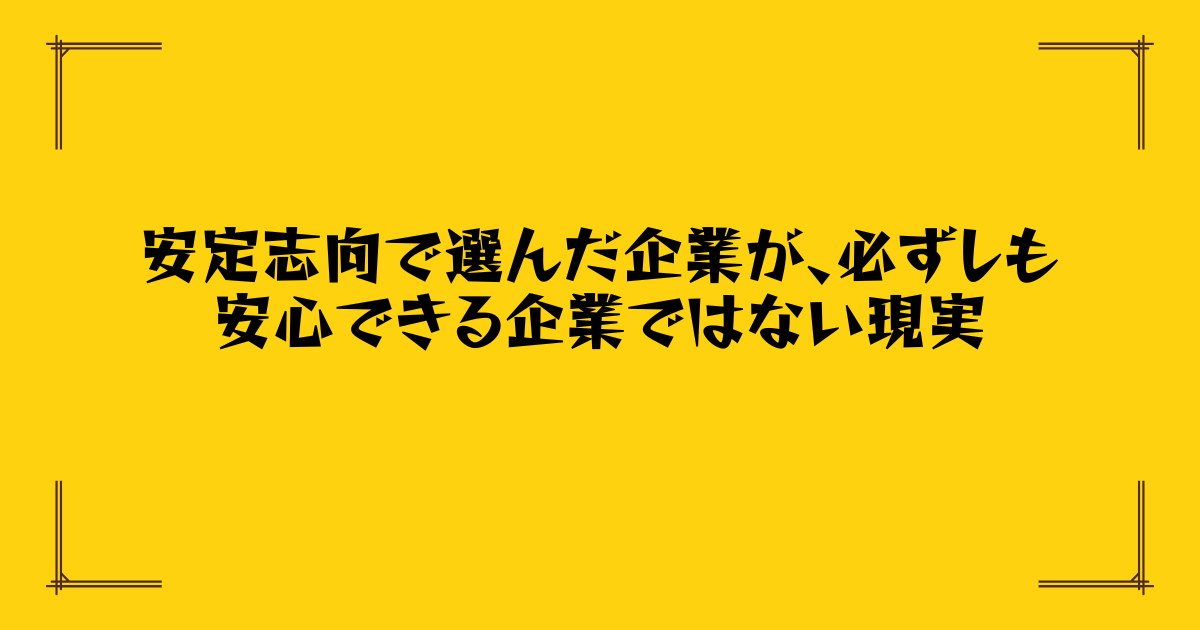「安定=大手・公務員・インフラ」志向の就活が生まれる背景
学生の大半が“失敗しない”選択を優先する理由
就活を始めたばかりの学生の多くは、まず「安定した企業に行きたい」と口にする。これは決して間違っていないが、その“安定”の定義が曖昧なまま、なんとなく大手や公務員、インフラ業界を選んでいるケースが目立つ。
背景にあるのは、「就活で失敗したくない」という思いだ。自分の将来をまだ具体的に描けない段階で、親や周囲の大人から「潰れない会社」「年功序列で安心」「福利厚生がいい」といった言葉を聞けば、「大手=正解」と考えるのは当然である。
さらにSNSや口コミサイトなどで「○○商事に内定!」という報告を見ると、「自分もそこに行けば間違いない」と思い込んでしまう。だがその選択が、本当に自分に合っているのかを吟味しないまま就職先を選ぶと、入社後にギャップに苦しむリスクが高まる。
「大手病」にかかると、自分の“軸”を失う
特に、大学名や成績に自信がある学生ほど「自分は大手に行ける」という思い込みがある。もちろん能力が高いことは悪くないが、それが過信につながり、「ベンチャーや中堅企業は受けない」という“選り好み”に変化していく。
結果として、大手企業の人気職種に応募が集中し、倍率数百倍のレッドオーシャンに突入する。ESで落とされ、面接で落とされ、自信を失ったときにはもう選考は終盤。残された企業には興味を持てず、焦りと妥協で入社を決めてしまうという流れが多発する。
「安定」を求めて就職した結果、3年以内に辞める人が多い理由
「思っていた仕事と違った」は“情報不足”だけが原因ではない
新卒入社後3年以内に約3割が離職すると言われるが、その大半が「仕事内容にギャップがあった」「職場の雰囲気が合わなかった」といった理由を挙げている。
ここで見落とされがちなのが、「安定志向で企業を選んだ学生ほど、このギャップに弱い」という点だ。そもそも“安定=つまらない仕事でも我慢できる”と誤解して入社した学生は、想像以上に仕事の変化が少なかったり、キャリアの展望が見えなかったときに、早期離職を選びやすい。
「大手でホワイトと聞いたのに、なぜこんなにつまらないのか?」
「上司は優しいけど、何年も同じ作業しかしていない…」
こうした不満は、“安定”の代償として受け入れるべきものかもしれないが、想像と現実の落差が大きすぎると耐えきれなくなる。
安定志向が「受け身のキャリア」に陥らせる
安定志向で企業を選んだ学生の多くは、「入社さえすれば後は何とかなる」という考えになりがちだ。しかし、現実はそう甘くない。終身雇用が崩れつつある今、企業も“自己成長する人材”を求めており、受け身のままでは評価されない。
例えば、ある大手メーカーに入社した学生が、5年間同じ部署で淡々と作業をこなした結果、評価も上がらず、転職市場でも「何をしていた人か分からない」と見なされてしまったケースがある。
このように、「安定」に頼りすぎたキャリアは、“市場価値のない人材”に転落するリスクを秘めている。それは表面的な「安定」と引き換えに、将来の選択肢を手放す行為とも言える。
「安定志向」の落とし穴を回避するために考えるべき視点
「変化に耐えられること」が新しい“安定”
今の時代、技術革新や社会構造の変化が速く、企業自体の寿命も短くなっている。10年前に安定と言われた企業が、今や業績悪化で希望退職を募っているような例も珍しくない。
つまり、「変化に柔軟に対応できるスキルを持っていること」こそが本当の安定だと捉えるべきだ。新しい環境に適応し、自分の力でキャリアを作り直せる人材は、どこへ行っても生きていける。
「今の安定」ではなく、「将来の不安定を生き抜く力」にこそ目を向けるべきだ。
安定志向そのものを否定する必要はない
もちろん、安定した生活や環境を求める気持ちは悪ではない。大切なのは、その“安定”をどう定義するか、そしてそれが自分にとっての納得感を伴っているかである。
親に安心してもらいたい、結婚や住宅のことを考えたい、そうした価値観は真っ当だ。しかし、それが理由で「自分の可能性や挑戦を最初から捨てる」必要はない。
“自分にとっての安定”とは何か?
“環境に依存しない安心感”をどう身につけるか?
この問いから逃げずに向き合うことが、就活の本質に近づく第一歩となる。
「安定企業」ほど人を選ぶ現実と、就活生が知らない“内情”
見かけの“安定”と中身の現実は全く違う
「年功序列」「終身雇用」「のんびり働ける」は過去の話
就活生が思い描く「安定した会社」のイメージには、たいてい次のようなキーワードが含まれている。
年功序列で昇進
一度入れば一生安泰
無理なノルマがなく、定時退社ができる
リストラされることがない
こうしたイメージをもとに企業を選ぶ学生は少なくない。しかし、実際に「安定企業」とされる大手企業に入社した先輩たちのリアルな声に耳を傾けると、そのギャップに驚かされる。
たとえば、地方銀行に入社した学生は「安定だと思っていたのに、数年後には店舗統廃合で異動が連発。成果主義も強まって、数字に追われる日々」と語る。かつての「のんびり働ける銀行員」というイメージは崩壊しており、“安定”とは名ばかりの実力主義社会に変貌しつつある。
また、インフラ企業に入ったものの、社内の序列が厳しく、「若手が提案してもまず通らない」「仕事にやりがいを見いだせない」と感じて転職を考える人もいる。組織の硬直性が“安定”の代償になっているのだ。
安定企業は、むしろ選考がシビアで入り口が狭い
安定志向が生む“偏差値就活”のワナ
「どうせなら倒産しない会社に行きたい」「名の知れた会社に行きたい」と思って大手ばかり受ける人は多いが、それゆえに応募者が殺到する。つまり、安定企業ほど、最も入るのが難しいという現実がある。
たとえば、誰もが知る食品メーカーやテレビ局、鉄道会社などは、新卒採用において数百~数千倍の倍率を誇る。学歴・学部・経験・話し方など、あらゆる要素で精査され、ちょっとでも“平均的”だと判断されれば容赦なく落とされる。
「特別に悪くはないのに、どこも通らない」という人は、「平均的であること」が最大のリスクになる。つまり、「落ちないために安定企業を狙った就活」が、「どこにも受からない就活」に変わってしまうという矛盾が生まれる。
「無個性な人」が最も評価されない
安定志向に陥ると、志望動機や自己PRも没個性的になりがちだ。「御社の安定した経営基盤に惹かれました」「福利厚生が充実していて長く働ける環境に魅力を感じました」というフレーズは、どこかで聞いたことのある言葉で埋め尽くされている。
採用側からすれば、「自社にしかない特徴に気づいていない」「誰でも同じように言うことを言っている」と感じてしまい、選考に残らない。その結果、「大手しか受けていないのにどこにも受からない」「中小を受けるにも乗り気になれない」という就活の迷子が生まれてしまう。
「やりたいことがない学生」が安定志向に逃げる理由とその代償
「やりたいことがわからない」は普通。でも…
就活の初期段階で、「やりたいことがまだ見つからない」と悩む学生は多い。むしろ、それが自然なことであり、キャリアをスタートする段階で明確な夢や志があるほうが少数派だ。
しかし問題なのは、やりたいことが分からないから、とりあえず安定していそうな企業を受けるという発想である。「興味が湧く仕事はない。でも失敗したくない」という気持ちが、思考を停止させてしまう。
その結果、“誰でも知っている企業”を選び、“誰でも言えそうな志望動機”を語り、“誰でも落とされる”という流れに陥る。本人としては慎重に動いているつもりでも、実際には最もリスキーな道を選んでいる可能性がある。
自分を見つめない就活は「不安定な安定」を生む
安定志向は、「考えないで済む就活」にしてしまう。一見、合理的に見えても、自分の特性や価値観、働く意味に向き合わずに進めた就活は、入社後のミスマッチを引き起こしやすい。
結果的に、「安定している会社に入れたのに不満だらけ」「想像していた働き方と違った」「やりがいを感じられない」といった不安定な状態に陥ってしまう。これは皮肉なことに、安定を求めたはずの就活が、一番不安定な働き方に繋がっているという現実である。
安定志向を否定せず、「戦略」として活かすためには
「安定した企業でも、自分の視点で選ぶ」姿勢を持つ
大手・安定企業に行くこと自体が悪いわけではない。ただし、「自分にとって意味のある理由があるかどうか」が重要だ。周囲に流されて選ぶのではなく、自分の強みや価値観と照らし合わせて「この会社は自分に合っている」と言える理由を持てるかがカギとなる。
たとえば、安定した物流会社に惹かれたとしても、「モノが人に届く価値を支えたい」という具体的な関心があるなら説得力がある。一方、「安定してそうだから」というだけでは、面接で深掘りされたときに苦しくなる。
「安定と挑戦のバランス」を就活軸に持つ
就活では、安定と挑戦のどちらかを極端に選ぶのではなく、自分なりのバランスを見つけることが必要である。たとえば、「福利厚生がしっかりしていて、かつ新規事業に関われる企業」や、「業界的には安定しているが、職種としては裁量が大きい企業」などがある。
このように、安定だけを軸にするのではなく、「成長できるか」「自分らしく働けるか」「将来の市場価値が高まるか」といった視点を持つことで、就活の視野は一気に広がる。
「安定している会社に入れば将来も安泰」という思い込みの危うさ
安定企業でも辞める人は後を絶たない
入社後に見える“安定”の落とし穴
「安定しているからこの会社を選んだ」という学生が、3年以内に辞めていくケースは決して珍しくない。内閣府や厚生労働省の調査でも、大企業に入ったからといって離職率が著しく低いわけではなく、「ネームバリューのある企業=定着率が高い」とは限らないことが分かっている。
実際、名の通った企業に入社しても「想像していた働き方と違った」「上下関係が厳しすぎた」「意見が言えない社風だった」「異動が多くてキャリアが描けない」などの理由で早期退職する人が多い。これは、「安定=働きやすい」「安定=安心」といった先入観が裏切られた結果である。
特に新卒で入った最初の会社でこうしたミスマッチが起こると、自信を失ってしまうだけでなく、次のキャリア形成にも悪影響を及ぼす。このように、安定志向は“保守的”な選択のように見えて、実は“リスクの高い賭け”になってしまうこともある。
安定しているのは“企業”であって“自分”ではない
多くの就活生が混同してしまうのが、「安定した企業に入れば、自分も安定できる」という思い込みである。しかし、実際はどれほど大きな会社に入っても、“個人としての安定”が得られるとは限らない。
たとえば、経営が盤石なインフラ企業に入っても、社内の評価制度に合わなければ昇進できず、やりたい仕事にも就けない。あるいは、事業再編によって希望しない部署に異動させられたり、地方転勤が続いたりするケースもある。
つまり、企業の安定性はあくまで“組織としての話”であり、自分のキャリアが安定するかどうかは別問題である。にもかかわらず、その違いに気づかず就職活動を進めてしまうと、入社後のギャップに苦しむことになる。
安定志向がもたらす「視野の狭さ」が、就活を失敗させる
知らない業界・職種に目を向けられない
安定志向に陥ると、自然と選ぶ企業が偏ってくる。「誰でも知っている会社」「CMで見たことがある業界」「親が知っている企業」など、知名度やイメージに頼った企業選びになりがちだ。
この結果、本来であれば自分に合っていたはずの中堅企業やベンチャー企業、成長中のニッチ業界などに気づくことができず、狭い選択肢の中で不毛な競争に巻き込まれることになる。
たとえば、ITエンジニア職やSaaS業界、物流テック、地方創生系の企業などは、知名度こそ高くないが、将来性があり、若手の裁量も大きく、働き方も柔軟であるケースが多い。にもかかわらず、「安定っぽくないから」とスルーしてしまうのは、極めてもったいない。
“知っている=安心”という錯覚が、情報収集を止める
就活においては、“知らない企業・知らない職種”にどれだけ踏み込めるかが差になる。ところが、安定志向の人は、知っている企業ばかりを見てしまい、選考に進む前の段階で視野が狭くなる。
特に、「大手企業の合同説明会しか行かない」「就活ナビサイトの上位表示企業しかチェックしない」という姿勢では、情報が偏り、自分にとって最適な会社を見つけることが困難になる。
これは言い換えれば、「無知なまま就活を終えるリスク」を抱えるということ。本人が気づかないうちに、チャンスの扉を自分で閉じてしまっているのだ。
安定よりも「成長できる場所」を探すという考え方
若手が成長できる環境こそ、長期的には“安定”につながる
就活生が本当に考えるべき“安定”とは、「会社の業績が安定しているか」ではなく、「自分が将来的にどこでも通用するスキルや経験を積めるか」である。
たとえば、スタートアップや中小企業でも、若手に裁量を与え、プロジェクトの立ち上げや意思決定に関与できる企業も多い。こうした経験は、将来の転職や独立、社内昇進にも活きてくる。
一方で、大企業の歯車のような仕事に3年5年と従事していても、「会社がなくなったら何も残らない」「スキルが身につかない」という不安を抱える人もいる。そう考えると、「安定企業に入ること」が目的化してしまうのではなく、「市場価値を上げられる環境に入ること」こそが、個人にとっての安定なのだ。
成長の実感がある就活こそが納得感につながる
また、成長環境に身を置くと、毎日が刺激的で、自分の変化や進化を実感できる。これは働くモチベーションにもつながり、仕事への納得感も高まる。
就活生にありがちなのは、「将来が不安だから、とにかく安定したところに入りたい」という“守りの就活”。だが、実際に働き始めてから満足度が高いのは、「この会社で成長できる」「この仕事を通じて価値が生まれている」と感じられる“攻めの就活”をした人たちである。
「守りの安定」よりも、「攻めの納得」。この考え方が、結果的に自分の将来を守ってくれるという逆説的な事実がある。
就活生が見落としがちな「真の安定」の定義とは
本当に安定したキャリアとは、自分で人生をコントロールできること
本当の意味で“安定した社会人生活”とは、「会社が潰れない」ことではない。むしろ、「いつでも転職できるスキルがある」「自分の意思で職場を選べる」「働き方を選択できる自由がある」状態こそが、真の安定といえる。
つまり、企業に“守ってもらう”という発想ではなく、「自分でキャリアを築ける状態になる」ことが、最も安定した人生につながる。これは今の若者にとって非常に重要な価値観であり、20代のキャリアの歩み方によって大きく差が生まれるポイントだ。
「変化に対応できる力」を養える場所を選ぶ
社会の変化が激しい今、終身雇用や年功序列といった制度は崩壊しつつある。これからの時代に求められるのは、「変化に対応できる人材」であり、それを育ててくれる環境である。
だからこそ、企業を見るときは「今の安定」だけでなく、「将来への適応力がつくかどうか」という観点で見極める必要がある。たとえば、「自分で考えて動く仕事ができる」「複数の部署や職種にチャレンジできる」「社外との接点が多い」など、変化を経験できる環境は強い。
安定企業を目指すこと自体は否定しない。ただし、それを盲目的に信じすぎることなく、「自分にとっての安定とは何か?」を一度立ち止まって考えることが、就活成功のカギとなる。
「安定」にとらわれず、自分にとっての“納得できる選択”をするために
他人基準の「正解」ではなく、自分基準の「納得」で選ぶ
「安定していそう」「世間的に良さそう」は、自分の幸せとは違う
就職活動中、つい耳にするのが「ここの会社は安定しているからいいね」「親も安心してくれる」「誰でも知ってる会社なら安心」という言葉。たしかに社会的な評価が高い企業に入ることは、第三者的には“成功”のように見える。
しかし、他人からの評価と自分の幸福度は別問題だ。親や周囲が良いと思う会社に入っても、自分にとってやりたい仕事ができなかったり、働き方が合わなかったりすれば、結局苦しくなるのは自分自身。
納得できる就職を実現するためには、「どんな環境なら自分は心地よく働けるか」「どんな働き方に満足できるか」を自分の基準で言語化し、それに沿って企業を選ぶことが不可欠だ。
「安定=リスクがない」は幻想
世の中には「安定している会社に入れば、人生が保証される」と信じている人もいる。しかし、社会は変わり続けている。たとえば、10年前に「絶対に潰れない」と言われていた企業が経営危機に陥る例は枚挙にいとまがない。
どれだけ業界で安定していても、AIやテクノロジーの発展、人口動態の変化、政策の転換などでビジネスモデルが通用しなくなることはある。つまり、「企業の安定性に自分の人生を丸ごと預ける」という考え方こそが最も危険なのだ。
リスクをゼロにすることはできない。だからこそ、「変化しても対応できる力を持った人材になること」こそが、最大のリスクヘッジになるという価値観にシフトするべきだ。
自分の「軸」を言語化し、企業を見る目を持つ
就活の軸を「安定」以外で掘り下げてみる
就活で失敗しないためには、「安定しているから」ではなく、「この会社ではどんな経験が積めるか」「この仕事を通じて自分はどう成長できるか」といった軸で企業を見る必要がある。
そのためには、まず自分が何を大切にしたいのか、どんな価値観で働きたいのかを深掘りすることが欠かせない。以下のような問いを自分に投げかけてみると良い:
成長を実感できるのはどんな瞬間か?
どんな人たちと働くのが楽しいと感じるか?
長期的にどんなスキルを身につけたいか?
働き方における優先順位(時間・場所・裁量など)は?
これらの答えが出てくると、「自分はこういう環境でなら本領を発揮できる」という仮説が立てられ、その仮説に合う企業を探すことで納得感のある選択ができる。
自分が活躍できそうな“土壌”を探す
企業のブランドやネームバリューに惹かれるのは自然なことだが、本当に見るべきは、自分の個性や能力が活きる“土壌”がその会社にあるかどうかである。
たとえば、成果主義が強い社風の中でプレッシャーに燃える人もいれば、じっくり育成してくれる環境で力を伸ばす人もいる。どちらが良い悪いではなく、自分に合っているかどうかが全てだ。
就活では、「企業に入ってから頑張る」ではなく、「最初から頑張りやすい環境を選ぶ」ことがとても大切。だからこそ、自分にとっての“働きやすさ”を言語化する準備が必要になる。
就活を“将来のキャリア設計”として考える
「最初の会社がすべて」ではないが、「最初の会社の影響は大きい」
近年は転職が一般化しており、「最初の会社がすべてではない」という考え方も浸透している。ただし、最初の会社でどんな経験を積むかは、その後のキャリアの土台に強く影響することを忘れてはいけない。
たとえば、若手時代に自分の裁量で業務を進めた経験がある人と、マニュアル通りにしか動けない環境で育った人では、3年後のスキルにも差が出る。また、幅広い仕事に触れた人と、狭い業務しか経験していない人とでは、転職市場での評価にも差がつく。
「どんな会社に入るか」ではなく、「どんな経験を積める会社を選ぶか」。これがキャリア設計としての就職活動を成功させるカギだ。
キャリアの“起点”として、どこを選ぶかを戦略的に考える
安定志向で企業を選ぶと、戦略性のない“安心感だけの就職”になりがちだが、これでは中長期的なキャリア設計において不利になる可能性がある。
むしろ、以下のような視点を持って企業を選ぶと、納得感が高く、将来にもつながる選択になる。
若手がどこまで責任ある仕事を任されているか?
社内でのキャリアパスに柔軟性があるか?
変化に対応してきた実績がある会社か?
社風や働き方に透明性があるか?
こうした視点を持つと、仮に中小企業であっても自分に合った“最良の選択”ができるし、「有名ではないが、実力がつく会社」を見つけられるようになる。
“安定”という言葉から解放された就活を
「周囲と違う選択」ができる勇気を持つ
周りがみんな大手志向だと、自分もそれが正解のように感じてしまう。しかし、一番大事なのは“自分にとっての正解”を選ぶこと。それは大手かもしれないし、ベンチャーかもしれない。
就活は「レールの上を走るレース」ではない。むしろ、自分のレールを引く作業であり、他人と同じである必要はまったくない。安定志向から自由になったとき、初めて“自分の就活”が始まるのだ。
「納得感のある就活」が、社会人としてのスタートを変える
納得感のある就活をした人は、社会人になってからも迷いが少ない。なぜこの会社を選んだのか、なぜこの仕事をしているのかが明確だからだ。
一方で、「なんとなく安定そうだから」「みんながいいって言うから」といった動機で就職した人は、社会人になってから「本当にこれで良かったのか?」という迷いに苦しむ。
安定よりも納得、正解よりも自分らしさ。それがこれからの時代の就活の本質であり、それを掴んだ人から、社会での自分の居場所を見つけていく。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます