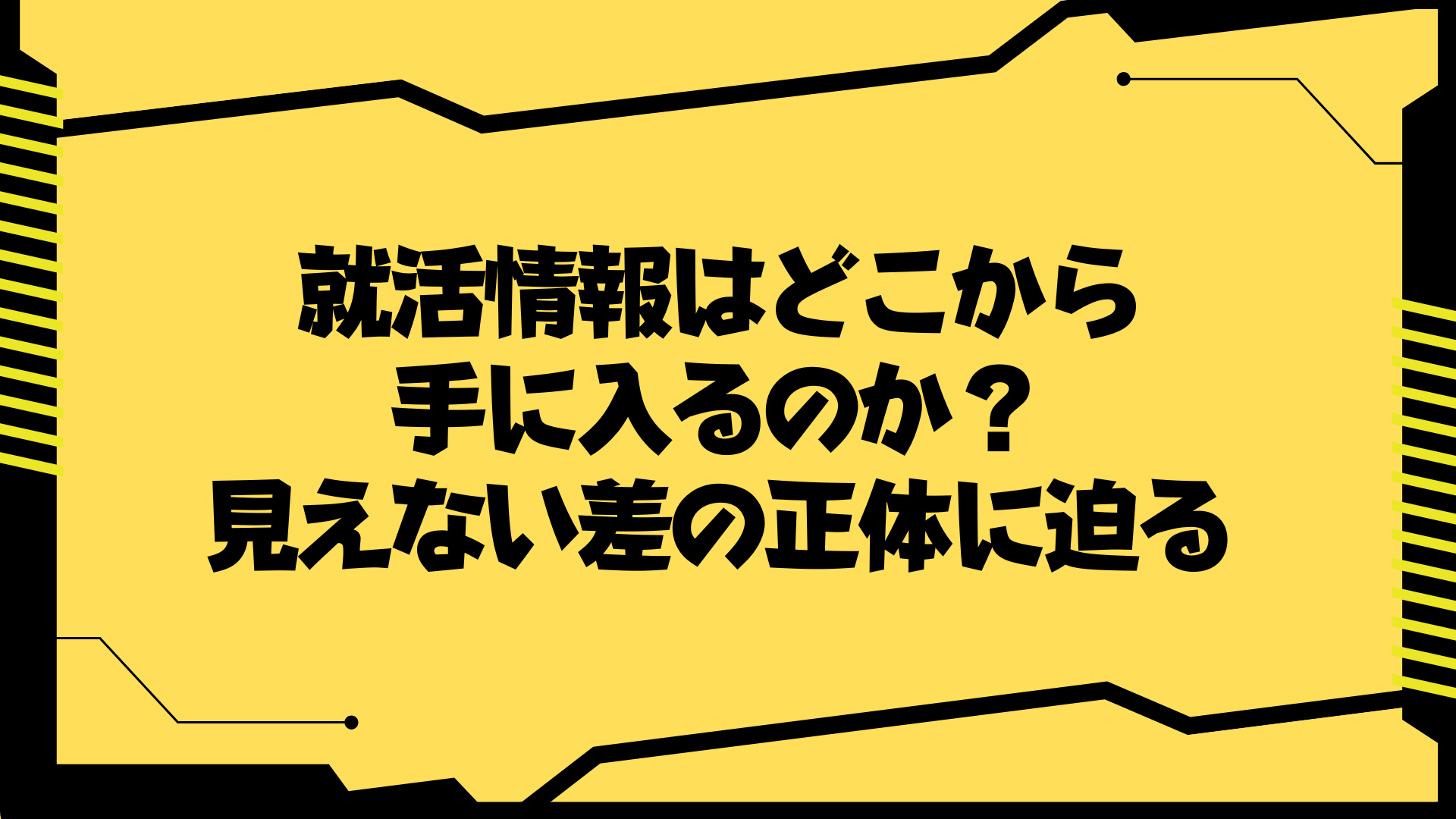SNSで就活情報を得る人が急増している背景
今や就活生の情報源として、SNSは欠かせない存在となっている。X(旧Twitter)やInstagram、TikTokでは、実際に選考を受けた学生の体験談や企業のリアルな評判が投稿されており、それらを日常的に見ている学生ほど「情報の粒度」が細かくなる傾向がある。
たとえば「◯◯企業は一次面接でこの質問が来た」「この時期に◯◯のサマーES通った」など、実際に就活を進めている人の投稿は非常に鮮度が高く、企業の公式情報よりも実践的なヒントを含んでいる。ただし、情報が断片的で正確性や信頼性にばらつきがあるため、受け取り方を間違えると逆効果にもなりうる。
SNSを活用している学生は、もともと情報感度が高い層が多く、日頃から就活アカウントを作ったり、ハッシュタグで企業分析をしていたりする。このような学生は、選考時期だけでなく、1年生・2年生の段階から情報をキャッチしている場合もある。
OB・OG訪問や大学経由の非公開情報は“知ってる人だけが得をする”
大学経由でのOBOG訪問や、キャリアセンターからの限定イベント情報なども、就活情報の格差を生む大きな要素のひとつである。特に早慶・旧帝大・国公立上位大学では、卒業生の進路や人脈が豊富で、「◯◯商事のOBOGに会える」「◯◯銀行のリクルーターが来る」などの非公開ネットワークが機能している。
こうした情報は、大学のメールやキャリアガイダンスで共有されるが、そもそもキャリア支援に熱心な学生でなければ見逃してしまう。さらに、OBOG訪問も「紹介してもらえる人脈がある学生」ほどチャンスに恵まれるため、家庭環境や高校時代の人脈、所属していた部活動やゼミなどによっても差が出てくる。
OB訪問からリクルーターにつながり、そこから特別選考ルートに進んだというケースは実際に存在する。つまり、「情報を取りにいけるかどうか」が、選考に進めるかどうかを左右するポイントになっている。
就活イベントや外部サービスにアクセスしている学生の動き方
マイナビ・リクナビをはじめとする大手ナビサイト、キャリアパーク、外資就活ドットコム、ONE CAREERなどの情報プラットフォームも、一定以上の情報格差を埋める手段となっている。しかし、それらを“情報収集”として使うか“行動につなげるための戦略”として使うかで、学生同士の差が大きく開く。
たとえば、ナビサイトにただ登録しているだけの学生と、スカウト機能や動画コンテンツ、企業比較機能まで活用している学生では、得られる情報量と就活への意識の深さがまったく異なる。
また、ナビサイト以外にも「逆求人型サービス」や「合同説明会」「企業別のWebセミナー」など、外部イベントやサービスを活用している学生ほど、企業との接点を早く・多く持っており、それが「自信」と「対策力」につながっている。
特に、就活エージェントやサマーインターン特化型イベントに早期から参加している学生は、「本選考で会う企業と先に接点を持っていた」というケースも多い。これらの動きは、情報の“早さ”と“質”の両方を押し上げる原動力になる。
身近な情報源は、友人・サークル・ゼミなどの“コミュニティ内共有”
意外と影響力が大きいのが、友人やサークル、ゼミなどの身近な人からの情報である。「◯◯がこの企業受けるらしいよ」「あの人はもう内定持ってるらしい」などの“うわさ”や共有から動き出す学生も多く、特に就活に消極的なタイプほど、こうした間接的な情報が行動のきっかけになりやすい。
しかし、ここにも落とし穴がある。たとえば、周囲が大手志向ばかりだと、自分もよく調べないまま大手企業にエントリーしてしまうケースがある。また、友人に誘われて参加したイベントで不完全な情報しか得られず、そのまま「自分には無理そうだな」と思い込んでしまう学生もいる。
つまり、友人経由の情報は「量」ではなく「質とタイミング」が重要であり、情報に振り回されない軸を持つことが求められる。
就活情報は「持っている人」と「取りにいける人」に集まる
就活の成否は“情報に触れる量”ではなく“行動に変えた数”で決まる
最終的に内定を取るのは、情報を多く持っている人ではなく、「その情報をどう活かしたか」である。たとえば、たくさんの企業を知っていても、ESを書いていなければ意味がない。逆に、限られた情報でも、1社に対して丁寧にアプローチできる学生は内定を獲得する可能性が高くなる。
その意味で、情報収集は「目的を持って行うこと」が鍵になる。ただ見るだけ・登録するだけでは、行動にはつながらない。自分がどんな情報を欲しているか、どの情報が“次のアクション”に役立つのかを見極めながら動いている学生ほど、就活がスムーズに進んでいく。
情報格差はどこから生まれるのか──就活のスタート地点にある“目に見えない差”
学歴による情報の質とスピードの違い
「高学歴の人は動き出しが早い気がする」という体感は、実際に多くの就活生が感じているリアルだ。そしてそれは、単なる印象ではなく、実際に行動データや大学の支援体制に裏打ちされた“差”である。
たとえば、旧帝大や早慶といった上位大学の学生たちは、1〜2年生のうちから就活セミナーに出たり、業界研究会に参加したりすることが多い。それだけでなく、卒業生とのネットワークが豊富で、リクルーターやOBOGが積極的に接点を取りに来てくれるという環境的なアドバンテージがある。
また、企業側も「青田買い」においては限られた大学をターゲットにすることが多く、たとえば外資コンサルや商社の早期選考は、特定大学の特定学部にだけ非公開で案内されるケースも存在する。こうした“選ばれた大学だけが得られる情報”は、同じ就活生であってもスタートラインが違うことを物語っている。
キャリア教育の差──大学のサポートはどれほど違うのか
大学によってキャリア支援の濃度は大きく異なる。大規模な大学やキャリア支援に予算を割いている大学では、専属の就職アドバイザーが常駐していたり、企業を招いてのセミナー・ガイダンスが頻繁に行われたりする。中には、就活専用ポータルを学内で整備し、ESの添削や模擬面接を何度でも受けられる環境を整えている大学もある。
一方で、地方大学や専門学校などでは、キャリアセンターのリソースが限られているケースも多く、学部によってはサポートが事実上ほとんど存在しないこともある。学生が自主的に動かなければ、ほぼ就活情報に触れないまま4年生を迎えるといった状況すらある。
つまり、「気づいたら周囲がもう動いていた」という状態になる学生は、本人のやる気だけでなく、大学の情報環境や支援体制によっても左右されているという現実がある。
家庭環境や地域差が情報感度に与える影響
もうひとつ、情報格差の出発点として見逃せないのが「家庭環境」と「地域格差」だ。たとえば、親がホワイトカラーの職業である場合、企業や職種に関する話題が日常の中で自然に共有されることがある。「営業はこういう仕事」「メーカーってこうやって利益出してる」など、普段から“ビジネスの感覚”が家庭の中にある学生は、就活時に理解が早く、志望動機もリアルになりやすい。
逆に、親が就職活動や企業選びに関してアドバイスできない場合、学生はゼロから情報を集めるしかない。どの業界が安定しているのか、どの仕事が自分に向いているのかを見極めるためには、それなりに調査や試行錯誤を重ねる必要がある。
また、都市部の大学と地方大学では、企業が接触しやすい環境かどうかという物理的な差も大きい。東京・大阪・名古屋などの大都市圏では、企業の説明会や面談、インターンが日常的に行われているが、地方在住の学生にとっては「物理的に行けない」「交通費がかかる」という障壁が立ちはだかる。
このように、情報格差は本人の意欲や努力以前に、「触れられる環境があるかどうか」によって生まれるものであり、社会的な背景と密接につながっている。
なぜ“行動が早い学生”は早期内定を取りやすいのか
情報が早ければ“対策”も“選択”も先手が取れる
早く情報を得た学生は、単に「知っている」だけではない。選考フローの全体像を把握し、業界の動向を読み、他の学生よりも早く“準備”に入ることができる。これは非常に大きなアドバンテージである。
たとえば、3月に解禁されるナビサイトを待つことなく、夏インターンから逆算して自己分析を始めた学生は、秋には業界絞りが終わっていることも多い。そして冬には早期選考や特別ルートに乗り、3月にはすでに内定が出ているケースもある。
こうした学生は、情報を得たタイミングで「今やるべきこと」を理解し、ES準備、面接練習、OBOG訪問などを前倒しで実行する。結果として、就活全体に余裕が生まれ、企業選びの視野も広がる。
情報が遅れると、行動がすべて後手になる
逆に、就活の動き出しが遅れた学生は、何もかもが“後手”に回る。周囲がインターンに参加していた夏を部活やバイトに費やし、3月に慌ててナビサイトに登録した頃には、人気企業のES締切がすぐそこに迫っていたり、インターン組だけが招待される選考ルートがすでに進行していたりする。
情報が遅いというだけで、「受けられる企業の数」が減り、「選考経験の蓄積」も少なくなり、「自分が何に向いているか」がわからないままエントリーが始まってしまう。結果として、初期に受けた企業の面接で落ち続け、自信を失い、さらに行動が鈍くなるという悪循環に陥りやすい。
情報を得るのが遅れることが、単なる“出遅れ”ではなく、“本来あったチャンスをすべて逃すリスク”になるという感覚は、あまりにも見過ごされている。
情報格差は“戦略の差”になり、やがて“人生の分岐点”になる
同じ大学でも、動いている人とそうでない人の差が開く
ここまで述べたように、情報格差は学歴や環境だけではなく、「その情報にどう向き合うか」「いつから動いているか」という、個人の行動パターンでも差がつく。実際、同じ大学・同じ学部であっても、早期内定を獲得している学生と、3月にやっとナビ登録をした学生では、半年以上の差がある。
これは学力や才能ではなく、「就活をどれだけ“自分ごと”としてとらえたか」の差にすぎない。つまり、情報格差は“能力の差”ではなく“行動習慣の差”から生まれるという事実を、もっと多くの就活生が知るべきである。
受け身型の就活から抜け出すために、まず“情報を取りにいく”習慣を持つ
情報を“待つ”人と“取りにいく”人の違い
就活において最も大きな差がつくのは、「情報をどう扱うか」にある。具体的には、“待っている人”は就活の波に流され、結果的に後手に回る。一方、“取りにいく人”は、能動的に動く中でチャンスに出会い、自分に合った企業選びやキャリア形成ができるようになる。
この差は、能力や知識の有無ではなく、日常的な情報の扱い方にある。SNSで偶然流れてきた情報を「たまたま見かけたからエントリーしてみる」だけなのか、自分で検索して「この業界の説明会が来月ある」と把握し、自分の予定に組み込むのか。その違いが、就活の主導権を握れるかどうかを分ける。
情報が平等に与えられることはない。だからこそ、「どうやって、どこから、誰を通じて情報を取っていくか」が、最終的な内定の質と数を決める要素になる。
今すぐできる“情報収集の5つの行動”
情報感度を高め、受け身から抜け出すには、以下の5つの行動が効果的だ。
1. 就活用のSNSアカウントを作る
InstagramやX(旧Twitter)で、就活情報をまとめて発信しているアカウントをフォローする。企業アカウント、就活エージェント、就活メディアなどを数十個フォローしておけば、自然とタイムラインに有益な情報が流れてくるようになる。アルゴリズムが“自分の興味”に合わせてくれるため、就活の感度が高まる。
2. 学内キャリアセンターを“日常的に”利用する
意外と使われていないのがキャリアセンターだ。「あまり良い求人がない」という声もあるが、ES添削や模擬面接のようなマンツーマンサポートを無料で受けられるのは大きい。また、大学によっては企業から非公開のインターン案内が届くこともあるので、定期的に足を運ぶだけでも差がつく。
3. OBOG訪問を定期的に行う
OBOG訪問は「行動するほど情報が濃くなる」典型例だ。1人に会えば1社の実態がわかり、3人に会えば比較軸ができる。特に、ナビには載っていない「働いてみてのギャップ」「就活時にやっておいてよかったこと」「この会社に入った決め手」などの本音情報を得られるのは大きな強みになる。
4. 就活イベントに実際に参加する
オンラインイベントを含め、就活系の合同説明会やインターン説明会は思った以上に“生の情報”が得られる場所だ。たとえば、企業の雰囲気や社員の話し方、ブースの熱量から、その企業の“リアルな空気感”が伝わってくる。資料では得られない情報が、五感を通して入ってくる体験は、選考への志望度にも影響する。
5. 同期・友人ネットワークを活用する
「他人と比べない」と言いつつも、就活において“横のつながり”は大切だ。就活を早く始めている友人からイベント情報をもらったり、面接の感想を聞いたりするだけで、自然と自分の動きが前倒しになることもある。ライバル視するよりも、“就活仲間”として情報共有できる関係性をつくることが、受け身から脱却するきっかけになる。
情報収集を「やった気」にしない──質を見極め、行動に落とし込む
情報を“集めるだけ”では意味がない
ここで注意したいのは、「情報を得ること=就活の成果」ではないということ。よくあるのが、SNSや就活サイトでたくさんの情報を“見た”ことで満足してしまい、行動に移せていないケースだ。
情報は行動して初めて意味を持つ。インターン情報を見たなら、締切を確認してエントリーまで済ませる。OBOGの体験談を読んだなら、自分も大学のOBOG検索をして実際にアポをとる。見ただけ・知っただけでは、実際の差にはならない。
特に情報が多い時代だからこそ、「使いこなす」「行動につなげる」ことを意識する必要がある。
就活の軸がない人ほど、行動しながら仮説を立てる
「何がやりたいかわからないから動けない」という声も多いが、これは本末転倒である。動かないからこそ、情報も軸も育たない。最初から明確な軸を持っている人は少ない。ほとんどの人が、“動きながら自分の志向を知っていく”というプロセスを踏んでいる。
実際、業界研究をしていくうちに「自分はBtoCの方が興味あるかも」「裁量が大きいベンチャーの話がワクワクする」といった感情の動きが軸につながることもある。そのためには、手を動かし、足を動かし、人に会い、ESを書き、面接を受けることが欠かせない。
情報格差は“行動格差”でしか埋まらない──戦える土俵に立つには
情報収集は努力量ではなく“やり方”で変わる
よく「自分は不器用だから」「効率が悪いから」とネガティブに感じている人がいるが、情報収集の差は、必ずしも“能力”によるものではない。むしろ、やり方を知っているかどうか、続けられる仕組みを持っているかどうかで決まる。
たとえば、「就活アカウント専用のXを作る」だけでも、TLが就活モードに変わり、自然と情報が入ってくるようになる。スマホのトップに就活系アプリを並べるだけでも、毎日1回は意識が向くようになる。
意志ではなく仕組みで動く。情報格差を埋める第一歩は、そうした“環境づくり”である。
行動した人だけが見える景色がある
情報は、動いた人にしか見えてこない構造になっている。たとえば、就活エージェントに登録した人にだけ紹介される非公開求人、OBOG訪問した学生にだけ届く特別選考ルート、インターンに参加した人だけが知る社員の“本音”。
つまり、“本当に価値のある情報”は、行動した先にしか存在しない。
就活は平等なようでいて、動いた人間にしか開かれていない扉が数多くある。だからこそ、動き出した人から内定に近づいていくのだ。
情報格差が内定格差を生む──就活の“勝敗”を分ける構造的な違い
情報を持つ人は“準備の早さと質”が違う
就活において「情報を持っている人」と「持っていない人」では、選考に臨むまでの準備の質とスピードに決定的な差が生まれる。たとえば、早期にサマーインターン情報を知っていた人は、大学3年の6月にはすでにESや面接の経験を積み始めている。さらに、複数企業の社員と接点を持つことで業界理解が深まり、自分に合う企業の傾向も見えてくる。
一方で、情報を知らなかった人は「冬にインターンの話を聞いたけどもう終わっていた」「説明会のことを知ったときには応募締切が過ぎていた」といった経験をする。これは個人の能力とは無関係に、“情報の有無”というスタート地点で大きな差がついている状態だ。
この差は、企業選び・選考対策・内定先の納得感にまで影響を及ぼす。早くから動いていた人ほど「この企業は違う」「この仕事には向いていない」といった“選ばない判断”ができるようになる。一方、後手に回った人ほど「とりあえず応募」「なんとなく内定が出たところに決める」といった妥協の決断に陥りやすい。
“気づける人”と“流される人”の分岐点
情報を持っている人は、就活の中で小さな違和感やチャンスに“気づく力”がある。企業の説明会で担当者が話す口調や言葉の選び方から「ここはトップダウンの社風だな」と感じたり、インターン先の先輩の態度から「この会社は若手に厳しいかも」と察知できたりする。
一方、情報が少ない人は、「なんか雰囲気が良かったから」といった曖昧な印象だけで判断してしまう。これは経験の差というよりも、情報に触れてきた量と質の差が“感度”をつくっている状態であり、選考を通じてますます差が広がる要因にもなる。
情報格差が“選考中の行動”にも影響を与える
面接・ESでの「語れるエピソード」が変わる
情報を多く持っている人は、自然とエピソードの質が高くなる。たとえば、サマーインターンに参加して「実際の現場でどう働いたか」を語れる人と、アルバイトやサークルの経験だけで就活を戦う人とでは、伝えられる内容の深みが違う。
また、情報収集を通じて「企業が求めている人物像」や「過去に評価されたESの傾向」などを知っている人は、自分のエピソードを企業に合わせて編集することができる。これは“対策の精度”に直結する。
逆に、情報の少ない状態でESを書くと、「誰にでも当てはまる自己PR」や「無難すぎる志望動機」になりやすく、人事の印象にも残らない。これが、ES通過率や面接突破率に現れることは言うまでもない。
“企業を選ぶ側”になれるかどうかの違い
就活では「企業に選ばれる側」であると同時に、「自分が企業を選ぶ側」でもある。しかし、情報を持っていない状態では、“選ぶための材料”が圧倒的に不足してしまう。
企業選びに必要なのは、「知名度」や「給与」だけではない。社風、働き方、成長環境、評価制度、社員の雰囲気など、入社後に影響する多くの要素を事前に見極めておく必要がある。そのためには、口コミやOB訪問、インターン、社員のSNS発信など、多角的な情報源を活用することが求められる。
情報を持っている人ほど、企業の“中身”を見て志望先を決める。だからこそ、「入社後に後悔する確率」が格段に下がるのだ。
情報格差を乗り越える──これから就活する人への提案
「自分は情報弱者だ」と思ったときにやるべきこと
これまでの話を読んで、「自分は出遅れている」「学歴も高くないし不利だ」と感じた人もいるかもしれない。しかし、情報格差は“行動の差”でしか埋められないからこそ、いまからでも十分に挽回が可能だ。
第一歩は、「誰かから聞くのを待つ」のをやめること。次に、「検索してみる」「フォローしてみる」「聞いてみる」「申し込んでみる」といった、小さな行動を積み重ねていくことで、“情報にアクセスできる位置”に自分を置くことが大切になる。
必要なのは、優秀さではなく「情報への感度」だ。感度は意識で変えられる。今日からSNSのフォローを整理し、就活アプリを入れて、学内のキャリアセンターに話を聞きに行くだけで、流れてくる情報は確実に変わる。
情報に対する“姿勢”が就活の本質を変える
就活において、情報は単なる材料ではなく、意思決定そのものを形づくる根幹だ。「何を知っているか」が「どう行動するか」に影響し、それが「どこに内定するか」につながっていく。
さらに言えば、就活だけでなく、社会に出てからもこの構造は続く。「知っている人」がリスクを回避し、チャンスをつかみ、「知らなかった人」は後手に回り、悔しい結果を味わう。情報をどう扱うかという姿勢は、キャリアの質を決める根本的なスキルになる。
まとめ──就活で“情報を持つ者”が得る3つの優位性
準備の早さと質が違う
選考を受けるまでに得られる経験・対策が圧倒的に増える。
企業選びの軸が明確になる
選ばれる側であると同時に、自分からも企業を選べる。
“納得感のある内定”を得やすい
情報によって判断軸が育ち、選んだ企業に確信を持てる。
情報を取りにいく姿勢を持つ人は、就活だけでなく、その先の社会人生活でも“選択に強い人”になっていく。逆に言えば、「何を知り、どう動くか」が、未来のキャリアの質を決める。
「情報を得た人から、就活は変わる」──その事実を、あなたが最初の内定で証明することができる。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます