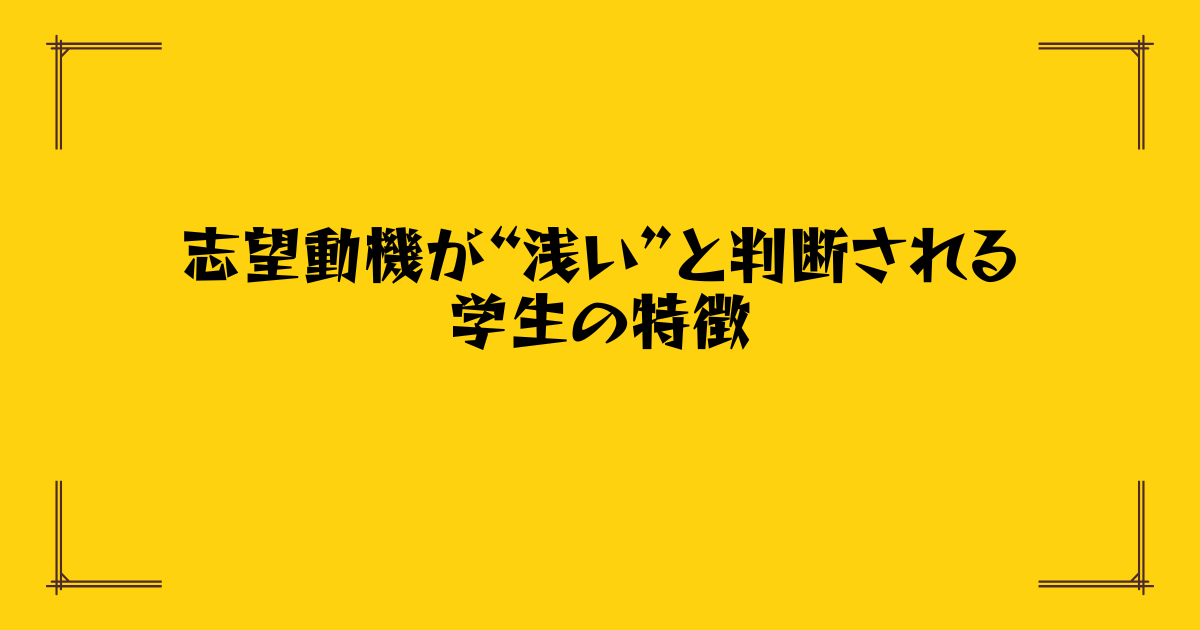どれだけ正しくても「響かない」志望動機がある
表面的な言葉は、選考官にすぐ見抜かれる
志望動機でよくあるパターンの一つが、「御社の〇〇という事業に惹かれました」「若手が活躍できる環境に魅力を感じました」といった、いかにも“正解らしい”フレーズの羅列である。
一見すると問題がなさそうな文章だが、選考官はすぐに“浅さ”を察知する。なぜなら、これらの表現はどの企業にも使い回しができる内容であり、本人の考えが一切反映されていないからである。
志望動機で本当に重要なのは、「その企業でなければならない理由」と「自分自身の価値観や経験との接点」を言語化することである。誰かが書いた例文をなぞったような動機には、企業側は熱意を感じない。
「企業理解の浅さ」よりも「自己理解の浅さ」が問題
浅い志望動機の原因として多いのは、企業研究が足りていないことだと考えられがちだが、実はそれ以上に重要なのが自己理解の浅さである。
自分がどんな価値観を持ち、どういう仕事をしたいのか、どんな環境で力を発揮できるのか。この土台が曖昧なまま企業を選んでいると、どれだけ企業について調べても「自分なりの言葉」で動機を語ることはできない。
つまり、「どの企業に行きたいか」ではなく、「なぜその企業に惹かれるのか」が語れない限り、面接官の心には響かないのだ。
なぜ浅い志望動機では内定が取れないのか
“意欲があるかどうか”は動機に現れる
企業は選考を通じて、「この学生が入社後に活躍できるか」「長く働いてくれそうか」という点を見ている。その判断材料として、志望動機は最重要項目の一つだ。
実際に「どんなきっかけで志望したか」「どこに魅力を感じたか」「なぜ他社ではなく当社か」といった質問は、ほぼすべての企業で聞かれる。ここで曖昧な答えしか返せない学生は、「うちに本当に入りたいのか?」「ちょっと言い訳っぽいな」と判断され、落選する確率が跳ね上がる。
企業は“受かりたいから取り繕った動機”ではなく、“入社後に活躍する確信”を求めている。志望動機の浅さは、その確信を持たせる力がないということを意味する。
曖昧な動機は「なぜ?」を繰り返すと崩れる
面接官は志望動機に対して、「なぜそう思うの?」「それは他社でもできるのでは?」といった形で深掘りをしてくる。ここで答えに詰まるようであれば、学生本人がその企業について、そして自分について、十分に理解していないことがすぐに明らかになる。
たとえば、「若手が活躍できると聞いたからです」と言えば、「なぜ若手が活躍できる環境がいいと思ったの?」と聞かれる。そこに自分の過去の経験や価値観の背景がセットで語れなければ、志望動機は“崩壊”する。
面接官が見ているのは、動機の“美しさ”ではなく、“本気度と納得感”である。浅い志望動機は、深掘りされるとすぐに“見せかけの言葉”であることが露呈してしまうのだ。
浅い動機に陥る人の共通点とは
とりあえず内定が欲しい気持ちが強すぎる
多くの学生が「どこでもいいから受かりたい」というモードに入り、エントリー数を増やしすぎたり、志望度が低い企業にも無理やり志望動機を書く場面に直面する。そうなると当然、内容は薄くなり、言葉に気持ちが乗らない。
この状態で提出されたESや面接での発言は、採用担当者から見れば“必死だけど本気ではない”ように見える。表面的には努力していても、そこに「この企業じゃなければダメだ」という熱意がなければ、選考で勝つことは難しい。
志望動機が浅い学生の多くは、自分の感情を見ないふりをして、正解らしい言葉を並べる。だが、それでは「他にもたくさん受けてるんだろうな」という印象を与えてしまい、“志望度が低い人”として扱われてしまう。
比較・分析の視点が欠けている
志望動機を深くするためには、「なぜこの業界なのか」「なぜこの職種なのか」「なぜこの企業なのか」という三層構造を丁寧に整理する必要がある。
しかし、浅い動機の人はこの比較が弱い。「どんな他社と比較した結果、ここが魅力的だったのか」「似た業界や職種との違いは何なのか」といった視点がないため、単なる“印象ベースの好意”のような志望動機になってしまう。
企業としては、「うちのことをちゃんと見てくれている」「競合と比較したうえで選んでくれた」と感じられる志望動機の方が、信頼度も評価も高くなるのは言うまでもない。
志望動機を“深くする”には自己理解が最優先
「自分が何を大切にしているか」を言語化する
就活に必要なのは「就活用の自分」ではない
志望動機が浅くなる原因の根本には、「自分が何を大切にして生きているのか」という問いへの答えがないことが多い。表面上は「成長できる環境に惹かれた」「社会課題の解決に貢献したい」と言っていても、なぜそう思うのかを問われると答えが出てこない。
これは、就活という“見られる場”での自分を演じようとして、本来の自分を置き去りにしてしまうからである。結果、誰にでも当てはまりそうな言葉しか出てこなくなり、志望動機に“自分らしさ”が消える。
志望動機に深みを持たせるためには、まず「自分がどうありたいか」「何にやりがいを感じるか」「どんな時に力を発揮できるか」を他人に説明できるレベルまで言語化することが不可欠だ。
経験の棚卸しは「抽象化」と「価値観の発見」が鍵
自己分析というと「サークルでの役職」「アルバイトでの成功体験」などエピソード集めに走りがちだが、それだけでは不十分。重要なのは、その経験を通じて自分が何を大切にしてきたのかを見つけることにある。
たとえば、飲食店でのバイトで「忙しい時間帯でもミスが少ないよう仕組み化を考えた」という経験があるとする。この事実の裏には、「自分の工夫でチームが円滑に回ることに喜びを感じる」という価値観が隠れているかもしれない。
このように、具体→抽象→価値観の発見という流れで経験を棚卸しすることで、単なる出来事が“自分らしさ”の証明に変わっていく。
企業選びの視点を根本から見直す
「なんとなく」で企業を選ぶと動機が浅くなる
就活生の多くが、「有名だから」「福利厚生がいいから」「OBが多いから」といった“なんとなくの印象”で企業を選びがちである。そのまま選考に進み、無理に志望動機を捻り出すことで、“薄っぺらいES”や“ぎこちない面接”に繋がってしまう。
この“なんとなく就活”から抜け出すためには、まず自分の価値観に合った仕事とは何かを再定義する必要がある。その上で、その価値観が企業とどのように接続するのかを見極めることが、深い志望動機を構築する土台となる。
「働き方」「職場の空気」「評価制度」も比較する
企業を選ぶうえで、「業界・職種」だけでなく、「企業文化」「働き方」「マネジメントスタイル」なども視野に入れることが大切である。
たとえば、同じ営業職でも、個人主義的な数字重視の営業と、チームで目標達成を重んじる営業では、求められる働き方も価値観もまったく異なる。これに気づかずエントリーすると、動機に説得力が生まれにくく、入社後のミスマッチにも繋がる。
志望動機を深くするには、「この仕事を通して、どんな成長をしたいか」「そのためにどんな環境が合うのか」という視点で企業を選び、その選定基準を言語化することが不可欠だ。
「言語化練習」で動機の精度を高める
書いてみないと見えないことがある
自己分析や企業研究をしても、頭の中だけで整理していると、自分の考えが曖昧なままになりやすい。そこで有効なのが、実際に志望動機を書き出してみることである。
言葉にしてみると、「なんかしっくりこない」「どこか説得力が弱い」といった違和感が浮き彫りになる。その違和感の正体を追求することで、初めて本質的な志望動機が見えてくる。
また、志望動機を誰かに話してみることも効果的だ。第三者の視点から「それって他社でも言えるんじゃない?」「なんでそれに惹かれたの?」とフィードバックをもらうことで、自分では気づかなかった“薄さ”や“あいまいさ”を客観視できる。
「動機=企業に合わせること」ではない
深い志望動機とは、企業が喜びそうな言葉を並べることではなく、“自分の価値観や経験が企業とどう交差するか”を伝えることにある。つまり、動機を作るとは「企業に合わせて自分を偽ること」ではなく、「自分の核と企業の特性が重なる点を探す作業」だ。
この意識があるかどうかで、志望動機の質はまったく変わってくる。他の学生が企業の魅力をなぞったような内容を書いている中で、自分だけが「自分の意思」と「企業の特徴」を結びつけた動機を提示できれば、それは面接官の印象に強く残るはずだ。
志望動機に“深さ”を与える3つの具体要素
自分の経験・価値観・行動のつながりを明確にする
「なぜそう思うか」を3回掘り下げる
深い志望動機とは、「私は◯◯に惹かれました」だけで終わらず、その背後にある価値観や体験、行動との一貫性が見えるものだ。そこで重要になるのが、「なぜそう思ったのか?」という問いを3回掘り下げていく姿勢である。
たとえば、「人の役に立つ仕事がしたい」と考えた場合、それを深めると以下のようになる。
なぜ人の役に立ちたいのか?
→中学時代に部活で後輩の指導をしたときにやりがいを感じたから。
なぜそのときにやりがいを感じたのか?
→相手が自信を持って動けるようになることで、自分の存在価値を実感できたから。
なぜ存在価値を感じることが大事だと思うのか?
→幼少期に自分の意見が否定され続けた経験から、誰かに肯定されることに意味を感じるようになった。
このように掘り下げることで、「人の役に立ちたい」という一見ありきたりな志望動機が、唯一無二の個人の背景とリンクする説得力ある動機へと変わる。
「経験→価値観→志望」の流れを意識する
志望動機の質を高めるには、「私は◯◯を経験して、△△という価値観を持つようになり、それが□□という理由でこの企業を志望する」という一貫した流れをつくることが不可欠だ。
たとえば、こんな構成になる:
経験:学生時代に高齢者向けイベントを企画・運営
価値観:誰かの“できない”を“できる”に変えることにやりがいを感じる
志望:その価値観を活かせる福祉業界の中でも、利用者の自己実現に注力している貴社に魅力を感じた
このような構成にすれば、単なる「志望先の説明」ではなく、自分の“人生の延長線上にある志望”だと納得感を持って伝えられる。
企業分析と“接点”の見つけ方
志望動機に「企業固有の文脈」を入れる
「なぜうちなのか?」を説明できないと、他社でも使い回せる志望動機と判断され、通過率が下がる。だからこそ重要なのが、その企業の“固有性”を把握することだ。
具体的には以下のような要素をチェックする:
その企業が業界内でどういう立ち位置にあるか
他社と違う価値提供やサービス設計があるか
経営理念や企業風土がどう表現されているか
これらの情報と自分の価値観を結びつけて、「自分はこういう価値観を持っていて、それが御社の◯◯という特徴と一致している」と言えるようにする。
この“接点の明示”こそが、志望動機に深さと独自性を与える最重要ポイントである。
面接官が「他社でもよくない?」と思う瞬間とは
企業側が見ているのは、「この学生は本当にうちに入りたいのか?」という点だ。「成長できるから」「社会貢献できるから」などの表現だけでは、それは他社でも実現可能であり、動機として弱い。
面接官は、志望理由を聞いたときに「それってうちじゃなくてもよくない?」と思った瞬間に興味を失う。この反応を避けるには、自分の経験や価値観と企業の特徴が具体的に結びついている必要がある。
たとえば、「学生時代に多様な価値観を持つ人と共同作業する機会が多く、そうした経験が貴社のグローバルプロジェクトにも活かせると考えた」と言えるなら、それはその企業でなければならない理由になる。
志望動機を伝える文章構成フレーム
「PREP+自己経験+企業特徴」の三層構造が効果的
説得力のある志望動機の伝え方として有効なのが、PREP法(Point→Reason→Example→Point)に、自分の経験と企業特徴を組み込む三層構造である。
以下はその構成例:
Point(結論):「私は貴社で〇〇の分野に取り組みたいと考えています」
Reason(理由):(なぜなら)「人々の暮らしを支える仕組みに関心があるからです」
Example(体験):(その背景に)「学生時代、商店街活性化のプロジェクトに携わり…」
Point(再提示):「この経験から、地域に密着し持続可能なインフラに貢献する御社に強く惹かれています」
この構成にすることで、論理性・自分らしさ・企業との接点の3つをすべて押さえることができ、面接官に刺さる志望動機が仕上がる。
“熱量”を込めるには書き手の確信が必要
志望動機に熱量を込めるには、自分が心から納得しているかどうかが最重要である。表面的にきれいな言葉を並べても、自分でも「何かしっくりこない」と思っていれば、それは言葉の端々に出てしまう。
だからこそ、志望動機を仕上げる最終段階では、何度も書き直してみること、声に出して読んでみることをおすすめする。自分が本当にそう思っているか? その企業でなければならない理由があるか? に違和感がなくなるまで、ブラッシュアップを重ねる。
志望動機とは「就活のために用意するもの」ではなく、自分の人生の価値観と、企業の存在意義が一致する地点を探し出す作業である。それが伝わったとき、ようやく“深い志望動機”と呼べるのだ。
志望動機を選考で活かすためにやるべきこと
書類・面接の両方で一貫性を保つ
エントリーシートと面接の内容がブレないようにする
選考で最もよく起きる失敗のひとつが、「ESと面接で話す内容が違って見える」ことだ。これは準備不足ではなく、「ESはそれっぽく書けたけれど、自分の言葉ではない」ことが原因である。企業側は、一貫した動機や価値観の流れが見えているかどうかを見ているため、書類と面接の整合性がないと信頼性が下がる。
たとえば、ESでは「チームでの挑戦に価値を感じている」と書いていたのに、面接では「個人で結果を出したい」と語ってしまえば、「なんとなく作った志望動機」だと見抜かれてしまう。一貫性を保つには、自分の軸を明確に言語化しておくことが欠かせない。
自分が“納得できる言葉”を使う
志望動機は、自分自身が腑に落ちている必要がある。他人に説明しようとするとき、納得していない言葉や、借り物のフレーズを使っていると、それは面接官に伝わってしまう。
たとえば、「社会課題の解決に貢献したい」と言いながらも、「なぜそれがしたいのか?」と問われて詰まる学生は多い。深い志望動機に仕上げたつもりでも、自分自身の納得が伴っていないと、選考では機能しない。
だからこそ、どんなに綺麗な構成でも、「自分の実感と言葉で語れるかどうか」を最終確認する必要がある。
面接で志望動機を強く伝えるコツ
抽象と具体を往復しながら話す
深い志望動機を伝えるためには、抽象的な価値観だけで終わらず、それを支える具体的な経験や行動にまで言及することが重要だ。
たとえば、「多様性を大切にする企業文化に惹かれた」という話なら、「実際に自分はどういう多様性に向き合ったのか」「どういう行動でそれを表現したのか」を語る必要がある。
抽象:多様な意見がある中で共創することにやりがいを感じる
具体:異文化背景の学生が多いゼミで、進行役として議論をまとめた経験がある
このように、価値観(抽象)→体験(具体)→企業の特徴との接点(応用)という流れで語ると、面接官に刺さる志望動機となる。
質問を“チャンス”に変える意識を持つ
面接で志望動機を話している最中に「どうしてその業界なの?」「うちのどこに惹かれたの?」などと追加で聞かれると、不安になるかもしれない。だがそれは、“もっと深く聞いてみたい”というポジティブな反応であることが多い。
だからこそ、「質問=詰問」と捉えず、「自分の熱意を伝える追加チャンス」として捉える視点が重要だ。特に志望動機に関しては、突っ込まれてからが本番とも言える。
この意識を持つだけで、焦ることなく、自分の背景・価値観・行動をつなげて話すことができるようになる。
“志望動機を使いまわさない”姿勢が差を生む
業界ごとではなく“企業ごと”に動機を用意する
「食品業界が志望です」「IT業界に関心があります」など、業界レベルで志望動機をまとめてしまう学生は多い。しかし、企業は業界ではなく“自社”を見てほしいと思っている。
だからこそ、「この企業を志望する理由は何か?」を毎回組み立て直す作業が必要だ。もちろん土台の価値観や経験は共通でもいいが、それをどうその企業に応用できるか、どこに惹かれたのかは個別に考える必要がある。
たとえば、同じ「挑戦できる環境に惹かれた」という動機でも:
A社:新規事業を積極的に仕掛ける文化がある
B社:若手の裁量権が広く、1年目から顧客対応を任される
といったように、「挑戦」に対する特徴は企業ごとに異なる。ここに言及できれば、“どの企業でも使いまわせる志望動機”ではなく、“その企業のために組み立てた動機”になる。
志望度の高さは“行動”で示す
最終的に志望動機の深さを支えるのは、「どれだけその企業のことを調べ、実際に行動しているか」である。OB訪問、インターン参加、説明会での質問など、自分の志望動機が“知識”ではなく“体験”として積み上がっているかが判断基準になる。
たとえば、「OBの◯◯さんに伺ったお話の中で、実際のプロジェクト推進におけるチーム体制の柔軟さに感銘を受け…」というように、自分の言葉で説明できれば、表面的な理解を超えた志望動機として評価される。
ESだけでなく、自分の行動履歴そのものが志望度の高さを示す。その積み重ねがあるかどうかで、選考通過率は大きく変わる。
まとめ
志望動機は「作るもの」ではなく、「育てていくもの」である。自己理解の深さ、企業理解の解像度、実際の行動や経験。それらを結びつけながら言語化し、面接で伝える力へと昇華させる必要がある。
一貫性のある構成(価値観・経験・企業の接点)
自分が納得できる言葉での表現
抽象と具体の往復による深み
質問をチャンスに変えるマインド
志望動機は企業ごとに設計し、行動で補強する
これらを実践することで、「なぜこの会社か」「なぜあなたなのか」という問いに、胸を張って答えられるようになる。深く、納得感のある志望動機は、ESや面接だけでなく、内定後の配属やキャリア選択にもつながる“軸”となる。
就活という短期の活動のためではなく、自分の人生に意味を持たせるための“志”としての志望動機。それを育てる姿勢こそが、真に強い就活生をつくるのだ。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます