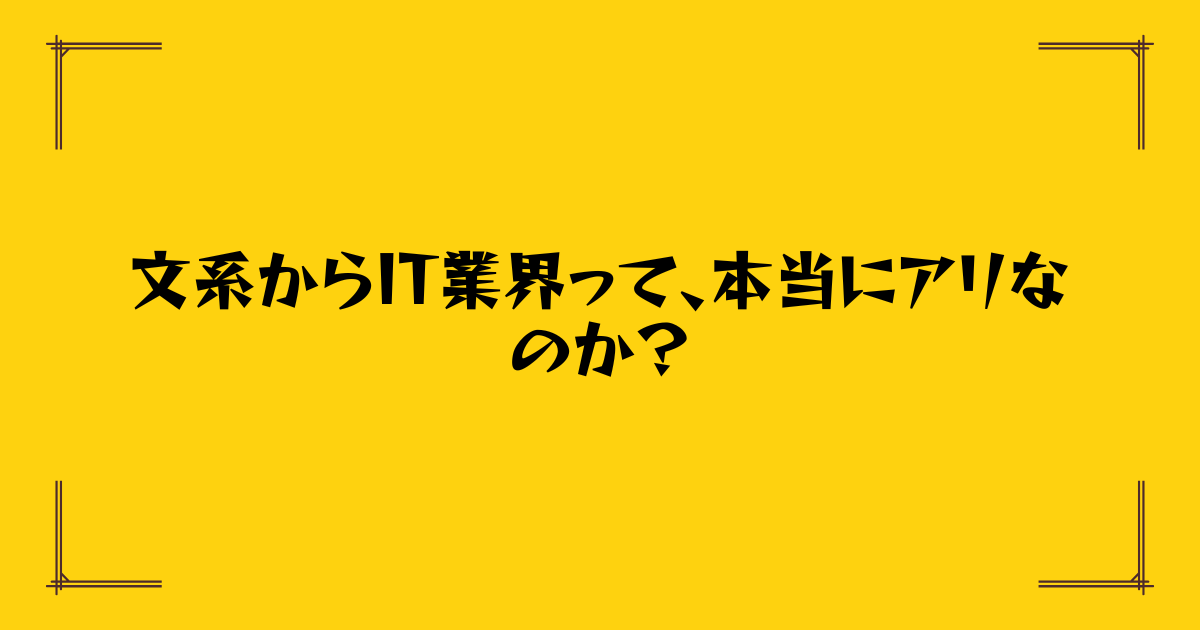「文系でもITに行ける」と言われるけど、実際どうなの?
就活サイトの“文系歓迎”は本当か?
「IT業界は文系でも行ける」「文系出身のSEも多い」――こんな言葉を見たことがある人も多いだろう。たしかに、IT業界の採用ページには「学部不問」「未経験歓迎」「文系出身者も活躍中」などのフレーズが並んでいる。しかし、それを見て安心していいのか?現実はもっと複雑だ。
実際に話を聞くと、「入社してからギャップが大きかった」「研修の時点で理系との差を痛感した」といった声も少なくない。文系でも採用はされるが、“その後”で苦労している人がいるのも事実だ。
IT企業の中には、未経験でも育てる前提で採用している会社もある一方、「理系前提」の開発チームに配属されると、専門知識のなさが足を引っ張る場面がある。つまり、「入り口は開かれているけれど、入ったあとが勝負」というのがリアルな現実だ。
そもそもIT業界の“文系向け”の仕事って何?
文系でも活躍できる仕事として、よく名前が挙がるのが「営業」「カスタマーサポート」「ITコンサル」「プリセールス」などだ。ただし、どの仕事も「ITのことがわかっている前提」で話が進むことが多い。
たとえばIT営業では、顧客の要望をヒアリングし、それを技術チームに伝える「橋渡し役」になるが、技術の理解が浅いと顧客の課題を正確に把握できない。ITコンサルも「コードを書かないから文系でもOK」と言われがちだが、ITシステムの仕組みを理解していないと、クライアントに信頼されない。
「文系向け=楽」では決してなく、「文系でも学べばできる」という意味でしかない。裏を返せば、“学ぶ気がない人には厳しい業界”だということを意味している。
ITに進みたい文系学生がぶつかる「見えない壁」
情報があいまいすぎて、イメージが湧かない
「IT業界=エンジニア」じゃないけど、それ以外がわからない
IT業界というと、多くの文系学生がまず「エンジニアは無理そう」と思う。そして、「他にどんな仕事があるの?」というところで止まってしまう。これは情報の出し方にも問題がある。
企業説明会では「幅広い職種があります」と言われても、実際には「どんなスキルが求められるのか」「どの程度の知識が必要なのか」といった話が曖昧で、結局イメージが湧かないまま終わってしまう。
そのまま就活を進めると、「何となく成長業界だから」「DXに興味があるから」くらいの理由で応募し、面接で深掘りされた瞬間に答えに詰まる。これは非常によくあるパターンだ。
「志望動機が薄い」と言われる文系学生の落とし穴
IT業界に興味があるという気持ちは本物でも、それを“言語化できない”と、面接で評価されにくい。「なんで文系のあなたがこの業界に来たいの?」という質問に、納得感のある答えが求められる。
その際、「成長業界だから」「安定しているから」といった理由だけだと、「他の業界でもいいんじゃない?」と思われてしまう。つまり、ITを選ぶ理由を自分なりに言葉にしておかないと、熱意が伝わらない。
文系学生でもITに向いている人、向いていない人
文系だから無理、ではなく「どう考えているか」で分かれる
自分で調べたり、勉強したりするのが苦にならない人は強い
文系か理系かというより、「自分から調べて学ぶことに抵抗がないか」が、IT業界での適性を分ける。ITはどんどん変化する分野で、常に新しい知識が求められる。そのため、「言われたことだけをやりたい」「教えてもらえるのを待つ」という姿勢だと、かなり苦しくなる。
一方で、「ググるのが得意」「知らない言葉を聞いたら調べるクセがある」という人は、文系であっても伸びる。実際、未経験から独学でスキルを身につけた人が活躍している例も多い。
「ITが好きじゃないけど安定してそう」だと長続きしない
文系学生の中には、「ITよくわからないけど、業界として伸びているから安定してそう」という理由だけで志望する人もいる。だが、それだけの理由だと入社後にギャップを感じやすい。
覚えることが多い、学ぶスピードが速い、専門用語が飛び交う――こうした日常が苦痛に感じると、モチベーションは続かない。「多少なりとも興味があるかどうか」が、文系のIT就職では特に重要だ。
文系がIT業界で「勝てる就活戦略」を立てるには
“未経験OK”を鵜呑みにしない情報リテラシーを持つ
「育成前提」の会社と「放置型」の会社の違いを見極める
IT業界の求人にはよく「未経験歓迎」「文系出身多数活躍中」といった文言が踊っている。だが、そこに安心して飛び込んでしまうと、思わぬ落とし穴にハマることがある。
企業によっては、「未経験OK」と言いながら入社後は“ほぼ放置”というケースもある。マニュアルやサポート体制がなく、「自分で勉強してなんとかしてね」という空気感の中で、結局、スキルが追いつかずに退職してしまう人もいる。
一方で、“育成前提”の企業は、研修制度が整っており、未経験者のつまずきやすいポイントも想定済みで教えてくれる。ここを見抜けるかどうかが、文系からIT業界で活躍できるかの分かれ目になる。
「エンジニアにならなくてもいい」なら、それ以外の仕事を知っておく
IT業界=エンジニアというイメージが根強いが、文系でも活躍できる職種は実は多い。たとえば以下のようなポジションだ:
IT営業(技術的知識を持ちつつ提案を行う)
プリセールス(営業と技術の橋渡し役)
カスタマーサクセス(導入後の運用支援)
ITコンサル(業務改善やDX支援)
これらの職種では、技術職ほどのプログラミングスキルは求められないが、ITの基本的な理解は必要になる。重要なのは、「自分はどう関わりたいのか」を明確にして、エンジニア以外の道も視野に入れることだ。
文系学生がIT業界の情報を集めるために必要なこと
IT企業の“採用広報”ではなく“現場の声”に触れる
現場社員が出てくる説明会やイベントに出てみる
企業の公式サイトや就活ナビサイトに載っている情報は、基本的に“ポジティブ寄り”に整えられている。そこで判断するだけでは、現場とのギャップを見逃してしまう。
特にIT業界は、「自社開発か?受託か?SESか?」というビジネスモデルによって働き方が大きく異なる。これらの違いは、採用ページではほとんど説明されていないことが多い。
本音で語ってくれる現場社員が登壇する会社説明会や、学生向けの座談会イベントなどに参加することで、言葉のトーンや雰囲気から“リアル”が感じ取れる。ネットだけで判断せず、実際に話を聞きに行く姿勢が、文系には特に重要になる。
OB・OG訪問では「未経験で困ったこと」を聞いてみる
文系出身でIT企業に就職した先輩がいれば、ぜひ話を聞いてみてほしい。その際、表面的なキャリアパスではなく、「入社してから何に困ったか」「自分でどんな勉強をしたか」を深掘りして聞くようにする。
「入社前にやっておけばよかったことは?」という質問は定番だが、答えに個人差が出やすいため、「何が難しかったか」「どう乗り越えたか」といった問いかけの方が、リアルな情報が引き出せる。
文系がIT企業にアピールできる“強み”の磨き方
技術より「伝える力」や「調整力」に目を向ける
“ITのことがわかる文系”は現場で重宝される
文系だからといって、技術に弱いままでいいわけではない。だが、「技術者と顧客をつなげる橋渡しができる人材」は、むしろIT業界で非常に重宝される。
たとえば、顧客の業務課題をヒアリングして、技術的な要件に落とし込む。技術者が話す専門用語を“翻訳”して、クライアントにわかりやすく説明する。こうした“通訳的ポジション”は、文系的な素養とITの理解の両方が必要とされる。
この役割を果たすために重要なのが、「知識をかみ砕いて説明する力」や「相手の立場に立って考える視点」。論理的思考力とコミュニケーション力が強みであれば、そこを自己PRに盛り込むと効果的だ。
未経験でも“自分で学ぶ姿勢”を示すことで印象は変わる
たとえ専門スキルがなかったとしても、「ITパスポートを勉強している」「HTMLやSQLを独学している」「ChatGPTでシステム開発について調べてみた」といったアクションがあるだけで、面接官の印象はガラッと変わる。
何もしていない状態だと、「IT業界に興味がある」と言っても説得力がない。しかし、小さなことでも自分から学んでみたという姿勢が伝われば、「この人は伸びるかもしれない」と判断される可能性が高まる。
文系の自分がIT業界で働く“納得感”を持てるかどうか
「何がやりたいか」よりも「どう働きたいか」が鍵
「やりたいことが決まっていない」ことを悲観しなくていい
IT業界に限らず、文系の学生は「やりたいことが見つかっていない」と焦る傾向がある。しかし、就職時点で明確なビジョンを持っている人の方が少数派だ。
むしろ、「どんな環境で、どんな価値観のもとで働きたいか」を自分なりに持っている方が、選考では強みになる。たとえば「自分で考えて提案できる環境がいい」「人と関わりながら進める仕事がしたい」といった視点を軸にすることで、IT企業の中でも自分に合った職種が見えてくる。
「自分で仕事をつくっていける業界」という視点を持つ
IT業界は、他の業界に比べて変化が速く、新しい分野や働き方が次々と生まれる。その分、「自分で仕事の形をつくっていける業界」とも言える。
文系出身でも、マーケティング、プロジェクトマネジメント、UI/UX設計、テックライティングなど、技術と人間理解をつなぐ仕事は多い。そうした可能性に魅力を感じるなら、たとえ不安があっても、踏み出す価値はある。
文系出身の若手たちが語る“リアルなつまずきと突破口”
未経験入社で感じた「専門用語の壁」
会議がまるで外国語。最初は“聞くだけ”でも焦らない
文系出身でIT企業に入った新卒の多くが、口を揃えて語るのが「言葉がわからない」という壁だ。
たとえば、社内の朝会やクライアントとのミーティングでは、「API」「インフラ」「SaaS」「負荷分散」といった専門用語が飛び交う。エンジニア同士のやりとりはとくにスピード感があり、最初の頃は“何もわからないけど笑顔でうなずいていた”という学生も少なくない。
ここで大事なのは、「わからない=ダメな奴」とは限らないという認識だ。入社直後の段階では、“聞き慣れてないから理解できない”というだけで、語彙力や思考力が足りないわけではない。
文系出身者の多くは、メモをとって後で自分で調べる、理解したことを先輩に確認する、というプロセスを通じて、徐々に「言葉の意味と使い方」を身体で覚えていく。
「すぐ理解しなきゃ」に縛られないことが鍵
「文系なのにITに来たから、誰よりも頑張らなきゃ」「理解力が低いと思われたくない」と焦る気持ちはわかるが、そこで無理をして空回りしてしまうと、逆に自信を失いやすい。
最初から完璧に理解できる新人などいない。重要なのは、“学ぶ姿勢を見せ続けること”であり、“わからないことを放置しない”ことだ。たとえば、Slackや社内チャットで「◯◯という単語、文脈的にこういう意味で合ってますか?」と先輩に質問できる素直さは、むしろ好印象につながる。
「プログラミング=無理」という先入観との向き合い方
コーディングが苦手でも“使い道”で理解を深める
「文法から学ぶ」より「何を実現したいか」で考える
文系出身者がプログラミングに苦手意識を持つのは当然だ。高校や大学でコードを書く機会がなかった人にとって、アルファベットと記号の羅列は“呪文”に見えてしまう。
しかし、実際の業務では「0からすべてのコードを書く」より、「既存のコードを読み解く」「APIを連携して処理を組み立てる」といった作業のほうが多い。大切なのは、「どういう処理をしたくて、そのためにどんなコードを書くのか」という“目的意識”だ。
たとえば、「このボタンを押したら、顧客情報を自動でデータベースに保存したい」というシーンがあるとする。そういった“業務上の必要性”が見えると、コードもただの記号ではなく、“手段”として理解できるようになる。
覚えるより「使って慣れる」ことを意識する
「写経(他人のコードを書き写す)しても意味がわからない」「本を読んでも実感がない」という悩みは多い。文系にとっては、概念的な知識よりも、“体験ベースで覚える”ほうが効率的なことが多い。
実際に文系出身で活躍している人の多くは、次のような工夫をしていた:
自分用の簡単なWebページを作ってみた
業務で使っているツールの仕組みを調べてみた
エラーが出たら“その原因と直し方”をノートにまとめた
このように、「使って理解する」アプローチをとることで、ただの学習が“血の通った知識”に変わる。
チームに馴染めない不安をどう乗り越えるか
「雑談が苦手」でも仕事の場では別物と割り切る
IT業界の“フランクさ”と“独特の距離感”を理解する
IT業界には「風通しが良い」「上下関係が緩い」というイメージがある。そのため、文系出身者の中には「会話が得意な人が多い」と思い込み、自己否定に陥るケースがある。
だが実際には、技術職の現場では“必要なことを必要なだけ共有する”文化が強く、無理に世間話をしようとする必要はない。チャットでのやりとりも、スタンプ一つで感謝を伝える文化が根づいていたりする。
「雑談力がない自分はITに向いてない」と感じてしまうのは早計だ。むしろ、自分の性格に合った“静かなコミュニケーション”が許される土壌があるのは、文系の中でも内向的なタイプにとっては救いになる。
仕事を通じた信頼構築が“人間関係”になる業界
“話がうまい人”より、“期限を守る人”“聞かれたことに正確に答える人”の方が信頼されやすいというのも、IT業界の特徴だ。つまり、「うまく会話できない」ということを過剰に気にする必要はない。
自分の担当タスクを確実にこなす、メンバーに感謝を伝える、エラーや困りごとを隠さず共有する。そうした“仕事のコミュニケーション”こそが、ITの現場における「人間関係」そのものだ。
“文系ならでは”の強みを仕事に活かしている人たち
技術を“使う人の視点”で見られる力
自分がユーザーだった経験が活きる
文系出身でIT業界に入ったある若手社員は、「エンジニアはコードを改善するが、私は“この機能って誰の役に立ってるんだろう”を気にする」と話す。自分がサービスの“受け手”だった経験が、仕事での問いかけに繋がるという。
たとえば、大学時代に使っていた就活サイトの不便さ。バイト先での業務の煩雑さ。そうした“使い手としての不満”が、ITサービスの改善につながるヒントになる。文系ならではの生活感覚は、ITの現場において“リアルな視点”として貴重なのだ。
“感情の変化”を観察できる目がUXに活きる
また別の社員は、文系出身でマーケティング職に就き、ユーザーの行動分析やUI改善を担当している。彼女は「技術そのものより、“人がどう感じるか”を想像するほうが得意」と語る。
ユーザーがどこで離脱するか、どの言葉に反応するか、どんなデザインが信頼を生むか。こうした感情ベースの観察力は、文系出身者の方が長けているケースも多い。ITは「人に届けてナンボ」の世界。人の動きや心を見つめる力は、十分に武器になる。
文系からIT業界を目指すなら、どんな行動を起こせばいいのか
業界研究ではなく「現場の雰囲気」を先に掴む
IT企業の選び方に“公式”はない
文系出身者の多くが最初に悩むのが、「どの会社を受ければいいかわからない」「自分に向いている会社がわからない」という不安だ。ITとひとことで言っても、SIer、Web系、自社開発、SES、スタートアップなど会社の種類や文化はバラバラで、いきなり「志望動機を書け」と言われてもピンとこないのは当然だ。
このときに有効なのが、「雰囲気重視で企業を見てみる」というやり方。業界や職種を無理に決めるのではなく、まずは社員との距離感、1日の業務の流れ、どんな雰囲気で働いているかなどを先に知ること。自社サイトよりも、現場社員が登壇するイベント、インターン、カジュアル面談などの“人ベースの接触”がヒントになる。
文系にとっては「仕事内容」よりも、「人との相性」や「文化の合う・合わない」がミスマッチの大きな要因になる。であれば、現場を感じ取ることを優先した方が、納得のいく志望動機にもつながりやすい。
現場社員と話せる場を自分で探しに行く
本音を言えば、企業HPや採用ページだけを眺めても、文系学生にとっては「よくわからないままエントリーする」状態になりやすい。IT企業の選考はスピードも早く、採用担当も専門的な説明をしてくれるとは限らない。
だからこそ、自分で“探しにいく”姿勢が問われる。オープンイベント、インターン、逆求人型サービス、社員のSNS投稿など、「企業の内側に触れられる場所」を意図的に見つけておくこと。たとえ直接選考につながらなくても、その会社を基準に「自分の合う企業像」が少しずつ見えてくる。
“IT職種”で求められるスキルをどう補うか
文系のままで勝負せず、1つでも「できること」を作る
“未経験OK”をそのまま信じすぎない
よく「IT企業の営業やPMは未経験OK」と言われるが、現実には“未経験者の中でもできる人”が内定を取っている。つまり、たとえ職歴や専攻がなくても、「自分からITを学んでいる」「ツールを触ってみた」「考え方を理解しようとしている」といった“姿勢”が評価されているということだ。
「知らない」「やったことがない」だけの状態では、やはり志望者の中で印象は薄くなる。逆に、「少しでも触れてみた」「参考書1冊終えた」「ノーコードで作ってみた」など、自発的に学びに触れた経験があれば、それはしっかり武器になる。
ゼロから学ぶなら「ツール」や「ノーコード」から
いきなりプログラミングを始めるのが怖いという学生には、NotionやSlack、Google Apps Script、STUDIO、Bubble、Canvaなどの“実務に近いツール”から入るのが現実的だ。
たとえば、以下のような行動は、すぐに始められて履歴書にも書ける内容になる:
Googleスプレッドシートで関数を組んでみる
自分用のタスク管理サイトをノーコードで作ってみる
Notionでポートフォリオや就活メモをまとめる
AIツールを活用して「自分の強み診断」を作ってみる
こうした経験は、「自分で学ぶ→形にする→説明できる」というサイクルを回す練習になる。文系だからこそ、「自分が何を作ったのか」「なぜ作ろうと思ったのか」を言葉で伝えられる点が活きてくる。
“情報弱者”にならないための就活リテラシー
情報源が偏ると視野も選択肢も狭くなる
大手ナビだけ見ていると、ITは見つからないこともある
IT業界の多くの企業は、大手ナビサイトに掲載していないか、掲載していてもエントリー数の少ない“穴場”に近い存在であることも多い。特に中小・スタートアップは、独自ルートで採用活動を行っており、情報が見えづらい。
そのため、「ナビで検索→志望動機を書く→面接」という従来型の就活フローでは、IT業界での本質的な企業選びには限界がある。結果として、「なんとなく知ってる会社ばかり受けて落ちる」「自分の行きたい会社が見つからない」という事態に陥る。
就活“だけ”をしていると、リアルなITに近づけない
文系でITを目指すなら、就活情報以外にも、“業界情報”や“現場で使われているツール・考え方”に定期的に触れておくことが重要だ。たとえば、YouTubeでエンジニアのVlogを観る、X(旧Twitter)でIT企業の若手をフォローする、Qiitaやnoteで技術・業務記事を読むなど、日常的に“肌感覚”を育てておく。
就活とは別軸でIT業界の空気感を知っておくと、面接で「実際にどんな仕事に関心があるのか」を聞かれたときにも、他の学生とは違うリアルな言葉が出てくるようになる。
最後に:文系だからこそIT業界で活きる視点を持てる
技術が「目的」ではなく「手段」だと理解している強み
ITの現場では、エンジニアでも営業でも、最終的に求められるのは「誰の、どんな課題をどう解決するのか?」という視点だ。そして、それはまさに文系が得意とする「人を観察する力」「背景を想像する力」「言葉にする力」に直結する。
たとえコードが書けなくても、サービスを分析し、使う人の気持ちを考え、それを誰かにわかる形で伝えることができれば、文系はIT業界で十分に評価される。むしろ、「技術にこだわりすぎない視点」こそ、チームにとって必要不可欠な存在にもなり得る。
まとめ
文系からIT業界を目指すことは“難しい”というより、“戦い方が違う”だけ
技術的な素養がなくても、「何を学ぼうとしたか」「どんな視点で関心を持ったか」が伝われば十分に勝機がある
コミュニケーションは雑談よりも「仕事を通じた信頼」の方が重視される業界
自分の中にある“文系的な視点”が、ITサービスや職場の中で価値を持つケースは多い
やりたいことが決まっていなくても、“まずは動いて触れてみる”ことで、徐々に自分の方向性が見えてくる
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます