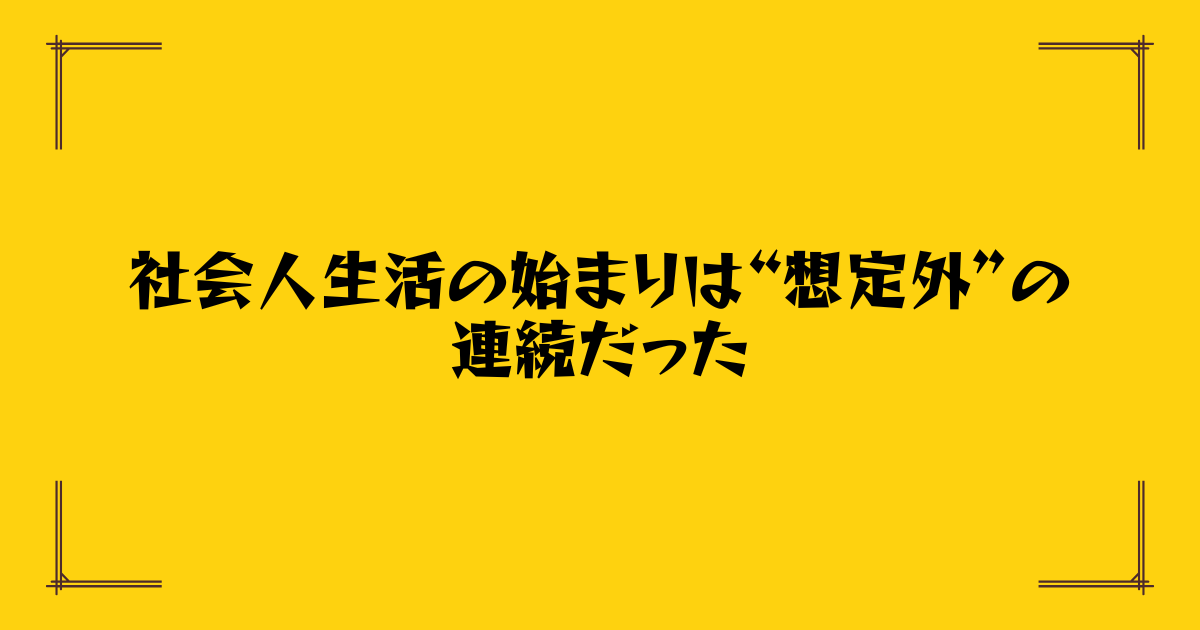「覚悟していたはず」の現実が違っていた
入社式が終わり、名刺を受け取って、いよいよ社会人としての第一歩を踏み出した。スーツを着て、会社に通って、自分の机があり、毎日先輩社員に囲まれながら働いている。そんな「想像していた社会人生活」と、実際に目の前にある現実との間に、違和感や戸惑いを感じている人は少なくない。就活中に「早く働きたい」「現場に出てみたい」と前向きな気持ちだった人でさえ、実際に社会に出ると、驚くほど多くの“想定外”にぶつかる。
多くの新入社員がまず最初に感じるのは、「思っていたより何もわからない」という感覚だ。学生時代は、初めての授業でもある程度は教えてくれるし、参考書やテキストが整っている。でも会社では「まずやってみて」と言われ、明確な手順や答えが用意されていない仕事を渡されることが多い。そこに戸惑いを覚えるのは当然のことだ。
「学生ノリ」は歓迎されないこともある
もう一つの想定外は、“空気感の違い”だ。特に人間関係において、学生時代と同じテンションで話してしまい、少し浮いてしまったり、真剣な場面で軽い発言をしてしまったりすることで、「まだ学生気分が抜けてない」と見られることがある。仲の良さやノリを重視する大学のサークル文化と、ビジネスの場での関係性はまったく別物であり、上下関係や責任、業務上の緊張感が求められる。
そうした環境の変化に戸惑い、無意識に萎縮してしまう人も少なくない。職場に馴染めない、うまく話しかけられない、自分だけ取り残されている気がする……そんな孤独感もまた、社会人一年目に多い“壁”のひとつだ。
「理想と違う」ことに気づいたときの戸惑い
入社してすぐの段階では、「この会社を選んでよかった」「やっぱりこの業界に来て正解だった」と自分を納得させようとする気持ちが働く。しかし、時間が経つにつれて、業務の詳細や上司の方針、会社の文化などが見えてきたとき、「あれ、思ってたのと違うかも」と違和感を覚えることがある。
この「理想とのズレ」は、自分のやりたいことと与えられる仕事のギャップであったり、企業文化への適応の難しさであったりする。志望動機で語った「社会貢献」や「グローバルな仕事」が実際には自分の部署では関係なかったというようなケースもある。もちろん、これはあなただけに起きていることではない。多くの新社会人が、このギャップにぶつかり、「このままでいいのかな」と立ち止まることになる。
最初にぶつかる“壁”は人間関係と仕事の理解
同期とは仲良くても、上司や先輩が遠い
人間関係の構築は、社会人にとって最も重要で、かつ最も難しい課題の一つだ。とくに新卒で入社したばかりの時期は、年齢も経験も大きく離れた人たちに囲まれ、「話しかけにくい」「何を考えているかわからない」と感じることが多い。学生時代のようなフラットな関係ではないため、遠慮や緊張から自分を出せず、会話がぎこちなくなりがちだ。
さらに、業務についてわからないことがあっても「こんなこと聞いたら迷惑かも」と感じてしまい、質問を躊躇してしまう。その結果、わからないことが蓄積し、ますます距離ができてしまう。この悪循環に陥らないためには、「今の自分には分からないことが多くて当たり前」という前提を持ち、勇気を出して相談することが重要だ。
「何をしている会社なのか分からない」という悩み
もうひとつよく聞かれる悩みが、「自分の仕事が何の役に立っているのか分からない」というものだ。特に新卒で配属された部署では、補佐的な業務やルーティン作業が多く、「こんな作業の繰り返しでいいのだろうか」と不安を抱える人が多い。成果が見えにくいポジションであるほど、その不安は強くなる。
だが実際には、どんな業務にも意味がある。その仕事が社内のどのプロセスに関わっているのか、誰の仕事につながっているのかを知ることで、自分の役割に自信が持てるようになる。周囲に「この作業って何のためにやってるんですか?」と率直に聞いてみることも、理解の第一歩になる。
想定外が多いのは“あなたが劣っているから”ではない
他の人がうまくいってるように見えても気にしない
新入社員の頃は、同期や他部署の同世代とつい比べてしまうことがある。「あの人はもう〇〇のプロジェクトに入ってるのに、自分はまだ雑務ばかり」「同じ日に入社したのに、あの子は上司からよく頼られている」など、自分だけが成長していないように感じることがあるだろう。
しかし、それはあくまで外から見た印象であり、必ずしも実態とは限らない。むしろ、焦らずに自分の足元を固めることが、後々の信頼や成長につながる。今は“地味”に思える作業も、組織においては大切な基盤を支えている。そこに誠実に取り組む姿勢が、信頼につながる。
「向いてないかも」と感じても、すぐに結論を出さなくていい
新社会人の1〜3ヶ月目にありがちなのが、「この仕事、自分には向いてないかも」と感じてしまうことだ。たしかに、向き不向きというのは存在するし、長期的にはその見極めも重要だ。しかし、入社して間もない段階では、“まだ仕事を知り切っていない”状態であることを忘れてはいけない。
一度も自転車に乗ったことがない人が、「乗れそうにないから無理だ」と言っているようなもので、慣れていない状態では判断は難しい。少なくとも半年、できれば1年は「自分を知る期間」「仕事に慣れるための時間」として捉えるほうが、精神的にも安定しやすくなる。
思ったより“放置される”新社会人のリアル
手取り足取り教えてもらえると思っていたのに
多くの新入社員が入社前に抱くイメージのひとつが、「最初は丁寧に教えてもらえるだろう」という期待だ。学生時代のアルバイトやインターンでさえ、初日は先輩がそばにいて業務を説明してくれた経験がある人は多い。だからこそ、「社会人になって最初のうちは、もっと手厚くサポートしてくれるのでは」と考えていたという声は少なくない。
しかし、実際には「わからないことがあったら聞いてね」「とりあえずやってみて」というスタンスの先輩や上司が多く、細かく教えてくれる場面は意外と少ない。「初めてなんだからちゃんと教えてほしい」という気持ちはもっともだが、現場の忙しさや“社会人の常識”のようなものが前提となっていることも多いため、丁寧なフォローがされないまま時間が過ぎていく。
この状況は、「自分には期待されていないのでは?」「見捨てられてる?」と感じさせ、強い不安感につながることもある。しかし、この“ある程度放任される空気”は、実は多くの企業に共通している新卒教育のリアルだ。
「聞いていいのか分からない」から動けなくなる
先輩が忙しそうにしていると、「こんなことで声をかけていいのかな」と気を使ってしまう場面も多い。質問のタイミングを逃し、聞けないまま作業を進めようとしてミスをする。そうすると、「聞けばよかったのに」と言われ、さらに自信をなくしてしまう。こうした悪循環は、まじめで空気を読もうとするタイプの新入社員ほど陥りやすい。
さらに、「なにが分かっていないのか、すら分からない」という状態も新社会人にありがちだ。言葉の意味、ツールの使い方、仕事の目的……すべてが曖昧なまま、なんとなく「進めたふり」をしてしまうと、後で一気に信頼を失うことにもなりかねない。
ここで大切なのは、「分からない状態を隠さない勇気」を持つこと。質問が多いからといってマイナス評価されることはない。むしろ「理解しようとしている」「素直に学ぼうとしている」とポジティブに受け取られるケースが圧倒的に多い。迷ったらまず聞く。聞き方に迷ったら「この言葉の意味って確認してもいいですか?」など、前置きを加えると自然に質問ができる。
「教えてもらうのが当然」という意識を捨てる
放置されると感じる背景には、「教える側の余裕がない」という現実もある。先輩社員も自分の仕事に追われていることが多く、丁寧に説明する時間を確保できないまま、「とりあえずやってもらおう」と考えてしまう。これは決して新入社員に冷たいわけではなく、現場の人員や業務量のバランス上、仕方なくそうなっているケースがほとんどだ。
こうした環境では、「聞かれたら答えるけど、自分からは言わない」というスタンスが常態化しているため、自ら動かないと何も進まない。つまり、「教えてもらうのが当たり前」という意識でいると、成長のチャンスを逃してしまう。理不尽に感じるかもしれないが、社会人として早く成長するには「自分から動いて情報を取りに行く姿勢」が欠かせない。
仕事を覚えるコツは「メモ」と「確認」に尽きる
曖昧な理解で終わらせない習慣を持つ
業務の説明を受けたとき、すべてを一度で覚えるのは不可能だ。だからこそ、細かくメモを取ることが重要になる。ポイントは、単に言われたことを記録するだけでなく、「自分の言葉で整理すること」。例えば、言われた指示が「このファイルをAさんに送って」とだけだったとしても、「何の目的で送るのか」「どのタイミングで送るのか」「ファイル名や送信先の注意点」など、自分なりに解釈して書き加えておくことで、再現性が上がる。
また、分かったつもりで進めるのではなく、「こういう意味で合ってますか?」と確認を入れることで、認識のズレを防げる。初期の段階での“聞き直し”や“確認”は、のちの大きなミスを未然に防ぐ。質問することで不安が減り、安心して作業に集中できるようにもなる。
業務日報やふりかえりを活用する
新入社員が最初の数か月で飛躍的に成長できるかどうかは、「自分で振り返る習慣があるかどうか」で大きく分かれる。毎日の業務を終えたあとに、「今日何をしたか」「何に戸惑ったか」「次にどう改善したいか」をメモに残すだけでも、思考の整理になる。
多くの企業では、新入社員に業務日報や研修レポートの提出を求めているが、それを「やらされ仕事」にするのではなく、自分の成長のための材料として活用することが重要だ。何度も同じミスをしてしまう人は、同じようなことを毎日繰り返してしまっていることが多い。記録を残しておくと、自分のクセや傾向に気づきやすくなる。
「放置されても伸びる人」と「迷子になる人」の差
自分の“役割”を自覚して行動しているか
先輩があえて細かく指示しない理由のひとつは、「新入社員にも考えて動いてほしい」という期待が込められているからだ。すべて言われた通りにしか動けない人よりも、自分で状況を判断して動こうとする人のほうが、仕事の幅を早く広げられる。
例えば、「これ、Aさんに確認しておいて」と言われたときに、「なぜAさんなのか?」「何を確認すればいいのか?」「先にメールをしておいた方がいいのか?」など、考えて動ける人は自然と信頼される。仕事の指示をそのまま処理するのではなく、「自分の役割はなにか」を常に意識して行動することで、仕事に対する理解と責任感が育っていく。
言われなくても動ける人になるために
「言われたことを完璧にこなす」ことが新人の役割だと考える人も多いが、実際の現場では「指示の先を読んで動ける」人のほうが重宝される。これは才能ではなく、習慣で身につけられる。
たとえば、「この資料を印刷しておいて」と言われたときに、「相手は会議に使うのかもしれない」と想像できれば、「ホチキスで留めた方がいいか」「配布部数は?」と次の行動につながる。こうした“ちょっとした気配り”ができる人は、短期間で信頼を得やすい。最初はうまくいかなくても、「相手の立場で考える」習慣を持つことで、徐々に行動力が変わってくる。
期待した“やりがい”が感じられない理由
目の前の仕事に意味を見いだせない感覚
新社会人として働き始めて数週間から数ヶ月が経つと、徐々に仕事にも慣れ、業務の流れも掴めるようになる。一方で、「このまま続けていて本当に意味があるのか?」「やりたい仕事と違う気がする」といったモヤモヤを抱える人も少なくない。入社前に思い描いていた“やりがいのある仕事”が実際には地味で単調な作業の繰り返しだったり、ミスを恐れて積極的に動けなかったりと、自分の存在意義に疑問を感じ始めるタイミングがやってくる。
特に、学生時代に自己分析やキャリア設計に力を入れていた人ほど、「理想と現実のギャップ」に戸惑いや失望を覚えやすい。「人の役に立つ仕事がしたい」と思って就職したはずなのに、与えられた業務はデータ入力や資料作成、会議室の準備といった裏方の雑務ばかり。「こんなことのために就職したんじゃない」と感じるのも無理はない。
小さな仕事の“先”に目を向けられるか
しかし、仕事の意味ややりがいは、最初から与えられるものではない。特に新卒社員のうちは、どの職種でも“土台を固める時期”として、地味で目立たない仕事からスタートすることがほとんどだ。それは、組織の流れやルール、ツールの扱いに慣れ、仕事の基礎を身につけるために欠かせないステップだからだ。
たとえば、毎日のようにやらされるコピー取りも、内容や宛先、部数、タイミングなど、少しの配慮で成果物の質が変わる。議事録の作成もただの記録ではなく、要点をどう抽出し、次のアクションにつなげるかという“編集力”が求められる。目の前の作業にどれだけ意味を込められるか、それをどう捉えるかによって、同じ仕事でも“成長の糧”になるか“つまらない雑務”で終わるかが分かれる。
成長実感がないのはアウトプットが足りないから
「やりがいがない」と感じる背景には、「自分が何を成し遂げたか分からない」という状況もある。インプットばかりで、アウトプット(報告・提案・振り返り)がないまま日々が過ぎると、自分の成長も成果も可視化されず、達成感を得にくくなる。
解決策の一つは、「やったこと・学んだこと」を毎日言語化する習慣を持つことだ。たとえば、「上司に言われる前に資料の修正案を出した」「朝礼の話を参考に、業務改善を提案した」といった小さな成功体験を自覚することで、自己肯定感が育ちやすくなる。
さらに、学びを共有する機会があれば、自分の成長を人と比べるのではなく、「自分の中で積み上がっているかどうか」で判断できるようになる。「なんとなく働いてるだけ」で終わらせないために、アウトプットを意識した働き方が必要だ。
周囲と比べて焦る気持ちとの向き合い方
すごい同期に自信を失ってしまう
入社後、数ヶ月も経たないうちに「同期のあの子はもう一人で商談してるらしい」「あの部署の人は毎日残業してバリバリ働いてる」などといった情報が耳に入るようになる。そうした情報に触れるたびに、「自分はまだ何もできていない」「同じ新入社員なのにこんなに差がある」と焦りや劣等感を感じる人は多い。
特に、成長意欲の高い人ほど、「出遅れているのでは?」「もっと頑張らなきゃ」と自分を追い込みやすい。SNSなどでも“意識高い発信”が目に入ることが多く、自分とのギャップが大きく見えてしまう。
だが、他人のペースで生きようとすると、燃え尽きたり、自信を失ったりしやすくなる。社会人としての成長は“短距離走”ではなく“マラソン”だ。見えないところで積み上げている人が、最終的に大きく成長していくケースも少なくない。
自分の成長軸を“昨日の自分”に置く
焦りを和らげるには、「昨日の自分より成長しているか」という基準を持つことが有効だ。たとえば、先週まではミスを連発していた作業を、今週は1回で完了できるようになった。先輩の話をメモするだけだったのが、自分から提案できるようになった。こうした“小さな変化”を積み上げていく意識が、焦りや比較の罠から抜け出す鍵となる。
また、「自分が得意なこと」「他人より少し早く覚えられたこと」に目を向けることも重要だ。どんなに優秀に見える同期でも、苦手なことや苦戦している分野はある。自分の強みや興味に注目し、そこを深掘りして磨いていくことが、長期的に見て最も成長につながる。
心が折れそうな時のリセット法
「全部ダメ」と思ったらまず睡眠と食事
仕事で失敗した、怒られた、評価されなかった……そんな日は誰にでもある。何度も同じミスをしてしまったり、先輩とのコミュニケーションがうまくいかないと、「自分はこの会社に向いてない」「働くこと自体が向いてないのかも」とまで思ってしまうこともある。
そんなとき、無理に前向きになろうとせず、まずは「身体を回復させる」ことを意識してほしい。人は心が疲れるとき、実は身体の疲労が蓄積していることが多い。特に新社会人の生活リズムは大きく変わるため、慢性的な寝不足や栄養不足になっている人も多い。
よく眠り、よく食べる。それだけで、物事の見え方が変わることは多い。リセットの基本は「体調を整えること」だ。
立ち止まっても、逃げなければ大丈夫
心が折れそうになったら、「ちょっと止まる」「余白を作る」ことも大事だ。キャリアや成長のことを考えすぎると、頭の中がパンパンになってしまい、かえって身動きが取れなくなる。
そういうときは、無理に“前向きな思考”を押しつけるのではなく、「立ち止まっても、ゼロにはならない」と考えるのがよい。1日休む、誰かに話す、思い切って全然関係ない趣味に没頭してみる。少しの“脱線”が、結果的にリズムを整える回復につながる。
重要なのは、立ち止まっても「逃げ出さない」こと。逃げずに考え続けている限り、ちゃんと前に進んでいる。自分を責めずに、丁寧に向き合っていくことが、社会人として長く続けていく上での力になる。
乗り越えるための“環境の使い方”と“支援の求め方”
一人で頑張らないという戦略
新社会人が陥りやすいのは「すべて自力で乗り越えなければいけない」という思い込みだ。もちろん自律性は社会人にとって大切な資質だが、現実には「相談できる相手」「情報を得られる環境」を活用できる人ほど、挫折や壁を効率よく乗り越えている。
特に就職したばかりの時期は、上司や先輩、同期、他部署の人間など、会社内に“話せる人”を見つけることが鍵になる。ここで重要なのは、相手に「解決策をもらうこと」を期待するのではなく、「考えを整理するために話す」というスタンスを持つこと。答えが欲しいと期待して話すと、思うようなリアクションが得られなかった時にさらに落ち込んでしまう可能性がある。自分の中のモヤモヤを言語化する場として“対話”を活用すれば、それ自体が前進の一歩になる。
また、職場以外に相談できる環境を持つのも有効だ。大学のキャリアセンター、社会人向けのキャリア相談、同じ立場の友人たちなど、話す相手の立場が変わるだけで、視点やアドバイスの切り口が大きく異なる。自分だけの感覚や視野に閉じ込められないよう、複数の「外の窓」を持っておくことが、心の柔軟性を保つうえで役立つ。
“同期”の存在をどう捉えるか
同じ会社の同期、あるいは他社に就職した同年代とのつながりも、新社会人にとっては大きな支えになる。ただし、同期は“ライバル”でも“比較対象”でもなく、“安心して弱音を吐ける関係”であるほうがいい。
たとえば、仕事の失敗談や上司とのやり取りに苦戦しているエピソードなどを共有できる同期がいるだけで、「自分だけがつらいんじゃない」と思えるようになり、精神的な回復力が高まる。
もちろん、すべての同期と気が合うわけではないし、中には“マウント気質”のある人もいる。無理に付き合う必要はない。気が合う、信頼できる数人だけでもいれば十分だ。重要なのは、「職場以外にも味方がいる」と思える環境を自分の手で作っていくこと。
キャリアの“主導権”を取り戻す視点
入社1年目は“キャリア形成期”である
新社会人の1年間は、言わば「働くことの基礎体力」を養うトレーニング期間であり、本格的なキャリアの土台を築く重要なフェーズだ。どの会社、どの職種であっても、配属初期に与えられる仕事には、「業務の流れを覚える」「報連相の精度を高める」「責任感を持ってやりきる」という基本的なスキルセットを育てる狙いがある。
だからこそ、「やりたい仕事ではない」「配属が希望通りではなかった」としても、“遠回り”だとは決めつけないでほしい。むしろ、思い通りにならないことをどう咀嚼し、そこから何を学べるかが、将来のキャリア選択の自由度に大きく影響する。
「今の環境では自分のやりたいことができない」と感じたとしても、そこで得た人間関係の築き方や課題解決の経験は、次のステージで大きな武器になる。大切なのは、“自分のキャリアを会社に委ねないこと”。会社の方針に従うのではなく、あくまで自分が「この環境をどう使いこなすか」を意識して動けるかが鍵だ。
将来の選択肢は“1年目の動き”で広がる
新社会人がキャリアの主導権を握るには、1年目から「意図を持って動く」ことが大切だ。これは「転職を前提に考えろ」という意味ではない。むしろ、今の会社や職場でどんなスキルを得て、どんな実績を積むのかを戦略的に捉える意識を持つということだ。
たとえば、事務職で配属されたとしても、「この業務の流れを全体で理解していれば、どの部署でも活かせる知識になる」「Excelの関数や業務フロー管理の経験は将来の業務改善に活きる」といったように、自分の現在地を客観的に分析し、将来の選択肢につなげる視点を持つ。
また、「社外の人と接点を持つ仕事を積極的に希望する」「資料作成のスキルを磨いて企画書を書けるようになる」といった目標設定をすれば、日々の業務にも“目的”が生まれ、やりがいを感じやすくなる。主体性を持った行動の積み重ねが、将来の選択肢を豊かにする。
まとめ:つまずくのが普通。だからこそ“最初の壁”が力になる
社会人1年目は、多くの人にとって人生初の“本格的な挫折”や“違和感”を経験するタイミングだ。想像していた仕事とのギャップ、人間関係の難しさ、成長が実感できないもどかしさ、周囲との比較による焦り。そうした“想定外”の連続に、自信を失い、苦しみを感じることは珍しくない。
だが、それはあなただけの話ではなく、多くの新社会人がぶつかる“最初の壁”であり、むしろこの壁をどう越えたかが、今後の働き方に大きく影響していく。
つまずいたときに必要なのは、完璧に乗り越えることではない。転びながらも、“立ち上がる方法”を自分なりに見つけていくこと。体調を整え、話せる相手を持ち、小さな成功体験を積み、昨日より少し前に進む。この地道な積み重ねが、やがて大きな自信につながっていく。
仕事に“正解”はない。だからこそ、“正解のない世界”でどう振る舞うかを試されるのが、社会人としての最初の1年だ。その経験こそが、あなたのキャリアを豊かにし、働く意味を自分自身で育てていくための礎になる。焦らなくていい。立ち止まっても、悩んでも、ちゃんと進んでいる。そう信じて、一歩ずつ進んでいこう。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます