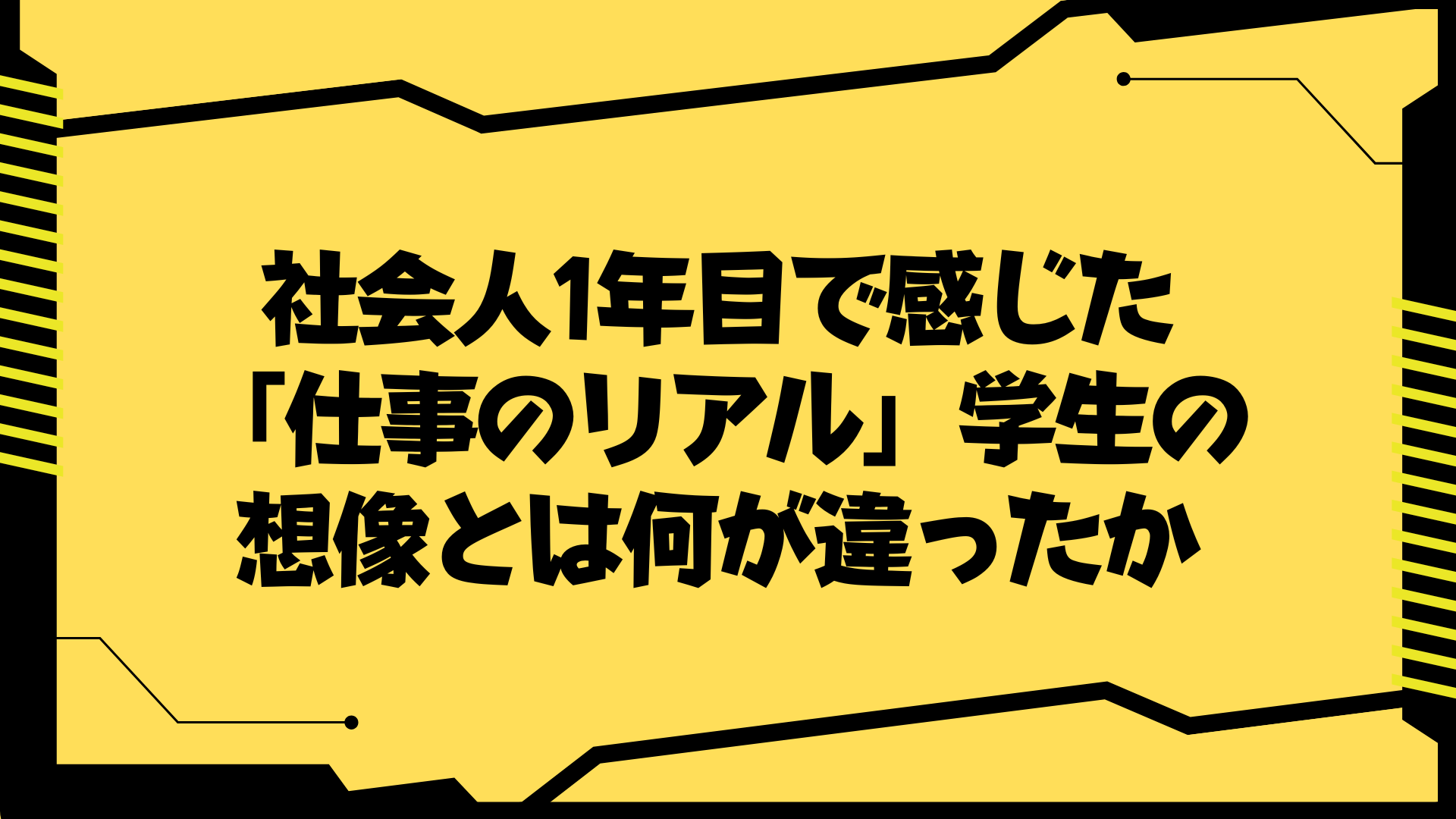理想と現実のギャップはなぜ起こるのか?
「働くってこういうことだと思っていた」の落とし穴
大学時代、就職活動を通じて企業を見て、「この会社ならやりがいがありそう」「この職種なら自分の強みを活かせるはず」と期待を膨らませて入社する学生は多い。だが、実際に入社してみると「思っていたのと違う」という現実に直面するケースも珍しくない。
たとえば、こんな声がある。
「裁量があるって聞いてたのに、毎日ルーティン業務ばかり」
「若手でも意見を言える社風と聞いたのに、発言する場がない」
「面倒見が良いと聞いていた先輩が全然構ってくれない」
このようなギャップは、就職活動中の情報収集や企業説明会での言葉と、実際の配属先の現場環境との間に“温度差”があることが原因で起こることが多い。企業は総じて「理想の会社像」を語る傾向が強く、学生もそれを素直に受け取ってしまうため、「現実」の温度に触れた瞬間に大きな違和感となって表出する。
だが、こうしたギャップは“騙された”というよりも、情報の解像度不足と想像力の不足の合わせ技によって生じている。
社会人1年目のリアル:思っていたよりも「自由は少ない」
時間は自分で決められない
学生生活の最大の特徴は、「時間の自由」があることだ。講義やアルバイト、ゼミ、サークルなど、自分の裁量でスケジュールを組むことができる。しかし社会人になると、会社の始業時刻や会議の予定、他部署との連携などにより、自分の意志ではどうにもならないスケジュールの中で生きることになる。
会議が朝8時から入る
昼休みが自分の希望通りに取れない
突発的な依頼が入って残業になる
こうした環境の中で、初めて「自由に使える時間」がほぼ存在しないことに気づく。働くとは「お金をもらう」ことではなく、「責任を引き受けること」であり、それは“自由”をある程度手放すことと同義だ。
業務内容の決定権は自分にない
配属された部署での業務は、必ずしも希望通りとは限らない。たとえば「企画職として入ったのに、最初は営業から」というのはよくある話だ。企業側からすれば、「全体を知るためにまず現場から」という方針があったとしても、本人からすると「希望と違う」「なんでこの仕事をやっているんだろう」と感じる。
学生時代のバイトでは、「これをやりたい」と言えばある程度希望が通る環境もあったかもしれない。しかし企業の中では、全体のバランスや配属枠、リソースの事情など、個人の希望だけでは動かない要素が圧倒的に多い。
成長を感じられない時期が思っていた以上に長い
毎日やってるのに「自分は成長してるのか?」
多くの学生が「働けば成長できる」と信じて社会に出る。しかし、いざ働き始めてみると、「この業務の意味がわからない」「単純作業ばかり」「言われたことをやってるだけで、自分の判断で動いていない」といった思考に陥り、“自分が何もできていない”ように感じる時間が続く。
これはほとんどの新卒社員が通る「停滞感のトンネル」だ。入社直後は右も左もわからず、手探りで仕事を覚える。次第に覚えた業務をこなすようになるが、応用が利くわけではないため、「誰でもできることをやってるだけじゃないか?」と不安になりやすい。
しかしここで大事なのは、“自覚がないだけで、確実に成長している”ということ。たとえば以下のような変化は、本人には見えづらいが周囲から見れば明確だ。
同じ質問を何度もしなくなった
指示待ちではなく、自分で動くようになった
ミスに気づけるようになった
これらはすべて、“基礎力が身についてきた証拠”だが、自分では当たり前になっているため気づきにくい。
成長とは「自分の手応え」ではなく「他人に役立てている実感」
多くの学生が、「やりがい=自分の成長実感」と思いがちだが、社会人になって見える現実は少し違う。仕事における“やりがい”は、「誰かの役に立った」と感じられた瞬間に初めて芽生えることが多い。
たとえば、資料作成を任されたときに、それを上司が会議で使い「これ、助かったよ」と言われた瞬間、自分の仕事に意味があったと実感できる。逆に、どれだけスキルを磨いても、それが誰にも求められていなければ達成感は薄い。
成長とは、自分のためではなく、他者の期待に応えられる状態になることだ。この視点に気づけるかどうかが、社会人1年目の壁を乗り越えるカギになる。
「向いてないかも」と感じたときに見直すべき視点
「向いてない」ではなく「慣れていないだけ」かもしれない
新卒1年目の壁の一つに、「自分にはこの仕事、向いてないかも…」という不安がある。だが、ここで重要なのは“本当に向いていないのか”と“ただ慣れていないだけなのか”を区別することだ。
慣れていないだけで起きる現象には以下のようなものがある。
効率が悪く、時間ばかりかかってしまう
ミスが多く、周囲に迷惑をかけてしまう
指示の意図がわからず、混乱する
これらは“経験不足”が原因であり、「向いていない」のではない。逆に言えば、同じことを繰り返すうちに慣れ、苦手意識が薄れる可能性があるということだ。
ただし、仕事の価値観や職場の文化がどうしても合わないと感じた場合は、見極めが必要になる。これは次回以降で詳しく掘り下げる。
社会人1年目の「辞めたい」の正体:本当に仕事が合っていないのか?
「辞めたい」と感じる瞬間は誰にでもある
ネガティブな感情の出発点
新卒で入社して数ヶ月から半年ほど経つと、多くの若手社員が「辞めたい」と感じる瞬間を経験する。残業が続く日々、理不尽な上司、成果が出せないプレッシャー、職場の人間関係のストレスなど、理由は人によって異なるが、その根底には「自分には無理なのではないか」「このままでいいのか」という不安がある。
この時期の悩みの特徴は、漠然とした焦燥感や孤独感である。「誰かに相談してもどうにもならない」と感じ、自分の中だけで問題を抱え込みやすい。周囲は忙しく、自分のことを気にかけてくれないように見えることも少なくない。
だが、こうした感情は決して珍しいものではなく、むしろ誰にでも起こる「自然な通過点」である。
辞めたい気持ちの背景にある3つの要因
辞めたいという感情には、大きく分けて以下のような要素がある。
身体的・精神的な疲労の蓄積
業務に慣れない中での残業や緊張状態の継続は、心身にダメージを与える。
達成感や成果の欠如
目に見える結果が出ず、やりがいを感じられない期間が続くとモチベーションが下がる。
自分の価値が見えなくなる
周囲と比べて自信を失い、「自分だけが置いていかれている」と思い込む。
この3つが絡み合うと、「辞めたい」という感情が現実味を帯びてくる。しかし、ここで大切なのは、“辞めたい”と“辞めるべき”は別問題だということだ。
見極めるべきは「環境の問題」か「自分の方向性の問題」か
職場環境に問題がある場合
職場でのパワハラ、過度な残業、極端な人手不足など、明確なブラックな要素がある場合は、早期に環境を見直すべきである。働く上での安全・安心が確保されていない職場は、長くいるだけで心身に悪影響を及ぼす。
また、業務内容や職場文化が極端に自分の性格と合わない場合も、長く留まることで自己否定感が強まり、パフォーマンスが下がる危険がある。たとえば、内向的な人が過度に体育会系の営業部署に配属された場合、単なる「慣れ」の問題では済まないケースもある。
このような場合は、「逃げ」ではなく「自分を守る判断」としての転職が正当化される。
自分の中に問題がある場合
一方で、「上司が厳しい」「仕事がつまらない」「思っていたのと違う」という感情が強いものの、客観的に見て業務や環境が特段悪いわけではない場合、見直すべきは“自分の働き方”や“期待値”の可能性がある。
社会に出るまでに思い描いていた「働く自分」の理想像が高すぎると、目の前の現実とのギャップに失望することは多い。だが、それは多くの場合、自分の期待値を現実に寄せていく“調整力”がまだ足りていないだけである。
このようなケースでは、数ヶ月の経験と内省を経て「仕事の見え方」が大きく変わることもあるため、焦って結論を出すのではなく、まずは少し立ち止まり「自分が変えられる部分」を探してみることが重要だ。
「合っていない仕事」と「楽しくない仕事」は違う
最初から楽しい仕事は存在しない
「この仕事は自分に向いていない」と感じたとき、多くの人が「じゃあ、向いている仕事に就けば楽しく働けるはず」と思いがちだ。しかし現実には、どんな仕事も最初から楽しいと感じられることはほとんどない。
新しい業務、知らない業界、慣れない人間関係。すべてが初体験の中で「楽しい」と感じるには、相応のスキルと余裕が必要になる。つまり、「楽しくなる前の段階」で辞めてしまうと、“本当の向き不向き”を判断する材料が揃わないまま終わってしまうのだ。
一方で、向いていない仕事とは、以下のような傾向を指す。
継続的に極端なストレスを感じる
何をやっても改善が見られない
小さな成功体験すら積めない
このような場合は、転職を含めた選択を検討する価値がある。ただし、「嫌だから向いてない」と判断するのではなく、原因を深掘りした上での判断が不可欠である。
「今は辞めない」という選択肢の価値
辞める自由と、続ける価値は両立する
現代の就職市場では、以前ほど「石の上にも三年」という価値観は強くない。「無理だと思ったら早めに辞めるべき」という意見も増えている。しかしその一方で、辞めないことが大きな意味を持つこともある。
たとえば、「半年後に異動のチャンスがある」「来月からプロジェクトメンバーに入る」など、先の見通しがある場合、多少の我慢や踏ん張りが経験値として蓄積されることがある。結果的に、その経験が自信になり、次のステップでも大きな武器になる。
自分なりの「納得感ある結論」を持つ
重要なのは、「辞める」か「続ける」かを“感情”だけで判断しないことだ。納得感のある結論とは、以下のようなものだ。
〇ヶ月頑張っても改善がなければ退職を検討する
自分の目標に対してこの職場でできることが限られていると判断した
精神的・身体的な限界を超えていると自覚した
このように、主観だけでなく客観的な材料を揃えて結論を出すことで、「あのときやめてよかった」「あのとき続けてよかった」と自信を持って言える未来につながる。
本当に自分に合う仕事とは何か:適職を「探す」より「育てる」視点
「やりたいことがわからない」問題の正体
多くの人が抱える“職業選択の迷子状態”
新卒の段階で「これが天職だ」と断言できる学生はほとんどいない。「なんとなく営業職」「安定してそうだから事務職」といった曖昧な理由で職種や企業を選ぶことは珍しくなく、社会に出てから「本当にこれでよかったのか?」という疑問を持ち始める。
「やりたいことがわからない」という悩みの裏には、以下のような思考がある。
ひとつの仕事で一生を決める前提になっている
“向いている仕事”を他人やネットから探そうとしている
仕事=楽しいもの・ワクワクするものだと思い込んでいる
しかし現実には、やりたいことは行動と経験によって見つかるものであり、最初から明確に定まっているケースの方が少ない。
「何が向いているか」は自己認識ではわからない
向いている仕事を見つけたいという願望は自然なことだが、初めて経験する仕事に対して、事前に適性を見抜くのは不可能に近い。というのも、人間の適応力や成長の速度は“やってみないとわからない”からだ。
たとえば、「話すのが苦手」と思っていた学生が、営業職でお客様と接するうちに「人と話すことが好きになった」というケースは珍しくない。逆に、文章を書くのが得意だった人が、ライティング業務の締切や修正の多さに疲弊し、「好きなことを仕事にするのは辛い」と感じることもある。
つまり、「向いているかどうか」は、最初ではなく“続けてから”でないと判断できないという現実がある。
適職は「探す」より「育てる」もの
最初は“相性50%”でも問題ない
多くの人が「100%自分に合った仕事」を求めようとするが、実際には最初から完全に相性のいい仕事に出会える人はごく少数だ。むしろ、「50%くらい合っている」と感じた仕事を、経験や工夫によって“育てていく”という姿勢の方が現実的である。
具体的には以下のような工夫が挙げられる:
苦手な業務の中にも「得意にできる可能性がある」部分を探す
成果を可視化してモチベーションを維持する
自分なりのやり方を模索して、楽しめる工夫をする
こうした工夫を積み重ねることで、当初は苦痛だった仕事も「自分なりに意味を見出せる仕事」へと変化していく。
これが「仕事を育てる」という考え方である。
職場環境が「向いている仕事」を育てる後押しになる
同じ仕事内容でも、職場の環境や上司・同僚の存在によって感じ方は大きく変わる。例えば、フィードバックが丁寧な上司や、相談しやすいチームに恵まれた場合、たとえ向いているとは言えない業務でも前向きに取り組めることが多い。
逆に、どんなに自分に合っていそうな業務内容であっても、劣悪な人間関係や評価されない職場であれば、「向いていない」と早合点してしまう可能性がある。
したがって、適職を見極める際には仕事内容だけでなく、環境との相性にも目を向けることが重要である。
「合う仕事」は“納得感”と“成長実感”がカギ
やりがいは「成果×意味付け」で育つ
どんな仕事でも、やりがいや達成感を得るには時間がかかる。最初のうちは「何の意味があるんだろう」と感じるルーティンワークでも、継続と工夫を重ねることで、“自分なりの意味”を見つけることができる。
たとえば、毎日繰り返す電話応対も「お客様のニーズを最初に把握する大事な接点」と捉えられれば、そこにやりがいを見出せる。
このように、仕事に意味を与える力=意味付けの能力は、自己肯定感や職務満足度にも直結する。
「自分なりの成長」を指標にする
向いている仕事かどうかを見極める際、他人との比較は参考にならない。なぜなら、人それぞれのスタート地点も、成長のスピードも違うからである。
「半年前より○○ができるようになった」
「先輩に任される仕事が増えた」
「苦手だった対応がうまくいった」
こうした“自分なりの小さな成長実感”こそが、仕事との相性を判断する一つの材料になる。
他人と比べて「向いていない」と決めつけるのではなく、過去の自分と比べて成長しているかどうかを基準に考える方が、健全な職業観を育む助けになる。
判断を誤らないために必要な視点
「今がすべて」ではないという認識
社会に出たばかりの1〜2年は、どんな仕事も“自分らしく働ける感覚”を得にくい。経験不足、人間関係の構築途上、社内文化の理解など、すべてが不安定な状態だからだ。
この時期の不安や不満をすぐに「向いてないから辞めよう」と結論付けるのではなく、「この仕事が合っているかは、もう少し続けてみてからでも判断できる」という余白を持つことが大切である。
「仕事観の変化」を見越しておく
人の価値観や働き方の優先順位は、年齢やライフイベントによって変化していく。20代のうちは成長や挑戦を重視し、30代以降になると安定やワークライフバランスを重視する人も増える。
つまり、「今の自分」に合う仕事が、「将来の自分」にも合っているとは限らない。その逆も然りだ。
だからこそ、最初の職場がすべてではなく、これから先も仕事観は変化し続けるという前提で働くことが、キャリアを長く楽しむコツである。
本当に辞めるべきタイミングと、後悔しないためのキャリア判断
「辞めたい」と感じたとき、まず考えるべきこと
一時的な感情か、継続的な不一致かを見極める
仕事をしていると、誰しも一度は「もう辞めたい」と思う瞬間がある。それは、ミスをしたとき、理不尽な対応を受けたとき、あるいは評価されないと感じたときかもしれない。しかし、その感情が一時的なものであれば、辞める理由としては弱い。
退職を検討する際は、まず以下のような点を振り返る必要がある:
「辞めたい」と感じた理由は突発的なものか、それとも繰り返し起きているか
1ヶ月後、3ヶ月後も同じように辞めたいと思い続けているか
状況を改善するために行動したか、誰かに相談したか
このように、「環境を変えること」よりも「自分が働きかけること」で改善できる余地があるかを見極めることで、早まった判断を避けられる。
体調・精神状態の悪化は例外的に最優先
ただし、心身の健康を著しく害している場合は、状況の改善を待つべきではない。以下のような状態が続いている場合は、迷わず退職や配置転換の相談をすることが望ましい:
毎朝会社に行くことが強い苦痛になっている
睡眠障害や食欲不振が続いている
会社や上司からのプレッシャーで涙が止まらない日がある
このような状態は、職場環境ではなく命に関わる問題であるため、速やかな対応が必要だ。自分の健康を守ることが、結果的に今後のキャリアをつぶさない選択につながる。
転職を決断する前に整理しておきたい視点
「なぜ辞めたいか」を言語化する
辞めたいと思ったとき、感情的に「合わない」「つらい」で済ませてしまうと、転職しても同じような悩みにぶつかりやすい。そこで重要なのが、辞めたい理由を具体的に言葉にして整理することである。
たとえば:
「上司の指導スタイルが自分に合わず、毎日萎縮してしまう」
「目標が売上重視で、お客様に寄り添った対応ができない」
「この業務を続けてもスキルが伸びていく実感がない」
こうした整理ができると、自分が何を大事にしているのか、どんな環境で力を発揮しやすいのかが見えてくる。そして転職先を選ぶ際にも、自分の基準を持った判断が可能になる。
「次を決めてから辞める」は正しいか
多くの人が「次の転職先を決めてから辞めるべきだ」と考えるが、これは一概には正しいとは言い切れない。なぜなら、在職中に転職活動を進めるには、時間的・精神的な余裕が必要だからである。
とくに心身の疲労が深い場合、働きながら活動を続けることで逆に判断を誤ることもある。そんなときは、「一度立ち止まって休む」という選択も視野に入れるべきだ。
重要なのは、「仕事を辞めた=失敗」ではなく、その後の時間をどう活かすかという視点でキャリアを考えることである。
「転職=逃げ」ではなく「戦略的撤退」と考える
長期的に見たキャリア設計の視点を持つ
本当に合わない職場に長く留まることが、キャリア上の“損失”になることもある。スキルが身につかず、評価も上がらず、年齢だけ重ねて市場価値を下げてしまうことは避けたい。
転職をすることが、「逃げ」ではなく「戦略的撤退」であるためには以下の条件が重要になる:
自分なりに「ここで努力したこと」「成長できたこと」がある
自分の価値観や志向とずれている点が明確に言語化できる
転職先の候補に対し、条件だけでなく“なぜそこに行きたいか”を語れる
こうした思考整理ができていれば、たとえ短期間での退職であっても、それは自分のキャリアを立て直すための合理的判断と見なされる。
「自分に合う仕事」は、1社目で決まらなくてもよい
1社目がすべてではない。むしろ1社目は“職業観を鍛えるためのトレーニング期間”であり、理想とのギャップを実感しながら、本当に自分が大事にしたい価値観や働き方を見極めるプロセスでもある。
転職することは、ゴールではなく手段である。問題は、転職を繰り返すことではなく、「なぜ辞めたか」「次はどこへ向かうのか」が説明できない状態でキャリアを動かしてしまうことだ。
自分の言葉で、自分の納得のいく理由を持って選んだ道なら、それが正解である。
まとめ:仕事選びは“正解探し”ではなく“納得探し”
「自分に合う仕事」は最初から見つけるのではなく、働きながら“見極めていく”もの
「向いているかどうか」は、実際にやってみて、経験を積んでからでないと判断できない
職場環境や人間関係も、仕事との相性に大きく影響する
合わないと感じたときこそ、自分の価値観や成長を見つめ直すチャンス
辞める判断をする際は、感情的な動機だけでなく、自分なりの「納得感」や「意味付け」を持つことが大切
就活においても、社会人として働くなかでも、「絶対に正解の会社」は存在しない。大事なのは、選んだ道に対して自分がどう向き合うか、どう意味づけるかである。
“合う仕事”は、出会うものではなく、自分自身の納得によって形作られていくもの。
その納得を積み重ねることが、長いキャリアを支える土台になる。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます