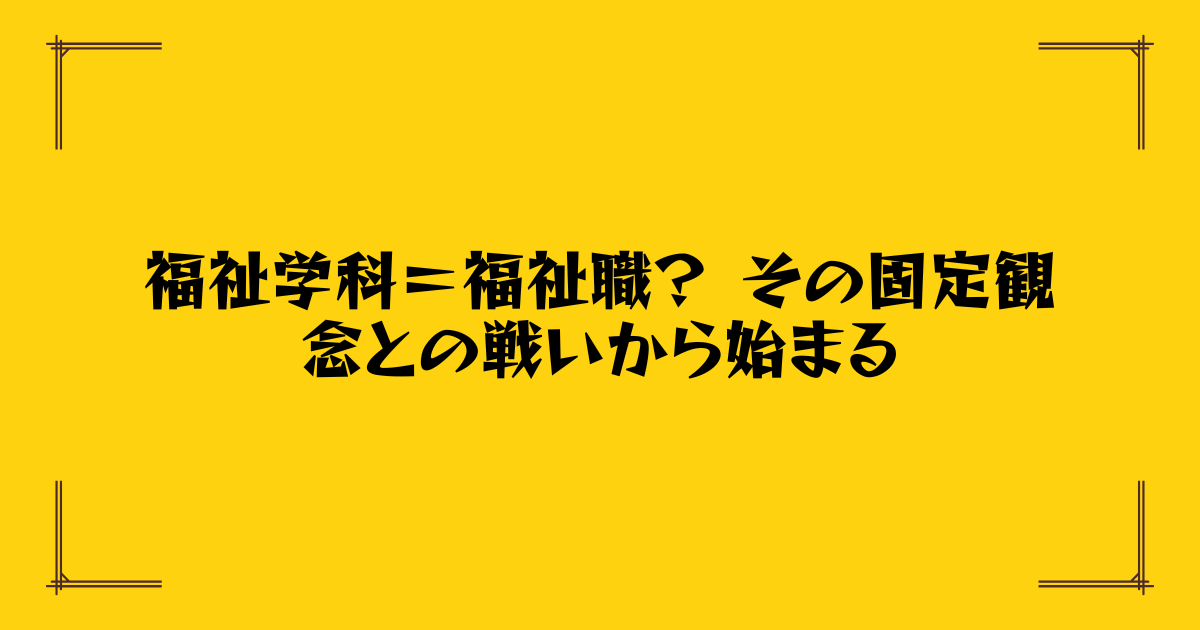「福祉=現場」という空気に縛られていないか
福祉学科にいるだけで進路が決まってしまうような雰囲気
福祉学科に所属していると、いつの間にか「卒業後は福祉職に就くのが自然」といった空気に囲まれることがある。教授やゼミの指導者も、当然のように介護、行政、支援団体への進路を前提に話を進めてくる。実習先も、社会福祉施設や行政系がほとんどで、「民間企業に行きたい」「総合職を受けたい」と話すと、一瞬空気が変わることもある。
福祉の現場には尊い仕事が多いし、そこで働く人を否定するつもりはまったくない。しかし、だからといって「現場で直接ケアする仕事じゃないと“人のためになっていない”」といったようなプレッシャーを、無自覚に感じてしまう学生も多いのではないだろうか。
「人のために働きたい気持ちはある。でも、現場職は違う気がする」その感覚は間違いではないし、自分の適性を見極めようとする誠実な姿勢の表れだ。だが問題は、“違う道”を選ぼうとしたときに、その道が見えにくくなっていることにある。
「なぜ民間に?」と問われたときの視点
現場が嫌=逃げ?という決めつけに負けないこと
福祉系の進路指導や面接の場では、「なぜ福祉現場に行かないのか?」という問いが必ず出てくる。それを聞かれたとき、どこか後ろめたい気持ちになってしまう学生も多い。「体力的に不安だから」「介護の実習でつらかったから」といった“否定”から答えてしまうと、どうしても“逃げているように見える”印象になってしまう。
ここで重要なのは、「現場がダメだったから」ではなく、「自分には別の形で人のために貢献する力があると思ったから」といった、“プラスの動機”で語ることだ。たとえばこういう視点がある:
「現場での経験を経て、制度や組織の側から支える役割に興味を持った」
「一対一の支援ではなく、仕組みを整える側で多くの人を支えたいと思った」
「人の話を聞いて、状況を整理し、支援に繋げる力を活かしたい」
このように、軸は「人のために」という価値観に置きつつ、アプローチの方法を変えたいというスタンスで語れば、説得力も自己理解も伝わりやすくなる。
「人のために働きたい」は、どんな職場でも通用する
そもそも「人のために働きたい」という気持ちは、決して福祉現場に限ったものではない。民間企業の中にも、ユーザーの声に耳を傾け、サービスをより良くしようと奮闘する仕事はたくさんあるし、顧客対応、商品開発、人材支援、教育支援など、社会と接点のある仕事に就けば、十分に「誰かのため」になることができる。
問題は、「福祉=人のために働ける」「民間=利益重視」というような、安易な構図に縛られてしまうことだ。実際には、民間企業の中にも「人の感情や生活に寄り添える職場」は数多く存在するし、むしろ“仕組み”や“仕掛け”をつくる側に回ることで、より多くの人に影響を与えることも可能になる。
「誰のために」「どんなふうに役立ちたいのか」まで考えることで、福祉学科出身だからこそ語れる言葉が生まれてくる。
福祉学科の学びをどう活かすか、再定義してみる
「福祉知識」ではなく「人へのまなざし」を活かす
介護技術や制度知識ではなく、“人を見る力”が活きる
福祉学科で学んできたことの本質は、介護技術や制度論にとどまらない。むしろ重要なのは、「目の前の人がどう感じているのか」「どんな支援があれば前を向けるのか」という、対人理解力だ。
これは面接でも語りやすいポイントだ。たとえば、実習でのエピソードを「制度や介助方法の習得」ではなく、「利用者の言葉に対してどう受け止めたか」「周囲との連携をどう図ったか」といった視点で話せば、単なる“資格職志望”とは異なる印象になる。
営業職やカスタマーサポート、採用、人材、教育などの分野では、この「人を深く理解しようとする姿勢」が強みになる。福祉学科の学びを、“人を支える思考力”として語れるようにしておくと、民間企業でも響く自己PRに変換できる。
「相手目線」の訓練をしてきたという強み
多くの文系学部では、「相手の立場で考える」という力は授業ではあまり鍛えられない。一方で福祉学科では、実習や演習の中で「相手が何を感じているか」「どう関わるべきか」を徹底的に考えさせられる。
これは、実は非常に“実務に近い”視点であり、BtoCサービスを提供する企業にとっては重宝される。たとえば、接客、ユーザー対応、ヒアリング、要件整理など、すべて“相手の立場に立つ”ことが基本になる場面ばかりだ。
「介護の技術は使わないけれど、相手に対する視点の持ち方は日々活きている」──そんな形で、自分の経験を民間企業の業務とつなげて考えておくことが、就活では大きな武器になる。
「自分の進路は間違ってない」と言えるために
「何となく違和感があった」という直感を信じる
「福祉学科出身ならこうするべき」に対する違和感
大学の進路指導や周囲の空気に、どこか“型”のようなものを感じていないだろうか。たとえば、「福祉を学んだなら、資格職に進むのが当然」「人のために働きたいなら、現場だよね」というような決めつけ。
でも、現実のキャリアはもっと自由だし、複雑だ。現場に出た後に管理職になる人もいれば、途中で企業に転職する人もいる。最初から現場に行かないという選択をしたっていい。「何か違うな」「私はこのままじゃない」と感じたその直感を、まずは大事にしてみてほしい。
「なぜそう思ったか」を言語化できるかが勝負
直感だけでは、面接では通用しない。だから大切なのは、その直感の背景にある気持ちを、自分の言葉で整理しておくことだ。たとえば:
実習で心をすり減らす自分がいた
自分の強みが「手を動かすこと」ではなく「考えること」「調整すること」だと気づいた
現場よりも、人を支える仕組みづくりに興味が湧いた
これらの気づきを丁寧に言葉にしていけば、「現場がイヤだったから」ではなく、「自分に合った別の貢献方法を選んだ」という説明ができるようになる。これは、企業側にも納得されやすい論理になる。
民間就職で“活かせる”福祉的視点とは何か
民間企業が本当に求めている「人間力」とは
資格や知識よりも、対人感受性と状況把握力
「民間企業で福祉学科の学びが活かせるのか?」という疑問を持つ学生は多い。実際、就活ナビサイトで自分の学科を登録して企業検索をしても、ヒットするのは介護・福祉施設、社会福祉協議会、行政関連団体などが中心だ。だが、民間企業においても、福祉的な視点が生きる場面は少なくない。
企業が文系学生に対して求めているのは、専門的知識よりも「人と関わる力」「状況に応じた対応力」「周囲と協力しながら物事を前に進める力」など、いわゆる“人間力”である。特にBtoC(対個人)サービスの現場では、相手の気持ちを察して対応する力、先回りして気配りする力が求められる。これはまさに、福祉学科での学びや実習で日常的に磨いてきた力だ。
「支援視点」で動ける人材はどこでも重宝される
企業活動の中にも「誰かを支援する」「相手の課題を汲み取って動く」といった仕事はたくさんある。たとえばカスタマーサポートや人材紹介、営業支援、教育研修、人事などは、いずれも“相手を理解する力”が問われる業務だ。
福祉学科の学生は、利用者・家族・地域・支援者という多層的な関係性の中で、「誰が、何に困っていて、どうすれば前に進めるのか」を考える訓練を受けてきている。これは、企業での「顧客」「チーム」「パートナー」との関係性理解に直結する。
単に「人と話すのが得意です」と言うのではなく、「相手の課題に気づく視点」「他者に寄り添いながらも、客観的な対応を心がける力」があるという点を、自分の特性として言語化できれば、採用担当者にも刺さるはずだ。
「現場で働かない」=「福祉を捨てた」ではない
自分の視点を“現場”から“構造”に変える
一対一の支援から、一対多数の支援へ
福祉職は基本的に一対一、あるいは一対数の関係性の中で仕事が完結する。一方、企業の中には「一度に多数の人の役に立つ仕組みをつくる」ことができる職種がある。
たとえば、保険会社での保険設計・サポート業務、人材会社でのキャリア支援、教育系企業でのコンテンツ企画やサポート、自治体連携を通じた社会課題解決など。これらはすべて、間接的ではあっても「人の生活や安心を支える」ことに貢献している。
現場で汗を流すことだけが“人のため”ではない。制度や情報、サービスの側から生活者を支える立場にも、大きな意味がある。むしろ、広い視点で動ける分だけ影響範囲も広く、自分の裁量が大きくなる可能性もある。
「人のために働く」を自分の言葉に置き換える
就活では、「あなたはなぜその仕事をやりたいのか」「どうしてその企業なのか」といった問いが常につきまとう。そこで一貫して問われるのが、「自分は誰のために、どう役に立ちたいのか」という視点だ。
「人のために働きたい」と思っていても、それを自分の言葉で語れないと、面接では説得力を持たない。そこで重要になるのが、自分なりの“人のため”の定義を見つけることだ。
たとえば、
「安心して相談できる人がいることの重要さを知った」
「一人では前に進めない人の背中をそっと押す存在でありたい」
「誰かの“わからない”を一緒に言語化してあげられるような仕事がしたい」
こうした言葉は、福祉現場だけでなく、民間企業の多くの職種に通じる。それを企業の業務や役割に紐づけて話せば、「この人は現場を離れても福祉の心を持っている」と好印象を持たれるはずだ。
コミュニケーション力は“共感力”だけじゃない
福祉学科で培った「調整型」の力を認識する
目立たないけど重要な「間をつなぐ力」
福祉学科の中で特に育まれるのは、「調整力」だ。現場の実習では、本人の思い、家族の状況、現場の制約、制度の枠組み、職員同士の関係性など、複雑な要素を見極めて行動することが求められる。ここで必要なのは、感情を汲みつつも、冷静に物事を進めるバランス感覚だ。
これは企業においても極めて重要な力であり、特に“調整役”が求められる場面──たとえば営業と開発の間、人事と現場部門の間、クライアントと社内の間などで強く発揮される。
面接では「コミュニケーション力がある」と言う学生は多いが、単なる“話し上手”ではなく、「複数の利害や意見をすり合わせて物事を前に進める力があります」と説明できる学生は少ない。そこに福祉的視点の真価がある。
「傾聴」から「対話」へ──一段上のスキルへ
もうひとつ注目すべきは、“傾聴力”をどうビジネススキルに昇華するかだ。福祉学科の教育では、「相手の話を否定せず、丁寧に聴く」ことが基礎として徹底される。これはカスタマーサポートや営業においても極めて重要だ。
しかし、社会人として求められるのは“ただ聞く”だけでなく、“聞いたうえで、的確に返す”ことである。つまり、傾聴に加えて、整理・要約・提案といったコミュニケーション技術が必要になる。
福祉的視点を持ったうえで、こうしたスキルを身につければ、単なる「共感できる人」ではなく、「相手の意図を正確に捉えて行動できる人」として評価されるようになる。
“他と違う学科出身”を強みに変えるために
社会課題への関心を民間企業に翻訳する
社会福祉の知見を“事業の目的”と接続させる
福祉学科で学ぶ中で、貧困、障害、少子高齢化、地域課題などの社会的テーマに触れてきた学生は多いだろう。こうした視点を持った学生は、営利企業の中でも、CSR(社会的責任)やCSV(社会価値創出)といった考え方にフィットしやすい。
たとえば、教育格差の是正をミッションに掲げる企業や、高齢者支援を事業化している企業などに対しては、「課題感をもった上でこの企業を志望している」というロジックが作れる。
「社会課題を自分ごととして考えてきた経験があります」と伝えることで、他学部出身者との差別化にもなる。
「違う」ことを恐れず、「違うからこそ伝わる強み」にする
就活ではどうしても、「法学部だから企業法務」「経済学部だから営業」「工学部だから開発」など、学部と職種が紐づけられやすい。しかし福祉学科出身であることが、必ずしも「不利」になるわけではない。むしろ「違う視点を持ち込める存在」として、歓迎されることもある。
大事なのは、自分の学びと仕事を無理につなげようとするのではなく、「なぜその学びを経て、この職種に興味を持ったのか」を明確に語れること。その筋道が立っていれば、たとえ他学部出身者が多い職種でも、十分に戦える。
福祉学科出身者が目指せる職種・業界と、その受け方
「人のために働きたい」を具体的な業務に落とし込む
自分の価値観に合う仕事のタイプを見極める
福祉学科の学生が「人のために働きたい」と考えるとき、その“人”が誰か、どんな形で“ためになる”のかを突き詰めることが重要だ。直接支援を希望しないのであれば、間接的に人を支える仕事を選ぶという選択肢が出てくる。
たとえば、以下のような方向性が考えられる:
「生活を安定させたい」→ 金融・保険業界のカスタマーサポート・営業
「働くを支えたい」→ 人材業界のキャリアアドバイザー・リクルーティング
「学びを広げたい」→ 教育業界の事業企画・サポート職
「社会課題を解決したい」→ NPO連携企業・CSR部門・地方創生事業
「安心感を届けたい」→ インフラ・通信・住環境関連の総合職・企画
「人のために」という抽象的な言葉を、自分の関心と照らし合わせて「どんな価値を誰に届けたいのか」と定義し直すことで、自分が進むべき業界や職種が明確になる。
「支援職」だけが人のためじゃない
就活では「この会社は人のためになる仕事か?」という視点で企業を選ぶ学生が少なくないが、それは誤解を生みやすい。民間企業のほとんどは、誰かの課題を解決するために存在しており、その形が“直接”か“間接”かの違いでしかない。
営業職はモノを売るだけの仕事ではなく、顧客の課題を聞き取り、最適な提案を行う仕事。人事は社員が安心して働ける環境を整える仕事。企画職はユーザーの使いやすさや満足度を考え抜く仕事。これらはすべて“誰かのため”を基点とする。
大切なのは、「支援」という言葉を、狭く専門的に捉えすぎず、自分が貢献できるフィールドの広がりに気づくことだ。
民間で目指せる代表的な職種の紹介と戦い方
営業職:対人支援経験が活きる職種
福祉的視点が営業で強みになる理由
営業職と聞くと、「ガツガツ数字を追う」「押し売り」のようなイメージを持ってしまいがちだが、実際は「ヒアリング→課題把握→提案→調整→信頼関係の構築」という一連の流れを丁寧にこなす仕事である。
福祉学科の実習で経験する“アセスメント(相手の課題を把握)→プランニング→支援実施→フィードバック”の流れと構造的には非常に近い。違うのは「相手」が利用者から顧客へと変わる点と、そこに“ビジネス”としての視点が加わることだ。
「課題の見えない顧客に、丁寧に聞き取りをし、納得のいく解決策を提示する」ことは、営業職に求められる大きな資質であり、まさに福祉的な視点が活かされる場面である。
人材業界・教育業界:支援の気持ちをそのまま活かせるフィールド
キャリア支援・学習支援の文脈で福祉性を発揮
人材業界のキャリアアドバイザーや、教育系企業のカスタマーサポート・スクール運営といった職種は、相手の人生や未来に関わる重要な支援業務である。福祉学科で学ぶ「成長・自立・生活支援」の考え方は、非常に相性が良い。
人材系なら…面談で話を引き出す傾聴力、応募企業に応じた支援力
教育系なら…学習の悩みや生活とのバランスを考慮したカリキュラム提案
また、こうした業界は「やりがい」を重視する傾向のある学生に向いており、企業側も“福祉学科出身”というバックグラウンドに価値を感じやすい。
よくある質問「なんで福祉現場に行かないの?」への答え方
「逃げ」ではなく「選択」であることを伝える
本当に大事なのは“なぜこの選択をしたか”
面接で最もよく聞かれるのが、「どうして福祉の現場に進まないの?」という質問だ。これは決して意地悪な質問ではなく、「なぜこの人は学んできた領域と違う方向に進むのか」を確かめたいだけだ。
ここで重要なのは、“現場が嫌だからやめた”という話をしないこと。そうではなく、
「現場での支援に限界を感じ、もっと多くの人に関わる方法を探した」
「現場職の経験を通じて、自分が“仕組み側”の支援に興味があると気づいた」
「自分の特性として、物理的な支援よりも情報提供や制度設計に強みを感じた」
といったように、自分の意思で選んだ“選択”であることを明確に伝えることが大事だ。
「やりたいことは変わっていない」と補足する
自分の選択が「軸からズレていない」と伝えるために、“やりたいこと”の定義はそのままにしておくと伝わりやすい。
たとえば、
「人のために働きたいという軸は変わっていません。対象やアプローチが変わっただけです」
「自分は“関わった人が安心する”ような場をつくる仕事をしたいと思っています。福祉現場か、企業かという形式よりも、その想いをどこで実現できるかを基準に就職先を考えています」
このように、志望動機の一貫性を保ちつつ、選択肢の広がりとして“民間就職”を語ることで、納得感のある説明ができる。
「自己PR」や「志望動機」の作り方にも工夫を
抽象的な「優しさ」や「人のため」は避ける
エピソードと目的意識で具体性を持たせる
就活では自己PRや志望動機を伝える場面が非常に多く、「人のために動ける」「誰かの役に立ちたい」といったワードは多用されがちだ。しかし、それだけでは抽象的すぎて印象に残りにくい。
そこで有効なのが、「福祉学科での経験」×「自分なりの価値観」×「その企業で活かしたい理由」という3点をセットにする方法だ。
たとえば、
「私は福祉学科で、実習を通して“相手の本音を言葉にする難しさ”に直面しました。表情や行動の裏にあるニーズを読み取る重要性を学んだ経験を、顧客との信頼構築が求められる営業職で活かしたいと考えています」
このように語ることで、単なる“福祉らしさ”が、“企業で使える強み”へと変換される。
周囲と違う進路を選ぶ覚悟と向き合い方
福祉学科で「福祉職以外」を目指すと孤独になりがち
教員や実習先との温度差
福祉学科のカリキュラムは、多くの場合「現場職」に直結するように組まれている。実習も介護施設や福祉事業所が中心であり、指導教員の進路観も「福祉=支援現場」に偏りがちだ。そのなかで、「民間志望」と言うと、「せっかく勉強したのにもったいない」「本当にそれでいいの?」と、否定まではされなくても、理解はされづらい。
これは個人の考え方というより、「福祉=国家資格」「=支援現場」という固定観念の根深さから来ている。それに違和感を持ち、企業の総合職や企画職、営業職を志すあなたの考えが間違っているわけではない。
むしろ、それが自分自身の特性を踏まえた「選択」であるなら、自信を持っていい。その道が正解かどうかは、進んでからの努力と行動次第で決まる。
周囲の進路と違うとき、比較してしまう不安
就活が本格化すると、クラスメイトが続々と福祉法人に内定を決めていく。そのスピード感に焦る学生も多い。「福祉法人は早めに内定が出る」一方で、「民間企業はサマーインターン→秋選考→冬選考」と段階的に進むため、スタートダッシュで遅れを取ったように感じる人もいる。
「私はこのまま決まらないんじゃないか」「やっぱり福祉職を受けた方がよかったのか」と迷いが生じるのも自然なことだ。しかし、それはあくまで進む道が違うからタイミングも違うだけで、正解が別ということではない。
周囲と比較しすぎず、「今の自分は、今後の人生をどう描いていきたいのか」に軸を置くことが、就活では何より重要だ。
あなたの「人のために」という想いは、現場だけではない
支援の形はひとつじゃない
「間接支援」こそ、自分らしい選択かもしれない
福祉学科の学びの中には、制度・地域・行政など、「仕組みづくり」の視点もあるはずだ。にもかかわらず、多くの人が「利用者の隣にいること」こそが正しい福祉の形だと誤解してしまう。
しかし、たとえば「企業でCS(カスタマーサポート)として働き、数千人の悩みに寄り添う」「保険会社で相談業務を行い、安心を届ける」「人材紹介で、職を失った人と企業をつなぐ」といった支援の形も、“間接的”ではあっても、人の人生に関与する大切な仕事である。
自分がどんな距離感で、どんな規模で、どんな人たちと関わっていきたいか。それを考えた結果、現場よりも“企業”を選ぶという決断は、むしろ誠実で前向きなものだといえる。
「あなたの支援の形」はあなただけのもの
「人のために働きたい」という言葉は、抽象的だからこそ広く使われる。しかしそのぶん、自分の中で「どんな人に、どんな支援を、どんな立場で」届けたいのかを突き詰めないと、就活では評価されにくい。
だからこそ、「現場が合わない=人のためを諦める」ではなく、「現場ではなく企業で、人を支える方法を探す」視点を持つことが、就活成功へのカギとなる。
“やりたいことがわからない”からの逆算就活
「やりたいこと」より「できそうなこと」から探す
「やりたいことがない」=悪ではない
福祉学科に限らず、就活で多くの学生がつまずくのが「やりたいことが見つからない」問題だ。特に民間企業を目指す学生は、「福祉」から大きくフィールドが変わることで、方向性がわからなくなることも多い。
しかし、やりたいことが見つからないのは当然であり、むしろ社会に出てから育っていくものだという前提を持つことが大切だ。大事なのは、「自分は何が得意で、何をしているときにストレスが少ないか」を把握し、まず“できそうなこと”から職種や業界を絞っていく姿勢である。
「得意なコミュニケーションの種類」から広げる
福祉学科の学生には、コミュニケーション力が高い人が多い。ただしその中でも、「1対1が得意」「調整型が得意」「聞くのが得意」「説明するのが得意」など、人それぞれタイプがある。
「1対1でじっくり話すのが得意」→ 人材業界・カウンセラー職
「相手の状況を整理するのが得意」→ 営業・保険・不動産
「集団をまとめるのが得意」→ 企画・イベント運営
「細かく丁寧に説明するのが得意」→ カスタマーサクセス・教育サービス
このように、「自分が自然にできること」「疲れないコミュニケーションの形」をもとに職種を広げていくと、意外にしっくりくる選択肢が見つかる。
「自分らしさ」を手放さないための就活をしよう
遠回りに見えても、それが“本当に向いている道”かもしれない
福祉学科から民間企業の総合職を目指す道は、近道ではない。学内のサポートも福祉系寄りで、インターンの情報も乏しく、自己PRやESも自力で構築する必要がある。周囲にロールモデルが少ない分、迷いやすいし、孤独も感じやすい。
それでも、安易に「なんとなく現場へ」進むより、自分の特性・将来像・適性に向き合って、手探りでも道を切り拓いていく方が、長期的には「後悔しないキャリア」になる。
面接で何度も否定されても、自分の意志を持ち続けること。そのためには、「自分がなぜ福祉学科に進んだのか」「その中で何を感じたのか」「なぜ企業で挑戦したいのか」という問いに、何度も向き合うことが必要だ。
就活は「合否」ではなく、「相性探し」である
就活をしていると、落ちた企業=自分を否定されたと感じることがある。しかし実際は、企業と学生の“相性”の問題に過ぎない。どんなに優秀でも、その企業の社風や仕事と合わなければ選ばれない。
逆に、自分の価値観や特性にフィットした会社に出会えれば、福祉学科出身であることがむしろ「強み」として評価される場面もある。
だからこそ、就活で一番大切なのは、自分を信じてブレずに動き続けること。そして、自分の意思で「人のために働く」形を選び直したという、その選択自体に、何よりの価値がある。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます