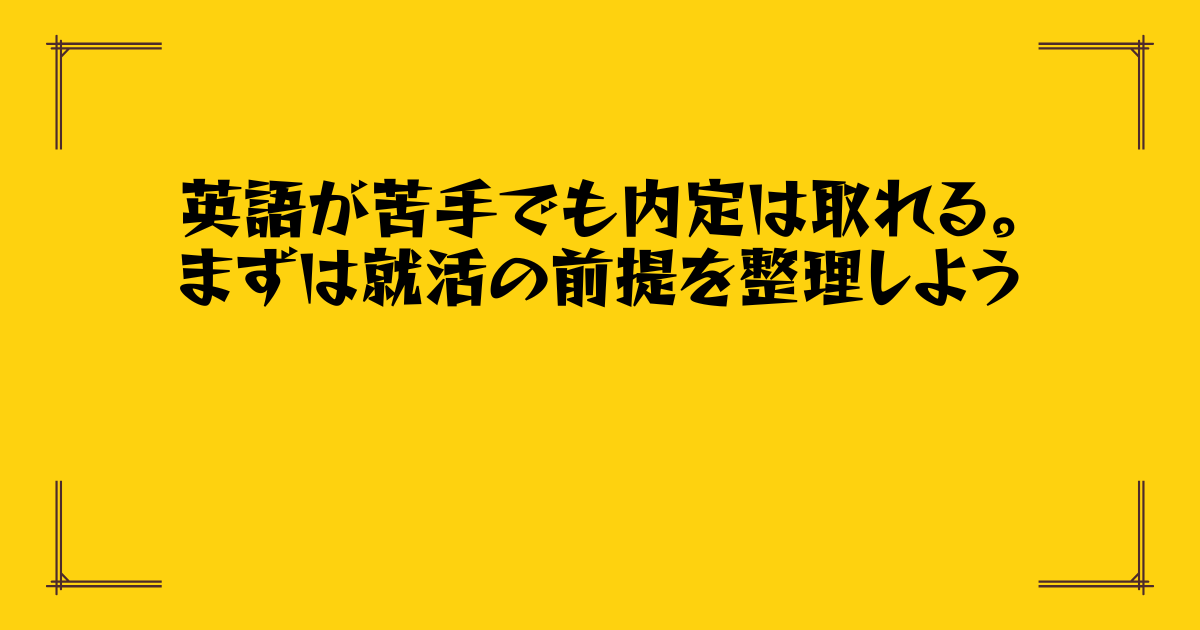「英語が苦手=不利」ではないという事実
就活を前にして、「英語ができないから自信がない」と感じる学生は少なくない。特にTOEICの点数や海外経験を重視する企業が目立つ中で、自分にはそんなスキルがないと落ち込む気持ちはよく分かる。しかし、それは一面的な見方にすぎない。
そもそも、新卒採用で「英語が必須」となる企業は全体の中でそれほど多くはない。たとえばメーカーに限っても、「英語を活かすポジション」と「英語力を特に必要としない国内向け職種」は明確に分かれている。つまり、英語が苦手だからといって、メーカーへの就職全般をあきらめる必要はない。
企業によっては「英語ができればプラス」というだけであり、それが「できないとマイナスになる」とは限らない。だからこそ大切なのは、「英語を使わない仕事を前提に、自分に合った企業や職種を見極めること」だ。
英語が苦手なら“無理にアピールしない”方が得策
自己PRやESでよく見かけるのが、「英語に不安があるけど、がんばります」という文言だ。しかし、このスタンスは実は損をしていることが多い。企業側からすると、「得意でもないのに、なぜ英語を武器としてアピールしているのか?」と疑問を持たれてしまうこともあるからだ。
むしろ、英語をアピールしない代わりに、自分の強みや経験の中で「成果や行動のプロセスが明確なこと」に焦点を当てたほうが好印象を持たれる。たとえば次のような構成が有効だ。
チームで問題解決した経験
地道に努力を継続して成果を出した経験
制約条件の中で工夫して結果を出した経験
英語ができないことをネガティブに捉えすぎず、「ほかの力で十分カバーできる」という発想が重要だ。
日系メーカー志望なら知っておきたい“選び方のコツ”
英語が苦手で日系メーカーを志望する場合、ただ「日系だから大丈夫そう」といった感覚的な企業選びは危険だ。実際には、同じ日系メーカーでも、海外展開の度合いや職種によって英語の使用頻度は大きく異なる。
1. 海外売上比率の低い企業を狙う
企業のIR資料や会社説明会で公開されている「海外売上比率」は、英語の使用頻度を測る目安になる。たとえば海外売上が全体の10%未満であれば、基本的には国内市場が主戦場であり、英語を使う頻度も低いと考えてよい。
一方で、大手のグローバルメーカー(たとえば家電・自動車など)では海外売上が7割を超えていることもあり、職種によっては英語力が問われる場面もある。その場合は、文系でも経理や営業管理などの一部職種で英語メールの読み書きが日常になることもある。
2. 技術職・製造現場・事務系職種は英語不問が多い
特に製造現場に近い職種(生産管理・品質管理・工場事務など)は、国内拠点での業務が中心になりやすく、英語を日常的に使うことは少ない。加えて、事務系の職種でも、社内向けの総務・経理・人事などはグローバル対応の範囲外であることが多いため、比較的安心して応募できる。
ただし、「事務系総合職」といっても配属リスクはゼロではないため、説明会やOB訪問で「実際に英語を使う部署がどのくらいあるのか」「配属の傾向はどうか」といった情報を確かめる姿勢が大事になる。
3. 地方メーカー・BtoBメーカーは狙い目
英語が不安な学生にとって穴場となるのが「地方の中堅メーカー」や「BtoB(法人向け)事業中心のメーカー」だ。これらの企業は海外拠点を持たない、もしくは持っていても少人数体制で、語学力よりも“安定性”や“ものづくり理解”を重視する傾向にある。
たとえば、電子部品、素材、部品加工、医療機器などの分野では、製品そのものよりも技術力・安定供給・品質対応が重視されるため、英語よりも「現場との連携能力」や「真面目さ」が評価されやすい。
自分に合ったポジションの見つけ方
「日系メーカーを志望したいけど、どの職種がいいのか分からない」という人は少なくない。そんなときは、以下のようなアプローチを取ると方向性が見えてくる。
1. 職種研究を軸に企業を探す
業界から選ぶのではなく、「この仕事をやってみたい」という職種から企業を逆引きする方法もある。たとえば、
コツコツと数値を扱うのが得意 → 経理職・購買職
書類や社内ルールを整理するのが好き → 総務職・人事職
現場の人と調整するのが得意 → 生産管理・資材調達職
こうした視点で選べば、無理に語学や営業力をアピールしなくても、素直に自分の強みを活かせる職種が見つかる。
2. 同じ境遇の人がどこに内定しているかを調べる
「英語が苦手で日系メーカー志望」という条件は決して珍しくない。だからこそ、就活サイトやキャリアセンター、SNSなどで「同じような条件で就職した人の例」を調べてみると有効だ。
特に、大学の過去の内定実績やOBOGの就職先データを見ると、「どういう業界・企業が英語不問で採用しているか」が見えてくる。そうした事例は、自分の選択に安心感を与えてくれるはずだ。
英語が苦手でも“勝てる企業選び”と“選考対策”を現実的に進める方法
「行ける企業」ではなく「行きたい企業」を見つける
英語ができないことを気にするあまり、「どうせ自分には大手は無理だろう」と最初から志望先のレベルを下げてしまう人は多い。しかし、企業は英語力だけで人を選んでいるわけではない。逆に、英語が得意でも「協調性がない」「受け答えが曖昧」といった要素で落ちる学生もたくさんいる。
つまり、「英語が苦手な自分でも勝てる企業を探す」のではなく、「自分の強みが活かせて、英語が必須でない企業を見つける」ことが大事だ。まずやるべきは、“英語を使わない職種”のリストアップではなく、“自分がどんな働き方をしたいのか”を言語化すること。たとえば次のような問いから始めるとよい。
チームで協力して何かを進めるのが好きか?
ルーティンよりも変化のある環境が向いているか?
現場との調整役か、裏方でのサポートが得意か?
自分の特性に合う職種が見えてきたら、次にそれを扱っている企業を洗い出していく。
“英語が不要な会社”の探し方と見極め方
企業ホームページや採用ページだけでは「英語をどの程度使うか」はわからない。そこで役立つのが、以下のような情報源だ。
1. 求人票の職種説明文
「英語スキル歓迎」「TOEIC○点以上」などがある場合は、それが必須でなくても業務で求められる可能性がある。一方で、「社内外との調整が中心」「国内顧客とのやりとりが多い」などの表現がある場合、英語は使わないことが多い。
2. 社員インタビュー
多くの企業では新卒採用ページに若手社員のインタビューが掲載されている。「入社後のギャップ」や「業務内容」の具体例を読むと、実際の働き方やスキルの活かされ方がわかる。
3. OpenWorkやキャリコネなどのクチコミサイト
クチコミ情報も過信は禁物だが、部署によって求められる語学力の違いや、職種ごとの雰囲気などはリアルに語られていることが多い。営業職・事務職などに絞って検索することで、自分に近いポジションの実態が見えてくる。
4. OB・OG訪問やキャリアセンター
最も確実なのは、実際に働いている人に聞くこと。たとえば「総合職で入社して海外配属になる人は何割くらいか」「英語が苦手な学生がどの部署に入っているか」などは、説明会では教えてもらえない情報だ。
面接で“英語が苦手”をどう扱うか
志望動機や自己PRを考えるうえで、「英語が苦手であること」をどう伝えるべきか悩む人も多い。結論から言えば、“あえて言わなくていい”が基本方針だ。理由は以下の通り。
1. 苦手なことより得意なことを語るべき
英語が苦手であることは、採用に大きくマイナスになるものではない。しかし、面接でそれを持ち出すと、「この人は自分に自信がないのかな」「言い訳をしているのかな」といった印象を持たれるリスクがある。
企業が見たいのは、「仕事でどんな価値を発揮してくれるか」「職場に馴染めそうか」という部分なので、自分の強みや実績を前向きに語ったほうが印象が良い。
2. 職種や志望企業によっては聞かれることもある
一方で、企業によっては「英語が必要な場面もあるが大丈夫か」と聞かれるケースもある。そのときは正直に答えて構わない。たとえば、「現時点で得意ではないが、必要になれば文書読解程度は勉強する意欲はある」「メールなど定型文で対応することなら努力します」など、前向きなトーンを保つことが大事。
ただし、「苦手です」とだけ言って終わるのは避けるべきで、代わりに「英語以外で活かせるスキル」や「学生時代に頑張ったこと」で印象を補強するのが効果的だ。
英語が苦手でも“評価される就活軸”をつくる
企業は必ずしも“スキルの高さ”だけで評価しているわけではない。特に新卒採用では、「その人が持っている姿勢や考え方、成長意欲」が重要視される。だからこそ、英語が苦手でも、以下のような軸で選考を突破する人は多い。
1. 経験の深さと行動力を武器にする
バイトや部活、ゼミなどの経験から、「どういう問題があって、どう解決したか」「どれだけ主体的に動いたか」を掘り下げて伝えること。こうした“プロセスの論理性”や“誠実さ”は、英語力よりもずっと面接官の評価ポイントになる。
2. 志望理由の納得感を高める
「なぜメーカーなのか」「なぜその企業なのか」を具体的に言語化することで、英語スキルの有無に関係なく“本気度”が伝わる。たとえば、「生活に身近な製品に関わりたい」「現場に近い職種でユーザーの声を活かしたい」など、自分なりの軸を明確に語れる学生は強い。
3. コミュニケーション力や協調性
チームでの活動経験や、周囲と関係を築くために工夫したことがあれば、そこはアピールすべきポイントだ。特に英語を使わない職場では、言語能力よりも「社内連携のうまさ」や「まじめに業務をこなせる安定感」が評価されやすい。
英語が苦手でも狙える大手企業と、選考を突破する戦い方
英語不要で入れる大手企業は実在する
「英語が苦手だから、大手はもう無理かも」そう思っている就活生は多いかもしれません。しかし、現実は違います。英語を業務で使わない大手企業は、今でも多く存在します。
たとえば、以下のような業種では英語スキルが選考基準になることはほとんどありません。
インフラ(JR、東京メトロ、関西電力など)
日系メーカー(花王、ライオン、キッコーマン、ロッテ、キヤノンなど)
金融機関(地方銀行、大手証券、生保・損保会社など)
住宅・不動産(積水ハウス、大和ハウス、野村不動産など)
小売・外食・サービス(イオン、セブン&アイ、オリエンタルランドなど)
いずれも従業員数1万人超えの大企業でありながら、「英語が苦手でも問題ない」「TOEIC点数提出が任意」な企業ばかりです。実際に「TOEIC未受験」でも内定を獲得している学生は多数います。
大手企業の多くは、新卒を“将来の戦力候補”として総合的に評価しているため、語学力はあくまで補足的な評価要素にすぎません。
英語が苦手でも評価される選考対策のポイント
英語ができない場合、「他で勝負する」意識が必要になります。そこで重要なのが以下の3点です。
① 志望動機で「企業理解の深さ」を見せる
「なぜこの企業を志望するのか」に明確な理由を持つこと。業界研究・企業研究を深掘りし、その会社の製品・サービス・価値観を自分の経験と結びつけることで、語学力よりも高く評価されます。
例:
「貴社の生活インフラを支える姿勢に共感し、直接人々の暮らしに貢献したいと考えました」
② 面接で「素直さ」と「努力姿勢」を伝える
英語に限らず、自分の弱みを正直に伝えつつ、「苦手だけど逃げずに取り組んでいる」という姿勢があると、誠実さや成長性が評価されます。
例:
「英語は苦手意識がありましたが、最近は少しずつ聞き取れるようにTOEIC教材に触れています」
③ 学生時代の取り組みを“プロセス重視”で伝える
「何をしたか」よりも「どう考えて、どう行動し、何を得たか」を伝えることが大切です。特に日系大手企業は、堅実に努力してきた人を好む傾向があるため、地道なエピソードでも構いません。
例:
「3年間アルバイトを続ける中で、後輩指導や業務改善にも関わり、組織を円滑に回す大切さを学びました」
TOEICスコアを聞かれても焦らない姿勢が大事
一部の企業では、面接で「TOEICスコアは?」と聞かれることがあります。しかし、その答え方次第で印象は大きく変わります。
未受験の場合:「英語に苦手意識があり、まだ受けていませんが、今後のために取り組みは始めています」
低スコアの場合:「まだスコアは高くないですが、仕事で使う場面に備えて継続的に学習しています」
重要なのは“逃げていない”ことを示すこと。点数の高低よりも、「それに向き合っているか」の姿勢を評価しているのが現実です。
英語が苦手なまま就活を終えないために、今からできること
語学が弱みでも「準備している姿勢」が大きな武器になる
英語が苦手だからといって、何もしないまま就活を終えるのは避けたいところです。なぜなら、選考では「できるかどうか」よりも「向き合う姿勢」が問われるからです。とくに大手や日系メーカーでは、英語が完璧でなくとも、「苦手でも努力している人」は評価されやすい傾向にあります。
英語力に自信がない人がやるべきことは、「苦手なままで終わらせない」「努力のスタートを切っていることを伝える」ことです。実際にTOEICの参考書を買って学習を始める、ニュースを英語で少し聞いてみる、簡単なフレーズを覚えるなど、小さな行動が大きな印象につながります。
また、ESや面接で「英語が苦手でも挑戦したい理由」「英語力以外で貢献できる強み」を明確に伝えることで、語学に頼らない就活戦略を成立させることができます。
英語アピールが不要な職種・部門を見極める
選考対策においては、企業選びの段階で「英語を求められる場面が少ないポジション」を狙うことも有効です。以下のような職種は、英語使用が限定的または全く必要とされないことが多く、英語が苦手な学生でも十分に戦えるフィールドです。
技術職・研究職(理系)
製造や品質管理、生産技術など、国内拠点で完結する業務が中心の技術系職種では、英語の使用頻度はほとんどありません。英語が必要になるのは、海外取引や海外工場との調整が発生するごく一部です。
総務・人事・経理などの管理系職種
本社のバックオフィス部門である総務・人事・経理系は、社内業務が中心であり、日常的に英語を使うことはほぼありません。企業によっては将来的な語学研修や海外担当の可能性もありますが、新卒段階では国内対応が前提の業務が多く安心です。
販売職・営業職(BtoC系)
BtoCビジネスを展開する企業の営業職(食品、化粧品、日用品、住宅、保険など)では、主に日本国内の顧客とのやり取りが中心であり、英語スキルの有無が選考に直結することはほとんどありません。むしろ、人柄や対話力、行動力が評価されます。
内定後を見据えて準備しておくと差がつくこと
英語が苦手な人でも内定を獲得できたあと、「入社後の業務に支障が出たらどうしよう」と不安に思うことがあります。そこで大切なのは、「苦手のままにしない」意識と、小さな努力の継続です。就活中から少しずつ準備しておくことで、入社後も自信を持ってスタートできます。
① 無理に完璧を目指さなくていい
英語を使う機会があるとしても、初めからネイティブレベルを求められることはありません。とくに文系総合職や事務職などでは、「中学英語+少しの単語知識」で十分にこなせる業務も多いです。実際に必要なのは、英文メールの読み書き、電話での簡単な受け答え、取引先の国名・部署名の理解など、限られた範囲の英語です。
② スキマ時間に取り組めることから始める
「NHKラジオ英会話」などを通学時間に聞く
「スタディサプリ ENGLISH」などのスマホアプリで1日5分だけ学習
「日本語→英語」の変換練習ではなく、「英語を見て雰囲気をつかむ」ことから慣れる
このように、自分のペースで英語に“慣れておく”ことがポイントです。毎日少しでも触れておくことで、「聞くことへの抵抗感」が和らぎます。
③ 英語以外でアピールできるスキルを育てる
英語力が弱みになるなら、その分、他のスキルで差をつければいい。たとえば以下のようなスキル・経験を身につけることで、企業への説得力あるアピールが可能になります。
エクセル、パワポなどのPCスキル
長期インターンでの業務経験
アルバイトでのリーダー経験や改善提案
プレゼン・発表経験
大手企業は「総合力」で学生を評価しているため、「英語ができない=即落ち」という図式にはなりません。
まとめ
英語が苦手でも、就活をあきらめる理由にはなりません。特に日系メーカーやインフラ系、国内営業が中心の企業では、語学力よりも“地道に努力できるか”“誠実に伝える力があるか”が評価されるポイントです。
英語が不安なままでも、やるべき準備を着実に進めていけば、堂々と大手企業の選考にも挑戦できます。そして、その姿勢こそが評価される最大の強みになります。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます