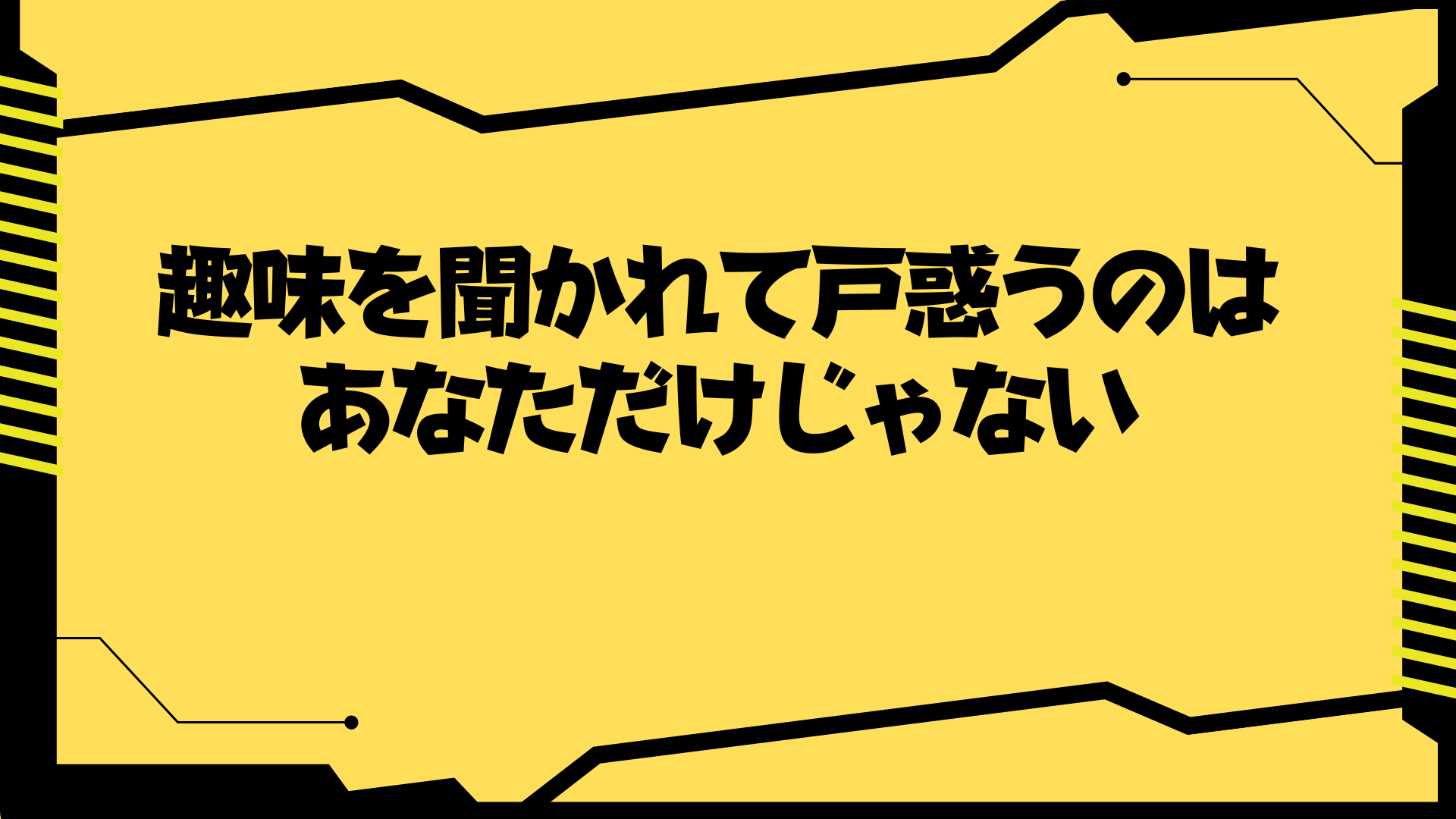「面白いこと言わなきゃ」がプレッシャーに
普通すぎる趣味では印象に残らないと悩む学生たち
「読書」「映画鑑賞」「音楽を聴く」──こうした趣味を就活で答えることに抵抗を感じる学生は少なくない。理由は単純で、「他の人と被るし、印象に残らないから」。加えて、趣味に関する質問は、面接の冒頭でなされることが多く、「アイスブレイク」の役割を担っているとはいえ、初対面で自分を表現する難しさを一層感じさせる。目立つ趣味や珍しい経験がないとダメなのでは? と感じてしまい、自分を大きく見せようと考え込んでしまうのだ。
「趣味=ユニークな話」という誤解
多くの学生が「面白く話さなければ」「人と違う趣味を言わないと」と思い込んでしまう。だが、これは大きな誤解だ。面接官はあなたのネタ見せを期待しているわけではなく、「人柄」や「素の一面」を見たいと思っているだけだ。にもかかわらず、“期待されている答え”を考えすぎてしまい、かえって不自然な回答になるケースも少なくない。
「趣味がない」は悪なのか
“趣味”と呼べるほどの熱意がない人の不安
「趣味は特にありません」と正直に言いたくなる気持ちも理解できる。だが、実際には面接の場でこの答えは避けるべきだ。なぜなら、趣味を通じて学生の価値観や日常の過ごし方を見ようとしている面接官に対し、会話の糸口を遮断してしまうからである。「趣味がない」というより「趣味として意識していないだけ」の可能性も高く、改めて考えれば、日常の行動の中に趣味のタネが見つかることは少なくない。
“何もしていない”のではなく“言葉にしていない”だけ
例えば、毎日スマホで漫画アプリを開いている、コンビニの新商品をチェックしている、寝る前に必ずYouTubeを観る──こうした行動が「趣味」と呼ばれていないだけで、実はその人らしい行動パターンであり、十分な会話の材料となる。問題は、これらを“趣味”として認識していないため、就活では「何もない」と思い込んでしまうことにある。
実は“答え方”次第で印象は変わる
趣味の内容より「なぜそれが好きか」が重要
面接官は趣味そのものよりも、それをどう語るかに注目している。たとえば「筋トレが趣味です」というだけでは薄い印象になるが、「自己管理の一環として毎朝続けており、週に1度は友人とジムに行きます」といったエピソードが加われば、日々の習慣やコミュニケーション力を示すことができる。趣味の“ジャンル”より、“なぜそれを続けているのか”“どんな工夫をしているか”という背景が、印象を大きく左右するのだ。
笑わせようとしなくていい、共感されればそれでいい
学生の中には、「インパクトのある趣味」で笑いを取ろうとする者もいるが、これはあまり得策ではない。面接官が知りたいのは、その人がどんな価値観を持っているか、どんな時間の使い方をしているかという生活のリアルだ。共感される話題の方が、面接官との距離を縮めやすく、結果的に人柄をうまく伝えることができる。
企業が「趣味」を聞く本当の理由とは
面接官の狙いは「個性」より「人柄」
“変わった趣味”を求めているわけではない
「企業は面白い人材を探している」という都市伝説的な話を真に受けて、奇抜な趣味を用意しようとする学生がいる。だが実際には、企業は個性的なエンタメ要員を採りたいわけではない。チームで働けるか、協調性があるか、柔軟に対応できそうか、といった“人としての土台”を見ている。そのうえで、「趣味」という比較的リラックスした質問を使って、学生の“素”を引き出そうとしているのだ。
「趣味=その人のキャラクターを映す鏡」
たとえば「映画鑑賞が趣味」と言ったときに、「どんなジャンルが好き?」「最近観た中で印象に残っている作品は?」というように、面接官は深掘りしてくる。これは“知識”を試しているのではなく、どんな話し方をするか、どんな感性を持っているかを見ようとしているのである。趣味は、その人の価値観や行動スタイルをさりげなく知るためのツールとして使われているにすぎない。
趣味に“中身”がなくても会話はできる
面接官は話を広げるのがプロ
学生側は「大した話ができない…」と不安になるが、面接官は話を広げるプロフェッショナルだ。たとえば「カフェ巡りが好きです」と言えば、「どんなカフェに行きますか?」「最近行ったカフェで印象的だったところは?」といった質問で深掘りしてくれる。大切なのは、会話を通じて“あなた自身”を少しずつ理解してもらうこと。趣味の知識の深さではなく、受け答えの姿勢や相手との関係性づくりが重視されている。
正直な“好き”が会話のきっかけになる
例えば、「猫の動画を見るのが好きです」と答えると、意外にもそこから面接官との共通点が見つかることがある。あるいは、「休日はひたすら昼寝しています」という答えに、面接官が笑って「私もです」と共感してくれることも。就活は緊張しがちな場面だからこそ、「素直な好き」に基づいた話題は、相手の心をほどく可能性がある。
「なんとなく話してみたい」が本音
面接官も“探っている”段階にすぎない
企業側も最初から「この人を採りたい」と思っているわけではなく、「一緒に働けそうか?」「職場になじみそうか?」という観点で見ている。そのため、趣味の話題は“人間味”や“空気感”を知るための入り口であり、「どんな返しをしてくるのか」「雑談で気まずくならないか」といった“空気の読め方”も含めて見ている。
自分を演じるよりも、肩の力を抜くことが大切
就活では自分を良く見せたい気持ちが強くなりすぎるが、「趣味」質問はあくまで自然体で臨むべきものだ。完璧な答えを準備するよりも、「普段どんなふうに時間を過ごしているのか」をありのままに伝える姿勢の方が、むしろ好印象につながる。自分らしさが伝わることこそが、この質問の本当の意味での“正解”なのである。
「趣味がない」は本当か?を疑ってみる
趣味とは「好きな時間の使い方」にすぎない
多くの学生が就活で「趣味を教えてください」と聞かれたときに答えに詰まる理由の一つは、「趣味=何か特別な活動」と思い込んでいるからである。例えば登山やバイオリンのような“わかりやすい”趣味をイメージしてしまうと、日常の過ごし方が“趣味”として認識されにくくなる。しかし実際には、趣味とはもっと広義のものであり、自分の意思で時間を割いている行動すべてが対象になる。
「面白くも特別でもない」ことが強みになることも
たとえば、「毎日スマホでレシピ動画を眺めるのが好き」「日曜は決まって近所のパン屋に行く」など、一見地味な行動でも、それが習慣化していたり、好きで続けていたりするのであれば、十分に“趣味”として語ることができる。むしろ、等身大のリアルな話だからこそ、面接官との共感を呼びやすいのだ。背伸びした答えではなく、自分のリズムで話せるテーマを探すことが、就活における趣味の準備の第一歩となる。
「好きでも得意でもないこと」が答えになる例
続けている理由があるなら“趣味”と呼べる
中には「そんなに好きでもないけど、なぜか毎日やっていること」がある学生もいる。たとえば、なんとなくアプリで将棋を続けている、日課として日記をつけている、毎朝ニュースアプリを開くなど。これらは一見趣味とは言えないように見えるが、「なぜか続けてしまう」「やらないと落ち着かない」という感覚があるなら、それは立派な趣味の種である。
「無理して好きになる必要はない」
就活では「熱中していることがないとダメ」と思い込んでしまいがちだが、実際にはそうではない。面接官が知りたいのは“その人らしさ”であり、そこに強い情熱があるかどうかは二の次である。好きの度合いは浅くてもよく、むしろ「なぜやっているのか」「どんなふうに習慣化されているか」といった生活に根ざしたエピソードの方が、面接では印象に残りやすい。
「SNSを見る」「動画を観る」も立派な趣味
スマホ時間の中にも“語れる趣味”が眠っている
「スマホでSNSを見ているだけ」「YouTubeで動画を流し見している」といった日常行動は、いまや多くの学生にとって当たり前の過ごし方である。だからこそ、「それじゃ趣味とは言えない」と思われがちだが、実は逆である。これらの行動も、「どんなアカウントを好んで見るのか」「なぜそれに惹かれるのか」「どんな発見があるか」などを言語化すれば、十分に個性のある話題になる。
「暇つぶし」が自分の傾向を語る材料になる
たとえば、「韓国のメイク動画ばかり見ている」「動物の癒し動画が好き」「ルーティン系Vlogをチェックする」など、SNSやYouTubeで何を選ぶかは、その人の感性や傾向を自然に表している。それらを「暇つぶし」ではなく、「癒しの時間」「情報収集の手段」として捉え直せば、それは立派な“趣味”として通用する。面接で大切なのは、何をしているかよりも、どうしてそれを選び、どう楽しんでいるかを語れることにある。
思い出せる・話せる・広げられる趣味の選び方
「毎日続けていること」を棚卸し
無意識の習慣にヒントがある
「特に趣味がない」と感じている人でも、日々の生活を細かく思い出すと、意外と続けていることが見つかる。朝のコーヒーを淹れること、電車内で読んでいる漫画、夜にするストレッチ、コンビニの新商品チェックなど、それらを一度書き出してみると、自分でも気づいていなかった“趣味の芽”が見えてくることがある。
趣味とは「意識的に楽しんでいる時間」
大事なのは、そうした行動を「ただの習慣」として終わらせず、「意識的に楽しんでいる」と再定義することだ。たとえば、「朝に音楽を聴くのが日課です」とだけ言えば普通だが、「1日の気分を音楽で切り替えるようにしていて、気分によってプレイリストを変えています」と話せば、自分の感性や生活スタイルを伝えることができる。
過去にハマったことを振り返る
一時的に夢中になったことも材料になる
「今はやっていないけど、昔はすごく好きだった」ものも趣味の候補になる。たとえば、中学生の頃にガンプラに夢中になっていた、大学1年の頃に読書にハマっていた、など。一度熱中した経験があれば、それにまつわるエピソードや気づきも残っているはずだ。その背景を語ることで、継続の有無にかかわらず十分な話題となる。
「なぜやめたか」も会話のフックになる
趣味に関する話は、「今現在の状態」だけでなく「始まり」や「やめた理由」にも価値がある。「受験期に忙しくなってやめた」「引っ越して環境が変わった」などの変化も、人柄を伝えるきっかけになる。大切なのは、自分がそれをどのように捉えていたか、何を感じていたかという“主観”であり、それを伝えることで話がふくらむ。
「その話、もっと聞きたい」と思わせる一工夫
話題の選び方で印象は変わる
趣味として何を話すかよりも、「どう話すか」によって印象は大きく変わる。たとえば、「料理が趣味」と言う人が「自炊が節約のための手段になっていて…」と話せば、生活力や自立性が伝わる。「ライブによく行きます」と言う人が「音楽だけでなく、その空間が好きで」と語れば、感性や人との関わり方が垣間見える。面接官が「もっと聞いてみたい」と思う話題には、必ず“その人らしさ”がにじみ出ている。
オチはいらない、自然な感情を添えるだけでいい
就活では「結論のある話」や「整った構成」が求められる場面が多いが、趣味の話に関しては、そこまで構えすぎる必要はない。むしろ、「それをやっているときは気分が落ち着きます」「日々のちょっとした楽しみになっています」といった自然な感情を添えるだけで、十分に面接官に伝わる。“完璧な話”をしようとするより、“自分が日常に何を求めているのか”を率直に話すことのほうが、印象に残るのである。
盛りすぎた趣味は見破られる
ウケ狙いがスベったケース
話せないネタは“嘘”とみなされる
「少しでも印象に残るように」と、面接で盛った趣味を披露しようとする学生は少なくない。たとえば、「利きビールが得意」「路地裏の神社を巡るのが趣味」など、ユニークな設定を無理に考えてしまうケースだ。だが、そうした“狙いすぎた趣味”は、少し深掘りされたときに話が続かず、嘘がバレるリスクが高い。「おすすめの神社はどこですか?」「どの銘柄のビールが好きですか?」と聞かれて詰まってしまえば、信用が失われるだけでなく、空回りした印象さえ与えてしまう。
話の“スベり”は空気を凍らせる
ウケを狙った趣味は、面接官との相性が良ければ成功することもあるが、そうでない場合はかえって「滑った」印象になる。とくに集団面接や若手社員が同席していない面接では、冗談や個性的な表現が受け入れられにくく、話が空回りしてしまう。結果的に、話題そのものよりも「空気の読めなさ」が評価を下げる原因となることもある。
実は“嘘の趣味”はリスクが高い
面接官は見抜くプロ
面接官は、数多くの学生と会っている。趣味の話で嘘をついたり、知識のない分野を装ったりすれば、その不自然さはすぐに見抜かれる。とくに経験豊富な人事担当者は、深掘りの質問を通じて「これは本当に好きなことか?」「自分の言葉で話しているか?」を見極めようとしている。作られた趣味は、深掘りに耐えられないことが多く、結果的に話が破綻してしまう。
バレなくても“嘘の緊張”は伝わってしまう
たとえ話の内容がバレなくても、嘘をついているときの独特な緊張感や言葉の選び方、間の取り方から「違和感」が伝わってしまうことがある。自信を持って語れない趣味は、話している本人もどこか不自然になる。面接官はそうした“空気”を敏感に察知するため、無理して嘘を重ねるくらいなら、ありのままの趣味を自然体で語る方が、よほど印象が良い。
「詳しく話せますか?」で沈黙する地獄
趣味の“設定”だけでは面接は乗り切れない
「映画鑑賞が趣味です」と言った後、「最近観た作品は何ですか?」「好きな監督はいますか?」と質問されることはよくある。にもかかわらず、「えっと…最近はあまり観られていなくて…」と答えてしまえば、せっかくの話題が逆効果になってしまう。「趣味の設定」だけを用意しても、会話の中で中身が伴わなければ、逆に信頼を損ねてしまう。
“語れる”という前提が必要になる
趣味の話は、“語れる”ことが前提になっている。別に専門的な知識が求められているわけではないが、「なぜ好きなのか」「どんなときにやっているのか」「それによってどんな気分になるのか」といった、最低限の語りができなければ成立しない。趣味に関しては、「一つ深掘りされても大丈夫」と思えるネタを選ぶことが、安心感につながる。
面接官の印象に残る趣味の語り方
「なぜそれが好きか」を語れるか
趣味の“背景”が自分を映す
たとえば「漫画が好きです」と言ったときに、「どんな作品が好きか」だけでなく、「なぜ漫画に惹かれるのか」「どんな時間に読むのか」といった背景を語ることで、単なる娯楽の話が“自己開示”に変わる。面接官は、趣味の中に見える“価値観”や“思考パターン”を見ているため、その人らしい理由づけがあることで、印象が大きく変わる。
感情を伴うと伝わり方が違う
「それをしていると落ち着く」「癒される」「自分に戻れる気がする」など、感情のこもった語りには、人柄がにじむ。感情に触れた話は、事実を並べるだけの話よりも印象に残りやすく、記憶に引っかかる。「趣味=好きなこと」だからこそ、そこにある小さな感情の動きが、自分の輪郭を際立たせてくれる。
「仕事につながる要素」はむしろいらない
無理に“志望動機化”しない方がいい
「旅行が好きだから、グローバルに働きたいです」「読書が好きなので、インプット力があります」など、趣味を仕事に強引に結びつけようとする学生も多いが、これはやや逆効果になりやすい。面接官はすでに志望動機や自己PRを通じて“仕事との接点”を聞いているため、趣味の場では純粋にその人の“オフの顔”を見たいのである。
趣味は“余白”としての役割がある
むしろ趣味は「休日にリフレッシュできているか」「ストレス解消の手段を持っているか」といった、働くうえでの“余白”を知るために聞かれる。常に仕事と直結している人は、燃え尽きやすい。だからこそ、面接官は趣味という“私的な時間”をどう過ごしているかを見て、長く働けるか、バランスの取れた人かを感じ取ろうとしている。
人柄がにじむエピソードの力
「ちょっと変わってるけど共感できる」話が強い
「一人カラオケにハマっている」「お風呂でラジオを聴いている」「雑誌の占いコーナーを信じてしまう」など、少しユニークで個人的なエピソードは、面接官の興味を引きやすい。特に、日常の“ちょっとしたこだわり”を含んだ話は、真面目一辺倒の面接の中で、印象を大きく変える可能性がある。
「その話、もっと聞きたい」と思わせる空気をつくる
面接の場では、趣味が“すごい”必要はない。むしろ、「へえ、面白いですね」「それってどういうことですか?」と自然に続くような話題が望ましい。そのためには、語るテーマよりも語り方に気を配り、「自分だけのちょっとした視点」や「ふだんの感じがわかるトーン」を意識することが大切である。趣味の話が終わった後、場の空気が和らいでいるかどうかが、成功のサインとも言える。
就活の趣味質問は「雑談の訓練場」
面接は情報交換より“関係性づくり”
趣味の話から見えてくる「話しやすさ」
就活の面接は、学生が自分を売り込む場であると同時に、企業側が「一緒に働きたいか」を見極める場でもある。その中で、「趣味はなんですか?」という質問は、まさに“関係づくり”の入口として機能している。面接官が趣味を尋ねる目的は、応募者の興味関心を見るというより、会話のキャッチボールができるか、自然なやりとりが成立するかを確かめるためだ。
話のキャッチボールができる人は安心される
仕事では、自分の意見を伝える力だけでなく、相手との温度感やテンポを合わせる力も問われる。趣味の話題での応答は、その“やりとりの質”を見られていると言ってよい。質問に対して一方的に答えるのではなく、「〜なんですよ。○○さんはどうですか?」と返す力や、「それはちょっと恥ずかしいんですけど…」と場に合わせたトーンで話せる柔軟さが、面接では高く評価される。
趣味の話題から見られているのは“余裕”
話す内容より「どこまで自然に話せるか」
趣味に関する質問は、面接の序盤やアイスブレイクで使われることが多い。そのため、学生の緊張感や余裕のなさがそのまま言葉に出る場面でもある。無理に“良く見せよう”とせず、自分の言葉で自然に話している学生は、相手に安心感を与える。一方で、台本を読み上げるような話し方や、盛った話で空回りする学生は、「入社後も無理をしそう」「背伸びしすぎるのでは」といった不安を抱かせる。
自然体で話せることが「一緒に働けそう」につながる
結局のところ、面接官がもっとも重視しているのは、「一緒に働く姿が想像できるか」という点である。趣味の話で自然に笑い合えた、落ち着いたやりとりができた、という体験があると、それだけで評価は上がる。学生側は「評価される趣味」ばかりを探しがちだが、本当は“その人らしいトーン”で会話ができることの方が、はるかに重要なのである。
意外と重視されている「聞かれたときの反応」
質問への第一声が、そのまま印象をつくる
趣味を尋ねられたときに、「えっと…どうしよう…」「あまり趣味って言えるものがなくて…」と戸惑ってしまう学生は多い。だが、その“反応の一瞬”が、面接官に与える印象を左右することがある。重要なのは、言葉に詰まっても、そこに素直さや謙虚さ、明るさがにじんでいるかどうか。「ちょっと地味なんですが…」と前置きしつつ、前向きに語れる姿勢があれば、それだけで印象は大きく変わる。
「話す準備をしてきた人」には安心感がある
逆に、自然に答えられない理由が“準備不足”だと伝わる場合、「他の場面でも抜けがあるのでは」と警戒されることもある。趣味の質問は、選考の本題からは外れているが、それだけに「きちんと準備してきたか」が浮き彫りになる場面でもある。言葉を選びつつ、自分らしく語れるように練習しておくことは、小さなことだが、大きな印象差につながる。
あなたらしい「趣味の話し方」のつくり方
深掘りされても苦しくない話題とは
“無理せず話せること”を趣味にするのが正解
面接での趣味の話は、事前に内容を決めることよりも、「掘られても慌てないテーマ」を選ぶことが重要である。知識の量や成果の有無ではなく、自然に話せるかどうかが問われている。たとえば、「最近パン屋巡りにハマっていて…」という話であれば、「どんなお店が好き?」「なぜパンなの?」と聞かれても答えやすく、むしろ会話が楽しく広がっていく。自然体の中にこそ、自分らしさは宿る。
“広がるネタ”は相手との関係性を深めやすい
面接官とのやりとりを意識するなら、少しでも話題が広がりやすい趣味を選ぶのも一つの工夫である。「音楽鑑賞」と言っても、最近観たライブや、通勤中に聴いているプレイリストなど、具体的なエピソードを交えられると話が広がる。大事なのは、相手に質問の余地を残すこと。面接はプレゼンではなく“対話”であるため、一方通行の話にならないことが何よりも重要だ。
嘘をつかず、でも印象に残る“本音トーク”
平凡な趣味にも“切り取り方”がある
「読書」「料理」「散歩」など、一見どこにでもある趣味でも、切り取り方次第で印象は変わる。たとえば、「寝る前にベッドで読む短編集が好きです」「1時間歩いて銭湯に行くのが日課です」など、具体的で少しだけ“自分の視点”を交えると、話に温度感が生まれる。趣味とはつまり、その人がどんなふうに物事を見ているか、どんな価値観を持っているかを感じ取れるテーマでもあるのだ。
“盛らない”話こそ、信頼感につながる
印象に残る趣味とは、決して派手な話や珍しい体験ではない。むしろ、「この人の話は素直で心地よい」と思わせるような、落ち着いた話し方の方が信頼されやすい。特に、仕事では地道なやりとりや誠実さが求められるからこそ、面接官は“話し方”からその片鱗を感じ取ろうとする。盛らず、等身大で語れることが、もっとも面接で強い武器になる。
趣味に“特別さ”はいらない
「普通のことを、ちゃんと語れる人」は貴重
就活の場では、“普通”であることに価値を見出せない学生も多い。だが、社会に出ると「自分の言葉で丁寧に話せる人」「空気を読みながら雑談できる人」は、実はとても重宝される。趣味を聞かれて「普通で申し訳ないんですが…」と前置きしながらも、穏やかに、誠実に語れる姿勢は、それ自体が評価される。面接官が見ているのは、答えの“内容”だけではなく、その人の“ふるまい”なのである。
まとめ
就活の「趣味」質問で落ちる人はいない
趣味は評価項目ではなく、会話の入口であり、人柄を見るためのトピックにすぎない。その意味で、趣味を“理由にして落とされる”ことはまずない。だが一方で、趣味の話で印象を上げることはできる。会話が広がった、場が和んだ、素の自分が伝わった──そうした積み重ねが「この人と働いてみたい」という好印象につながる。
でも、“印象”は趣味の語り方で大きく変わる
話の中身よりも、話し方・反応・空気感。趣味という小さな問いかけの中に、学生の“らしさ”が自然ににじむ瞬間がある。だからこそ、無理に盛らず、自分の言葉で話せること、掘られても困らないこと、素直な感情を添えられることが大切になる。正解を探すのではなく、「自然体でいられる話題」を選ぶことが、最大の準備となる。
趣味は「答え方」で自分らしさを伝えるチャンスになる
「就活の趣味は評価されないから意味がない」と感じる人もいるかもしれない。しかし、雑談の中にこそ、その人の空気感、価値観、柔軟性が垣間見える。趣味を通じて「ちょっと話していて心地よかったな」と思われれば、それだけで選考の通過率は上がる。“差をつける”ために奇抜な趣味を用意するのではなく、“自分を伝える”ために、日常の好きなことを丁寧に語れるようになろう。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます