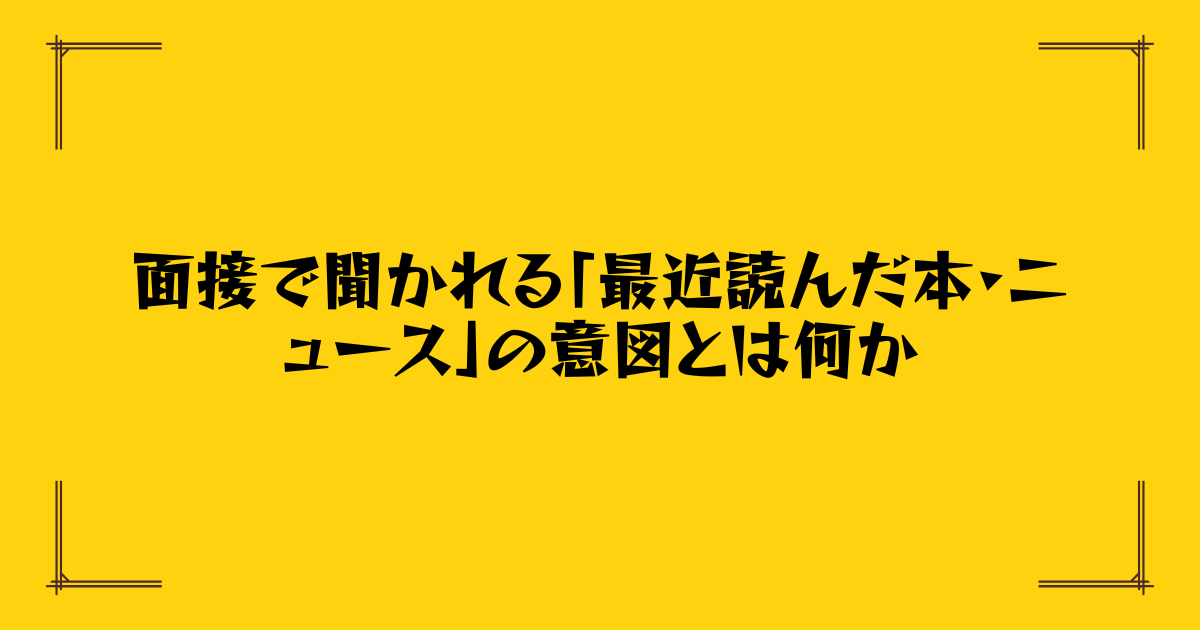ただの雑談ではなく「評価される質問」である
面接の場で、「最近読んだ本はありますか?」「最近気になったニュースは何ですか?」と問われることは少なくない。だが多くの就活生は、この問いを軽視しがちで、「何か答えなきゃ」と焦ってしまったり、「特にないです」と正直に言ってしまったりする。しかしこの質問は、企業側が就活生の本質に迫ろうとする“評価対象”の一部だ。志望動機や自己PRのように直接的な評価軸ではないが、「この人はどんな視点でものを考えられるのか」「情報に対する感度はあるのか」といった、思考の質や社会的関心を見極める材料になっている。
就活では、「話題のニュースを把握しているか」というよりも、「そこからどんな問題意識を持ち、何を考えたか」に重きが置かれる。そのため、どんな内容であっても、自分の視点や思考をしっかりと語ることができれば、高い評価につながる可能性がある。つまり、知識の披露ではなく、“考える姿勢”を見せる場であるという認識が重要だ。
書籍・ニュースの内容そのものより「咀嚼力」が見られる
たとえば、経済ニュースを取り上げたからといって評価が高くなるわけではない。同様に、話題のビジネス書を挙げたとしても、内容を理解していなかったり、自分の価値観や行動に何もつながっていなければ、単なる知識披露で終わってしまう。一方で、エンタメ寄りの作品でも、「なぜその作品に惹かれたのか」「そこから何を学んだのか」を語ることができれば、十分に評価対象となる。
また、“何となく読んだ”“なんとなく気になった”といった理由では思考の浅さが見抜かれてしまう。大切なのは、情報を一方的に受け取るのではなく、自分なりに問いを立て、背景や今後への影響などを多面的に考察する姿勢である。たとえ知識が少なくても、「自分なりに深く考えた」という態度は伝わる。そのため、答える準備をする際には、「何を読んだか・見たか」だけでなく、「そこから何を感じたか・何を学んだか」をセットでまとめておく必要がある。
「本」か「ニュース」かはどちらでもいい
就活生のなかには、「本を読んでいないので答えられない」と不安になる人もいる。だが、企業が知りたいのは“活字文化に親しんでいるか”ではなく、“社会や自分の関心領域に対してどう向き合っているか”という姿勢だ。そのため、新聞やWebニュース、YouTubeのドキュメンタリー、Netflixの教養系作品でも構わない。それらを起点にして、きちんと自分の言葉で思考を語れるかどうかが評価の鍵である。
もちろん、「ビジネス書を読んでおくと無難」という見方もあるが、そこに個性がなければ埋もれてしまう。むしろ、身近なトピックや関心事をもとに深い考察を見せられる学生の方が、印象に残りやすい。「○○というニュースをきっかけに、自分の志望業界の課題について考えるようになった」といったように、自分なりの問題意識につなげられるかどうかが重要になる。
企業が見ているのは「情報感度」と「思考の軸」
情報収集に対する“習慣”の有無が伝わる
この質問を通じて企業が感じ取ろうとしているのは、就活生が普段からどれくらい社会の動きに関心を持っているかだ。たとえば、日経新聞やNHKのニュースを日常的に読んでいなくても構わない。ただ、「最近の話題を何も知らない」「言葉として聞いたことがあるだけで、自分の中で咀嚼できていない」という状態では、社会人としての基本姿勢に疑問を持たれてしまう。
情報をキャッチアップする習慣があるか、気になった情報に対して自分で調べてみる癖があるか。たとえば、「“生成AI”という言葉をよく聞くので、基礎から調べてみた」「就活を始めてから、業界紙やニュースアプリを使うようになった」など、意識して情報に触れようとしている姿勢は評価されやすい。情報の収集力や知識量よりも、“自分から動いているか”の方がはるかに重要なのである。
思考の深さが「語り方」でわかる
どんな本・ニュースを選んだとしても、語り方に差が出る。良い例は、「○○というニュースを通じて、現代の△△という構造的な課題を感じた」と語るようなケースだ。ここでは、ニュースの表面だけではなく、背後にある社会構造や因果関係にまで踏み込んで考えていることがわかる。
一方、「○○というニュースを見ました。驚きました。」で止まっていると、思考が浅い印象を与えてしまう。同じニュースを題材にしても、「どう考えたか」「どう行動に反映したか」の有無で印象がまるで違ってくる。話すときには、「①なぜそれに興味を持ったか→②どんな内容だったか→③何を考えたか→④どう活かそうと思ったか」の順番で構成できると、思考の深さが自然と伝わる。
志望理由とリンクさせると強力な武器になる
最も効果的なのは、自分の志望業界や職種と絡めて話すことだ。たとえば、IT業界志望の学生が「サイバーセキュリティに関する国際会議のニュースを読んで、デジタル社会の裏側の脆弱性を考えさせられた」と語れば、関心の本気度が伝わる。あるいは、消費財メーカー志望の学生が「環境配慮型パッケージに関する記事を読んで、自社努力の具体的な動きを知り、ESG経営の現実味を感じた」と語ることもできる。
このように、「最近読んだ本やニュース」を単体の話題にとどめず、自分の志望動機や価値観とセットにして語れるかどうかが、面接で差をつけるポイントになる。ただ「話題を知っている」だけの人と、「そこから行動や志望につなげている」人では、企業の印象がまったく違う。
面接で語れる「本・ニュース」ジャンル別のおすすめ例
就活生が扱いやすいジャンルとその特徴
「何を選んで話せばいいのか分からない」という悩みは多い。実際、特別な知識がないと話せないと思い込んでしまいがちだが、面接官が求めているのは“プロの評論”ではなく“等身大の思考と関心”だ。そこで、就活生でも扱いやすく、かつ印象を残しやすいジャンルを以下に整理して紹介する。
社会問題系:自分の価値観が問われる
気候変動、ジェンダー、少子化、AIと労働の未来などの社会課題は、業界を問わず多くの企業が注目しているテーマだ。たとえば「ヤングケアラー」に関するニュースを取り上げた場合、「これまで見えていなかった課題に気づかされた」「今後どのように社会制度で支援していくかに興味を持った」といった視点で語ることができる。答える際は、“課題に気づいた→自分なりの視点を持った→就活との関連に触れる”という流れを意識すると深みが出る。
経済・ビジネス系:志望業界に近いテーマを選ぶと強い
業界分析や企業研究にも通じる分野だ。たとえば「値上げラッシュ」に関するニュースから、「消費者行動の変化」「価格戦略の難しさ」「企業がどう信頼を守るか」など多角的に展開できる。特にメーカー志望や流通志望の学生にはおすすめだ。無理に難解な記事を読む必要はなく、Yahoo!ニュースや日経電子版の要約記事などで十分に準備ができる。
テクノロジー系:未来への関心が伝わる
AI、ブロックチェーン、5G、ロボティクスなど、未来を形づくる技術系の話題も評価されやすい。特に、IT系志望でなくても、例えば「ChatGPTを使って就活準備を効率化した」といったエピソードに絡めれば、話題性もあり、自発性や適応力をアピールできる。ポイントは、技術そのものの仕組みよりも「それが社会や働き方にどう影響するか」にフォーカスすることだ。
身近なニュースやエンタメもOK
「海外旅行の再開」「新型感染症後の働き方」「人気ドラマが社会に与える影響」など、一見すると就活と無関係に見える話題でも、深く考察することで評価される場合がある。たとえば、「Netflixの社会派ドキュメンタリーを見て、報道のバイアスやSNS時代の情報の危うさを感じた」と話せば、視野の広さやメディアリテラシーへの意識を示すことができる。
具体的にどう語るか:4ステップで構成する
構成を決めておくと、どんな話題でも安心
どんな本やニュースを題材にしても、伝え方の構成がしっかりしていれば内容はブレない。以下の4つのステップを使えば、どんなジャンルでも整理された答え方になる。
ステップ1:きっかけを語る(Why)
「なぜそれを読もう・見ようと思ったのか?」を語ることで、自分の関心の方向性が伝わる。たとえば、「就活で企業選びに悩んでいたので、ビジネス書を手に取った」「業界の動向を知りたくて、関連するニュースを読むようになった」といった背景があると納得感が生まれる。
ステップ2:内容を簡潔に説明(What)
実際に読んだ・見た内容を、専門用語を避けて簡潔に要約する。ここでは“詳細”よりも“伝わりやすさ”を意識する。たとえば、「この本では、誰もが創造的な仕事をする時代に必要な考え方が紹介されていた」といった要約で十分だ。ニュースであれば、「○月に発表された政府の政策で、若年層の教育支援に関する新たな方針が示された」など、事実をコンパクトに述べる。
ステップ3:自分なりの視点を加える(Think)
最も重要なのがこのパートだ。「私はこの内容から何を考えたのか」「自分の考えや立場はどうか」を語ることによって、他の学生との差がつく。たとえば、「社会的な弱者に対する制度の限界を感じ、自分に何ができるのか考えるようになった」といった視点があると、面接官は「深く考える力がある」と感じる。
ステップ4:行動や志望に結びつける(Do)
最後に、その読書やニュースの理解が“今の自分の行動”や“将来の志望”とどう結びついているかを語ることで、説得力が一気に増す。「このニュースをきっかけに、BtoB企業のインフラの重要性に気づき、業界への関心が高まった」「この本の内容を活かし、自己分析のやり方を見直した」といった形で、就活との接点を示そう。
模範回答例とその解説
回答の完成度は“内容の深さ”と“話し方”で決まる
「最近読んだ本やニュース」への回答に正解はないが、“よくある失敗”と“好印象を与える構成”は存在する。この回では、模範例をいくつか挙げ、どのような構成で話せばよいのか、そしてNGパターンに陥らないためにはどう工夫すればよいのかを解説していく。
模範例1:「ニュース」系(AIと働き方)
回答例(模範)
「最近読んだ印象的なニュースは、『生成AIと労働の未来』に関する特集です。特に注目したのは、定型業務の自動化が加速することで、今後“人間にしかできない仕事”へのシフトが求められるという視点でした。私はこの内容から、自分がどのように社会に価値提供できるかを改めて考え直すきっかけを得ました。例えば、これまでのアルバイト経験を振り返る中で、“人との信頼関係”が大きな成果に繋がっていたことに気づき、そうしたコミュニケーション力をさらに磨いていきたいと思っています。このような社会の変化にも適応し続けられる人材になりたいと感じています。」
解説
この回答では、「何のニュースか(概要)→なぜ印象的だったか→自分の行動や考え方にどう影響したか→就活とのつながり」という流れで一貫性を持って構成されている。「AI」という話題性のあるテーマを扱いつつ、抽象的な知識の披露ではなく“自分ごと化”して語っている点が評価される。
模範例2:「本」系(ビジネス書)
回答例(模範)
「最近読んだ本は『1分で話せ』(伊藤羊一著)です。この本では、“結論から伝える重要性”や“論理的に話すための構造化の技術”が紹介されており、面接やプレゼンに不安を持っていた私にとって非常に実践的な内容でした。読後は、自己PRや志望動機の話し方を見直し、ノートに結論と根拠をまとめる練習をしています。就活を進めていく中で、“伝える力”が自信の源になると感じており、この本はまさにその第一歩を与えてくれたと実感しています。」
解説
ここでは「ビジネス書」という就活に直結しやすいジャンルを選んでいる。読んだ内容を表面的にまとめるだけではなく、それを“どのように実践しているか”まで語っている点が優れている。「読む→考える→行動に移す」という3段階が入っているかどうかが、回答の深さを決める重要ポイントだ。
NGパターンとその改善方法
よくあるNG例とその背景
1. 内容が曖昧で“印象に残らない”
「最近読んだのは、なんかビジネス書だったと思います。成功するためには挑戦が大切みたいな話でした。」このような内容は、曖昧すぎて面接官に何も伝わらない。“何を読んだか”すら明確に覚えていない印象を与えると、「意欲がない」「取り繕っている」とマイナス評価につながる。
→【改善策】:タイトル・内容・感想の3点は最低限押さえておく。読み込めていないなら、ニュース記事など短くても語れるものを選ぶ方が良い。
2. 知識を語るだけで“自分の視点”がない
「この本ではマーケティングの4P理論について書かれていて、Product、Price、Place、Promotionが重要とされていました。」このような説明は、参考書の要約のようになってしまい、自分の視点が伝わらない。知識量だけを披露しようとするほど、印象は弱くなる。
→【改善策】:たとえ知識系の内容でも、「自分はこれをどう考えたか」「それを踏まえて何をしたか」を語ることが重要。
3. 面接官との共通点狙いで“背伸びしすぎる”
「日経新聞を毎日読んでいます」と言ってみたものの、突っ込まれて答えられずしどろもどろになる例も多い。話の内容に興味を持たれても、深掘りに耐えられなければ意味がない。
→【改善策】:難しいテーマを選ぶより、自分の中で“語れるストック”がある話題を選ぶほうが安心。共感されやすい身近な内容でも、視点や構成で十分に評価される。
どこまで準備すればよい?就活生に最適な“ストック戦略”
「1ニュース+1冊の本」を持っておくと安心
複数企業を受けていく中で、同じような質問を何度もされることになる。そのたびに新しい話題を探すのは現実的ではない。だからこそ、「本とニュース1つずつ」を自分の定番ネタとして準備しておくと良い。繰り返し話すことで回答が洗練され、自信にもつながっていく。
“就活日記”で思考を整理する
読んだ内容をその場で話せる人は少ない。だからこそ、読書やニュースに触れた後に“就活用メモ”として簡単にまとめておく習慣があると強い。「タイトル/読んだ理由/印象的なポイント/自分の考え/行動への影響」という5つの項目だけで構わない。話す訓練よりも先に、思考の整理ができていることが最大の武器になる。
模範回答例とその解説
回答の完成度は“内容の深さ”と“話し方”で決まる
「最近読んだ本やニュース」への回答に正解はないが、“よくある失敗”と“好印象を与える構成”は存在する。この回では、模範例をいくつか挙げ、どのような構成で話せばよいのか、そしてNGパターンに陥らないためにはどう工夫すればよいのかを解説していく。
模範例1:「ニュース」系(AIと働き方)
回答例(模範)
「最近読んだ印象的なニュースは、『生成AIと労働の未来』に関する特集です。特に注目したのは、定型業務の自動化が加速することで、今後“人間にしかできない仕事”へのシフトが求められるという視点でした。私はこの内容から、自分がどのように社会に価値提供できるかを改めて考え直すきっかけを得ました。例えば、これまでのアルバイト経験を振り返る中で、“人との信頼関係”が大きな成果に繋がっていたことに気づき、そうしたコミュニケーション力をさらに磨いていきたいと思っています。このような社会の変化にも適応し続けられる人材になりたいと感じています。」
解説
この回答では、「何のニュースか(概要)→なぜ印象的だったか→自分の行動や考え方にどう影響したか→就活とのつながり」という流れで一貫性を持って構成されている。「AI」という話題性のあるテーマを扱いつつ、抽象的な知識の披露ではなく“自分ごと化”して語っている点が評価される。
模範例2:「本」系(ビジネス書)
回答例(模範)
「最近読んだ本は『1分で話せ』(伊藤羊一著)です。この本では、“結論から伝える重要性”や“論理的に話すための構造化の技術”が紹介されており、面接やプレゼンに不安を持っていた私にとって非常に実践的な内容でした。読後は、自己PRや志望動機の話し方を見直し、ノートに結論と根拠をまとめる練習をしています。就活を進めていく中で、“伝える力”が自信の源になると感じており、この本はまさにその第一歩を与えてくれたと実感しています。」
解説
ここでは「ビジネス書」という就活に直結しやすいジャンルを選んでいる。読んだ内容を表面的にまとめるだけではなく、それを“どのように実践しているか”まで語っている点が優れている。「読む→考える→行動に移す」という3段階が入っているかどうかが、回答の深さを決める重要ポイントだ。
NGパターンとその改善方法
よくあるNG例とその背景
1. 内容が曖昧で“印象に残らない”
「最近読んだのは、なんかビジネス書だったと思います。成功するためには挑戦が大切みたいな話でした。」このような内容は、曖昧すぎて面接官に何も伝わらない。“何を読んだか”すら明確に覚えていない印象を与えると、「意欲がない」「取り繕っている」とマイナス評価につながる。
→【改善策】:タイトル・内容・感想の3点は最低限押さえておく。読み込めていないなら、ニュース記事など短くても語れるものを選ぶ方が良い。
2. 知識を語るだけで“自分の視点”がない
「この本ではマーケティングの4P理論について書かれていて、Product、Price、Place、Promotionが重要とされていました。」このような説明は、参考書の要約のようになってしまい、自分の視点が伝わらない。知識量だけを披露しようとするほど、印象は弱くなる。
→【改善策】:たとえ知識系の内容でも、「自分はこれをどう考えたか」「それを踏まえて何をしたか」を語ることが重要。
3. 面接官との共通点狙いで“背伸びしすぎる”
「日経新聞を毎日読んでいます」と言ってみたものの、突っ込まれて答えられずしどろもどろになる例も多い。話の内容に興味を持たれても、深掘りに耐えられなければ意味がない。
→【改善策】:難しいテーマを選ぶより、自分の中で“語れるストック”がある話題を選ぶほうが安心。共感されやすい身近な内容でも、視点や構成で十分に評価される。
どこまで準備すればよい?就活生に最適な“ストック戦略”
「1ニュース+1冊の本」を持っておくと安心
複数企業を受けていく中で、同じような質問を何度もされることになる。そのたびに新しい話題を探すのは現実的ではない。だからこそ、「本とニュース1つずつ」を自分の定番ネタとして準備しておくと良い。繰り返し話すことで回答が洗練され、自信にもつながっていく。
“就活日記”で思考を整理する
読んだ内容をその場で話せる人は少ない。だからこそ、読書やニュースに触れた後に“就活用メモ”として簡単にまとめておく習慣があると強い。「タイトル/読んだ理由/印象的なポイント/自分の考え/行動への影響」という5つの項目だけで構わない。話す訓練よりも先に、思考の整理ができていることが最大の武器になる。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます