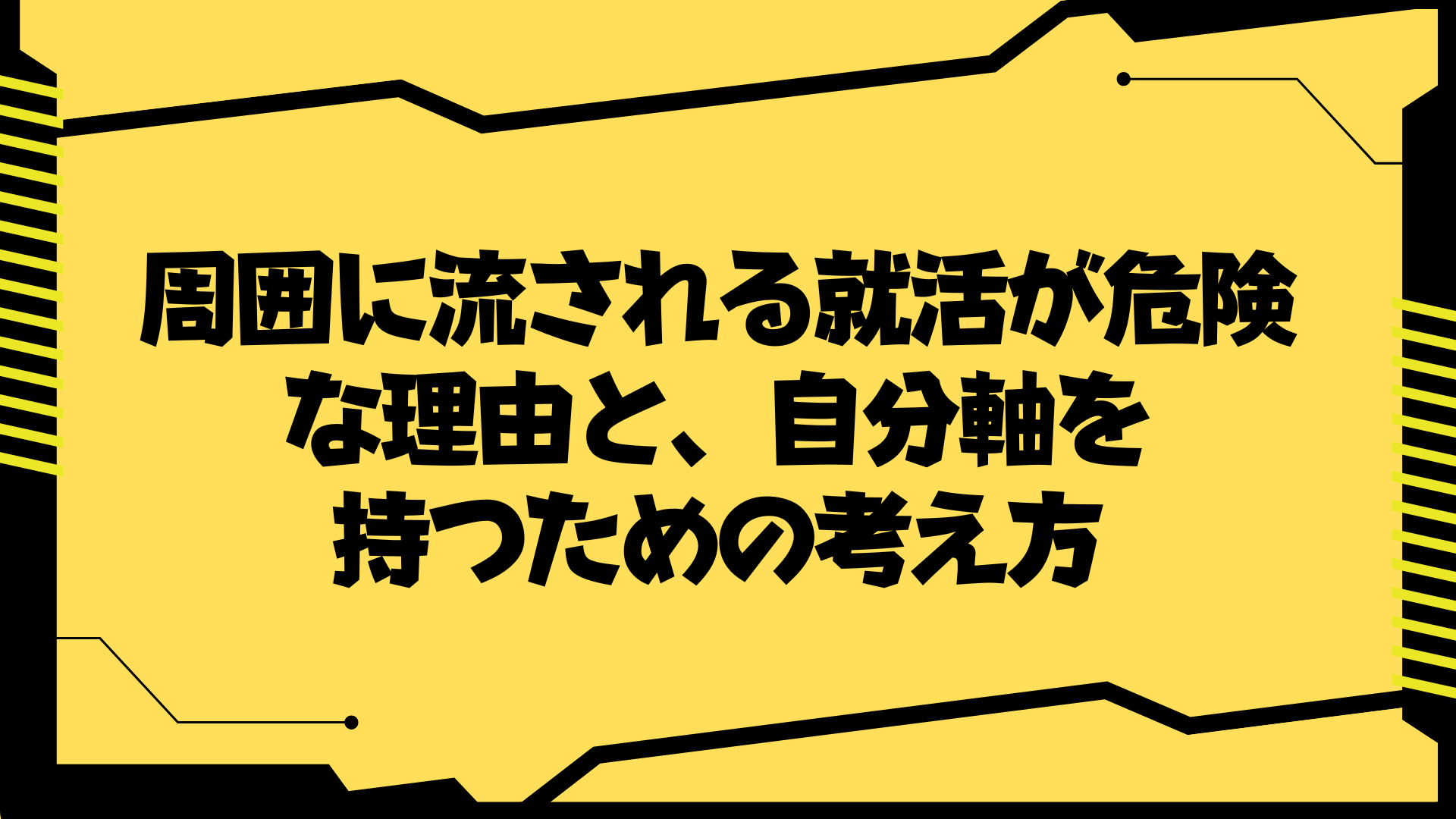なぜ「みんながやってるから」は危険なのか
“空気で決める就活”が引き起こす本質的な問題
就職活動が始まると、多くの学生は「みんなが動き出したから」「大学の友達がその企業を受けてるから」という理由で企業選びやエントリーを始めてしまう。これは表面的には“協調性がある”とも取られるが、根底にあるのは自分の意思が欠如していることに他ならない。
就活において、周囲に合わせて動いてしまうと次のようなリスクが生じる。
企業とのミスマッチが起きやすい
書類や面接での説得力が乏しくなる
内定を取っても納得感が持てない
入社後の早期離職につながる可能性が高まる
つまり、「なんとなく選ぶ」「流されて決める」就活は、長期的なキャリア形成の土台を揺るがしかねない危険性を含んでいる。
周囲のペースと比較しても意味がない理由
「もう20社エントリーした」「3月に最終面接受けてる人がいる」といった情報に焦って動いてしまう学生も多いが、これは就活の本質から外れている。
なぜなら、就活はスタートダッシュよりも“自己理解と企業理解の深さ”が勝負を分ける構造になっているからだ。エントリー数や行動量に囚われると、結果が出ない原因が見えなくなり、振り返りや修正もできなくなる。
周囲と比較することに意味はない。意味があるのは、自分のやるべきことに向き合っているかどうか、それだけだ。
「自分軸を持っている人」が就活で有利な理由
軸がある人は情報を“取捨選択”できる
自分の価値観や将来像がある程度言語化できている人は、就活の情報を鵜呑みにせず、「これは自分に必要な情報か」「この企業は自分に合っているか」を判断できる。
これは大きな差となって現れる。情報過多の時代において、「選べる力」がないと、どれだけ行動しても迷いが深くなってしまうからだ。
自分軸がある人は、志望企業の選定においても一貫性があるため、ESの説得力も高く、面接でも「この人は自分で考えて選んでいる」と評価されやすい。
「選ばれる」よりも「選ぶ」視点に立てる
就活のフェーズが進むにつれ、内定が出ない学生ほど「どこかに拾ってもらいたい」という受け身のスタンスになっていく。しかし、この姿勢は企業に見透かされやすく、“やる気が感じられない”“なんとなく受けている印象”を与える原因にもなる。
逆に、自分の軸を持って企業選びをしている学生は、「自分の意思でこの企業を選んでいる」という自信が面接の受け答えにも現れ、結果として企業側からも「一緒に働きたい」と思われやすくなる。
自分軸のない就活にありがちな行動とその結末
周囲の“なんとなく大手志向”に乗っかってしまう
「親が知っている企業だから」「人気ランキングに載っていたから」「周りがみんな受けているから」という理由で、何となく大手企業ばかりを受ける学生は少なくない。しかし、このような動機では選考で志望度を問われたときに答えに詰まりやすく、説得力が出ない。
結果として、選考に通らないだけでなく、通ったとしても「本当に行きたかった会社だったのか」と後悔することもある。最悪の場合、入社後にミスマッチが顕在化し、早期離職へとつながってしまう。
受けている会社の“共通点”が自分でも分からない
自分軸がない学生ほど、企業選びに一貫性がなくなりがちだ。ITも受けていればメーカーも、ベンチャーも受ける。そしてそれぞれに違う志望動機を用意することになり、結果としてどれも中途半端になる。
企業側はその不自然さをすぐに見抜く。「本当にこの仕事をしたいのか」「うちの会社じゃなくても良いんじゃないか」と思われるのは、自分軸が曖昧なまま就活を進めてしまっている証拠である。
自分軸を見つけるための“はじめの問いかけ”
何をしているときに“時間を忘れる”か
就活で使える自己分析にはさまざまな方法があるが、もっとも基本的で有効な問いのひとつが「何をしているときに自分は時間を忘れて没頭していたか」である。
その問いの答えには、自分が何に価値を感じ、どんな瞬間に充実感を覚えているかが詰まっている。過去の経験の中から、以下のような切り口で考えると良い。
課外活動や部活での役割と充実感
アルバイトで評価されたときのエピソード
チームで取り組んだ中で特に達成感があった瞬間
このような体験を振り返ることで、自分が何を重視しているのか、自分が活きる環境はどのようなものかの輪郭が浮かび上がってくる。
“向いていること”ではなく“やっていきたいこと”に目を向ける
よくある間違いが、「向いているかどうか」ばかりで仕事を選ぼうとすることだ。もちろん、自分の性格やスキルに合った仕事を探すのも大切だが、それだけで判断すると“無難な選択”に落ち着きやすく、成長実感や充実感が得られにくい。
向いているかどうかではなく、「この分野を深めていきたい」「この働き方をしていたい」と思えるかを基準にすることで、就活そのものが“義務”ではなく“意思ある選択”へと変わる。
自分軸を構築するステップと、それを就活に活かす方法
自分軸を構築するための3つの視点
「経験」から探る価値観の源泉
自分軸とは、「どんなことを大事にしているか」「どんなことにやりがいを感じるか」を言語化したものである。まず最初に取り組むべきは、自分の経験の棚卸しだ。
ポイントは、結果ではなく「そのとき何を大切にしていたか」を見つけること。例えば、部活で副キャプテンとしてチームを支えた経験があるなら、
主役ではなく縁の下の力持ちにやりがいを感じた
目立たない努力を評価されると嬉しかった
周囲との信頼関係づくりに熱中していた
というように、その体験の「核」になっている価値観を丁寧に拾い上げる。この作業を3~5つの経験で行うと、共通して現れる要素が見えてくる。それが、自分軸の原材料となる。
「怒り・違和感」から探る否定の価値観
もう一つの視点が、「怒り」や「違和感」を感じた出来事だ。これは、自分の価値観が裏切られた瞬間に現れる反応であるため、非常に有効な手がかりになる。
例えば、
理不尽な上下関係に納得がいかなかった
頑張っている人が報われない組織に憤りを感じた
成果主義ばかりで人間関係が切り捨てられていた環境に違和感を覚えた
このような出来事を振り返ると、「自分は公平さを重視している」「人間関係を大切にするタイプだ」「協力し合うチームにいたい」といった、自分の“守りたい価値観”が見えてくる。
「羨望」から探る理想の働き方
最後に注目したいのが「羨ましいと感じた人や働き方」だ。それは、現時点で自分が持っていないが、将来そうありたいと思っているイメージの反映である。
たとえば、
自分の意見を堂々と言っていた先輩に憧れた
社外の人から信頼されて活躍している友人が眩しく見えた
転職して楽しそうに働いている社会人が印象的だった
このような「自分の目指す方向性」が、将来像を描くヒントになる。経験・違和感・羨望の3軸を整理することで、自分の中にある“進みたい方向”が輪郭を持って立ち上がってくる。
見つけた自分軸を「就活に使える言葉」にする
価値観を抽象化 → 具体的な行動に落とし込む
自分軸が見えてきたら、それをそのまま使えばいいかというと、そうではない。就活では、抽象的な価値観を“企業が理解できる言葉”に変換する必要がある。
たとえば、「人間関係を大事にしたい」という軸があった場合、そのままだと曖昧すぎる。これを以下のように変換すると、選考でも伝わりやすくなる。
【抽象的】:人間関係を大切にしたい
【具体化】:チームでの連携や信頼関係を重視する環境で力を発揮したい
【裏付け】:ゼミでのプロジェクト進行時、メンバー全員と1on1で進捗確認を行い、関係構築を徹底していた
このように、「価値観→表現→実例」の流れを作ることで、自分軸は企業に伝わる“言葉”となる。
「企業選び」の基準として活用する
自分軸は、企業選びの“フィルター”としても非常に役立つ。これまで漠然と「名前を知ってる」「有名だから」という理由で選んでいた企業も、「自分の価値観と合っているか?」という基準で見直すことができる。
たとえば、
自分が「裁量権がある環境で成長したい」軸を持っているなら、年功序列の大企業より、若手に任せる文化のあるベンチャーの方が合っている可能性が高い
「安定性を重視する」という軸を持つなら、業界の安定性・財務体質・従業員満足度などを重視すべき
このように、自分軸が企業選びの「物差し」になることで、ブレずに選考を進められるようになる。
面接で「自分軸」を武器にする方法
“なんとなく志望”から卒業する回答例
多くの学生がやってしまいがちなのが、「御社の社風に惹かれました」「社員の方が優しそうだったから」という、印象ベースの志望動機だ。
一方で、自分軸を元に作った志望動機は、以下のように筋が通っている。
「私はゼミで意見の違う人同士をつなぐことにやりがいを感じてきました。説明会で感じた御社のチームでの共創的な文化は、その価値観と一致していると感じています。」
これは、自己理解→企業理解→接続という構造が成立しているため、面接官にも刺さりやすい。
“御社じゃなくてもいいのでは?”への対策
面接官がよく使う質問に「うちじゃなくても他の会社でも良いのでは?」というものがある。この質問は、学生の“納得度”や“企業理解”の深さを見極めるためのものだ。
この問いに対しても、自分軸を持っていれば明確に答えられる。
「私は挑戦できる環境を重視しており、貴社の若手に裁量を与える制度や、社員インタビューで語られていた失敗を許容する文化に最も惹かれました。他社と比較しても、これが最も自分の軸に一致しています。」
こうした回答ができると、「この学生は本気で企業研究をしてきた」「志望度が高い」と判断され、通過率が上がる。
自分軸があるだけで得られる“精神的な安定”
不安な時期にも振り返れる“拠り所”になる
就活では、「落ち続けて自信がなくなる」「周囲の成功がプレッシャーになる」といった不安がつきまとう。そんなときに、自分軸があるとブレにくい。
たとえ落ちたとしても、「あの企業は自分には合っていなかった」「ちゃんと自分の意思で選考に臨んだ」と思えるため、納得感が残る。結果的に、自己否定を避けながら継続的に選考に臨むことができる。
企業の魅力に“飲まれにくく”なる
選考が進むと、企業側も“魅せる工夫”をしてくる。オフィスの綺麗さ、社員の人柄、制度のアピール。これらは決して悪いことではないが、自分軸がないと、「なんとなく良さそうだから内定をもらったら行こう」という受け身の判断になりやすい。
だが、自分軸を持っている学生は、こうした要素を冷静に受け止めつつ、「本当に自分が望む環境か」を見極める視点を失わない。これが“企業に選ばれる”だけでなく、“企業を選ぶ”という視点を保つ鍵となる。
“大手志望”に潜む落とし穴と、その就活への影響
なぜ多くの学生が“なんとなく大手志望”になるのか
情報の偏りと「当たり前」による刷り込み
就活初期、多くの学生が口にするのが「とりあえず大手を目指す」という言葉だ。これは一見合理的な判断に見えるが、実際は“情報の偏り”に起因するケースが多い。大学のキャリアセンター、就活サイト、合同説明会などでは、露出の多い企業=大手企業ばかりが目立つ。これによって、「みんなが受けるから」「有名企業だから安心」といった、根拠の薄い“安心感”が生まれる。
また、親世代や社会人OBからのアドバイスも「大手に行けるなら行った方がいい」となることが多い。だが、このアドバイスには前提条件がある。昭和・平成の時代では、「大手に入れば一生安泰」「年功序列・終身雇用」が当たり前だったが、現在は状況が大きく異なる。リストラも起こり得るし、異動でやりたくない部署に行くこともありえる。つまり、“大手=安定”という方程式はすでに崩れつつあるのだ。
社名による“承認欲求の充足”
「どこ受けてるの?」「どこ内定出た?」という会話が飛び交う就活シーズン。そんな中で、誰もが知る大企業の名前を出せば周囲の反応はポジティブになりやすい。それが、知らず知らずのうちに“承認欲求”を満たす手段になっているケースがある。
たとえば、「本当はベンチャー企業で裁量を持って働きたいけど、◯◯商事の名前の方がすごいって思われるから、そっちに行く」といった行動は、完全に“他人軸”の選択だ。就活で一番避けるべきは、この「他人に褒められそうな企業を選ぶ」という姿勢である。
就活のゴールは“どこに入ったか”ではなく“どこで納得して働き続けられるか”にある。他人からの称賛を目的に進路を選ぶと、入社後に大きなギャップや後悔を生むリスクが高まる。
大手だからこそ直面する“成長の壁”
「歯車感」に耐えられない若手たち
大手企業に入社すると、確かに教育制度は充実している。しかし、その分「自分の裁量で物事を動かす」という実感が得られにくいケースも多い。研修、マニュアル、承認フロー…。大きな組織ゆえに、全てが“ルール通り”に進むため、若手が自由に動ける余地は少ない。
このような環境において、「もっと早く成長したい」「自分の意見を仕事に反映させたい」と思っていた人ほど、閉塞感や不全感を覚える。いわゆる“歯車感”だ。
「このまま3年働いても自分の市場価値が上がっているとは思えない」
「言われたことしかできないなんて、自分らしくない」
こうした声が入社後1年以内に多く聞かれるのは、まさにこの成長ギャップに原因がある。特に「若いうちから活躍したい」というモチベーションを持っていた人ほど、早期離職に至りやすい傾向がある。
評価制度が見えにくい構造
大企業では、人事評価の仕組みが複雑で、若手にとって自分の成長や成果がどう評価されているのかが見えにくいことも多い。評価される基準が曖昧だったり、直属の上司ではなく別部署が査定を担当していたりと、結果と報酬・昇進の連動性が低い構造になりがちである。
このような環境では、「頑張ったけど評価されていない気がする」「なぜあの人が先に昇格するのか納得できない」という“納得感の欠如”が生まれる。特にZ世代の就活生にとって、評価の透明性やフィードバックの質は企業選びの重要な要素であり、これを無視すると入社後のギャップが大きくなる。
知名度だけで企業を選ぶ危険性
知っている=自分に合っている、とは限らない
「この企業、聞いたことあるから」「テレビCMでよく見るから安心」という理由でエントリーする学生は少なくない。しかし、知っていることと、自分に合っていることはまったく別物だ。
たとえば、CMでおなじみの大手飲料メーカー。表面的には“楽しい・華やか・明るい”という印象があるが、実際の仕事内容は、営業で朝から晩までルート回り、配達作業に近い肉体労働ということもある。こうした“外から見た印象”と“中での実態”のギャップを知らないまま内定を承諾すると、ミスマッチが起こるのは当然だ。
業界内のポジションと将来性を見誤る
知名度があるからといって、その企業が業界内で最も影響力があるとは限らない。むしろ、知名度の割に業績が低迷していたり、成長領域から外れていたりする場合もある。
たとえば、出版やメディア業界は知名度が高いが、デジタル化の波で紙媒体が縮小傾向にあり、構造的に苦しい状況が続いている。金融業界でも、伝統的な銀行よりもフィンテック企業の方が革新的な動きをしているケースもある。
「自分は安定した業界に入りたい」と考えていたのに、気づけば将来的に縮小していく業界に足を踏み入れていた、ということも起こり得る。知名度だけに頼らず、業界全体の将来性や企業の戦略も冷静に見極めることが必要だ。
大手を選ぶ“明確な理由”があるなら問題ない
“大手を選ぶな”という話ではない
ここまで“大手志望のリスク”を述べてきたが、これは“大手を選ぶな”という話ではない。問題は、「自分の意志ではなく、なんとなく選んでいること」なのだ。
大企業には、確かに素晴らしい点も多い。教育制度が整っている、福利厚生が充実している、社会的信頼が厚い。こうした特徴に対して、自分の価値観と照らし合わせて「だから行きたい」と言えるなら、それは立派な志望理由であり、自分軸と合致している。
むしろ、どんな企業であれ、「この会社を選ぶ理由が明確にあるか?」が問われるのが就活である。大手でもベンチャーでも、自分の中に納得できる軸があれば、迷う必要はない。
自分に本当に合う企業の見極め方と判断軸のつくり方
就活は「選ばれる場」ではなく「選ぶ場」である
「受かるかどうか」より「合っているかどうか」
就活ではつい、「内定をもらえるか」「評価されるか」という“選ばれる視点”に意識が集中してしまいがちだ。しかし、企業選びはそもそも“選ぶ側”でもあるべきだ。つまり、自分に合っていない企業からの内定を獲得することに大きな価値はない。
この視点の転換ができないまま就活を進めると、最終的に“なんとなく決める”という最悪の結果を招く。特に大手企業や有名企業に複数内定をもらった際に「どれもそれなりに良さそうだけど決め手がない」という状況は、この“自分軸の欠如”に起因している。
選考が進む中でこそ、自分が本当に納得できる判断軸が必要になる。逆に言えば、「この企業から内定をもらっても承諾しないだろうな」と感じたら、早めに辞退や見直しを考える判断も重要だ。
「内定が出たから行く」では後悔しやすい
「たまたま通ったから」「評価してもらえたから」「落ちたくなかったから」という理由で承諾した内定は、入社後の満足度や定着率が低くなる傾向がある。なぜなら、それは“内定が出たこと”を目的にした選択であり、キャリアとしての意志や展望が欠けているからだ。
企業はあくまで“スタート地点”であり、人生のゴールではない。「入社後にどんな環境でどう成長したいか」「どんな仕事に喜びを感じるか」という視点で判断しないと、入社してから“違和感”に苦しむことになる。
「自分に合っている企業」とはどういう企業か?
仕事内容よりも「環境と価値観の一致」が大事
多くの学生が企業選びで最初に見てしまうのが“業種”や“職種”だ。しかし、実際に働くうえで大きく影響するのは「働く環境」や「組織の価値観」との一致度である。
たとえば、同じ営業職でも、成果主義でどんどん裁量が与えられる会社もあれば、チームで丁寧に育成する文化を持つ会社もある。事務職でも、単純作業の繰り返しを重視するか、提案型で業務改善に関われるかで、大きく意味が変わってくる。
つまり、同じ“職種”や“仕事”でも、会社の文化・上司のタイプ・評価制度・裁量権の大きさなどによって、体験する中身はまったく違うのだ。自分がどういう環境で力を発揮しやすいか、どんな働き方にモチベーションを感じるかを掘り下げておく必要がある。
「人」「育成方針」「価値観」で選ぶ
企業選びにおいては、「どんな人がいるか」を重視することも極めて重要だ。なぜなら、社会人になってから最も影響を受けるのは、“隣で働く人”だからである。
「人事や現場の社員が親身で、本音で話してくれた」
「若手を放任せず、段階的に育てようとする姿勢が伝わった」
「働く目的に共感できた。自分の価値観と近かった」
このような“相性”や“価値観の一致”を感じた企業ほど、入社後のギャップは少なく、長期的にモチベーションを保ちやすい。逆に、どれだけ条件が良くても「社員と波長が合わない」「話が建前ばかり」な企業は、違和感が積もりやすい。
企業の“本質”を見抜くための情報の取り方
説明会や選考で見るべき視点
企業側は当然ながら“魅力的な部分”を前面に出してくる。だが、就活生はその裏側にある“リアル”を見抜かなければならない。そのためには、以下のような視点で情報を得ることが重要である。
「若手社員は何年目でどのような業務を任されるのか?」
「辞めていく人の理由や、実際の離職率は?」
「評価のされ方は?数字だけ?行動も見られる?」
「職種間・拠点間で格差はあるか?」
「現場と人事で語る内容にズレはないか?」
こうした質問を選考中に投げかけると、企業の本音や実態が垣間見えることがある。また、人事担当者だけでなく、現場社員・若手社員から話を聞く機会がある場合は、必ず「入社前後でギャップを感じたこと」などを尋ねてみるとよい。
OB・OG訪問は“生の温度感”を得られるチャンス
大学のキャリアセンターやSNSを活用すれば、OB・OG訪問の機会は意外と多い。可能であれば「同じ学部・同じようなキャリア志向の先輩」にアプローチすることで、より実感に近い情報が得られる。
OB・OG訪問では、「仕事の大変さ」や「上司との関係性」「やりがいと悩みのバランス」など、パンフレットには載らない“生活の温度”が分かる。たとえば、「月曜の朝、会社に向かうときどんな気持ちですか?」という質問だけでも、相手の働き方や満足度がにじみ出る。
「志望動機」は“相手に伝える”だけでなく“自分を確認する”ためにある
自己理解の浅いまま志望動機を書くと迷走する
「なぜこの会社を志望するのか?」という問いに、自分自身が明確に答えられないまま就活を進めてしまうと、受ける企業がどれも似たような理由になってしまい、結果として面接で“熱意が感じられない”印象を与えてしまう。
志望動機は、単なる選考対策ではなく「自分がこの会社をどう評価し、どんな未来を期待しているか」の確認作業である。つまり、自分の価値観・働き方・成長意欲と、企業の方向性や制度とが一致していることを証明する言葉が、志望動機なのだ。
これが曖昧なままだと、「大手だから」「福利厚生が良いから」程度の薄い志望動機になってしまい、選考通過率も下がる。
まとめ
就活で「なんとなく大手志望」になることは、他人軸・曖昧な自己理解・誤った情報判断など、さまざまな“ズレ”を引き起こす要因になり得る。就活において重要なのは、自分に合った企業を見極めるための“判断軸”を持つこと。そして、「企業に選ばれる」だけでなく、「自分が企業を選ぶ」姿勢を持つことである。
知名度や待遇の良さはあくまで“条件の一部”であり、働くうえで本当に大切なのは「どんな人たちと、どんな価値観で、どんな働き方をするか」である。それを見抜くためには、情報収集・自己分析・企業分析の三位一体が必要だ。
他人の評価ではなく、自分の基準で納得して企業を選べた人こそが、“最初の内定”をきっかけに、後悔のないキャリアを築いていくことができる。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます