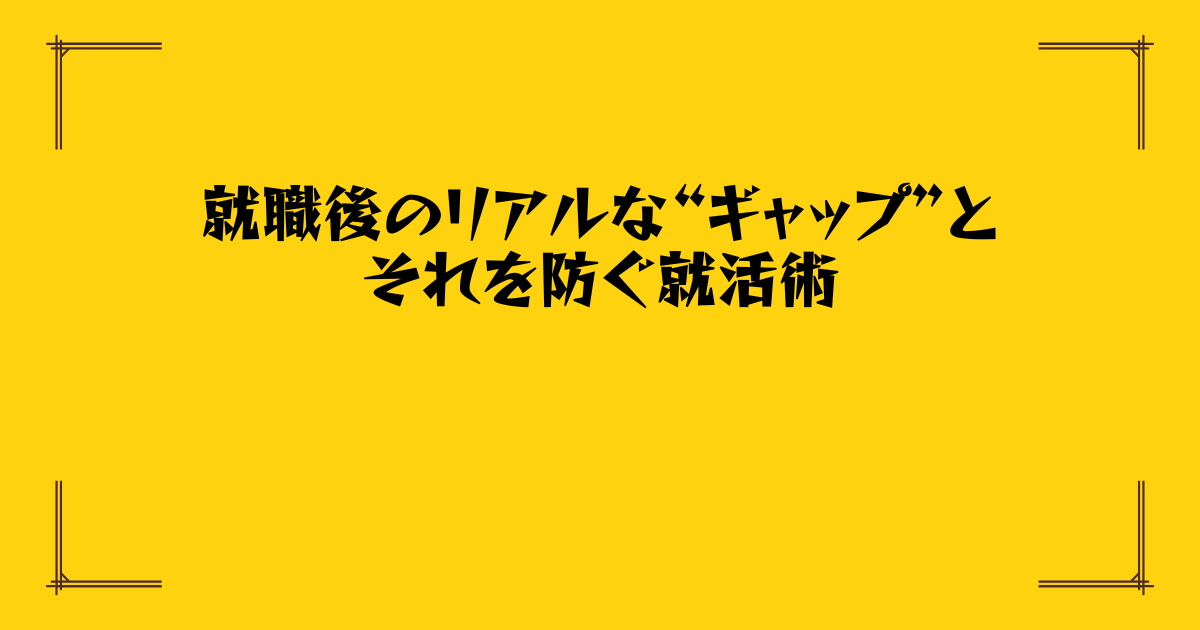就職後に多くの若手が感じる“想定外のギャップ”
なぜ就職後すぐに違和感が生まれるのか
「思っていた仕事と違う」はなぜ起こるか
新卒入社から数ヶ月も経たないうちに、「この仕事、自分が想像していたものと違う」「こんなに単純作業ばかりだとは思わなかった」「人間関係が意外にストレス」といった声が聞かれることは多い。実際、厚生労働省の調査でも、新卒の3年以内離職率は大卒で3割前後。これは単なる「飽き」や「根性不足」ではなく、就活時に抱いていた期待と現実の間にあるギャップの大きさに原因がある。
このギャップは、「会社選び」が間違っていたというよりも、選び方の“視点”が甘かったことが大きい。つまり、仕事内容や職場環境、人間関係、成長機会など、仕事の本質に関する情報が不足していたまま意思決定をしてしまったケースが多いのだ。
「社会人のリアル」に触れていない就活のリスク
就活中の学生は、説明会やインターン、OB・OG訪問といったイベントを通じて企業理解を深めるが、そこで得られる情報はあくまで「表面的なリアル」であることが多い。企業側は当然、自社にとって都合の良い情報を強調するし、就活生もまた「こういう答えを期待されているだろう」と思って質問を控えめにしてしまう。
結果として、キラキラした企業の表面だけを見て“なんとなく良さそう”と判断し、入社後に想定外の現実に直面することになる。これは、個人の責任というよりも、就活という構造自体が“本質から目を逸らさせる設計”になっていると言ってもいい。
「ギャップ」が起きやすい具体的なポイント
実際の仕事内容と想像のズレ
多くの学生が最も戸惑うのが、「入社後に任される業務内容」のリアルだ。たとえば営業職。就活時は「顧客に提案し、課題解決に貢献するやりがいある仕事」と説明を受けていたはずなのに、実際には「毎日飛び込み訪問と電話営業」「定型資料の量産」「数字の詰め」に終始し、クリエイティブさや裁量はほとんどないというケースも多い。
また、事務職を選んだつもりでも、実態は営業サポート業務に近く、事務というよりも“縁の下の雑務全般”だったという話も珍しくない。こうしたズレは、「企業理解」の不足というよりも、“職種理解”の浅さから来ている。
社風や人間関係の現実
もう一つ大きなギャップの原因となるのが、組織文化や人間関係のリアルだ。学生時代にはあまり想像できないが、実際の職場では「体育会系の上下関係が強い」「管理職が旧態依然」「ミスがあると感情的に叱責される」「上司に気を遣って忖度しないとやっていけない」といった空気が支配している企業も少なくない。
また、採用広報では「風通しがいい」「チームで支え合う文化」と謳っていても、実態は各自が黙々と仕事をし、孤独な環境で成果だけが求められるといった矛盾もある。このような“文化的ギャップ”は、配属ガチャや上司ガチャに左右される部分もあるが、事前の情報収集と観察によってある程度は予測可能だ。
キャリアの選択肢が思ったよりも狭い
学生の多くは、「最初の会社でスキルを身につけ、将来的に転職や独立も視野に入れたい」と考えている。しかし、実際には「数年働いても専門性が育たない」「異動が多くて一貫性のあるキャリアにならない」「転職市場で評価されにくいポジションに偏っている」といった問題に気づく。
これは、企業ごとの人材育成方針や社内キャリア設計が明確でない場合に起きやすい。「若手にどんな裁量が与えられるのか」「昇進のスピード感はどうか」「ジョブローテーションの頻度」など、就活段階で確認すべき情報があるにもかかわらず、十分に掘り下げられていないことが多い。
就活に必要なのは「事実に触れるリテラシー」
情報を“表面”で受け取らない姿勢が必要
説明会やパンフレットは「正解の一部」でしかない
企業の説明会や公式HPで語られる内容は、いわば“理想像”や“成功例”であることが多い。もちろん嘘ではないが、そこには採用ブランディングの戦略が反映されており、「どんな人に来てほしいか」や「選ばれやすい価値観」を前提に構成されたメッセージである。
だからこそ、表面的なPRワードだけを信じて「この会社は合いそう」と判断するのは危険だ。たとえば「成長できる環境」という言葉の裏には、「放置されて自力で乗り越えなければならない」という現実があるかもしれないし、「フラットな組織」というワードが「指示系統が曖昧で責任の所在が不明」といった意味である場合もある。
言葉の定義を疑い、具体的にどういうことかを突き詰める習慣を持つことが重要だ。
リアルな情報をどう収集するか
若手社員や退職者の話に触れる
もっとも信頼できる情報源の一つが、「若手社員の実体験」と「既に辞めた人の話」である。特に、入社後2〜3年で辞めた人の声には、ミスマッチの要因や会社の本質を表す要素が凝縮されている。
もちろんネガティブな内容もあるが、それこそが現実であり、就活生にとっては最も有益な材料だ。SNSやYouTube、noteなどにはそうした体験談が数多く公開されており、積極的に読み込むことで「その会社で何が起きやすいか」をイメージできるようになる。
就活で“ギャップ”を防ぐために必要な情報の見極め方
「リアルな情報」と「キレイな情報」を区別する力
企業が発信する情報には意図がある
企業が発信する情報は、当然ながら“採用マーケティング”の文脈で設計されている。つまり、どんな人材を惹きつけたいかを逆算して構成されているということだ。たとえば「若手が活躍中!」という言葉の裏には、「離職率が高くベテランが少ない」といった背景があるかもしれない。
また、「挑戦できる社風」とは言いつつも、その“挑戦”が許されるのはごく一部のエース社員に限られる場合も多い。就活生がこのような表現をそのまま受け取り、「この会社は合っていそう」と思い込むのは非常に危険である。
本当に必要なのは、企業の言葉をそのまま信じるのではなく、“その言葉が実際の業務や制度の中でどう運用されているか”を想像する視点である。
「聞いたこと」と「体験したこと」の区別をつける
多くの就活生は、企業説明会やインターンで話を聞いた時点で「この会社をよく知った」と錯覚してしまう。だが、情報を受け取っただけでは“納得”とは言えない。たとえば「社員同士の距離が近い」と言われたとしても、それが「業務外でも付き合いが必要」なのか、「建前として仲が良いように装っている」のかによって印象は大きく異なる。
つまり、情報はそのまま受け取るのではなく、“どんな意味でその言葉が使われているのか”を検証する姿勢が必要である。可能であれば、実際に職場に足を運び、社員の様子や社内の空気感に触れるような「観察ベース」の理解を意識することが望ましい。
リアルな比較ができる企業研究とは何か
同じキーワードを複数社で見比べる
就活生が陥りがちな失敗のひとつは、1社ごとの情報を“単体で”評価してしまうことだ。たとえば、ある企業が「自由な働き方」とPRしている場合、それを「いい会社」と解釈するのではなく、「他の企業が言う“自由”とどう違うか?」という比較軸を持つことが大切だ。
つまり、1つのワードについて、複数社を横並びで比較して初めて“意味のズレ”や“リアルな違い”が見えてくる。このような企業研究を通じて、自分の価値観に本当に合う企業を選ぶことができる。
たとえば「若手が活躍」というワードでも、
A社:人数が少ないので若手でも自然と責任ある仕事を任される(属人的)
B社:教育体制が整っており、計画的に若手を育てていく(制度的)
という違いがある。この違いを理解せずに「若手活躍=魅力的」と短絡的に判断すると、入社後のギャップにつながる。
SNSや掲示板も“正しく”活用する
就活生の中には、企業口コミサイト(OpenWork、転職会議など)やX(旧Twitter)などをチェックする人もいるだろう。たしかに、こうしたSNS・口コミ系は“企業のリアルな裏側”に触れられる貴重な場だが、感情的な投稿や一方的な批判を鵜呑みにするのは危険である。
口コミはあくまで「個別の体験」であり、それが自分にも当てはまるとは限らない。だからこそ、複数の情報源を見て“共通して現れる特徴”を抽出する姿勢が求められる。
さらに、情報を見て終わりではなく、「それが自分にとってマイナスなのか?許容できる範囲か?」を自分の価値観で判断することが大切だ。
リアルな声に触れる方法と、質問力の重要性
OB・OG訪問は「聞き方」が命
質問の設計次第で得られる情報は変わる
OB・OG訪問は就活において最もリアルな情報を得る場のひとつだが、聞き方を間違えると「どの会社でも同じような話」しか得られない。たとえば、「やりがいはありますか?」「社風はいいですか?」といった抽象的な質問は、曖昧な回答しか返ってこない。
それよりも、
「1日の業務スケジュールを教えてください」
「新人の失敗でよくあるものは?」
「職場でストレスを感じる場面はありますか?」
といった具体的なエピソードや行動を引き出す質問を意識すると、表面的でないリアルな実態を把握できるようになる。聞いた内容はすべてメモして、他の会社と比較していくと、見えてくるものが変わる。
同じ社員に複数回会うのも有効
もし可能であれば、同じ社員と2回以上会うことも有効だ。1回目は一般的な話、2回目はより具体的な社内文化や配属、人間関係についてなど、信頼関係ができたあとに深堀りできるテーマを聞くと、より真実味のある情報に触れられる。
初回では言いにくいことも、2回目以降の会話ではぽろっと本音が出るケースもある。就活においては、「何社受けるか」よりも「1社をどこまで深掘るか」が重要になってくる。
就活生が自ら行動して“真実”に迫る姿勢が重要
「誰かが教えてくれる」という甘えを捨てる
多くの就活生は、企業が教えてくれる情報やナビサイトに掲載された内容を“信じること”を前提に動いてしまう。だが、就活の世界には「正解」も「保証」もない。だからこそ、自分で情報を探し、比較し、矛盾を突き、違和感を検証していく姿勢が求められる。
リアルな情報は、能動的な行動の中でしか手に入らない。そして、そこで得た情報こそが、入社後の納得感や離職リスクの低減に直結する。
入社後の「後悔」を減らす企業の見極め方
なぜ多くの新卒が「会社選びに失敗した」と感じるのか
企業選びの軸が曖昧なまま内定を取ってしまう
就職活動を進める中で、最も多く聞く声のひとつが「入社してから思っていたのと違った」という後悔だ。これは企業側の情報開示不足だけが原因ではなく、学生側が“何を基準に企業を選ぶか”を明確にしていないことも大きい。
たとえば「人間関係が良さそうだった」「若手でも活躍できそうだった」といった印象ベースの選び方では、入社後に「実際はパワハラが多い」「若手はただ責任だけ重くて放置されている」といったギャップに直面するリスクが高くなる。
つまり、自分にとっての“働きやすさ”や“成長環境”とは具体的にどんな状態かを明文化しておく必要がある。曖昧なまま内定を得ると、企業の実態とのギャップが浮き彫りになるのは当然である。
「人の良さ」や「雰囲気の良さ」は信頼できない判断軸
多くの学生が「社員の人柄が良さそうだった」といった理由で企業を選ぶが、これは危険な判断軸だ。というのも、説明会や面談に出てくるのは“採用向けに選ばれた人材”であり、企業全体の平均像とは限らないからだ。
実際に、「面接官は優しかったけれど、入社したら直属の上司は怒鳴る人だった」というケースは少なくない。一部の人に好印象を持ったからといって、会社全体がそうだと思い込むのは極めて短絡的である。
自分にとって「働きやすい」とは何かを定義する
「企業の良し悪し」ではなく「自分に合うかどうか」
就職活動において大事なのは、「いい会社を探すこと」ではなく、「自分にとって合う会社を選ぶこと」である。この“合う”という感覚は抽象的だが、ポイントは「自分がどんな環境でなら力を発揮できるか」「どんな価値観の人と働きたいか」を明確にすることにある。
たとえば、以下のような問いに具体的に答えてみると、判断軸が明確になる。
ひとりで黙々と取り組む仕事と、チームで相談しながら進める仕事のどちらが好きか?
成果主義か、プロセス評価か、どちらに納得できるか?
厳しく指導される環境と、ゆっくり育ててもらう環境、どちらが合っているか?
こうした問いに明確な答えを持っておくことで、企業選びにおける“基準”がブレにくくなる。逆にこの軸がないまま選考を受けると、表面的な印象で判断してしまい、入社後に「思っていたのと違う」というズレが生じやすい。
給与・勤務地・休日日数だけで判断する落とし穴
もちろん、給与や勤務地などの“条件”は大切だ。しかし、それだけで企業を選んでしまうと、「条件は良かったが、精神的にきつすぎて続かない」といったミスマッチが起こる。実際、条件面で最初に惹かれた企業ほど、精神面でのギャップが大きくなりやすい。
たとえば、「完全週休二日制」と聞いて安心していたのに、実際は土曜に勉強会や社内行事が常態化していたり、「在宅勤務OK」とあっても、実質的には出社が必須の雰囲気だったりすることもある。
条件面を信じすぎず、「その制度が実際にどう使われているか」まで調べる姿勢が求められる。
「会社を見る目」を養う具体的な方法
実際に働いている人を観察する視点を持つ
採用イベントでは“質問する”より“観察する”が大事
説明会や座談会の場で「質問を考えてこよう」という姿勢は立派だが、同時に意識したいのが“観察”だ。たとえば、
社員同士の距離感はどうか?
年次の異なる社員が対等に話しているか?
話している内容に具体性があるか?
こうした観察ポイントを押さえるだけで、その会社の“リアルな雰囲気”が見えてくる。用意された説明よりも、社員の立ち振る舞いからにじみ出る空気のほうが、本質を表していることが多い。
インターンでは「自分の感覚」に注目する
短期インターンでも十分に得られるものはある。とくに、「働く人たちとの距離感」「意思決定のスピード」「役割の曖昧さと指示系統」など、業務を通じて感じる“しっくりくる/違和感”に敏感になることが重要だ。
たとえば、「議論が噛み合わない」「先輩社員の言っていることが理解しにくい」といった感覚は、その会社との文化的な相性を示している可能性がある。これを“自分の理解力が足りないせい”と片づけず、「相性が悪い可能性がある」という前提で見ていくことで、入社後の後悔を防げる。
最終判断は「第三者」と話すことで整理する
就活エージェントやキャリアセンターを活用する
最終的な判断をひとりで行うと、どうしても主観に偏ってしまう。そこで、大学のキャリアセンターや就活エージェントといった第三者の目線を取り入れることが効果的だ。彼らは多数の就活生を見てきており、あなたの判断に潜むバイアスや見落としを指摘してくれる可能性がある。
また、自分では気づかなかった「判断の軸」や「選択肢の視野の狭さ」を言語化してもらえることもある。就活の軸が曖昧なまま最終面接に臨むよりも、一度立ち止まって整理する時間を持つほうが、後悔のない選択につながる。
入社後の「現実」と向き合い、乗り越える視点
ギャップは“なくす”のではなく“前提にする”
完璧なマッチングは存在しないと理解する
就活生の多くが「自分にぴったり合う企業を探したい」と思うが、現実にはどんなに慎重に企業を選んでも、100%理想通りの環境は存在しない。これは相手が企業という“人の集合体”である以上、変化や曖昧さがつきまとうためである。
たとえば、「人間関係が良い」と思って入社しても、配属ガチャや上司の異動によって雰囲気が一変することもある。また、「成長できる環境」と聞いて入ったが、実際はOJTがほぼなく、自主性ばかりが求められるケースもある。
このように、ギャップは避けるべき対象ではなく、あらかじめ想定し、それでも納得できる“許容範囲”を持っておくことが重要だ。違和感があること自体は悪いことではなく、そのギャップをどう処理するかが、社会人としての適応力を問われる。
「向いていないかも」と思ったときの考え方
入社して数ヶ月〜1年ほど経つと、「この仕事、向いていないかも…」という不安を抱く人が一定数現れる。だが、その“向いていない”という感覚は、必ずしも適性の問題ではない。
たとえば、業務にまだ慣れていない時期は、ミスや不明点が多く「自分にはできない」という自己評価になりがちである。しかし、それは単に「知識や経験が足りないだけ」の可能性が高い。慣れていないものに対して「向いていない」と判断するのは早計で、少なくとも半年〜1年の経過を見てから自己判断するべきである。
入社後のギャップを“自分ごと”として乗り越える
「期待とのズレ」にどう対処するかが評価される
企業側が新卒に求めているのは、即戦力ではない。むしろ、環境に適応し、自分なりに成果を出そうとする姿勢が最も見られているポイントだ。つまり、理想と現実のギャップに対して「それでも自分ができることは何か?」と考え、行動に移せる人材が評価されやすい。
このとき重要なのは、「上司に相談する」「周囲のやり方を観察する」「社内の資料を読む」など、環境への理解を深める努力を自分から積極的に行うことである。受け身で「教えてくれない」「分かりにくい」と言い続けるだけでは、成長も評価も得られにくい。
周囲と比較せず、自分のペースで馴染む視点
入社後すぐにバリバリ成果を出す同期や先輩と比べ、「自分だけ劣っている」と感じる人は多い。しかし、仕事の習熟度や成長スピードは人によって大きく異なる。早く成果を出す人がいる一方で、時間をかけて信頼を築くタイプもいる。
大事なのは、自分に合った働き方と学び方を見つけていく姿勢だ。他人と同じようにできなくても、「自分はこういうやり方が向いている」と気づければ、それは立派な社会人としての第一歩である。
ギャップを見越したキャリアの設計を
最初の会社が“すべて”ではないという視野
転職が前提となる時代の就活観
現代の日本社会では、転職が当たり前の時代に移行している。新卒で入った会社が一生の職場であるという考えは、すでに古い価値観だ。実際に、20代で転職を経験する人の割合は年々増えており、企業側も“転職を前提とした育成”を視野に入れている。
このため、新卒で入社した会社に強い違和感を覚えた場合、「この会社でしか生きていけない」と思い詰める必要はない。むしろ、自分に合った仕事や環境を探し直すという選択肢を持っておくことは、キャリア設計において健全な判断である。
「転職前提」であることと「今を頑張らない」ことは別
ただし、「どうせ転職するから」と言って最初の職場をおろそかにすると、それもまた後のキャリアにマイナスに作用する。重要なのは、いま目の前の仕事でどれだけ誠実に経験を積むかであり、これは次の転職やステップアップの際の武器になる。
つまり、ギャップを感じても「すぐに辞める」ではなく、「何が合わないのかを見極める」「それでもできることを積み上げる」という姿勢が、その後の選択肢を広げてくれる。
まとめ:就活は「未来のギャップとの対話」である
ギャップを受け入れ、乗り越える力が社会人の第一歩
入社後のギャップは誰にでも訪れる。それは就職活動中に情報を集め尽くしたつもりでも避けられないものだ。ただ、そのギャップをあらかじめ想定し、「どう感じ、どう動くか」をシミュレーションしておけば、ダメージは格段に小さくなる。
つまり、就活とは「将来起こりうるギャップとの対話」である。入社後に感じる違和感を“失敗”と捉えるのではなく、“前提”として折り合いをつけ、前に進む力こそが社会人の本質だ。
企業選びで完璧を求めすぎず、また働き始めてからも「常に自分に問いかけ続ける姿勢」を持つこと。それこそが、就職後のリアルを乗り越える最大の武器であり、就活の本当のゴールはそこにある。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます