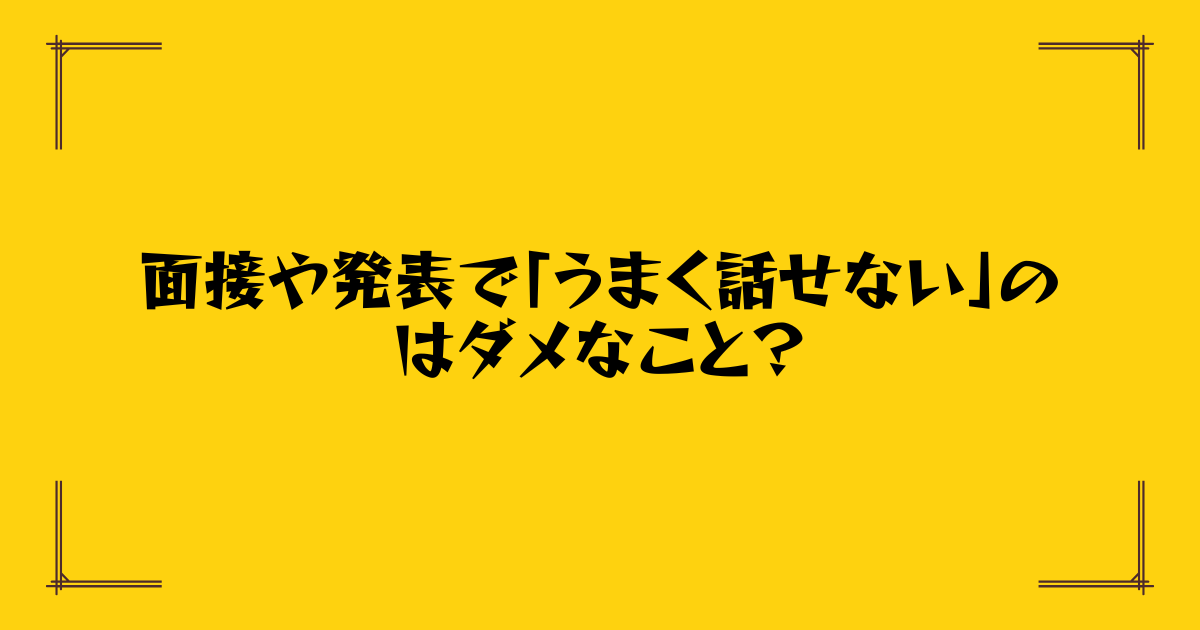「話せる=評価される」と思い込んでいないか
“話せる人=すごい人”ではない
就活における面接やグループディスカッション、さらには説明会後の質疑応答やインターンでの発表など、「人前で話す」機会は避けて通れません。こうした場でうまく話せないと、「自分は劣っている」と感じてしまう人も多いでしょう。
特に「自分の考えをその場で言語化すること」が苦手なタイプは、「話し上手じゃない自分は不利なんじゃないか」と焦ってしまいます。しかし、ここで確認しておきたいのは、“話す能力”と“その人の中身”はイコールではないということです。
滑らかに話せる人が必ずしも優秀なわけではありません。むしろ、論点が曖昧なまま話が上手いだけの人もいます。一方で、話し方に詰まりがあっても、伝えようとする熱意や内容に本質がある人のほうが、採用担当に「この人と一緒に働きたい」と思わせるケースも少なくありません。
面接官が見ているのは「印象」ではなく「中身」
就活における面接は「コミュニケーション能力」を見られる場ではありますが、それは“言葉の上手さ”だけを見ているわけではありません。採用担当が見ているのは、「この人は仕事を通してどう成長していきそうか」「チームに合うか」「素直に吸収する姿勢があるか」など、“話の裏にある人柄や思考の深さ”です。
「緊張してうまく話せなかった」「言い淀んでしまった」そんな場面も、誠実に伝えようとする態度が見えれば、マイナスにはなりません。逆に、うまく話そうとするあまり、借りてきたようなテンプレートの言葉を並べてしまうほうが、印象が薄くなるリスクがあります。
“うまく話す”ことが目的になってしまっていないか
面接の本質は「相手に伝わること」
多くの就活生が陥るのが、「面接ではうまく話さないとダメだ」というプレッシャーにとらわれすぎて、“伝える”ことより“取り繕う”ことを優先してしまうことです。面接はスピーチ大会でもプレゼンコンテストでもありません。「自分がどんな人間で、どんな価値観を持ち、なぜその会社で働きたいと思っているのか」が、面接官に届けば良いのです。
そのためには、完璧な流れや言い回しよりも、「自分の体験をどう捉えているか」「そこで何を考え、どう行動したか」といった自分の言葉での表現のほうがずっと大切です。
話し方に自信がない人でも、自分の経験や気持ちを素直に語れば、意外としっかり届きます。
覚えた台詞は「自分の言葉」じゃない
よくあるのが、「模範的な自己PR」や「就活サイトの例文」を暗記してそのまま話すパターン。たしかに滑らかには聞こえますが、言葉に“自分らしさ”が宿っていないため、聞き手の心には刺さりません。
たとえ言葉がつたなくても、「それを自分で考え、自分の中で消化してきたものかどうか」は伝わってしまうのです。自分の思考や経験を、ぎこちなくても“自分の声”で届けること。それこそが、面接で本当に評価される部分です。
話せない自分を責めすぎないこと
苦手意識が悪循環を生む
「また言葉が出てこなかった」「論理的に話せなかった」――そんな経験があると、次の面接でますます緊張してしまい、また話せなくなる。こうした悪循環に陥る人は多いです。でも、このサイクルを断ち切るには、「話せない自分を責めない」ことが第一歩になります。
「話すのが得意じゃない=内定が遠い」ではありません。企業側も人間であり、多様なタイプの応募者を見ています。緊張していても、言葉に詰まっても、真剣に向き合っていることが伝われば、それが評価される要素になるのです。
苦手だからこそ“準備”が味方になる
話し下手な人にとって最も有効なのは、「とにかく事前に考えておく」ことです。話し上手な人はその場で即興で言えることが多いですが、そうでないなら、想定問答を自分の言葉でメモしておく・録音して聞き返すなど、準備によって補うことができます。
準備することは、“ズル”ではありません。むしろ、自分の想いを正確に伝えるために必要なステップです。自信を持って挑むには、地道な積み重ねが一番の武器になるのです。
話すのが苦手な人が陥りやすい誤解と落とし穴
「うまく話せる人のマネ」をするほど伝わらなくなる
就活は「プレゼン」ではない
面接や発表の場で「うまく話す」ことを意識しすぎてしまうと、多くの人が「話がうまいあの人のように話さなきゃ」と考えます。たとえば、就活サイトに載っている“理想的な自己PR”や“模範解答”を暗記して、同じように話そうとする。でも、そうした「借り物の言葉」は、いざ本番になるとたいてい詰まります。なぜなら、自分の中にある実感や体験と結びついていないからです。
採用担当者もプロです。表面だけ取り繕った話は、すぐに見抜かれます。「この人、本音を話していないな」「誰かの言葉をそのまま借りてるな」と感じさせると、評価は上がりません。むしろ多少言い淀んでも、自分で考え、自分の頭で言葉を選んでいる学生のほうが、「この人と会って話してよかった」と思わせる力を持っています。
自信がない人ほど「他人の正解」に逃げたくなる
うまく話せない人ほど、自分の言葉に自信が持てず、「これは変な言い方じゃないかな」「もっと正しい表現があるんじゃないか」と考えがちです。その不安から、「こう言えばウケがいい」「こう言うのが正解」という型に頼ろうとしてしまうのです。
しかし、そうした型にはまった言い回しは、自分の思考を封じる罠になってしまいます。たとえば「ガクチカはアルバイトでリーダーを務めました」「協調性を活かして課題を解決しました」というような、テンプレ化された自己PRでは、何を伝えたいのかがぼやけてしまうのです。
大切なのは、「それが本当に自分の経験なのか?」「そのエピソードを通して何を感じたのか?」という、自分にしか語れない部分です。話し上手に見える言葉を真似るより、自分にしかできない話を、素直に、丁寧に言葉にすることが、ずっと効果的なのです。
話すのが苦手でも「伝える力」は伸ばせる
話す前に、伝えたいことを“削ぎ落とす”
「話すのが苦手」と感じる人の多くは、「話す前に頭の中が整理できていない」ことが原因です。面接や発表で緊張してしまうのも、自分が何を話すのか・どう話すのかが明確になっていないため、不安が増幅されてしまうのです。
そこで有効なのが、「伝える内容を削ぎ落とす」という視点です。たとえば自己PRなら、「強みを一つに絞る」「話したいエピソードを一つだけに絞る」「伝えたい価値観を明確にする」など、情報を絞り込むことで、話すハードルが下がります。
よく「たくさん話さなきゃ評価されない」と思いがちですが、本当に伝えたいことだけを、短く、明確に話すほうが、相手にとっても印象に残りやすいのです。
話す力は「準備」の量で変わる
話し下手な人にとって、最大の味方は“準備”です。「面接練習なんて恥ずかしい」「何を準備すればいいのか分からない」と思うかもしれませんが、準備こそが自信につながります。
たとえば次のような準備方法があります。
よく聞かれる質問(志望動機・自己PR・学生時代頑張ったこと)について、自分なりの答えを一度書いてみる
スマホのボイスメモなどで自分の話し方を録音して聞いてみる
自分のエピソードを“友達に話すように”話してみる
「こう聞かれたら、こう返そう」と想定問答を整理する
このような「自分のための準備」があると、「あとは伝えるだけだ」と思えるようになり、緊張も軽減します。準備ができていれば、話が多少詰まっても慌てることはありません。
面接官の立場で考えてみると見えてくる
採用担当は「話の内容」だけで判断していない
自分が話す側だと、「この言い方で伝わるかな?」「変なこと言ってないかな?」と不安になりますが、面接官は“話の内容そのもの”よりも“話す姿勢”を見ています。
たとえば、ある程度緊張していても、目を見て一生懸命に伝えようとする学生の姿には、自然と好印象を持つものです。「流暢に話していない=減点」ではなく、「この人は誠実か」「会社で活躍できる伸びしろがあるか」など、多角的に見ているのです。
“話せない自分”にしか伝えられないものがある
うまく話せない自分を責めてしまうかもしれません。でも、就活において「話し上手じゃない人が評価される場面」はたくさんあります。なぜなら、企業はスピーカーではなく、実際に働いて成果を出す人材を探しているからです。
たとえば技術職や専門職、研究開発職などは、緻密さ・集中力・探究心が重視されます。そうしたポジションでは、むしろ「話が得意じゃないけど、真面目に取り組む姿勢がある」ことが評価されるのです。
また、口下手であるがゆえに、「聞く力」や「相手の意図を汲む力」に優れている人もいます。面接で一方的に話すよりも、面接官の言葉をじっくり聞いて、丁寧に返す――そんな受け答えのほうが、企業にとっては「一緒に働きやすそう」と感じられることもあるのです。
話すのが苦手な人が“自分らしさ”を武器にする方法
苦手なことをごまかさず、“戦い方”を変える
自分のスタイルを受け入れることで、迷いが消える
「話すのが得意ではない」と自覚している人ほど、就活で“無理して話せる自分”を演じようとしてしまいます。「みんなスラスラ話しているのに、自分だけ緊張で何も言えない」「伝えたいことが頭から飛んでしまう」と感じるたびに、自信をなくしていく――これは、非常に多くの学生が陥るループです。
しかし、ここで大事なのは、“得意なやり方で戦う”という視点です。誰にでも得意・不得意はあり、「話すこと」が不得意なら、「書く」「考える」「構成する」といった他の強みを使って就活に臨めばいいのです。
無理に話し上手になろうとせず、「自分は丁寧に考え、言葉を整理してから伝えるタイプなんだ」と認識することが、戦略のスタート地点です。
面接を「話す場」ではなく「共有する場」と考える
「話すのが苦手」と思う人にとって、面接は“話を評価される場”に感じられます。しかし、企業側の視点に立てば、面接とは“あなたという人の思考や価値観を知る場”です。つまり、面接は話のうまさを競う場ではなく、「どれだけ相互理解できるか」が本質なのです。
だからこそ、話し上手になる必要はありません。むしろ、自分の考えを誠実に、落ち着いて伝えようとする姿勢のほうが好印象を与えます。「完璧に話さなければいけない」というプレッシャーから一歩引いて、「相手と自分の価値観をすり合わせる対話」として捉え直すことで、心の余裕が生まれます。
話すのが苦手な人に向いている選考対策
書く力を活かして“自分の軸”を整理する
「言葉に詰まる」「緊張して話が飛ぶ」と感じる人は、あらかじめ文章にしておくことで思考が明確になります。エントリーシートの準備段階で、自分のエピソードや考え方を丁寧に書き出しておくことで、面接の場でも「あのとき書いたことを話せばいい」と自信を持ちやすくなります。
この際、模範解答のような美しい文章を書く必要はありません。「なぜこのエピソードを話したいのか」「そのとき何を感じたのか」など、感情や価値観がにじむような、自分なりの言葉でまとめることが重要です。
また、文字に起こすことで「構成の整理」もできます。話す前に、次のような型をつくっておくだけで、話すハードルは大きく下がります。
結論(私は〇〇な人間です)
理由(なぜそう言えるか)
具体例(その価値観が見える経験)
今後どう活かしたいか
この型をもとに、あらかじめ3つほど“話せるストック”を用意しておけば、面接でも安心して話すことができます。
緊張しやすい人は「一問一答形式」を意識する
会話に苦手意識がある人は、「面接=ずっと話し続けなければならない」と思いがちです。しかし、実際の面接は“質疑応答”が基本です。一つの質問に対して一つの答えを返す、一問一答形式であることを意識すれば、「長く話さなきゃいけない」という焦りはかなり軽減されます。
また、短く、わかりやすく話す練習を重ねておくことで、面接中のストレスも減ります。例えば、「自分の強みは何ですか?」と聞かれたときに、30秒〜1分程度で話す“コンパクト回答”を用意しておけば、緊張してもテンポ良くやり取りができます。
長く話そうとして詰まるくらいなら、「簡潔な答え+必要に応じて深掘りしてもらう」ほうが、面接官にとっても好印象になるのです。
実際に「話すのが苦手」で評価された人の特徴
無理に話し上手になろうとせず“誠実さ”で勝負した
実際の就活で内定を獲得した人の中には、「自分は話し下手だ」と自覚していた人も多くいます。彼らが評価された共通点は、“等身大の自分を誠実に伝えていたこと”です。
たとえば、以下のような話し方をする人は、面接官からの印象が良い傾向にあります。
「緊張していますが、自分の言葉で伝えられるように頑張ります」
「話すのは得意ではないのですが、真剣に向き合ってきた経験なので、お話しさせてください」
「うまく伝えられるかわかりませんが、この経験から自分の強みが見えました」
このような言葉には、「自分を偽らず、まっすぐに向き合っている姿勢」が現れています。企業は、無理に自信満々な人よりも、誠実に自己理解している人を評価します。
小さな成功体験を「自信の種」に変えていく
話し下手な人は、就活の中で「失敗体験」が積み重なりやすいです。うまく話せなかった面接、詰まってしまった自己紹介、評価されなかったエントリーシート。こうした失敗を「自分はダメなんだ」と捉えるのではなく、「次に活かせる経験」としてリフレーミングすることが、成長につながります。
たとえば、以下のような変換をしてみましょう。
「話が詰まった」→「言いたいことが曖昧だったから、書き出して整理しよう」
「質問に答えられなかった」→「想定質問の範囲を広げておこう」
「緊張して声が震えた」→「本気だったからこその緊張。その姿勢は伝わっているはず」
このように、自分の経験に意味を持たせることで、“話せない自分”を肯定しながら、少しずつ改善していくことが可能になります。
うまく話せない人が“自分の言葉”で内定を掴むために
話すことが苦手=就活で不利、は思い込みにすぎない
話し下手な学生が“落とされやすい”のではなく、“伝え方に工夫がない”ことが問題
多くの学生が、「話すのが苦手だから面接で落ちた」と結論づけがちですが、実際には話が流暢かどうかだけで選考結果が決まることはほとんどありません。企業が見ているのは「その人が何を考えているか」「どんな価値観を持っているか」「入社後にどう貢献できるか」といった中身の部分です。
つまり、“話し下手”自体が不合格の理由ではなく、“伝え方に工夫が足りない”ことが問題なのです。丁寧に言葉を選び、自分なりの方法で思考を伝える努力があるかどうか。その姿勢こそが、面接での評価を左右します。
話が苦手な人ほど、自分を否定的に捉えがちですが、伝え方の設計・準備を怠らなければ、自分らしさを十分に武器にできます。
流暢さよりも“納得感”を意識する
面接官が「この人、いいな」と感じる瞬間は、話し方がうまいときではなく、「この人の考え方は納得できる」と思えたときです。だからこそ、面接で必要なのは話術ではなく、「なぜそう考えたのか」「なぜその行動をとったのか」といった自分なりの“理由づけ”です。
たとえば、「部活で頑張った」「ゼミで発表した」などの事実だけを話すのではなく、
そのとき何を大切にしていたか
なぜその行動を選んだか
そこから得た気づきや学び
といった背景まで語れるように準備しておくと、「言葉は多くなくても、深さが伝わる」面接になります。
話すのが苦手でも、納得感のある言葉を選べば評価はされる。これは、面接の本質を知っている人だけが実感できる真実です。
自信を失いそうになったときに、立ち返る視点
“自分らしさ”は、他人の真似では身につかない
就活の情報収集をしていると、「こんなガクチカが評価された」「この自己PRが通過率高い」といった事例があふれています。その結果、話すのが苦手な人ほど「自分も同じように話せるようにならなければ」と焦ってしまい、どんどん自己否定が深まってしまうのです。
でも、本来の就活は“自分らしさを伝えること”が軸にあるはずです。他人の真似をしても、自分がしっくり来ない言葉では説得力は生まれません。
話すのが苦手でも、自分で考えた言葉には芯があります。うまく話そうとせず、「自分の視点で物事を見てきたこと」「大事にしてきた価値観」を誠実に伝えること。それが、結果として面接官の印象に残る“自分だけのストーリー”になります。
面接は“試される場”ではなく“合うかどうかを確かめる場”
面接を“評価される場所”と捉えると、話すことにプレッシャーを感じて当然です。しかし、実際には企業側も「この人とうちの会社は合っているか?」という視点で面接をしています。
つまり、面接は“選ばれる”場であると同時に“自分が選ぶ”場でもあります。だからこそ、無理に自分を大きく見せたり、話し方を偽ったりする必要はありません。むしろ、自分に正直な言葉を使って、相手とフィットするかを見極める姿勢が大切です。
「話すのが苦手だから不利」ではなく、「話すのが苦手だからこそ、丁寧に向き合える」という強みがある。その価値に気づけた人から、面接の見え方は変わっていきます。
面接で自分らしさを伝えるためにできる準備
すべてを話そうとせず、伝えるべき軸を決めておく
話が苦手な人が最もやってしまいがちなミスは、「あれもこれも伝えようとして、結果的に話が散らかること」です。話すのが得意でないならなおさら、“一つのテーマに絞る”ことが重要です。
たとえば、自己PRであれば、
「困難を乗り越えた経験」
「地道に継続してきた習慣」
「自分なりに改善を重ねた姿勢」
など、自分の性格や価値観が最も表れるテーマをひとつ選び、そのエピソードに集中して準備しましょう。
逆に、あれもこれも話そうとすると、“全部が薄く”なってしまい、結果的に何も伝わらなくなります。だからこそ、「これだけは伝えたい」という軸を明確にし、それに必要な背景情報や学びを整理することが、話し下手の人にとっての最大の武器になります。
自分の話し方に“肯定的な評価”を与えてくれる環境をつくる
面接が不安な人は、事前練習や模擬面接を誰かに見てもらうことが多いですが、練習相手によっては“間違った自信の削られ方”をすることもあります。話すのが得意な人から、「もっと堂々と話したほうがいいよ」とアドバイスをもらっても、余計にプレッシャーになるだけということもあります。
そうではなく、自分の話し方を肯定してくれる人、受け止めてくれる人に見てもらうことが、話し下手な人の就活ではとても重要です。少しでも「自分の言葉が伝わった」と感じられた経験は、それだけで大きな自信になります。
話し方を磨くよりも、“話せる場”を増やすことが、話すことへの恐怖を減らす最大の近道です。
まとめ
話すのが苦手な人でも、就活で内定を取ることは十分に可能
面接は「話のうまさ」ではなく「思考の深さと伝え方」が評価される
話す前に“自分の言葉”を整理し、書いて構成を整えることが有効
自分の苦手を否定せず、得意な形で表現する姿勢が伝わる
面接は“選ばれる”場であると同時に“選ぶ”場でもある
すべてを話そうとせず、“伝えるべきこと”に絞って準備をする
自分を受け止めてくれる人との練習が、前向きな自信を育てる
「話すのが苦手」と感じているからといって、自分を責めたり、無理に変えようとする必要はありません。むしろ、自分の思考を丁寧に伝える努力ができるあなたにこそ、“自分の言葉で勝負する就活”が向いています。流暢さやテンプレートに頼らず、自分の価値観をそのまま届ける姿勢は、企業の心にもきっと響きます。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます