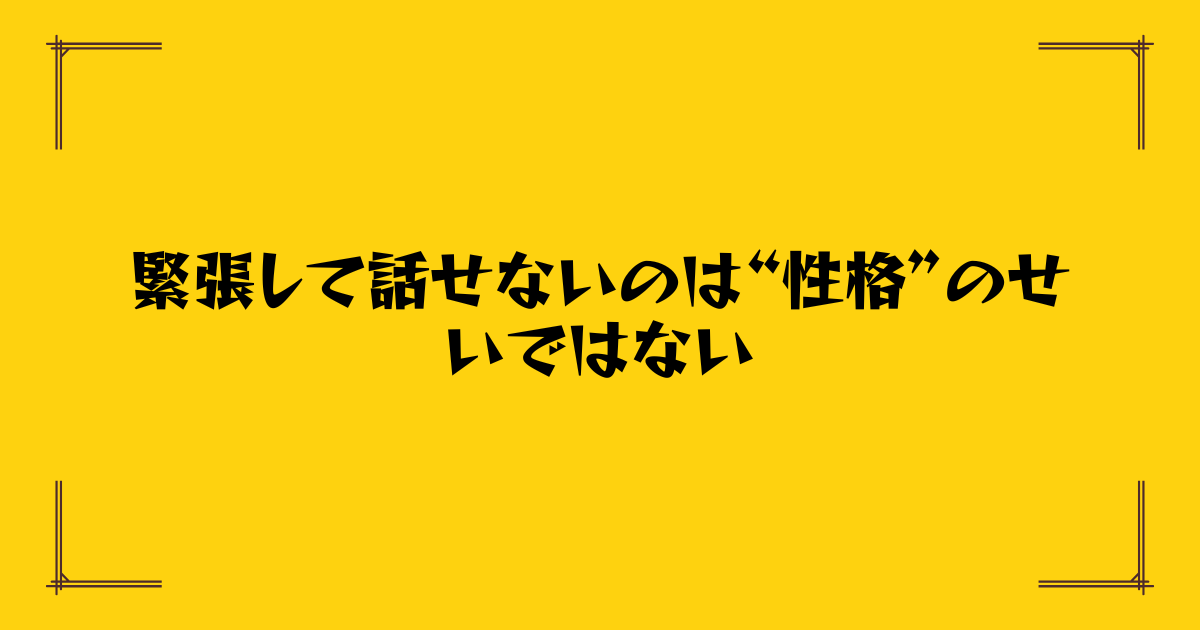「自分は話すのが苦手だから」と思っていないか
就活の面接でうまく話せないと感じるとき、多くの人は「自分は話し下手だ」「もともと人前で話すのが苦手だから仕方がない」と思いがちだ。しかし、そうした“話し下手な性格”が原因だと決めつけること自体が、実は面接を難しくしている。なぜなら、就活の面接で必要とされる「話す力」は、普段の雑談やプレゼンのような“話の上手さ”とは異なるものだからだ。
面接で求められるのは、饒舌さや説得力ではなく、「その人らしさ」が伝わる話し方である。ところが多くの学生は、面接=上手く話さなければいけないもの、と誤解して構えてしまう。その結果、必要以上に緊張し、自分の言葉が出てこなくなるという悪循環に陥る。緊張で言葉が出ないというのは、たいていの場合、内容や能力の問題ではなく、“話すことへの構え方”に問題がある。つまり、緊張して言葉が詰まるのは、性格のせいではなく「構えすぎるクセ」のせいであることが多い。
緊張の根本原因は“話す内容”ではなく“話す構え方”
面接で緊張してしまうとき、人は「何を話すか」にばかり意識を向けがちだ。しかし、実際に面接中に言葉が詰まったり、頭が真っ白になったりするのは、「どう思われるか」を気にするあまり、話すことに対して身体が構えすぎてしまっているからである。つまり、緊張の本質は「内容」ではなく「構え方」にある。
人は身構えるとき、心と体の両方に緊張が走る。例えば、面接の前日に答えを完璧に準備しても、本番で相手の表情や反応に引っ張られると、頭がフリーズしてしまう。このとき、「間違えてはいけない」「うまく話さなきゃいけない」というプレッシャーが、自分の言葉を封じてしまう。
一方で、「伝わらなくてもいいから、今の自分の考えを出してみよう」と考えている人は、肩の力が抜けた状態で話している。話が多少まとまっていなくても、気持ちが込められた言葉は面接官に届きやすい。つまり、面接で話す力は「知識量」や「話術」よりも、「構えの緩め方」で大きく変わるのだ。
緊張しやすい人がやりがちなNG準備とその改善策
緊張しやすい人ほど、面接前に「セリフ」を用意しすぎてしまう傾向がある。志望動機、自己PR、学生時代に頑張ったこと──これらを“正解”のように完璧に仕上げようとする。その結果、頭の中に原稿を作り、それを丸暗記しようとする。だが、実際の面接では想定どおりに質問が来ることは少なく、少しでも流れが違うと、セリフのどこから話せばいいか分からなくなる。
こうした“台本型準備”は、緊張を助長するだけでなく、自分の考えをその場で言葉にする力を弱めてしまう。話す内容を決め打ちするのではなく、「何を聞かれても、自分の体験や考えに戻って答える」というスタンスに切り替えたほうが、面接中に柔軟に対応できる。
改善策として有効なのは、「話すネタ」を用意するのではなく、「話す軸」を整理することである。たとえば、「自分は何にこだわる人間か」「何が許せないか」「何を面白いと感じるか」など、価値観の深堀りをしておくと、さまざまな質問にも自分の言葉で対応できるようになる。つまり、面接前の準備は“言葉を決める”のではなく“自分の判断軸を整理する”ことに重点を置くべきなのだ。
自分の言葉で話せないとき、人は“誰かの目”を意識している
言葉が詰まりやすい人の多くは、「相手がどう思うか」を過剰に意識してしまっている。自分の話を面接官がどう評価するか、どんな反応をするかを想像しすぎるあまり、自分の話したいことに集中できなくなる。結果として、話の途中で不安になり、言葉が止まる。
だが、面接官の役割は評価者であると同時に、“その人を知ろうとする聞き手”でもある。つまり、就活生が心から語ろうとすれば、面接官はその思いや背景を引き出そうとしてくれる。相手の反応を恐れるより、「私はこういうことを考えて生きてきました」と自分から開示することで、面接は対話の場になる。
意識を向けるべきは、「どう思われるか」ではなく、「自分はどう考えているか」「どんな人間として見てもらいたいか」である。このように、焦点を外側から内側に戻すことで、言葉は自然と出てくるようになる。
“緊張しないようにする”のではなく“緊張しても動ける自分”を目指す
面接で緊張すること自体は、決して悪いことではない。むしろ、緊張するということは、「この面接に本気で向き合っている証拠」であり、誠実な態度とも言える。大切なのは、緊張をゼロにすることではなく、緊張したままでも“最低限の自分”が出せる状態をつくっておくことだ。
たとえば、話すときに「ゆっくり話す」「最初の一文だけは決めておく」「あいづちや頷きを意識して、相手と対話するように話す」といった小さな工夫で、緊張状態でも言葉は出やすくなる。「話すことが怖い」から「話しても大丈夫」に変えるには、自分にとっての“緊張耐性ライン”を知っておくことも重要である。
また、自分が緊張していることをそのまま伝えるのも有効だ。「緊張していますが、自分の言葉でお話ししたいと思います」と一言添えるだけで、面接官も構えていた空気を緩めてくれる。無理に平常心を装うよりも、ありのままの自分として話す方が、結果として“伝わる面接”になっていく。
話せるようになる人に共通する“考え方のクセ”
「うまく話そう」が言葉を詰まらせてしまう
面接で言葉に詰まる原因の多くは、「うまく話そう」という意識の強さにある。人は本来、自然体で話すときには特に詰まらない。たとえば、友人と好きな映画について話すとき、途中で言葉が止まって困ることは少ない。それは、「正確さ」や「完璧さ」を求めず、ありのままの自分の感想を口にしているからだ。
ところが、面接になると「説得力のある自己PRをしなければならない」「ロジカルに話さなければ評価されない」という思い込みが強くなり、“うまくやろうとする姿勢”が自分を縛り始める。すると、話す内容そのものより、「どう聞こえるか」「面接官の反応はどうか」が気になってしまい、言葉が内側から湧き出てこなくなる。
言葉に詰まることを恐れるほど、さらに詰まりやすくなるという悪循環を止めるには、「うまく話そう」ではなく「自分のことをそのまま伝えよう」という考え方に切り替える必要がある。うまさを追求するのではなく、“自分の言葉で話す”ことに集中したとき、自然な表現が出やすくなる。
面接官は“情報”より“感情の流れ”を見ている
面接では、内容そのものよりも、その人の話し方や感情の流れに注目されることが多い。なぜなら、書類では伝わらない「人間性」や「熱量」を見る場が面接だからだ。つまり、面接官が見ているのは“言葉の中身”ではなく“言葉の背後にある人”である。
たとえば、「学生時代にアルバイトで接客を頑張りました」と話す学生が2人いたとしても、一方は事務的に成果だけを話し、もう一方は自分の気持ちや葛藤を交えて話した場合、面接官の印象は大きく異なる。後者の方が、その人の“思考や価値観”がにじみ出てくるため、記憶にも残りやすい。
伝える内容の正確さよりも、「なぜそれを選んだのか」「何が嬉しかったのか」「何に悩んだのか」といった感情の流れを含めて話すことが重要だ。緊張してうまく話せないと感じるときこそ、「事実を説明すること」に集中するのではなく、「自分の心がどう動いたか」を語るよう意識することで、面接官の印象は大きく変わる。
話し上手より“伝わる人”を目指す
就活の場では、話が上手な人が必ずしも評価されるとは限らない。むしろ、話し方に無駄なテクニックが多く、自分の本心が見えない人は警戒されやすい。一方で、少し言葉に詰まりながらでも誠実に伝えようとする人には、面接官が自然と耳を傾けることが多い。
つまり、目指すべきは「話し上手」ではなく「伝わる人」である。伝わる話し方とは、話す順序やテンポが整っているかよりも、「この人の言葉は信用できるか」「共感できるか」によって決まる。過剰に演出された自己PRよりも、等身大の経験やそこに含まれる“本当の気持ち”のほうがずっと印象に残る。
話すのが得意でなくても、誠実さや率直さをベースに話をすれば、それは必ず伝わる。相手にどう伝わるかを気にしすぎるよりも、自分の言葉が“自分の内側から出てきたものか”を大切にしていくと、自然と“伝わる話し方”へと変わっていく。
質問に答えるのではなく「対話をつなぐ意識」を持つ
緊張しやすい人の多くは、面接を“質疑応答の場”と捉えている。つまり、質問に対して正しく答えることが正解だと信じている。だが、面接が本来目指しているのは“対話”である。質問に答えることが目的ではなく、相互理解を深めていくプロセスそのものが面接の価値なのだ。
質問に答えるだけでは、会話のキャッチボールは続かない。むしろ、そこに「そう思った理由」や「そのとき感じた迷い」「今後どう活かしたいか」といった自分の視点を加えて話すことで、面接官とのやりとりは豊かになる。そうした“返す力”があると、たとえ緊張していても“話が止まらない人”になる。
また、対話を意識していると、想定外の質問にも柔軟に対応しやすくなる。たとえば、「失敗した経験は?」と聞かれても、“失敗というより学びがあった経験”として返すことができる。回答の正解を探すのではなく、“会話をつなぐ役割”として面接に臨むことが、緊張を軽くしてくれる最大のコツになる。
自分の“物差し”を持つことが話す力につながる
話す力とは、言葉のスキルではなく“思考の軸”から生まれる。つまり、自分が何を大切にしているか、どういう価値観で物事を判断しているかという“物差し”を持っている人は、どんな質問にもブレずに答えることができる。
たとえば、「あなたの強みは何ですか?」と聞かれたとき、「人と話すのが得意です」と答える人と、「相手の話の“間”を大事にできる自分が強みだと思っています」と答える人では、話の深さが違ってくる。後者は、自分の価値観に基づいた表現ができているため、言葉に“納得感”がある。
このように、自分の中に“判断の軸”を持っている人は、どんな質問にも自分らしく答えることができる。話す内容が浅くならないため、面接官にも信頼感を与えやすい。表面的なエピソードの引き出しを増やすのではなく、自分なりの視点を言語化する練習を重ねていくことが、本質的な話す力を育ててくれる。
緊張しても言葉が出る“面接前の習慣”
台本暗記ではなく“使えるフレーズ貯金”をする
面接が不安な人ほど、「想定質問に完璧に答えられるように」と、回答を丸暗記する傾向がある。しかし、その方法ではちょっとした質問のズレにも対応できず、思考が止まってしまう危険がある。むしろ効果的なのは、“文章全体”を覚えるのではなく、“話すときに使える自分の言い回し”をストックしておくことだ。
たとえば、「~を経験して、そこで初めて〇〇に気づいた」「自分の中ではそれがターニングポイントでした」といった、話の流れを支えるフレーズを持っていると、自由に組み立てながら話すことができる。これは文章の“素材”を用意するようなものであり、その場で臨機応変に使える土台となる。
ポイントは、実際に自分が“口に出して言いやすい表現”に絞ること。読みやすい文章と話しやすい言葉はまったく異なるため、書いたESの文章をそのまま話そうとするのは、実は危険な準備である。口に馴染んだ自分らしい言葉をいくつも用意しておくことで、緊張していても自然と口が動きやすくなる。
「ひとりごとトレーニング」で反射神経を鍛える
緊張して話せない人の多くは、「質問→考える→話す」という手順を頭の中で厳密にやろうとしすぎる。そのため、本番では思考が追いつかず、言葉が止まってしまう。これを改善するには、“考えながら話す癖”を日常の中で作っていくことが大切だ。
最も効果的な方法が「ひとりごとトレーニング」である。たとえば、「今日はなぜコンビニではなくカフェに行ったのか」「このニュースを読んで自分はなぜ違和感を覚えたのか」など、些細な出来事について即興で理由を言葉にしてみる。これを繰り返すことで、頭で考えたことをすぐに言語化する回路が強化されていく。
このトレーニングの目的は、“論理的に話す”ことではない。“思考→言語”のスピードを鍛えることで、緊張時でも反射的に言葉が出る状態をつくることである。面接では数秒の沈黙が長く感じられるが、普段からひとりで話す癖がある人は、間を恐れずに言葉を紡ぎ出せるようになる。
本番で言葉が出る人の「準備の質」はここが違う
面接で自分の力を発揮できる人と、緊張して力を出せない人の違いは、「準備の量」よりも「準備の質」にある。表面的な対策を繰り返すだけでは、少しでも想定外の質問が来ると反応できない。準備の質が高い人は、“どんな質問でも自分らしい答えにたどり着ける”ような状態を目指している。
具体的には、「自分がどんな価値観で判断しているのか」「どの体験が自分を変えたのか」「今後の働く軸は何か」など、あらゆる問いに共通する“内面の柱”を磨いておくことが挙げられる。これが明確であれば、どんな聞かれ方をしても、自分の言葉で話を展開できる。
さらに、本番に強い人ほど「質問をずらして答える力」も持っている。たとえば、「尊敬する人は誰ですか?」と聞かれても、答えにくければ「特定の人ではありませんが、◯◯のような姿勢に影響を受けてきました」といった形で、“答えやすい自分の土俵”に話を移していける。このような柔軟さを持つには、丸暗記型ではなく“考える余白を残した準備”が必要になる。
緊張時でも話し出せる「最初の一文」を用意しておく
緊張して話せないときに最もつまずきやすいのが、“話し始めの一言”である。実際、多くの就活生が「どこから話し始めればいいか分からず、頭が真っ白になった」と語っている。これを防ぐ最も有効な方法が、「最初の一文だけは事前に用意しておく」ことだ。
たとえば、自己紹介であれば「〇〇大学の△△と申します。本日は貴重なお時間をありがとうございます」、志望動機であれば「私が御社を志望した理由は、◯◯の考え方に深く共感したためです」といったように、最初のフレーズだけを決めておく。これにより、緊張していても“話し始め”のフリーズを防ぎ、自然な流れを作ることができる。
最初の一文は、話し全体のリズムを整える“助走”の役割を果たす。走り出しさえすれば、その後は徐々に落ち着いて話せるようになる。つまり、本番の不安を軽減するには、「最初に何を言うか」に対する準備が最も重要なのだ。
面接直前の「思考のスイッチ」を決めておく
どれだけ準備をしても、本番前に緊張するのは自然なことだ。重要なのは、“本番直前に気持ちを整える手段”を自分なりに確立しておくことである。多くの学生は、直前になると余計なことを考えすぎて、準備した内容すら飛んでしまう。そうならないために必要なのが、「思考のスイッチ」をあらかじめ設定しておくことである。
たとえば、「今からは“伝えること”だけに集中しよう」「自分の言葉が出せれば十分」「面接官と会話をしにいくだけ」といった、頭の中を“ひとつの目的”に絞るためのフレーズを持っておく。これは“儀式化された思考”とも言え、迷いや不安を振り払う効果がある。
このスイッチは、言葉にするだけでなく、深呼吸を3回する、両手を軽く握るといった身体の動作をセットにするとより効果的である。ルーティンのように毎回使うことで、本番に入る心と体の準備が整い、緊張していても言葉が出やすい状態を自分で作ることができる。
面接で本領を出すための“言語化スキル”の磨き方
話す内容は「順番」で決まる
話すのが苦手な人ほど、頭の中では伝えたいことがあっても、口に出す段階で整理できず、内容があいまいになる傾向がある。これは話の順番を意識せずに言葉を並べていることが原因だ。逆に、話す順番を工夫するだけで、内容は格段に伝わりやすくなる。
面接で効果的なのは、「結論→理由→具体例→再結論」という順番で話すことだ。たとえば、「私は挑戦を恐れないタイプです」と結論を先に述べたあと、「なぜなら、大学時代に未経験から長期インターンに挑戦した経験があるからです」と理由を添え、具体的なエピソードを加える。この構成なら、聞き手は話の全体像を掴みながら内容を受け取ることができる。
面接では限られた時間の中で印象を残す必要がある。だからこそ、話の構成は重要な武器となる。ただ順番を守るだけで、自分の話がグッと明快になり、自信を持って語れるようになる。順番を味方につけることが、話し下手をカバーする最初の一歩になる。
「言い切る力」と「説明する力」の両立がカギ
面接で自分の考えを話すとき、「なんとなく」「一応」「たぶん」など、曖昧な言い回しをしてしまう人は少なくない。これは自信がないというより、言い切る勇気を持てていない状態だ。だが、聞き手に印象を残すには、あいまいさではなく、言い切る力が必要になる。
たとえば、「人と関わるのが得意だと思います」よりも、「私は、人と関わる場面で最も力を発揮できます」と言い切った方が、説得力と明瞭さがある。もちろん、強い言葉を使えばいいという話ではない。大切なのは、“自分の信じていることを、自分の責任で語る”という態度である。
同時に必要なのが、“なぜそう思うのか”を丁寧に説明できる力だ。言い切るだけでは独りよがりな印象になるが、その背景に自分なりの視点や経験があれば、納得感のあるメッセージになる。この「断定」と「背景説明」のバランスを取ることが、伝わる話し方の基礎になる。
自分の言葉で話すために必要なのは“整理力”
「自分の言葉で話したいのに、どうしても誰かの文章のようになってしまう」という声はよく聞く。これは、自分の中で考えがまとまっていない状態で、無理に“それらしい文章”を話そうとすることが原因である。大切なのは、“内容を美しく仕上げること”ではなく、“頭の中を整理すること”である。
整理力とは、何を伝えるべきかを瞬時に選び取る力だ。エピソードが複数あるなら、どれが今の質問に最も適しているかを選び、無駄を省いて語る。過去の経験を並べるのではなく、「この質問に対して、自分のどの視点で答えるか」という思考を挟むことで、言葉は自然に洗練されていく。
この整理力を鍛えるには、日頃から「なぜそう思うのか」「本当に伝えたいことは何か」を内省することが欠かせない。面接の場で急に整理できるようになるわけではない。毎日の生活の中で、「これはなぜ嬉しかったのか」「何が引っかかっているのか」を言葉にする習慣を持つことで、自分なりの整理軸が育っていく。
日常の経験を「話せる形」に変換する力を持つ
面接で話すネタが思いつかないと悩む人は多いが、それは経験が足りないのではなく、“経験を話せる形に変換する癖”がないだけだ。実は、特別な成果や役職がなくても、日常の経験は十分に面接で使える素材になる。ただし、それを“面接で語れる形”に整える必要がある。
たとえば、コンビニでのアルバイト経験も、「作業の効率化に気を配った結果、お客様から『スムーズに買い物ができて助かった』と声をかけてもらえた」という視点を持てば、それは立派なエピソードになる。単なる出来事を、“そこで自分が考えたこと・工夫したこと・気づいたこと”に変換すれば、どんな経験も言語化できる。
この変換力は、慣れによって養われる。面接練習のたびに新しい体験を“話す練習素材”として捉え直し、「どう話せば相手に価値が伝わるか」を考える癖をつけていくことが、自然な言語化につながっていく。経験の有無ではなく、経験の“切り取り方”がすべてである。
書くことと話すことをセットにして習慣化する
言語化スキルを磨くには、「書くこと」と「話すこと」の両方をセットで取り組むのが効果的だ。なぜなら、書くことで考えが明確になり、話すことで伝える力が鍛えられるからだ。この2つはそれぞれ異なる脳の使い方をするが、どちらか一方だけでは言葉に深みが出ない。
たとえば、自分の価値観を日記に書き出したあと、それを要約して声に出してみる。あるいは、模擬面接のあとに「どこがうまく話せなかったのか」を振り返って書き留める。このように、書いて整理→話して実践→振り返って再整理、というサイクルを繰り返すことで、自分の言葉が強くなっていく。
また、書くことで得た気づきを他人と共有するのも効果的だ。人に話すことで、自分がどこまで理解していたかが可視化され、理解不足や表現の甘さにも気づける。言語化とは一人で完結するものではなく、“他者に伝える”という前提があってこそ洗練されるものだ。
まとめ
面接で話せないことに悩む人は多いが、その原因の多くは“能力の不足”ではなく“準備の方向性”にある。自分の考えや経験を、完璧に話す必要はない。大切なのは、自分の中にある思いや価値観を“自分の言葉”で整理し、伝える準備ができているかどうかである。
緊張をゼロにするのではなく、緊張しながらも“最低限の言葉”が出る状態をつくる。うまく話そうとするより、“伝えたいことを相手と共有する”という対話の姿勢を持つ。そのためには、普段からの言語化習慣と、経験を振り返る力が欠かせない。
面接とは、自分という人間を“言葉”という手段で届ける場である。その言葉が多少つたなくても、真っ直ぐな思いがあれば、聞き手にはきちんと届く。話せない自分を責めるのではなく、“どうすれば自分らしい言葉が出るか”を追求していく。そのプロセスが、話す力を育てる本質である。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます