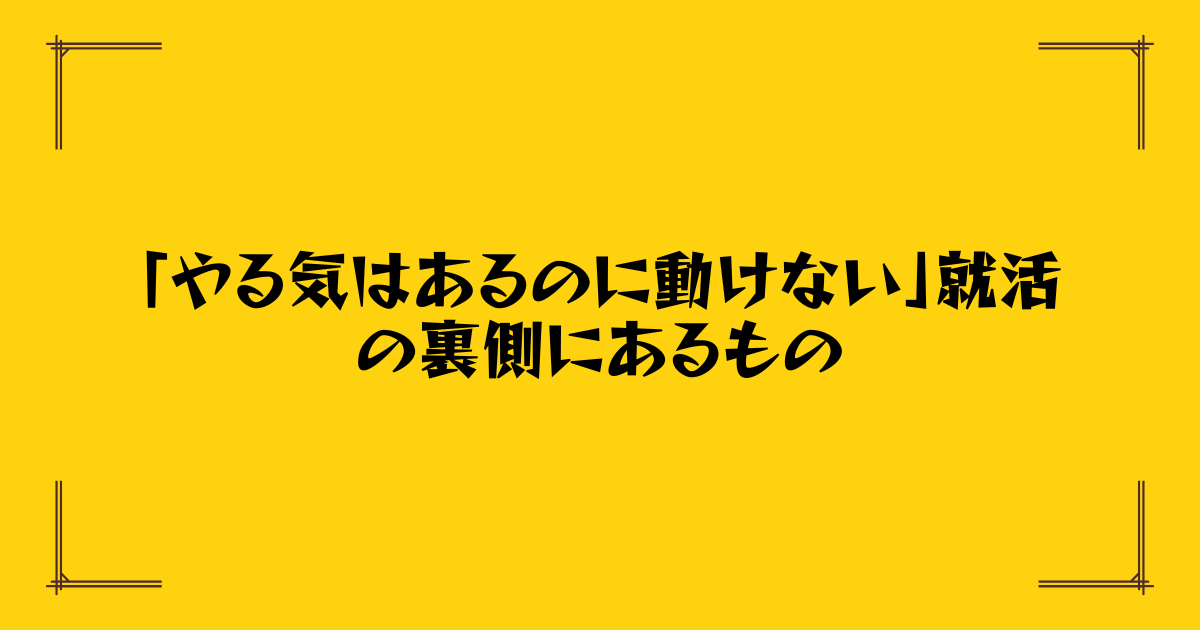ただの“怠け”ではない。動けないのには理由がある
「やらなきゃ」と思ってるのに動けない人は多い
「そろそろES書かなきゃ」「説明会も探さなきゃ」と思いながらも、何も手がつかないまま一日が終わる。
YouTubeやSNSを開いて現実逃避している自分に、うんざりしているのに、やっぱり何も進まない。そんな状態を経験したことがある人は、決して少なくない。
この“動けない自分”に対して、多くの人が「自分はやる気がない」「意志が弱いだけ」と決めつけてしまう。だが、実際にはこれは意志や根性の問題ではない。
むしろ真面目な人ほど、頭の中では「やらなきゃ」と思っていて、その葛藤が強くなるほど、動けなくなる。
行動できないのは、頭が整理されていないから
やる気があるのに動けないという状態は、脳内が“未整理のタスク”でごちゃごちゃになっていることが原因の場合が多い。
たとえばこんな状態だ。
「何から始めたらいいのかわからない」
「ESってどこに出せばいい?」
「インターンって今から間に合う?」
「そもそも何系の仕事を見ればいいのか…」
このように、複数の疑問や不安が同時に脳内に漂っていると、人は最初の一歩を踏み出せなくなる。
つまり、やる気がないのではなく、「動けるだけの情報整理がされていない」「次に何をすればいいかが決まっていない」だけなのだ。
動けない人に共通する“就活思考のブレーキ”
「ちゃんとやらなきゃ」が自分を縛っている
完璧主義が行動を止める
「どうせやるならちゃんとやらなきゃ」「中途半端にやるのは意味ない」
このような完璧主義の思考は、一見すると“責任感がある”ように見えるが、就活においては最大の足かせになることもある。
たとえばESを書くときも、「この1枚で人生が決まる」「完璧に仕上げないと落ちる」と思ってしまうと、なかなか書き始められない。企業研究も、「この会社のこと全部知らないと受けられない」と思えば、応募自体が億劫になる。
完璧にやろうとするほど、最初の一歩が重くなる。
その結果、「今日はまだ準備不足だからやめておこう」と、どんどん先送りが積み重なっていく。
動けない自分を責めて、さらに動けなくなる悪循環
さらに、動けなかった日が続くと、「周りは動いているのに自分は…」と落ち込み、自己否定が始まる。
この自己否定は、ただでさえ曖昧な就活への不安をさらに増幅させ、結果としてさらに行動しづらくなる負のスパイラルを生む。
やる気はある
でも動けない
動けない自分に罪悪感
自己肯定感が下がる
もっと動けなくなる
こうしたループに陥ると、就活に限らず、日常全体が“動かない自分”に支配されてしまうことさえある。
就活の“情報過多”が判断停止を引き起こす
情報は多いのに、なぜか前に進めない
「わかってるけど、できない」状態の正体
就活の情報は、今の時代いくらでも手に入る。SNS、YouTube、就活サイト、先輩の体験談など、検索すれば無数にある。
にもかかわらず、「何となくわかってるはずなのに、結局何も手をつけられない」という状態になるのはなぜか。
その理由は、情報を受け取るだけで“判断”が止まっているからだ。
たとえば「ガクチカを書こう」と思って動画を見たが、情報が多すぎて、「結局どうすればいいの?」という状態になる。
企業研究を始めても、サイトや口コミが膨大すぎて、「比較ができない」「決められない」とフリーズしてしまう。
つまり、情報を集めた“あと”にすべき「絞り込み」「決断」「行動」が抜けていると、人は判断停止に陥る。
情報の“受けすぎ”が自分の思考を奪っていく
特にSNSやYouTubeは、他人の就活体験談やアドバイスが無数に流れてくる。最初は参考になるが、次第に「この人すごいな」「自分は全然できてない」と、比較によって心が削られていく。
情報は多いのに、“自分が動けていない”という実感だけが蓄積され、行動意欲がどんどん低下する。
これは、就活だけでなく、今後の人生でも影響を及ぼす“情報麻痺”の典型的な状態だ。
「動けない人」の中にある、もうひとつの本音
本当は“何をしていいか”がわからないだけかもしれない
“選ばれる”ことを前提にすると苦しくなる
就活では、「企業に評価される自分にならなきゃ」「どこかに選ばれないと意味がない」といった意識が強くなる。
この“選ばれる前提の思考”は、自分の思考を他者基準に置いてしまうため、行動が止まりやすい。
自分の強みってなんだっけ…
この経験って通用するのかな…
志望動機ってどう書けばウケる?
これらの悩みの根底には、「選ばれなきゃいけない」という不安がある。
評価軸が自分ではなく企業側にある状態は、主導権を失った状態とも言える。
自分で決めていない就活は、動き出せない
そもそも、就活で「何をしたらいいかわからない」と悩んでいる人の多くは、実は「どこを目指したいか」が自分の中で決まっていない。
そして、何も決まっていないのに「行動だけ先にしなきゃ」と焦っても、動けないのは当然だ。
「とりあえずESを出す」が目的になる
「なんとなく合同説明会に行く」が行動の中心になる
「とにかく早く内定を」の焦りだけが先走る
これでは、行動しているようで実は“本質的な前進”にはなっていない。
動けない就活から抜け出す“再起動”の第一歩
状況を変えようとする前に、“視点”を変える
「動けない=怠け」ではないと思い出すことから始める
前回触れたように、「動けない就活生」が直面しているのは“やる気”や“努力不足”ではなく、情報過多・完璧主義・自己否定・方向性の不明確さといった心理的ハードルである。
まずこの前提をしっかり認識することが、再起動の第一歩だ。
いま動けていないのは、意志の弱さではない
混乱しているのは、考えが整理できていないから
情報が多すぎて判断停止しているだけかもしれない
このように捉え直すことで、自分を責める思考から抜け出し、冷静に現状を分析できるようになる。
再起動に必要なのは、“行動”の前に“自分への解釈”を変えることだ。
自分に足りないのは「エンジン」ではなく「地図」
動き出せないとき、人は「やる気(=エンジン)が足りない」と考えがちだが、実はそうではない。本当に足りないのは「地図」=方向性と判断軸である。
就活という広大なフィールドにおいて、どこに向かえばいいかわからなければ、ガソリンが満タンでも動きようがない。
やる気があるのに何もできないのは、まさに“目的地のないドライブ”をしようとしているからだ。
考えすぎる就活生のための「最小単位行動」戦略
完璧を捨て、「超小さな行動」に分解する
まず「就活の行動を1つだけ」に絞ってみる
やることが多すぎて動けないときは、“何でもいいから1つだけやる”という行動設計が非常に効果的だ。たとえば、
就活サイトを1つだけ開く
気になる企業を1社だけ見る
自己PRの1文だけ考えてみる
「全部やる」から「これだけやる」に切り替えることで、頭の中の情報が整理されはじめ、徐々に次の行動が見えてくる。
また、「一つ終えたら終わり」と決めておくと心理的ハードルが下がる。結果的に、思った以上に作業が進むこともある。
やる気は「行動のあと」に出てくる
やる気が湧かないから何もしない──これは人間の自然な反応だ。しかし実際は、やる気とは“行動したあと”に生まれる感情であることが心理学でも明らかになっている。
1つ行動したことで「自分も少し動けた」と思える
その安心感が次の行動を呼ぶ
やがて「少しずつやればいいんだ」と思えるようになる
つまり、最初からやる気を期待するのではなく、「動いてから気持ちがついてくる」ことを前提に設計することが大事だ。
“頑張りすぎない計画”を立てることで続けやすくなる
「1週間でやること」を具体的にリスト化する
抽象的な目標は「できない自分」を生む
「就活を頑張る」「企業研究をする」といった抽象的な目標では、実際に手を動かすときに何をしたらいいかが曖昧すぎる。
この状態だと、「目標は立てたのに結局できなかった」という罪悪感だけが残る。
そこで重要なのは、具体的な“行動ベースの目標”に変えることだ。
×「自己分析を進める」
○「過去に嬉しかった経験を3つ書き出す」
×「企業研究をがんばる」
○「気になる企業の公式HPを1社読む」
このように“やるべきことを明文化”し、かつ“できそうなサイズ感”に落とすことで、「できた実感」を積み重ねられる。
継続のコツは「ノルマを減らすこと」
真面目な人ほど、「1日1社エントリー」「毎日2時間就活」などとノルマを高く設定してしまいがちだが、それは継続を難しくする原因になる。
むしろ、「週に1社でいい」「1日15分だけやる」くらいの“ぬるいルール”が意外と長続きする。
就活は短距離走ではなく、持久戦。だからこそ、自分を追い込むよりも、“自分が走りきれるペース”で動き続ける工夫が重要だ。
迷ったら「人と話す」ことで再起動できる
情報を“頭の中だけ”で処理しない
1人で悩むと視野が狭くなる
動けなくなる就活生の多くが、自分の頭の中だけで情報処理と判断を完結させようとする。
この状態が続くと、だんだんと思考が堂々巡りになり、「自分だけが遅れている」「もう取り返せない」といった極端な結論に飛びつきやすくなる。
実は、自分の状況を整理するのに最も有効なのは、“誰かに話すこと”である。
「実はまだ何もやってないんだよね」と言うことで客観視できる
話す中で、自分が何に悩んでいるのか明確になる
他人の視点から“ずれていないこと”に安心できる
とくに就活の初期段階では、「動けない=悪」ではないというフィードバックを得ることが、再起動のトリガーになる。
就活仲間を持つのも、いい“言い訳”になる
一緒に動く仲間がいることで、「あの人が頑張ってるから自分も少しだけやってみよう」と思える。これは、モチベーションというより“比較”による自発的行動の誘発だ。
やることを共有し合う
成果を報告し合う
一緒に企業説明会に参加してみる
こうした関係性は、“やる気が起きない日”をサポートしてくれる仕組みになる。
動き出した就活に「軸と意味」を持たせる思考
何のために就活するのかを“自分の言葉”で再定義する
「とりあえず内定」が行動を曖昧にする
再起動し、少しずつ動けるようになった就活生が最初にぶつかるのが、「なんでこの企業を見ているんだろう?」という曖昧さだ。
行動しているようで、自分の中に「目的」や「納得」がないと、選考が進んだとしても迷いや不安がつきまとう。
そしてその感覚は、自己分析の甘さや軸の不在から生まれている。
なんとなく有名だから
周りも受けてるから
勧められたから
こうした“他者由来の選択”で動くほど、就活は疲弊しやすくなる。
「働く意味」と「自分の選択」を接続する
就活において、「自分にとって仕事とは何か?」を一度立ち止まって考える時間は極めて重要だ。
この問いにすぐ答えられる必要はないが、答えを探すプロセスそのものが、行動の指針になる。
たとえば以下のような問いを自分に投げてみるとよい。
どんなときにやりがいを感じる?
どんな働き方なら頑張れる?
どんな人と一緒にいたい?
どんな環境なら安心して挑戦できる?
こうした問いに言葉で向き合っていくことで、「なんとなく動いている状態」から「選んで動いている状態」へと進化できる。
自己分析は“自分の取扱説明書”を作ること
過去の出来事を「感情」で読み解く
出来事の“事実”ではなく“感情”に注目する
自己分析を進めるとき、多くの学生が「実績」や「成果」を振り返ろうとする。しかし、選考で問われるのは数値や賞ではなく、「あなたらしさ」や「価値観」だ。
そのため、出来事そのものよりも、そのとき自分が何を感じていたか、どう判断したかにフォーカスする必要がある。
「なんでそれを選んだ?」
「どんなときに楽しかった?」
「何がしんどかった?それでも続けた理由は?」
こうした問いに答えていくと、自分の中にある価値観や行動原理が浮かび上がってくる。
“誰かに説明できる感情”が言語化のカギになる
ただ感じて終わるのではなく、他人に伝えられるレベルで言語化することが、自己分析において極めて重要だ。
たとえば「楽しかった」ではなく、
「自分のアイデアが形になって、誰かに喜ばれたときに嬉しかった」
「目標に向かって仲間と協力する過程が心地よかった」
など、具体的な背景や理由が加わると、それは「再現性ある強み」として選考で使える武器になる。
「強み」や「軸」は“外にある正解”ではなく“内にある納得”
自分の言葉で語れるようにするためのステップ
自己PRを“探す”のではなく“育てる”
よく「自分の強みがわかりません」と悩む就活生がいるが、強みは突然見つかるものではなく、経験を丁寧に振り返る中で“育つ”ものだ。
たとえば「リーダー経験がない」としても、「誰かのフォロー役に徹した」「自分から声をかけて雰囲気を作った」などの行動からは、
周囲を支える力
自発的な行動力
空気を読んで調整する柔軟性
などが見えてくる。
大事なのは、表面的な肩書き(リーダー・主将など)ではなく、日常の中にある「らしさ」を拾い上げることだ。
「自分の軸=働くうえで譲れないもの」を探る
就活の“軸”とは、志望動機の裏側にある「この会社を選びたい理由」の土台になるものである。
これは「何をしたいか?」というよりも、「何があれば前向きに働けるか?」という条件や価値観の優先順位に近い。
以下のような視点から考えてみよう。
働く環境(裁量/サポート体制/上下関係)
関わる人(個人主義/チーム主義/協力性)
成長実感(スキル/評価/挑戦機会)
社会との接点(貢献実感/影響力/やりがい)
これらを組み合わせることで、「自分が心から納得して働ける企業像」が見えてくる。
自己分析の“正解”は存在しない
他人の就活と比べないための思考法
「自分の深さ=就活の軸」になる
就活では、「あの人はもう○社も選考進んでる」「自分はまだ方向性も見えてない」と、つい他人と比べて焦りがちだ。
しかし、就活の評価基準に“スピード”も“量”もない。
むしろ、自分の内面をどれだけ深く掘り下げているかが、ESや面接で伝わる説得力を決定づける。
表面的な言葉ではなく、経験の裏にある意味まで語れるか
他人の言葉を借りず、自分の言葉で語れているか
一貫した価値観が軸としてにじみ出ているか
このような“深さ”こそが、他人と比べることのできない、自分だけの評価軸になる。
「正解」を探すほど自信は失われる
自己分析でやってはいけないのが、「就活でウケる自分像」を探すことである。
企業が欲しそうな人物像
先輩が評価された話し方
YouTuberが言ってた正しい自己PR
こうした“外の正解”をなぞるほど、自分の言葉はぼやけていき、説得力を失う。
面接官は、どんなにきれいに整った志望動機よりも、“その人らしさ”に興味を持つ。
就活で求められるのは、自分の言葉で、自分の過去を語れることであり、それができる人には共通して「選ばれる力」が備わっている。
再起動した就活を“前進”に変える企業選びと選考準備
自己理解から企業選びへつなげる視点の持ち方
「合う企業を見つける」のではなく「自分が選べる状態」を作る
自己分析を通じて「どんな価値観を大切にしたいか」「どんな働き方なら自分らしく頑張れるか」が見えてきたら、次にするべきは企業選びである。
ただしこのとき、やみくもに「自分に合う企業を探す」というスタンスでは、また迷子になる可能性が高い。
大切なのは、「自分が何を判断軸にして選びたいか」を言語化し、それに沿って企業を“能動的に見ていく”態度を持つことだ。
社風に共感できるか
若手に裁量があるか
人を育てる文化があるか
長期的に働ける制度があるか
こうした観点を自分の中に持っていることで、“なんとなく選んでしまう”を避けられる。
そして、それが選考でも「なぜこの会社なのか」を話すときの説得力につながっていく。
「好き・嫌い」ではなく「合う・合わない」で見ていく
企業選びでありがちなのが、「なんとなくいい感じ」「好きかも」といった感覚だけで判断してしまうこと。
感覚は大切だが、それだけでは選考で説明できないし、入社後のミスマッチも起こりやすくなる。
そこで使いたい視点が、「好きか嫌いか」ではなく「自分にとって合うか合わないか」という冷静な目線である。
雰囲気が合うか(自由/厳格、上下関係/フラット)
働き方が合うか(裁量/指示、スピード重視/丁寧さ重視)
評価軸が合うか(成果重視/プロセス重視)
このように、自分の価値観と企業の方向性を照らし合わせながら判断することで、選考対策にも迷いが少なくなる。
“行けそうな企業”ではなく“行きたい企業”から動く
「受かりやすさ」で選ばない勇気を持つ
“安全圏”ばかりに逃げると、モチベーションが下がる
就活が後ろ倒しになっている学生の多くは、行動を始めたときに「自信がないから、受かりそうなところから受けてみよう」と考える。
確かにそれも戦略の一つだが、「どうしても働きたい会社」や「心が動いた会社」から逃げ続けると、やりきるエネルギーが湧きにくくなる。
特に、動き出しが遅かった人ほど、「自分なんてもう選ばれない」と思い込み、最初から妥協を前提にしてしまいがちだ。
だが、本当に納得できる内定がほしいなら、「行きたい企業への挑戦」を避けないことが重要だ。
そのチャレンジが、モチベーションの源になる。
「志望度が高い会社のために練習する」という逆転思考
選考を受けることそのものを「練習」として活用するのは悪くない。
しかしその練習も、「本命企業の内定に近づくため」という視点があれば、意味が変わってくる。
どんな自己PRが刺さるか試してみる
面接で緊張しない準備を積んでおく
企業の質問傾向を把握しておく
こうした行動は、すべて「自分の軸を活かした選考対策」に直結する。
つまり、「動けなかった過去を否定する」のではなく、今から本命に向けた練習に切り替えるという思考が、行動に納得感を与える。
自分のペースで進める選考対策の“型”をつくる
ESも面接も、準備は“型”から始めて“自分らしさ”で仕上げる
自己PR・ガクチカは「3つの軸」で整理する
自己分析をもとに、実際に選考書類や面接で自分をどう表現するかは、行動に落とすうえで非常に重要なステップだ。
よくあるのは、「自己PRのネタがない」「何を話せばいいかわからない」という悩みだが、これは多くの場合、話を整理する「型」を知らないから起こる。
まずは以下の3つの軸で考えるとよい。
どんな状況だったか(背景・課題)
どんな行動をしたか(工夫・役割)
どんな価値観が表れたか(学び・活かし方)
このように分けることで、「単なる出来事の羅列」ではなく、「自分らしさがにじむ話」に変えられる。
練習は“答え合わせ”ではなく“言語の筋トレ”
面接の練習やES添削を通じて、「言い回しが変」とか「こっちの言い方がいい」とアドバイスを受けることは多い。
そのときに注意したいのは、「正解を探そうとしすぎない」ことだ。
大事なのは、自分が何を伝えたいかをぶらさず、伝わる形に磨き上げる感覚である。
自分の言葉を使って話せているか
詰まっても言い直せるほど、内容を理解しているか
相手の反応を見ながら調整できる柔軟さがあるか
このように、「自分の経験」と「伝える技術」をつなげていくことが、“選考の強さ”につながっていく。
まとめ:動けなかった自分を否定しない再起動の就活
動けない就活は、意志ややる気の問題ではなく「迷い」「情報過多」「不安」が原因である
再起動のきっかけは、「自分を責めない思考」と「小さな行動」の積み重ね
自己分析は、「自分の感情」と「価値観」を言語化し、「選べる自分」になるプロセス
企業選びでは、「合うか合わないか」という主観的視点が、自分の選択に意味を与える
選考対策は、「正解」ではなく「納得感」を軸に設計し、言語の筋トレで整えていく
就活とは、自分と向き合い続ける行為であり、動けなかった過去も含めてすべて“素材”になる。
どんなに出遅れていても、どんなに空白があっても、再起動できる人が、結果的に“選ばれる人”になっていく。
スタートの遅れよりも、自分のペースで動けるかどうかが未来を分けるのだ。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます