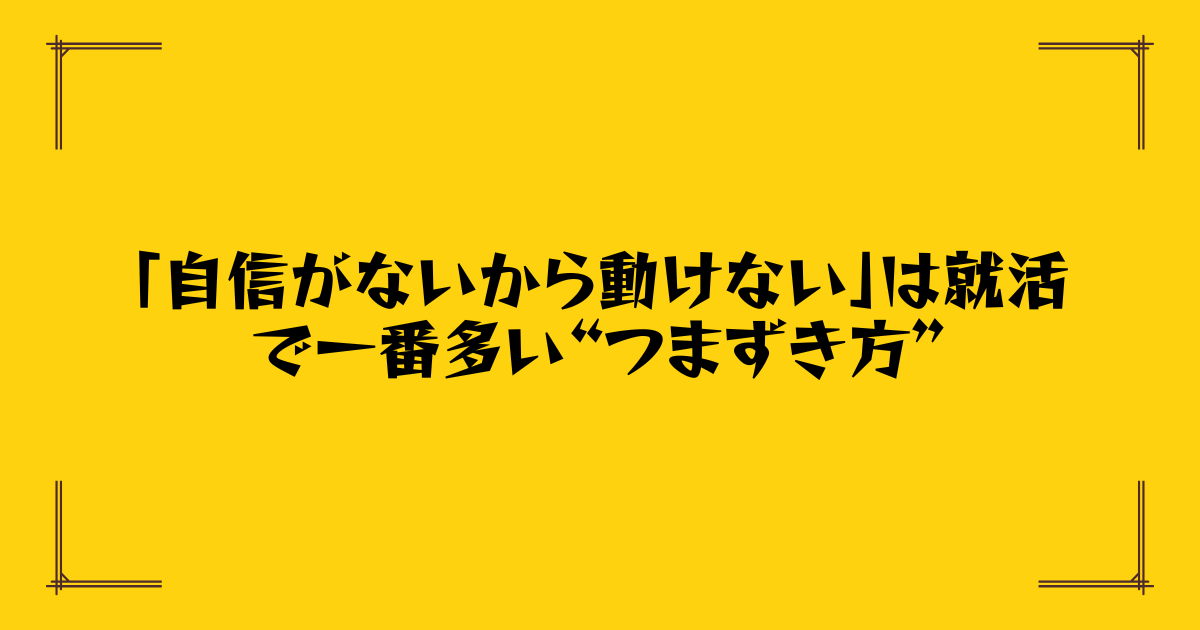動けない理由は能力じゃない。「自分には何もない」という感覚
自信のなさは「根拠のある劣等感」じゃない
「自信がないから就活が怖い」
「自己PRもない、強みもない、書けるガクチカもない」
こう感じている人は、実はかなり多い。むしろ、“最初の内定を取れない人の共通点”と言ってもいいくらいだ。
ただ、この「自信がない」という感覚、冷静に見れば“具体的な欠点”というより、「何をどうしていいか分からない不安」の集合体だったりする。
つまり、自信がないのではなく、“比較材料がなくて怖い”だけ。
「他の人みたいに、留学もボランティアも、リーダー経験もないから話せることがない」
そう思っている人は多いけど、実際に面接で評価されているのは“話のネタ”ではなく、“そこにある視点や考え方”。
にもかかわらず、「これと言ってすごい話がない」という理由で応募すらできず、就活のスタート地点にすら立てない人が増えている。
でもそれって、本当にもったいない。
自信がある人より、「動ける人」の方が内定を取っている
就活において「自信がある人」が有利かというと、必ずしもそうではない。
実際、最初の内定を早く取るのは、「完璧な自己PRがある人」でも「圧倒的な成果を持っている人」でもなく、動ける人、試せる人、失敗しても戻ってこれる人だ。
動けるかどうかの差は、“自分にOKを出せているかどうか”にある。
たとえば、「これでいいかわからないけど一社エントリーしてみよう」
「とりあえず面接受けて、どんな質問されるか知ってから考えよう」
そうやって正解が分からない状態でもとりあえず進んでみることができる人のほうが、気づけば内定に近づいている。
なぜ自信が持てないのか?その本質は「比較」と「承認欲求」
比較癖が生む“根拠のない劣等感”
SNS、友達、内定報告…すべてが自分を責める材料になる
就活が始まると、どうしても「他の人と比べてしまう」瞬間が増える。
就活アカウントをフォローすれば、「3月で内定出ました」「30社エントリーして○社通過中」といった報告が流れてくる。
友達と話せば、「あの子はもうベンチャー受けてるらしい」「○○のインターン通ったって」など、気づけば周囲の情報に飲み込まれていく。
すると、「自分はまだ何もしてない」「このままだと取り残される」と思ってしまう。
でも、実際はそんなことない。
みんな“できてるように見える自分”を演じてるだけで、内心は不安を抱えている。
就活で大事なのは、「他人と比べてすごいか」ではなく、「自分の中で納得できるか」。
にもかかわらず、他人の進捗が可視化される現代の就活では、“焦らされる構造”そのものが不安の正体になっている。
自信がないときこそ「承認欲求」と向き合わなきゃいけない
「内定を取って親に安心させたい」「すごいねって言われたい」
この気持ちは自然なことだけど、裏返すと、「他人に評価されないと自分を認められない」状態でもある。
これが強すぎると、就活では苦しくなる。
なぜなら、就活は“不合格の連続”だからだ。
どんなに実力がある人でも、5社・10社は普通に落ちる。
つまり、「落ちた=自分の人格が否定された」と思ってしまうと、メンタルがもたない。
だからこそ、就活は“自己肯定感の筋トレ”でもある。
自分で自分をどう見るか。
どんなときに「今の自分でいい」と思えるか。
これを言語化できるようになると、自信がなくても動けるようになる。
自信がない人ほど「戦い方を変える」ことで勝てる
王道の就活ルートがすべてじゃない
ガクチカがなくても受かる企業は実在する
「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)がない」
「サークルやインターンもやってない」
そんな人でも、ちゃんと内定は取れる。
むしろ、企業によっては「個人の考え方」や「入社後の伸びしろ」を重視しているところも多い。
特に、1次面接から現場社員が出てくる企業や、自己PRより“対話”を重視する会社は、過去の実績より「一緒に働きたいか」を見ている。
つまり、「すごい経験がある人が勝つ」ではなく、「ちゃんと話せる人が残る」就活ルートも存在する。
自信がない人ほど、「王道」や「成功例」ばかり見てしまいがちだけど、自分に合った土俵を選ぶことも戦略である。
自信がないなら、「自信がないまま」話せばいい
就活では、「盛って話す」「強く見せる」ことが良しとされがちだけど、それができない人にとっては逆効果。
むしろ、正直に「今まで自己PRなんて考えたことがなかった」「やりたいことが分からなくて不安だった」と伝える方が、“本音で語れる人”として評価される場面もある。
嘘やテンプレではなく、リアルな言葉で伝えること。
それが、経験よりも響くときがある。
だからこそ、「自信のなさ」は隠すべき弱点ではなく、“出し方次第で伝わる強さ”にもなる。
自信がなくてもできる「就活の入り口」を見つける
大きなことをする前に、「小さい動き」を作る
就活は“自己解決型ゲーム”じゃなくていい
「何から始めればいいのか分からない」
「何をやっても意味がない気がして動けない」
こういうとき、多くの人は“いきなり完璧を求めすぎている”。
たとえば、「自己PRを完成させてから説明会に出よう」
「志望動機が固まるまではエントリーしないでおこう」
これは一見まじめに見えるけど、実は“動かないための言い訳”にもなってしまう。
就活は“動きながら整えるもの”。
最初から完成された自分なんて誰もいないし、どこかで雑なまま飛び込まないと、何も始まらない。
完璧を目指すより、「雑でもいいから、一歩目を踏み出すこと」の方がずっと価値がある。
スモールスタートは「気まずくない情報接触」からでいい
たとえば、以下のような行動から始めてみるといい。
1社だけ、企業説明会を予約してみる(オンデマンドでも可)
就活系YouTubeの動画を1本見る
友達の就活状況を聞いてみる(相談ではなく雑談レベルで)
これだけでも、「やってみた」という実感が生まれる。
ポイントは、“重くないこと”から始めること。
最初の一歩に必要なのは、やる気でも根拠でもない。
「動けた自分」に対する肯定感なのだ。
自信は「結果」じゃなくて「行動のあと」に生まれる
自信がない人は「自信がつくのを待たない方がいい」
成功体験ではなく“行動体験”を積み重ねる
「自信がついてからエントリーしよう」
「面接に慣れてから選考に進もう」
こう考えていると、何も始められない。
そもそも就活における自信って、「成功したかどうか」よりも、「動いた経験の積み重ね」によって生まれる。
たとえば、たった1社でも面接を受けてみると、「こういう質問が来るんだ」「ここで詰まったな」と、経験値が蓄積される。
この“小さな把握感”が、自信の最初の芽になる。
逆に、どんなに情報を集めても、エントリーしなければ何もわからない。
だからこそ、経験に触れる→気づく→整える→また試す、というループを早く作った人が強くなる。
自信のなさをごまかすより、“行動で上書き”する
自信がない人ほど、エントリーシートや面接で“自分を強く見せよう”としがちだ。
でも、無理して演じようとすると、逆に自信のなさがにじみ出てしまう。
そうではなくて、「等身大の自分でもいいから、まず動いてみる」という姿勢の方が、企業には好印象に映る。
そして、行動するたびに「これで大丈夫だった」「意外と通った」という小さな成功が積み重なると、
それが“本物の自信”に変わっていく。
「自分には何もない」と思っていても、話せる材料はある
ガクチカがなくても“日常”に語れることは転がっている
すごい成果じゃなくて、“気づき”が評価される
「部活もしてない」「インターンも行ってない」「アルバイトも普通」
そう感じる人ほど、ガクチカや自己PRのハードルを高く設定している。
でも実際には、企業が聞きたいのは“すごい話”ではなく、“その人がどう考えて動いたか”だ。
たとえば、
アルバイトでクレーム対応したとき、どう感じてどう工夫したか
苦手だったゼミで、どうやって乗り切ったか
遅刻を繰り返した自分が、改善するためにどんな工夫をしたか
こういう、「自分なりに向き合ったプロセス」こそ、話せる材料になる。
大きな成果や肩書きがなくても、“人柄”や“思考”を感じさせる話は、面接官に刺さる。
書けないなら「口に出してみる」から始める
「ESが書けない」「自己PRがまとまらない」という人は、まず紙に書く前に「話してみる」ことをおすすめしたい。
友達に話してみる
録音して自分の声を聞いてみる
模擬面接アプリで練習してみる
書くより話す方が、思考の整理がしやすい場合がある。
そして、言葉にすることで、「あ、自分ってこんな風に考えてたんだ」と自分で気づけることが多い。
ここに、自信の芽が生まれる。
“言葉にできること=自分で認識できていること”でもあるからだ。
自信がない人こそ「合う企業」の見つけ方が鍵になる
自信のなさは「企業選び」で大きく左右される
“企業に合わせよう”とすると、さらに苦しくなる
自信がない就活生の多くがやってしまいがちなのが、「企業に合わせる」という発想だ。
「この企業が求めてる人材像に自分を寄せて話さなきゃ」
「自分に合ってるかじゃなくて、受かりそうかどうかで判断する」
こうなると、就活がどんどん“他人軸”になっていく。
そうなると、自分の強みや志望理由がぼやけて、面接でも“どこか借りてきた言葉”しか出てこない。
結果、受からない。落ち込む。ますます自信がなくなる――この悪循環に入ってしまう。
だからこそ、自信がない人ほど、“自分が合いそうな会社”を丁寧に見つける必要がある。
そのためには、「自分が話しやすいか」「素を出しても嫌われなさそうか」という感覚の判断軸が必要になる。
「優秀な学生が行く会社」=「あなたが幸せになれる会社」ではない
「有名企業」「年収が高い」「東大生も受けている」
こういう要素に引っ張られて企業を選びたくなる気持ちは分かる。
でも、それが自分にとっての“働きやすさ”や“成長”と直結しているとは限らない。
むしろ、優等生タイプじゃない人や、話すのが得意じゃない人、計画的に物事を進めるのが苦手な人にとっては、
「自由度がある会社」や「失敗に寛容な会社」「少人数で密な関係が築ける会社」のほうが居心地がよく、伸びやすいこともある。
自信がないと、つい「強い会社」に行こうとしがちだけど、必要なのは“強い企業”ではなく、“自分が力を出せる環境”。
「背伸びしない就活」の方が、自分らしく戦える
本当に“自分らしさ”を出せる会社にしか受からない
すごい話より、「話せる話」の方が強い
就活では、“強いガクチカ”や“魅力的な成果”があると有利だと思われがちだ。
確かに、話としてキャッチーではある。
でも、それが“本人の言葉で語られているか”の方が、面接ではよく見られている。
企業側は、「この学生の話、どこまで本音だろう?」という目線で見ている。
だから、“等身大でも自分の言葉で話している人”の方が、信頼される。
派手な経験がなくてもいい。自信がなくてもいい。
でも、“それでもちゃんと話そうとしている”姿勢が伝わる人は、しっかり評価される。
合格するための就活じゃなく、“会話が通じる企業”を探す
自信がないまま受け続けると、「受かるかどうか」ばかりに意識が向いてしまう。
けれど、就活の本質は“対等なマッチング”だ。
企業も学生も、“一緒に働けそうか”を確認しているだけ。
つまり、「合格・不合格」というより、「相性が合うかどうか」の話だ。
そう考えると、変に自分を飾って合格しても、入社後に「合ってなかった」と感じてしまうリスクが高い。
だからこそ、「ちゃんと話を聞いてくれるか」「ありのままで話せるか」という視点で企業を見ることが、自信のない人にとってはとても重要だ。
自信がない人が受けやすい企業の“見えない特徴”
“スペック型”より“ポテンシャル型”の採用をしている企業
見分け方は「面接官のタイプ」と「質問内容」
自信がない人は、なるべく“スペック主義”の会社は避けた方がいい。
では、どんな企業が“ポテンシャル型”なのか?
以下のような特徴がある。
面接で「過去の実績」より「考え方」や「価値観」にフォーカスしてくる
過去の話を深掘りしすぎず、未来志向の質問が多い
面接官が圧迫型ではなく、共感ベースで話してくれる
こうした企業は、たとえガクチカが弱くても「あなたがどんな人か」「どんな風に成長しそうか」を見てくれる。
逆に、「成果を数値で示してください」や「なぜそれが他人より優れているのか」といった問いが多い会社は、“自信がない人”には厳しい傾向がある。
「理念共感」「社風重視」を打ち出している企業は狙い目
会社のコーポレートサイトや求人ページに注目してほしい。
「成長」「挑戦」「リーダーシップ」ばかりを強調している会社よりも、
「チーム」「つながり」「安心して働ける環境」などを重視している企業は、“人柄重視”の採用傾向がある。
こういう企業は、「自信のある発信」よりも「誠実なコミュニケーション」が評価されやすい。
つまり、素直に話すことが最大の武器になる可能性が高い。
自信がないことを責められるのではなく、「それでもがんばって話そうとしている」ことに価値を置いてくれる会社は、確かに存在する。
そして、そういう会社こそ、自信がない人にとっての“最初の内定”につながりやすい。
自信のなさと付き合いながら選考を受け続けるには
“自信がない”ことを否定せず、そのまま持っていく
自信は無理に作らなくていい。持ったまま動いていい
就活は「自信がある人のもの」というイメージが強い。
でも実際、面接官が見ているのは「この人は強く見えるか」ではなく、「この人と一緒に働きたいか」。
だからこそ、自信を無理に作って“強いフリ”をする必要はない。
むしろ、素のままで話そうとしている人にこそ、信頼感が生まれる。
自信のなさをごまかすより、その状態で話せるようになることの方が、よっぽど価値がある。
「まだ自信ないけど、でもここまで来てみた」
「緊張しているけど、自分の言葉で伝えたい」
そんな言葉が自然に出る学生は、面接官の記憶に残る。
自信を持とうとするより、“自分の位置”を把握する
「自信が持てない」と悩むとき、多くは“理想の自分と今の自分の差”に苦しんでいる。
でも、その差を埋めようとする前に、「今、自分はどこに立っているか」を冷静に見てみることが大事だ。
何ができるか
何が苦手か
どんな企業なら話しやすそうか
どんな環境なら力を出せそうか
この“自分の立ち位置”を正しくつかめれば、無理な背伸びをせず、自然に動ける。
そしてその姿が、企業にも伝わる。
就活で必要なのは、「できるフリ」じゃなくて、「自分を知ること」。
選考に落ちたとき、自信を失わないための考え方
落ちること=人格否定ではない
あなたが否定されたんじゃなくて、“相性が合わなかった”だけ
選考に落ちると、「自分なんて…」と落ち込んでしまう。
特に自信がない人ほど、「やっぱり無理なんだ」と強く思い込んでしまう。
でも、面接は“相性を見る場”であって、“人格の評価場”ではない。
たまたま質問に詰まった、うまく話せなかった、それだけで落ちることもある。
あるいは、企業が求める人物像と少しズレていただけかもしれない。
そんなことで、自分自身を丸ごと否定する必要はない。
むしろ、「ここは合わなかった」という結果を一つ受け止めて、次に行くだけの話だ。
落ちたことには“慣れ”が必要。反省しすぎると疲弊する
落選通知が届いたとき、「どこが悪かったんだろう」と考えすぎると、だんだん動けなくなってくる。
改善はもちろん大事だけど、反省しすぎるより、“慣れる”ことのほうが先かもしれない。
就活において“全落ち”は当たり前に起きる。
最終面接まで行って10社以上落ちる人も、普通にいる。
1社落ちたくらいで自分を全否定する必要は、まったくない。
自信がないまま“最初の内定”を取るために意識したいこと
「1社でいい」くらいの気持ちで動く
100社落ちても、1社決まればすべてが変わる
就活をしていると、「周りが何社も内定を取ってる」「自分だけ進んでない」と感じてしまう。
でも、どれだけ落ちても、最後に1社決まればその人も“勝者”になる。
その1社にたどり着くために、自信を持つ必要なんてない。
自信がなくても、話すのが苦手でも、志望動機が多少あいまいでも、
それでも「この子いいね」と思ってくれる企業が、必ずある。
最初の1社に出会うまでのプロセスは、全員バラバラ。
だから、自分のペースで、自分のやり方でいい。
誰かと比べるより、「昨日より進んだ自分」を見る
自信がなくなる理由の一つは、「比較癖」だ。
SNSや友達との会話で、自分より先に進んでいる人を目にすると焦る。
でも、その人とあなたのスタート地点も、準備状況も、志望業界も違う。
大事なのは、“昨日の自分より、1ミリでも進んだか”という視点。
昨日は説明会を見ただけ。今日はエントリーした。
昨日は何もしてない。今日は1社受けた。
それだけで、立派に“進んでいる”のだ。
まとめ:自信がなくても、内定はちゃんと取れる
就活をしていると、自信のある人が有利に見える。
でも、実際には、「等身大で話せる人」「自分の言葉で語れる人」のほうが信頼される。
すごい話がある人より、「ないなりに考えて話せる人」のほうが、企業には響く。
自信がなくても、やるべきことは決まっている。
小さく動いて、経験を増やす
自分に合いそうな会社を探す
自分の言葉で話す練習をする
落ちても慣れる、いちいち自分を責めない
比較せず、昨日より少し進めばOK
この積み重ねが、いつか“自信に近いもの”を育ててくれる。
そして、最初の内定にたどり着いた瞬間、これまでの不安が全部つながる感覚がくる。
その日が来るまでは、等身大のまま、動ける自分であり続けよう。
“自信がない自分”のままで就活を進めていい。そのままでも、ちゃんと未来は開けていく。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます