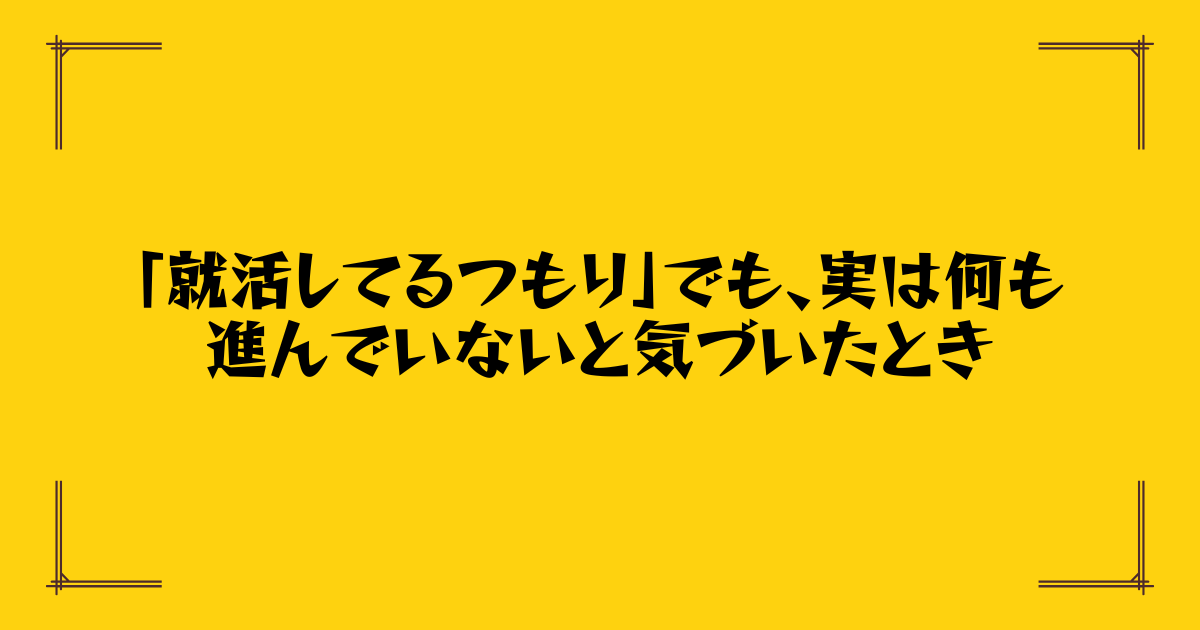とりあえず動いていたけど、不安が晴れない
「エントリーしてるのに、安心できない」感覚の正体
就活をしていると、ある瞬間ふと怖くなることがある。
ESも出してるし、説明会にも参加してる。マイページもいくつか登録してるし、面接にもポツポツ呼ばれ始めてる。
でも、ふと立ち止まったとき、「自分、何を目指してるんだっけ?」「このままでいいのか?」という不安が押し寄せる。
それは、表面的には“就活してる風”でも、中身がともなってないと自分で気づいているサインだ。
やってる「フリ」じゃなく、やってる「つもり」になってしまってる。
これが続くと、どれだけ数をこなしても、不安は消えない。むしろ積み重なっていく。
そんな“なんとなく就活”の危うさに気づいたとき、自分自身との向き合い直しが始まる。
不安の根っこは「自分の軸がないこと」にある
説明会に参加しても、企業の違いがよく分からない。
ESを書いても、毎回テンプレっぽくなる。
面接を受けても、「それって志望動機ですか?」と自分で思うこともある。
このモヤモヤの正体は、自分の就活の「軸」がないことにある。
「どんな仕事がしたいのか」「どういう環境なら自分が伸びるのか」――
そういった根本的なことを深く考えないまま動いているから、どの企業に触れてもピンとこないし、言葉にもうまくできない。
周りがどんどん進んでいく中、自分だけが“就活の輪郭だけ”をなぞってるような気分になって、
焦りと空虚感がセットで襲ってくる。
「就活してる感」に溺れてしまう理由
安心のために、形だけの行動を重ねてしまう
“やってる自分”を見て安心しようとしていないか
人は、不安なときほど“形”を求める。
「就活してると言える自分」でいるために、とりあえずエントリーだけはする。
「選考に進んでいる」と誰かに言いたくて、なんとなく受けてみる。
でもその結果、選考が進んでも進んでも、「なんか違う気がする」と感じてしまう。
これは、“行動の中身”よりも、“行動したこと自体”に安心感を求めてしまっている状態だ。
頑張っているようでいて、ただの確認作業になってしまっている。
安心するためのES提出
周りと差がつかないようにするための説明会参加
受かりそうな企業ばかりを選ぶ戦略
こうした動きの積み重ねは、表面的には“就活してる感”が出る。
でも、中身がなければ、どれだけ企業を受けても、本当の納得感は得られない。
自分の感情を“外からの基準”に合わせようとしていないか
就活が始まると、あちこちから「こうすべき」「こうあるべき」という情報が飛び交う。
「3月までにES20社出さないと遅れてる」
「夏までに内定がないとヤバい」
「SPIができないと終わる」
そういった言葉に押されて、自分の感情よりも“他人のタイムライン”に合わせて動こうとしてしまう。
でも本当は、就活に正解なんてない。人によって道筋もスピードも違う。
外から与えられた“基準”にばかり反応していると、
「自分が何を感じてるか」や「何に違和感を持っているか」が分からなくなってくる。
気づけば、「誰かの就活」に引っ張られて、「自分の就活」を失っている。
「なんとなく就活」から抜け出すための第一歩
“わかってない自分”を自覚する勇気を持つ
「何がわかってないか」すら分からない状態で大丈夫
就活がしんどくなるのは、「自分が何に悩んでるか分からない」ときだ。
この状態がいちばん不安で、いちばんつらい。
でも、それを自覚することこそが、抜け出すための最初の一歩になる。
「そもそも、どんな企業が合ってるか分からない」
「働きたい仕事なんて、はっきりしてない」
「自己PRって、自分で言えるほどの強みない」
こんな風に思ってる人が、実はほとんどだ。
就活では「自分を理解している学生」が評価されるように思えるけど、
本当は、「自分がまだ分かっていないことを認めて、考え続ける姿勢がある人」のほうが信用される。
自分をよく見せようとするより、わからない自分を直視することのほうが、よっぽど難しい。
でも、その自覚がある人ほど、迷っても軸を見つけやすくなる。
いったん“動かない”時間をとるのも立派な就活
焦りから無理に動き続けると、「数はこなしたけど、何も残ってない」状態に陥る。
そうなるくらいなら、いったん止まって考える時間を取ることのほうが、何倍も意味がある。
ノートを広げて、自分の価値観を棚卸ししてみる
「この会社、なんとなく嫌だったな」と思った理由を深掘りする
「あの人みたいな働き方は無理かも」と思ったことを言語化する
こうした“内省の時間”が、ちゃんとした就活の土台になる。
「とにかくエントリー」の数よりも、「納得して選んだ1社」に出会うための時間の方が重要だ。
立ち止まって、自分の「就活の軸」を見つける
やりたいことがなくても、就活はできる
「志望業界が決まらない=失格」ではない
「やりたいことがないから、就活がうまく進まない」と思っている学生は多い。
でも、実はそれが普通だ。明確な夢や職種志望を持ってる人なんて、一部にすぎない。
ほとんどの学生が、「何となく興味ありそう」くらいの感覚でスタートしている。
就活がうまくいかない人の多くは、「やりたいことがないと内定を取れない」と思い込んで、
自己分析も志望動機も書けなくなる。けれど、企業が見ているのは“やりたいことの完成度”ではなく、“働く意思と相性”だ。
大切なのは、業界や職種より先に、「自分がどんな環境に心地よさを感じるか」「どんな瞬間に力を出せそうか」といった、行動や価値観のレベルから探ることだ。
「やりたくないこと」から考えるのも立派な軸になる
「やりたいことが分からない」なら、「やりたくないこと」「向いてなさそうなこと」から考えてみるのも有効だ。
実際、多くの学生は「違和感のあるものを排除していくプロセス」で就活の軸を絞っている。
たとえば、
数字のノルマに追われるのはストレスを感じそう
常に競争的な環境は苦手かも
単純作業より、人との会話がある方がやりがいを感じる
そういった「苦手」「嫌だ」と思ったことを言語化することで、少しずつ輪郭が見えてくる。
そしてその中に、「これは避けたい」「これは向いてるかも」という感覚が育ってくる。
自分だけの“言葉”で考えるための思考法
よくあるフレーズに頼らず、自分の言葉に直す
「成長できる環境がいい」は誰でも言える
ESや面接でよく出てくるフレーズ――
「成長できる環境で働きたい」「社会貢献ができる仕事がしたい」「チームで働きたい」
これらは一見前向きだが、自分の内側から出た言葉ではない場合が多い。
誰かのES例文を見て、なんとなくそれっぽいと思って書いた言葉は、自分でもうまく説明できない。
面接官に突っ込まれると、すぐにバレる。
だからこそ、自分だけの“言葉”を使う意識が大事になる。
たとえば、
「成長したい」→「一度つまずいたことを乗り越えて、できるようになる感覚が好き」
「チームで働きたい」→「ひとりで背負うよりも、誰かと相談しながら進めるほうが自分らしく動ける」
このように、感情や経験を起点にした言葉に言い換えるだけで、説得力が一気に変わる。
自分のエピソードを“どう解釈したか”がカギ
ESで評価されるのは、「どんな経験をしたか」よりも、「その経験をどう捉えたか」「どう活かそうとしているか」だ。
アルバイトでも部活でも、華やかな成果がある必要はない。
たとえば、「コンビニのレジ打ちを2年間続けた」――
これも、ただの事実だけでは面白くない。
でも、「どんな人と接するのが苦手だったか」「どうやってその苦手を克服したか」「それが今どう活きているか」まで言語化すれば、立派なエピソードになる。
最初は接客が怖かった
でも常連客との会話をきっかけに、少しずつ自分から声をかけられるようになった
今では初対面の人とも自然に話せるようになってきた
→ 面接でも、その経験が活きて、緊張せずに話せるようになった
こういった流れを語れるようになれば、あなたにしか書けないESになるし、自信の土台にもなる。
軸が見えてくると、選考への向き合い方が変わる
志望動機が“借り物”じゃなくなる
「どこでも言える志望動機」から脱却する
就活の初期によくある悩みが、「志望動機が全部同じになってしまう」というもの。
どの企業にも「成長できるから」「人を大事にしているから」「社会貢献性があるから」と書いてしまう。
これは、自分の中に“選ぶ軸”がないから起きる現象だ。
逆に言えば、自分なりの視点を持てば、似た業界の企業でも「ここが違う」と思えるようになる。
この会社は、“人を支える仕事”に重点を置いてる
こっちは、“課題を見つけて解決する力”を重視している
自分は「支える」より「動いて解決する」方が向いてる気がする
→ だから後者のほうが合っている
このように言語化できれば、「この企業である理由」が自然に生まれてくる。
それが、説得力のある志望動機になる。
“自分が企業を選ぶ視点”を持つことが大事
就活では「企業に選ばれるかどうか」に意識が向きがちだが、本来は「自分がどんな企業を選びたいか」が重要な視点だ。
選ばれることばかり意識してしまうと、「とにかく受かりたい」という思考になって、自分を押し殺してしまう。
でも、「自分はこういう働き方がしたい」「こういう人たちと働きたい」といった視点があれば、企業を見る目が変わってくる。
説明会で何を聞くか
面接でどんな質問をするか
企業のどんな部分に共感するか
これらがブレなくなれば、就活の手応えも変わってくる。
自分の“軸”をもとに企業を選ぶと、動きが変わる
「条件」ではなく「相性」で見る視点に切り替える
「大手かどうか」より、「自分がそこでどう働けそうか」
就活ではつい「知名度」「年収」「福利厚生」などの条件に目が行きがちだ。
でも、それだけで企業を選ぶと、内定が出たあともずっとモヤモヤが残ることになる。
「この会社に入って、自分はどういう姿で働いてるか」がイメージできないまま選んだ企業は、後悔につながりやすい。
なんとなく大手だから受けた
周りがエントリーしてたから気になった
福利厚生がよさそうだから選んだ
どれもよくある理由だが、自分の軸から見たときに納得できるかどうかが大事だ。
たとえば、自分が「若いうちから裁量を持って動ける環境で働きたい」と思っているなら、
必ずしも大企業が最適とは限らない。
「少数精鋭の中で、幅広く経験できる」企業のほうが合っていることもある。
条件は参考程度にして、自分にとっての「働きやすさ」や「やりがい」を軸にして見る目を養うことで、
自分だけの企業選びができるようになる。
“世間の評価”より、“自分の違和感”を信じる
説明会や口コミサイトなどで「いい会社」と言われている企業でも、
自分が何かしらの違和感を覚えるなら、その直感を無視しない方がいい。
話を聞いていてワクワクしなかった
登壇している社員の雰囲気に馴染めなさそうだった
「うちの会社は体育会系です!」に引っかかりを覚えた
そういった感覚は、自分の価値観と企業のカルチャーが合わないサインかもしれない。
企業研究を深めるよりも前に、自分の“引っかかり”を丁寧に拾うこと。
「なんでそう感じたのか?」を自問自答するだけでも、企業選びの精度はぐっと上がる。
受ける企業をどう絞るか、どこまで広げるか
数をこなすより、「納得感のある選択肢」を増やす
「とにかく数を出せばいい」は正解じゃない
多くの学生がやってしまうのが、「とりあえず数をこなす就活」だ。
ESを10社、20社、それ以上出して、「数打ちゃ当たる」戦略に走ってしまう。
もちろん、初期段階ではある程度の行動量も必要だ。
でも、ESを書くたびに「この企業、なんで受けたんだっけ?」と思ってしまうなら、
その就活は時間と体力の消耗戦になる。
大切なのは、“書くたびに精度が上がる”状態にすること。
そのためには、受ける企業を絞り込み、毎回「自分なりの志望理由」を言語化できるようにしていく必要がある。
「自分はこういうタイプの会社が合う」という仮説を持ちながら受けることで、
受けた経験自体が“企業選びのヒント”になっていく。
「違った」と思った経験も、次の企業選びに活かせる
選考で落ちたり、「思ったのと違った」と感じることがあっても、それはムダじゃない。
むしろ、そこにしかない“感覚のズレ”をヒントに、次の企業の見方が磨かれていく。
「面接官の質問が圧迫気味だった」→ もっと対話重視の会社が合うかも
「評価基準がテストばかりだった」→ 数値より人柄を見る会社を探したい
「業務説明が漠然としていた」→ 職務内容が明確な会社を優先したい
このように、ひとつひとつの選考が「自分の就活感度」を上げてくれる。
だからこそ、ただ数をこなすのではなく、一社一社の経験に向き合い、意味を持たせる視点が大切になる。
就活の“自信のなさ”を言い訳にしないために
自信がないのは普通。でも「ないまま進める方法」はある
「自信がないから準備ができない」から抜け出す
多くの学生が陥るのが、「自信がないから行動できない」「ESに自信がないから提出できない」というループだ。
けれど、就活とは「自信を持つために動く場」でもある。
自信がないからこそ、面接で練習してみる
自信がないからこそ、ESを書いてフィードバックを受ける
自信がないからこそ、自己分析を繰り返す
このように、“自信がないこと”を起点に動けば、少しずつ「できること」が増えていく。
自信というのは、「準備が整ったから持てるもの」ではなく、「行動した先に生まれる副産物」だ。
自信よりも「納得感」のある言葉が大事
面接やESで評価されるのは、堂々とした態度やスムーズな話し方だけじゃない。
むしろ大事なのは、「その人が納得して話しているかどうか」だ。
自信がありそうに見えても、言ってることが空っぽなら意味がない
拙くても、自分の言葉で語れているほうが響く
つまり、“自信のあるフリ”をする必要はない。
「今の自分が考えたことを、自分の言葉で伝える」――それだけでも、面接官には伝わる。
だからこそ、準備段階では完璧を目指すより、「今の時点の自分」を受け入れて、言葉にする練習が大切になる。
「就活がうまくいかないとき」に考えるべきこと
うまくいかないのは、自分がダメだからじゃない
不採用が続くと「人格否定」されたように感じるが…
何社も落ち続けると、「自分ってダメな人間なんじゃないか」「何やってもダメなんじゃないか」と感じてしまうことがある。
でも、それは就活の構造上、誰にでも起こりうることだ。
就活は、たった1回の面接、数百字のESで評価されるシビアな仕組みだ。
しかも、応募者が数百人いるなかで、数人しか通らない。
これだけの競争率のなかで、落ちたからといって「人間的に劣っている」なんて結論は、どこにもない。
実際、別の企業では高く評価されたり、面接官によって印象がまったく違ったりすることもある。
だからこそ、「落ちた=価値がない」という思考には要注意だ。
就活で落ちるのは、単に「今回は縁がなかった」というだけのことだ。
「運」や「相性」も、就活の大きな要素
就活では「準備がすべて」「努力が報われる」とよく言われるけれど、
現実には「相性」や「運」も多分に含まれている。
面接官との相性が悪かった
一次の通過基準がその年だけ変わっていた
自分が得意な質問が出なかった
応募時期が遅れて、ポジションが埋まっていた
こういったことは普通に起こる。
それでも「自分のせいだ」と思い詰めると、どんどん就活が怖くなる。
だからこそ、うまくいかなかったときほど“自分を責めすぎない技術”が必要になる。
就活が長引いたとき、モチベーションを保つ方法
「動いてるのに報われない感覚」に耐える
就活は、すぐに結果が出ない“見えづらい努力”
スポーツや勉強と違って、就活の努力はすぐに結果に反映されない。
ESを10枚書いても、1社も通らない。
面接の練習をしても、本番で緊張して言葉が出ない。
この「報われない感じ」が続くと、何のためにやってるのか分からなくなる。
でも、それでもいい。就活とは、そういう“結果が遅れてついてくる”プロセスだ。
後になって「あの時の努力が役立った」と気づくこともある。
だから、目に見える成果よりも、「自分の変化」に目を向ける意識を持ってほしい。
以前より、自分の考えを言葉にしやすくなった
面接で緊張しても、ちゃんと受け答えできる場面が増えた
他人の価値観に振り回されず、自分の視点を持てるようになった
こうした変化は、内定よりも前に現れる“成長の証”だ。
気持ちが切れたら、いったん「休む」ことも戦略
どうしても就活がつらいときは、無理に頑張り続けない方がいい。
周りと比べて焦ったり、自己嫌悪になっているときほど、いったん手を止めて「自分の感情を取り戻す時間」をつくるべきだ。
就活のことを何もしない日を決める
気分転換に、全く関係ないことをしてみる
「今の気持ち」をノートに書き出してみる
こうした休息やリセットの時間が、結果的に“再始動のきっかけ”になる。
就活における本当の敵は「休むこと」ではなく、「自分を消耗させること」だ。
「就活=人生のすべて」と思わなくていい
就活は人生の“ひと区間”でしかない
どんな企業に入っても、すぐに“正解”とは限らない
「どこに内定するか」で人生が決まるような感覚に陥ってしまう学生は多い。
けれど、社会人になってからの現実は、もっとグラデーションがある。
入社してみたら、想像と違った
数年後に転職して、自分に合う場所を見つけた
入社時点では無名だった会社が、すごく自分にフィットした
就活は「一発勝負」ではない。
むしろ“今の自分が選べる最善の選択”をして、その後でまた軌道修正していくという生き方が、これからの時代には合っている。
だから、今の時点で「完璧な答え」を出そうとしなくていい。
「今の自分にできる選択をする」ことが大事なのだ。
「遠回り」や「寄り道」も、ちゃんと意味がある
新卒で希望の業界に行けなかったり、第一志望に落ちたりしたら、それだけで「終わった」と思ってしまうかもしれない。
でも、そんなことはまったくない。
社会人になってからも、キャリアはどんどん変化していく。
実際、まったく違う業界に転職して活躍している人もいれば、フリーランスとして道を切り拓いている人もいる。
「遠回り=失敗」ではなく、「その時に必要なプロセス」だったと捉えることが、長い目で見たキャリア形成には重要だ。
就活に「納得感」を持って終えるために
誰かの就活と比べない
就活では、「〇〇君はもう内定出た」「あの子は大手に決まった」といった話が耳に入ってくる。
それがプレッシャーになったり、劣等感になったりする。
でも、就活は本来「人と比べるもの」じゃない。
比べるべきは“昨日の自分”であり、“1か月前の自分”だ。
前は面接で言葉が詰まっていたけど、今は最後まで話せるようになった
昔は「なんで働くのか」分からなかったけど、今は少しだけ見えてきた
自信なかったけど、少しずつ言葉にできるようになった
こういった“小さな成長”の積み重ねが、就活の本質だ。
自分なりの「就活の終わり方」を見つけよう
就活のゴールは、「どこかから内定をもらうこと」じゃない。
「この企業に決めた理由に、自分で納得できること」が、本当のゴールだ。
妥協したように見えても、自分では納得している
理想通りじゃなくても、今の自分にとってはいい選択だった
迷いはあるけど、覚悟を持って入社を決めた
こう思えて就活を終えられたら、それは「勝ち」だ。
他人の評価ではなく、自分の感覚を信じる。
それが、「なんとなく就活」から抜け出す、唯一の方法なのかもしれない。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます