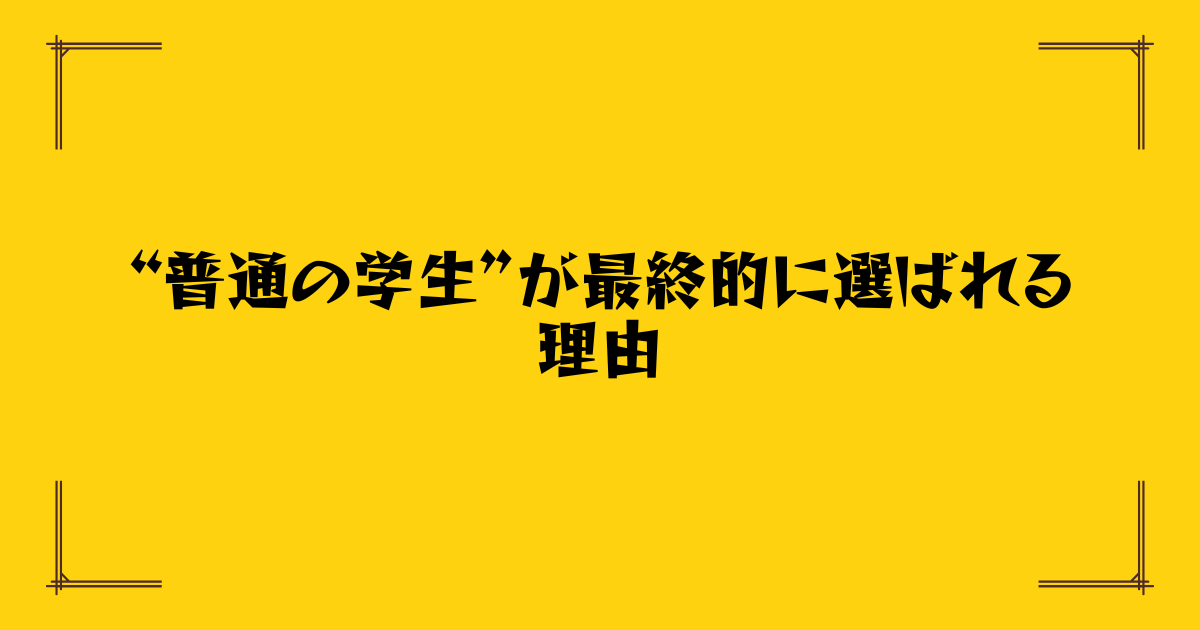求められているのは「尖ったスキル」ではなく「共に働ける安心感」
特別な武器がなくても、企業は採用する
就活を通じて、よくある誤解がある。「目立つスキルがなければ、どこにも評価されない」という思い込みだ。しかし実際、多くの企業が求めているのは“専門家”ではなく、“これから一緒に育っていける人”だ。新卒採用においては、即戦力ではなく“伸びしろ”が重要視されている。
たとえば、「特に実績もないし、目立った成果も出していない」という学生でも、面接の場で「自分が考えていることを、言葉にして誠実に伝えられる」だけで十分な評価を受ける。企業にとって重要なのは、入社後に育てやすい人かどうか。極端に言えば、「今すごいか」よりも、「一緒に働きやすいか」の方が重視される。
「強み」ではなく「関わりやすさ」が選考を左右する
たとえば、グループディスカッションや集団面接で、話し方が目立たない学生が最終的に評価されるケースがある。それは、その人が「他人の話をちゃんと聞ける」「場の空気を見ながら話せる」「押しつけがましくない」という理由で、“一緒に仕事がしやすい”と感じられたからだ。
このように、「強みがないから受からない」という構図は、実は就活の本質とはずれている。選考では、能力だけでなく、“人としての印象”が最終判断を左右する。だからこそ、派手なエピソードを用意するより、自分が自然にできる振る舞いに目を向けた方が、結果的に採用につながりやすい。
「ないもの探し」ではなく、「あるものを深掘りする」
武器は“探す”より“育てる”という発想へ
見つからないのではなく、見ようとしていないだけかもしれない
「自分にはアピールできるものが何もない」と思っている就活生の多くは、そもそも“自分の行動や習慣を見直す視点”を持っていないことが多い。強みというのは、「成果」や「賞」だけに宿るものではない。日々の取り組み方、癖、考え方の中にこそ、その人らしさがにじむ。
たとえば、「友達との会話で、いつも聞き役に回るタイプ」という人は、それを「自分には主張がない」と感じるかもしれない。しかしそれは裏を返せば、「相手の話を遮らずに聞ける」「場の空気を読みながら動ける」という能力だ。就活で必要なのは、“自分の特性を価値に言い換える”こと。つまり、武器は探すものではなく、“育てて言語化するもの”なのだ。
足りないところではなく、「続けてきたこと」に意味がある
自己PRを考えるとき、多くの人が「インパクトのある成果」を探す。けれど、本当に評価されるのは「続けてきたこと」や「踏みとどまった経験」だったりする。長くバイトを続けた、部活で控えだったけどやめなかった、派手な成果はないけど欠かさず報告していた――それらはすべて、“その人の姿勢”を表す大事な材料だ。
武器とは、目立つ実績や派手なスキルだけではない。「これだけは自分が意識してきた」という些細なことを、ちゃんと語れる力のほうが、むしろ面接官の記憶に残る。だからこそ、今の自分の中にある“小さな一貫性”を大事にしてほしい。
自信がない人ほど、“自分の言葉”で語る力が身につく
本当に伝わるのは、他人の評価ではなく“自分の実感”
「それでも、自分はこうだった」と言える強さ
就活で評価されるのは、確かに“説得力のある話”かもしれない。けれど、もっと大事なのは、「その言葉に実感があるかどうか」だ。たとえば、「私の強みは継続力です」と言うだけでは足りない。「なぜそう思ったのか」「どんな場面でそう実感したのか」がなければ、面接官の心には残らない。
自信がない人ほど、自分の過去を深く見つめ直す必要がある。だからこそ、その人の話には“温度”が宿る。「どうしても諦めたくなかった」「途中で逃げたかったけど続けた」「評価されなかったけど、自分なりにやった」――こうした語りは、たとえ整理されていなくても、聞き手にリアルに届く。
本音で語ることは、弱さではなく信頼の始まり
多くの学生が、就活では“よく見せること”を優先してしまう。しかし、それが返って逆効果になることもある。話を盛ったり、自信のあるふりをしたりすると、面接官は「本当のところが見えない」と感じてしまう。
一方で、「自分には誇れる実績はないけど、こういうところを大事にしてきた」と語る人には、逆に信頼感が生まれる。本音で語れる人こそ、信頼される。だから、自分にないものを嘆くよりも、「自分の中にあったもの」に目を向けて、それを言葉にしてほしい。
まとめ:武器がなくても、戦える就活はある
“武器がない”という感覚は、就活において非常に多くの学生が抱えるものだ。特に、目立った実績がない、自己PRで語れるエピソードがない、周囲と比べて自分だけが劣っているように感じる――そんな不安や焦りの中で、就活が怖くなってしまう人も少なくない。
けれど、「何もないからこそ、言えること」がある。自分には特別な経験がなかった。でも、毎日をどうにか頑張ってきた。それを認めてあげることが、“就活の突破口”になる。
就活における“強み”とは、過去の実績よりも、これからの可能性だ。そして可能性とは、自分の言葉で語れること、自分の考えで行動できることから生まれる。つまり、武器を“持っている人”より、“育てようとしている人”の方が、未来の企業に選ばれるのだ。
焦る必要はない。目立たなくても、戦えるやり方はある。大切なのは、あなた自身があなたの言葉で語れること。その力さえあれば、きっと“評価される人”になれる。
就活で「言葉が出てこない」原因を見つめ直す
緊張の裏にある「自分の話に自信がない」という本音
うまく話せないのは「準備不足」ではない
面接でうまく話せない理由を「準備不足だ」と自分を責めてしまう人は多い。確かに対策が不十分ということもあるかもしれないが、それ以上に大きな要因は、「自分の話に確信が持てていない」ことだ。つまり、「これを話しても評価されないんじゃないか」という疑念がある限り、自信を持って言葉を発することはできない。
自分のエピソードに対して「こんなの誰でもやっている」「これくらい話しても弱いかも」と感じていると、話す時に自然と声が小さくなり、言葉が曖昧になる。これは面接官にとっては「結局何を伝えたいのか分からない」という印象につながる。そして悪循環が生まれる。「うまく話せなかった → 落ちた → また自信を失う」というスパイラルだ。
「正解を言おうとする」ことが自分を縛ってしまう
就活において「面接官が求めている“正しい答え”を言おう」と考えてしまうのは、よくある罠だ。だが、実際の面接官が求めているのは「この学生はどういう人か」「どんな価値観を持っているか」であり、模範解答ではない。にもかかわらず、「正しい言い方」や「うまく話すこと」に意識が向きすぎると、本来の自分の考えや感情が隠れてしまい、むしろ伝わらなくなる。
“正解を言わなきゃ”と思う時、人は無難な言葉を並べたくなる。しかしそれが逆効果になることもある。たとえば、「私はチームでの協調性を大切にしています」と言っても、それが自分の経験に根ざした言葉でなければ、面接官には刺さらない。むしろ「一度チームでうまくいかなくて悩んだ経験があるんですが…」という素直な切り出しの方が、本音が伝わりやすいのだ。
面接が怖い人に必要なのは、「慣れ」より「納得感」
「しゃべる練習」ではなく「考えを言葉にする訓練」
面接練習だけしても、本番で詰まる理由
よく「面接練習を繰り返せば話せるようになる」と言われるが、練習だけでは限界がある。なぜなら、練習ではスムーズに言えても、本番になると一気に頭が真っ白になるのは、「話の意味や背景を自分で理解できていない」からだ。つまり、話の“骨組み”ではなく、“実感”がともなっていないと、本番では支えきれない。
たとえば、ESに書いた内容をそのまま暗記して臨んでも、「なぜそれをやったの?」「どうしてそれが自分の強みだと思ったの?」と深掘りされた瞬間に詰まってしまう。これは、自分の中でエピソードが“納得できる形”になっていないからである。練習より先に必要なのは、「自分がその経験から何を得たか」「どうしてそれを話したいのか」を自分自身に説明できることだ。
話すのが苦手な人は「言葉にならない思考」を抱えている
「話せない=伝える力がない」と思いがちだが、実は「考えているけど、うまく言語化できない」というケースの方が多い。つまり、頭の中ではいろんな感情や思考があるにもかかわらず、それを一つの筋道にして言葉にする“翻訳作業”が苦手なだけなのだ。
このタイプの人は、自分の感情や価値観をじっくり言葉にしていく過程が必要だ。たとえば、「なぜそのバイトを続けたのか」を問い直した時、「特別な理由はなかったけど、任されるのが嬉しかった」と気づくことがある。この“嬉しかった”という感情こそが、自分の軸をつかむヒントになる。思考を言葉にできないのは能力不足ではなく、“見つけるプロセス”を踏んでいないだけのことも多い。
伝えることに自信が持てるようになるプロセス
表現力より「掘り下げ力」が結果を変える
質問に答えられる人ではなく、「考えている人」が強い
就活では「質問にしっかり答える」ことが当然とされているが、それ以上に重要なのは「その場で考えようとする姿勢」だ。完璧な答えを出せなくても、自分の言葉で真剣に考えようとする態度があれば、それは十分に評価される。むしろ、想定通りにスラスラ話す人よりも、「少し間を取りながらも、丁寧に考えて話す人」の方が、面接官には信頼感が残る。
これは、企業が「正解を知っている人」ではなく、「現場で考えられる人」を求めているからでもある。面接で焦って言葉が出てこないとき、自分に問うべきは「なんで私はそれをやろうと思ったんだろう?」という素朴な問いだ。そこに答えようとする姿勢があれば、それは評価される。
自信は「語れる経験」ではなく「納得できる実感」から生まれる
最終的に、面接でうまく話せるようになるために必要なのは、「自分の経験に自信を持つこと」ではない。そうではなく、「自分はこれを語る意味があると思える」ことだ。それがあるかどうかで、話すときの説得力や表情、声の強さまでが変わってくる。
たとえば、「高校時代に部活でキャプテンだった」というエピソードがあったとしても、それを「仕方なくやった」「何もできなかった」と思っていたら語れない。しかし、「自分なりにメンバーの話を聞く姿勢を貫いた」「思ったような結果にはならなかったけど、最後までやりきった」と納得していれば、言葉は自然と出てくる。
自信を持つとは、自分を盛ることではない。「こういうことが自分にとって大切だったんだ」と腹落ちできるまで、自分の経験と向き合うこと。その積み重ねが、「話せる人」になる最短ルートである。
「自分の言葉」で話すために必要な準備と習慣
本当の意味での「自己分析」ができているか
自分の“好き嫌い”を説明できるようにする
多くの就活生が「自己分析はした」と言うが、それは就活用のテンプレートに沿って、長所・短所・価値観を並べただけということがほとんどだ。本当に自分の言葉で語れる自己分析とは、「なぜそう思ったのか」「何を大事にしているのか」を、他人にも説明できるレベルまで掘り下げられている状態を指す。
たとえば、「人と関わるのが好き」という言葉も、そのままでは誰にでも当てはまる。だが、「どういう関わり方をしたいのか」「何をしているときに心地よいと感じるのか」を言語化できてこそ、その言葉に自分らしさが宿る。過去の行動パターンや、人間関係の中で感じた違和感や納得感を言葉にできるかどうかが、自己分析の質を左右する。
そして、何より大切なのは、自分の“好き嫌い”を説明できることだ。「こういう働き方は自分に合わないと思う」「こういう環境だと力を発揮できる気がする」といった感覚は、誰にでもある。それをきちんと説明できるようになると、自分の価値観に軸が生まれ、面接でも自然体で話せるようになる。
過去の経験に“タイトル”をつけ直してみる
自分の経験に意味を見出すために有効なのが、「タイトルをつける」という視点だ。たとえば、文化祭で模擬店の責任者をした経験があるとする。ただ「模擬店をやりました」では表面的すぎるが、「自分より他人を優先する姿勢を試された経験」や「苦手だったリーダーシップに初めて挑戦した経験」といったようにタイトルをつけることで、その出来事の意味が立体的になる。
こうしたタイトルをつけることで、単なるエピソードが「語るべき経験」に変わる。それは、面接での質問に対しても自分の言葉で答える助けになる。話す内容を“暗記”する必要がなくなり、“納得”に基づいて説明できるからだ。自分の経験を自分なりに意味づけできたとき、初めて言葉が芯を持ち始める。
話す力より「語れる経験」を増やす工夫
「経験不足」を言い訳にしない考え方
小さなことでも「自分で選んだ」経験が力になる
「語れる経験がない」と感じる学生の多くは、経験そのものが少ないのではなく、「他人に語る価値がない」と勝手に判断している場合が多い。だが、どんなに小さな出来事であっても、「自分で選び、自分で考えて動いた経験」であれば、それは語る価値がある。
たとえば、「コンビニのバイトでミスが多く、辞めたいと思ったことがある。でも最後まで続けて、結果的に半年後には新人教育も任された」という話があったとする。これは一見よくある話だが、「なぜ辞めずに続けたのか」「どう考えて気持ちを立て直したのか」「その時、自分の中に生まれた価値観は何か」といった点を掘り下げることで、他の学生とは異なる“自分の言葉”になる。
重要なのは、“語ることができる経験”ではなく、“語る準備ができている経験”を自分の中に増やすことだ。そのためには、「この選択は自分の意思でやった」と言える行動を、どれだけしてきたかが問われる。たとえ規模が小さくても、自分の納得が込められていれば、それは自分だけのエピソードになる。
迷いながらも決めたプロセスが、武器になる
就活で評価されるのは、「迷いのなかった決断」ではない。むしろ、「迷った末に選んだプロセス」を語れる人の方が説得力がある。企業も、入社後に悩んだり迷ったりすることを前提としているからこそ、過去にそうした局面をどう乗り越えたかを重視する。
「アルバイトを掛け持ちすべきか迷った」「部活と学業を両立するか悩んだ」「自分に向いていないと感じたけどやりきった」――こうしたエピソードを、感情を含めて語れるようにしておくと、「この人は自分の人生に対して真剣に向き合ってきたんだな」と伝わる。
面接でスラスラと完璧に話すよりも、少し言い淀みながらも、等身大で語る方が信頼を得られる。迷い、考え、選んだというプロセスは、それ自体が“話せる強み”になるのだ。
面接で話すときの「構造」と「視点」の整え方
「どう話すか」ではなく「何を伝えたいか」
PREP法では不十分な理由
よく就活では「PREP法(Point→Reason→Example→Point)」で話すと良いと言われる。確かに論理的には整理しやすいが、実際の面接ではこの型だけでは伝わらないことも多い。なぜなら、PREPは“話し方の型”であって、“内容の掘り下げ”には不向きだからだ。
たとえば、「協調性があります。なぜなら、アルバイトで…」といったようにPREPでまとめた話は、聞こえは良いが本音が見えにくい。むしろ、「なぜその協調性を大事にするようになったのか」「それがなかったときに何が起きたのか」まで語れると、ぐっと深みが出る。
型を覚える前に、「自分は何を伝えたいのか」をしっかり定めることが優先だ。自分の価値観や行動原理を言葉にできていれば、話し方は多少乱れていても、面接官には十分伝わる。
経験を「他人目線」で見直す癖をつける
自分の経験を語るときにありがちなのが、「自分語り」で終わってしまうことだ。つまり、「自分はこうだった」「こういう風に頑張った」という内向きな話ばかりになると、聞いている側は共感できなくなる。
面接で印象を残すには、「自分の経験が他人にどう影響したか」「それを他者はどう感じたか」といった視点を持つことが大切だ。たとえば、「バイトでミスを繰り返していたが、先輩に毎日挨拶するようにしたら、自然と声をかけてもらえるようになった」という話には、他者との関係性が含まれている。こうした視点を持つことで、言葉に厚みが生まれ、自分の話が“独りよがり”にならなくなる。
面接当日に“自分の言葉”で話すための実践テクニック
緊張しても言葉を詰まらせないための準備法
「すべてを完璧に覚えようとしない」ことが本番力につながる
面接の場で緊張してしまうのは当然だ。多くの就活生が不安に感じるのは、「うまく話せなかったらどうしよう」「言いたいことを忘れたら評価されないのでは」という恐怖。しかし、この“完璧主義”こそが、自分の言葉を詰まらせてしまう最大の原因になる。
伝えたい内容を一語一句覚えてしまうと、言葉が一つでも抜けたときに思考が止まってしまう。そうではなく、「この質問では、これだけは伝えたい」という核のメッセージを決めておき、それさえ外さなければOKというスタンスで臨むことが大切だ。
たとえば、「困難を乗り越えた経験」の質問に対して、自分が話したい本筋が“逃げずに自分で考えて行動した経験”であれば、エピソードの順序や細かい数字がずれても問題はない。大事なのは、「どんな価値観を持ち、何を考えて行動したか」が面接官に届くことだ。その本質さえブレなければ、言葉に詰まっても、面接での印象は大きく変わらない。
「結論→背景→自分の思考」の順で自然に話す練習をする
話し方の型を意識しすぎると不自然になりがちだが、かといって完全に行き当たりばったりで話すと、伝わりにくくなる。そこで役立つのが、「結論→背景→自分の思考」の順で話す練習だ。
例として、「サークルでの取り組み」について話す場合はこうなる。
【結論】:私は“人が安心して関われる場づくり”を重視してきました。
【背景】:新入生が途中でやめてしまうことが多く、参加へのハードルが高いと感じたからです。
【思考】:そこで、雑談会や1対1の交流を増やす工夫をし、1年後には継続率が上がりました。
このように、話したいポイントを冒頭で明示し、なぜそう思ったか、どう考えて行動したかを伝えることで、聴き手に負担をかけず、自分の言葉で話せる感覚が身につく。書くと話すは全く別物なので、録音しながら一人で話す練習や、友人との模擬面接で“伝わる構成”を体感しておくことが有効だ。
緊張に飲まれず、いつもの自分で話すには
面接官を「評価者」としてではなく「対話相手」として見る
相手の目を見て話せないときの切り替え方
緊張しすぎて、面接官の顔が見られない、自信がなくて下を向いてしまう。そんな悩みを抱える学生は少なくない。だが、面接官も人間であり、目の前の学生が一生懸命話そうとしている姿勢はしっかり見ている。
目を見て話すのが難しいなら、まずは「相手の首元」や「ネクタイの結び目」に目線を置いてみるだけでも違う。これだけでも視線が合っているように見えるため、十分に印象は悪くない。話しながら徐々に相手の表情を拾えるようになると、対話のリズムが自然に生まれる。
「自分を評価しに来ている人」として相手を見ていると緊張が強くなるが、「この会社の価値観と自分が合っているかを確かめ合う人」と考えれば、対等な立場で会話ができるようになる。面接官との距離感を変えるだけで、話す姿勢は大きく変わっていく。
失敗しても「リカバリーできる」というマインドが余裕を生む
面接で言葉が詰まった、話が脱線した、途中で何を言っているかわからなくなった――それでもリカバリーは可能だ。実際、多くの面接官は「うまく話せなかったこと」自体よりも、「そこからどう立て直すか」に注目している。
たとえば、「すみません、少し話がそれてしまいましたが…」と自分で切り替えて、最初に伝えたかったことに戻れば問題ない。むしろ、自分の言葉で切り返すその一言が、誠実さや冷静さをアピールできるポイントになる。
失敗を恐れて黙ってしまうことが最も避けるべき事態だ。「言い直してもいい」「整理し直してもいい」という許容のマインドを持っていると、表情や話し方にも余裕が生まれる。これは一朝一夕には身につかないが、模擬面接や録音練習を重ねることで、確実に慣れていくものだ。
自分の言葉で話す就活は、誰にでも可能なスタイル
話し上手でなくても、“語れる人”は評価される
求められるのは「正解」ではなく「納得のいく説明」
就活において、「何を言うか」「どんな答えが正しいか」にばかり意識が向いていると、自分らしさを見失いやすい。だが、企業が見ているのは「その人の言葉に納得感があるか」「自分で考えて選んだ行動なのか」だ。
言葉の巧さやスピーチ力ではなく、「自分の意思を自分で持っているかどうか」が面接では評価される。多少話が回りくどくても、自分の人生をどうとらえてきたかを率直に語れる人は、信頼される。就活とは、完成された人物になることではなく、「伸びる余白のある人材」であることを見せる場なのだ。
「うまく話せない人」こそ、“本音”で差がつく
表面的にうまく話せる人は多いが、「なぜそう思ったのか」を本気で深掘りできる人は少ない。うまく話そうとしないで、「なぜそうしたのか」「なぜその仕事に惹かれるのか」を自分の言葉で丁寧に語る姿勢が、面接では強さになる。
たとえば、「営業職は得意ではないけれど、挑戦したい理由がある」「リーダー経験はないけれど、人を支える側でずっと努力してきた」というような本音の話には、企業も耳を傾ける。整った話より、納得できる話の方が刺さるのが“今の就活”である。
まとめ
就活で「自分の言葉で話せない」という悩みを抱える学生は多いが、話し方の技術よりも、自分が語るべきことを本当に理解できているかどうかの方が圧倒的に重要だ。日常の小さな選択、迷い、努力を丁寧に振り返り、そこにどんな価値観があったのかを自分なりに説明できれば、それは他の誰とも被らない“あなただけの話”になる。
完璧な話し方やテンプレートに頼る必要はない。むしろ、自分なりの言葉、自分なりの意味づけがあるかどうかで、面接の説得力は大きく変わる。
緊張してもうまく話せなくてもいい。伝えたいことの芯さえブレていなければ、面接官にはあなたの誠実さが伝わる。「自分の言葉で話す就活」は、誰にでもできる。必要なのは、技術ではなく“自分と向き合う覚悟”と“伝える意思”だけだ。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます