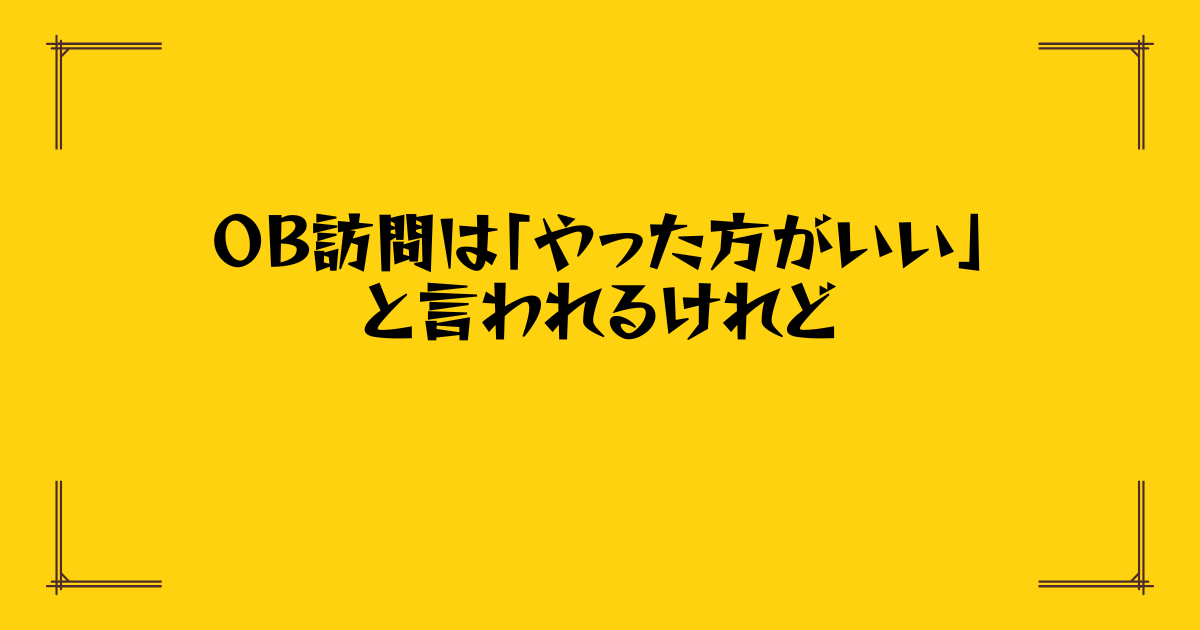「なんとなくやっておいた方がいい」という空気
就活が本格化すると、大学のキャリアセンターや先輩、就活系SNSなどで、「OB訪問はやっておいた方がいいよ」とアドバイスされることが増える。たしかに、企業や業界のリアルな情報を得る手段としては有効だし、実際にOB訪問を通じて志望度が上がったという学生も少なくない。
しかし一方で、「就活って忙しいし、そんなにOB訪問に時間を割く意味ある?」「選考には関係しないって聞くけど?」と感じる人も多い。特に内向的なタイプや人見知りの学生にとって、わざわざアポを取って知らない社会人に会うことは心理的ハードルが高く、億劫にすら感じられる。
では、OB訪問には本当に意味があるのか? その答えは、「どう活用するか」によって大きく変わる。つまり、無意味にもなりうるし、選考突破に直結することもあるというのが実情だ。
情報収集が目的だとしても“質”が分かれる
OB訪問の表向きの目的は、「業界や企業のリアルな実情を知ること」。これは間違っていない。ただし、ネットにあふれる情報との差別化ができていない訪問は、表面的なやりとりで終わり、結果として意味のない時間になってしまう。
たとえば「御社の強みはなんですか?」「働きがいを感じた瞬間は?」といったテンプレ質問だけで終わるOB訪問は、たとえ相手が丁寧に答えてくれたとしても、内実のある発見にはなりにくい。結局、帰宅後に「なんかいい人だったけど、よくわからなかったな…」という感想しか残らない。
一方で、企業の制度やキャリアパス、部門間の文化差など、OB訪問でしか得られない話を引き出せたときは、業界研究や志望動機作成の深みに直結する。つまり、目的が同じ「情報収集」であっても、その中身の濃さで“意味のあるOB訪問”か“無意味な訪問”かが分かれるのだ。
採用担当者にとってのOB訪問とは何か
企業が公式に「選考には関係ない」と言う理由
多くの企業が、OB訪問について「採用選考には一切関係ありません」と明言している。これは建前ではなく、実際にOB訪問の有無やその内容で書類審査や面接の合否を変えることは基本的にしていない。なぜなら、全員が平等にOB訪問の機会を持てるわけではないからだ。
大学によってはOBの数やつながりに偏りがあり、地方の学生や情報感度の低い学生には不利になる。このような不公平を避けるために、「OB訪問の有無は選考に影響しない」というのは合理的な運用方針といえる。
しかし、これは「採用に影響しない」=「全く意味がない」ということではない。むしろ、OB訪問で得た情報を元に志望動機や逆質問が深まり、結果として選考通過率が上がる、という間接的なプラス効果が発生しているケースは非常に多い。
OB・OG自身が人事に影響力を持つケースもある
一部の企業、特にベンチャー企業や社員数の少ない中小企業では、OB自身が人事や選考の判断に影響を持っていることもある。たとえば、「この学生、感じよかったから人事に推薦しておいたよ」といった“裏リファラル”のような動きが、水面下で起こることがある。
また、大手企業であっても、「OBからの高評価が内定に影響した」と語る内定者も少なからず存在する。もちろん公式ルートで評価されるわけではないが、面接前に人事が「この学生、〇〇部門の△△さんにOB訪問したらしいね。どうだった?」と確認することは珍しくない。
つまり、OB訪問そのものが選考ではないが、選考との間に非公式な橋がかかっているケースがある。この可能性を理解せずに、ただ“雑談して帰るだけ”のOB訪問で終わらせてしまうのは、チャンスをみすみす逃しているともいえる。
学生が勘違いしがちな“やる意味”の本質
「いい情報が聞けること」が価値ではない
多くの学生は、OB訪問の成功=「良い情報が得られること」だと考えている。しかし、それはあくまで表面的な話に過ぎない。真の価値は、自分の中でその情報をどう解釈し、行動に結びつけるかにある。
たとえば、「◯◯の部門は自由度が高い」という話を聞いたとしても、それを単に「良さそう」で終わらせるのではなく、「自分は裁量がある環境の方が力を発揮できるから志望度が高まった」と自己理解と結びつけることで、ESや面接での説得力が生まれる。
また、「△△な人が多い」といった価値観系の話も、ただの“企業のカラー”として消化するのではなく、「自分がどう感じたか」「自分に合うかどうか」を見極める材料にできるかどうかが重要になる。
就活を“面接対策”で終わらせないために
OB訪問のやる意味を考えるとき、「面接に出る質問への答えを準備する」だけにとどまっていると、本質を見誤る。面接はあくまでアウトプットの場であり、その土台となるインプットの質がすべてを決める。
このインプットを「説明会資料」や「企業HP」だけに頼っていると、誰でも言える表面的な志望動機しか作れない。一方で、OB訪問で得た具体的なエピソードや社員の価値観、自分との相性判断などがあれば、オリジナリティのある志望理由や逆質問につながる。
つまり、OB訪問とは「企業に評価されるためにするもの」ではなく、「評価される自分をつくるためのインプット」に過ぎない。そこに意味を見出せるかどうかが、OB訪問の価値を左右する。
OB訪問が「選考に影響する」って本当?
公式には影響なし、でも実際は?
多くの企業は「OB訪問の内容は選考に影響しません」と明言している。これは建前として正しいし、応募者全員が平等なチャンスを持てるようにするためにも、運用上そのように扱われるのが基本だ。
だが一方で、「あの学生、実は◯◯さん(OB)から評価高かったらしいよ」「あの人、OB訪問の後からやけにスムーズに進んでいた」など、就活生の間で流れる“謎の有利ルート”の噂も後を絶たない。これらはすべて都市伝説なのか、それとも実際に存在するのか。
結論から言えば、“影響する企業”と“しない企業”の両方がある。そして、学生がその違いを理解せずにOB訪問を行っても、効果は最大化されない。つまり、「どうせ関係ない」と思って行動しないのも、「やれば確実に有利」と過信するのも、どちらも危険だ。
OB訪問が影響する企業の特徴
ベンチャー・中小企業:人脈と印象が大きな武器になる
規模が小さく、組織の距離が近い企業では、OB訪問が明確に評価に影響することがある。なぜなら、そういった企業では「人柄重視」の採用が多く、面接だけでは測れない“空気感の相性”が重要視されるからだ。
また、ベンチャー系では、人事担当者と現場社員が密に連携していることが多く、OBからの推薦や印象がそのまま選考進捗に反映されるケースもある。「この学生、いい感じだったよ」といった非公式なコメントが、人事の印象に強く残り、他の応募者との差別化要因になるのだ。
たとえば、社員数30名の企業で、エンジニア志望の学生が現場エンジニアにOB訪問をしたとしよう。印象が良ければ、「この人と働きたい」という声が直接採用側に届く。つまり、公式に選考の一部ではないが、裏ルートとして機能している状態が発生している。
業界によって「見られる」度合いが異なる
業界によっても、OB訪問が“選考の材料”として扱われやすいかどうかには違いがある。
たとえば、コンサル業界や外資系企業では、OB訪問でのふるまいや会話の質がそのまま“地頭や論理性の判定材料”とされることがある。また、「OBからの評価が低いと面接官の印象も下がる」などの声も実際にある。とくにリファラル採用(社員紹介)文化が強い企業では、OBからの推薦が選考上の加点材料になりやすい。
一方で、メーカーや公的機関、インフラ系のように、OB訪問の有無があまり評価に結びつかない業界もある。こうした企業は、公平性を重視するため、OBが人事に口出ししない文化がある。情報収集目的での訪問には向いているが、“評価を受ける”という意味ではあまり戦略性が働かない。
OB訪問を“評価につなげる”ための条件
「誰に会うか」が重要すぎる理由
OB訪問の影響力は、「何を話したか」よりも「誰に会ったか」で決まることが多い。影響力のあるOBに会えば、あなたの印象が人事に伝わる可能性が高まり、逆に関係性の薄い若手社員に会っても、その場限りで終わることが多い。
では、影響力のあるOBとは誰なのか?以下のような特徴がある。
部署でリーダーやマネージャー的立場にある
採用プロジェクトに関わったことがある
明らかに人事と仲が良い
OB訪問の際に「人事に伝えておくよ」などの発言があった
このような人物に好印象を与えることができれば、結果的に人事の中で“顔の見える学生”として認知されやすくなる。逆に、形式的にアポを取って学生の話にただ相槌を打つだけの若手社員では、選考に結びつくような影響は期待しづらい。
「評価される学生」の共通点
OB訪問で好印象を残す学生には、以下のような特徴がある。
事前に相手のキャリアや部署を調べている
質問が“自分の軸”と結びついている
話を引き出すだけでなく、自分の考えも丁寧に話せる
礼儀や連絡マナーがしっかりしている
これは、「優等生になれ」ということではない。むしろ、形式だけ整えている学生は「どこにでもいる就活生」として埋もれてしまう。自分なりの視点を持ち、相手の話を自分の言葉で咀嚼できるか。これが見られている本質であり、そこが良い印象につながる。
実際にOB訪問で「この学生、頭いいな」「しっかりしてるな」と感じた場合、社員が自主的に人事に一言伝えるケースもある。これは学生の側からは見えないが、選考に効いている“影の推薦”ともいえる。
「有利になる」ために意識すべき3つのこと
意図的に“接触回数”を増やす
企業によっては、OB訪問を複数回することで印象に残りやすくなることがある。たとえば、イベント→座談会→OB訪問と段階的に接触した学生は、「熱意のある学生」として記憶に残る可能性が高い。
また、異なる部署のOBに会い、それぞれの視点を理解している学生は「業界理解が深い」「配属後のイメージも具体的」と評価されやすい。1人に絞らず、戦略的に複数人と会うことが“有利ルート”の布石になることもある。
会話の質より“印象管理”を徹底する
内容の深さも重要だが、それ以上に見られているのが「一緒に働きたいかどうか」という感覚的なポイント。これは面接でも同様だが、OB訪問ではより顕著に出る。
具体的には、以下のような要素が印象に強く作用する。
話すときの表情や相槌の打ち方
話の流れを理解する力(会話のキャッチボール)
意見の伝え方(否定しない、丁寧な言葉選び)
難しいことを言おうとするよりも、人としての柔らかさ、相手の話を受け取る姿勢のほうが重視される場面もある。これは面接以上に“人柄”が露出しやすい空間だからこそ意識すべき点といえる。
意味がないOB訪問とは何か?
なんとなくの訪問は、なんの価値も生まない
OB訪問に「やる意味があるかどうか」は、就活生側のスタンスによって決まる。表向きにはどのOBも「気軽に聞いてくれていいよ」「なんでも答えるよ」と言ってくれるが、実際には“やる気のない学生”はすぐに見抜かれる。つまり、意味がないOB訪問とは、何を聞きたいか自分で明確になっていない状態で行う訪問のことだ。
ありがちな失敗パターンとして、以下のような学生がいる。
OB訪問をした方がいいと聞いたから、とりあえずアポをとった
業界も企業もよく調べておらず、基本的な質問ばかりする
話を聞くだけで、自分の考えや価値観を一切示さない
会話を終えても「ありがとうございました」で終わるだけ
こうしたOB訪問は、どれだけ時間をかけても、学生にとっても企業にとっても何の収穫もない“空振りの面談”に終わることが多い。そして残念なことに、そういった印象は社員の中で記憶に残りやすく、マイナスの印象だけが蓄積されてしまう。
「話を聞くだけ」では逆効果になることもある
受け身すぎる学生は、好感を持たれにくい
「OB訪問だから聞き役に徹するべき」と考える学生も多いが、実際は受け身すぎる学生は評価されにくい。相手が一方的に話す時間が続くと、「この子、何を考えているのか分からないな」「質問してきても表面的だな」といった印象になるからだ。
本当に“意味あるOB訪問”をしている学生は、必ず会話のキャッチボールをしている。つまり、
質問を通して自分の考えを補足する
相手の答えに対して、感じたことや共感を伝える
自分の志向性と企業文化との接点を探る
といったやりとりを通じて、“自分の思考を伝える”時間をちゃんと持っている。話を聞くだけの学生は、単に情報収集だけして去っていく存在として、OBにとって印象に残りづらい。
「何を目的に来たか」が伝わらないと会話はズレる
意味のないOB訪問は、共通して“会話の軸がブレている”。たとえば、最初の5分で「今日は何を知りたくて来たの?」と聞かれたときに、明確な意図が言えない学生は、その後の話も抽象的になりがちだ。
「どんな仕事をしているか知りたいです」「働きやすさについて教えてください」など、あまりにも汎用的な質問ばかりだと、OBも答えに困る。逆に、「〇〇職に興味があるのですが、その実務内容と配属後の教育体制を知りたいです」といった具体性があると、話が深くなりやすく、学生のレベルも自然と高く見える。
意図がなく、準備もないOB訪問は逆効果
「知りたいことがないのに会う」は最悪の一手
とりあえず誰かに会わなきゃ、という焦りから、目的もなくOB訪問をする人もいるが、これはかなりリスクが高い。
そもそも学生が期待しているような“業界の裏話”や“選考に効く情報”は、OB訪問だからといって自然に出てくるわけではない。むしろ、相手から「この人には何をどこまで話していいのか」と探られることが多く、雑な質問をすると、むしろ警戒されてしまうことすらある。
また、「最近の若手ってどうなんですか?」「ぶっちゃけ、この会社ってブラックじゃないですか?」といった無神経な質問は、話しやすさではなく“距離感のなさ”としてマイナス印象に転じる可能性が高い。
「とにかく会う数を増やす」のは非効率
OB訪問を“量で稼ごうとする”戦略も、効果が薄い。特に、興味のない企業や職種に対して惰性的にアポをとり続けても、自分の考えは深まらないし、OB側にとっても熱意のない学生が増えていくストレスになりかねない。
逆に、しっかりと準備をして一人のOBから学びを深めた方が、就活の軸形成にもつながる。数をこなせば印象に残るというよりも、1回1回を“濃くする”方が圧倒的に選考への好影響がある。
たとえば、たった1回の訪問で相手に「お、この子は優秀だな」と思わせる学生は、メールの文面、質問内容、会話の流れ、終了後のフォローまで一貫している。それが1人目でできれば、無理に2人目3人目に会う必要はない。
学生側の誤解が「意味のない訪問」を生む
「何か裏技が聞けるかも」と思っていると失敗する
多くの学生がOB訪問に期待しているのが、“裏情報”だ。しかし、採用に関わらない現場社員が、選考ルートや評価基準などの情報を持っていることはほとんどないし、そもそも学生に漏らすような人は少ない。
したがって、「OB訪問すればESの通りやすい書き方が聞けるかも」「人事のウラ話が聞けるかも」といった期待で臨むと、話が浅く終わってしまう。OBもプロではない。面接官でもなければ、アドバイザーでもない。あくまで“実際に働いている人”としての経験談しか持っていないのだ。
本当に役立つのは、「その人がどういう考えでその仕事をしているか」「入社前と入社後のギャップ」「会社の価値観と自分との相性」といった視点。“情報”ではなく、“思考と価値観の接点”を得ようとする訪問が意味あるOB訪問となる。
「OBに好かれよう」と思いすぎるのも逆効果
選考に影響する可能性があるからといって、媚びすぎるとむしろ逆効果になることもある。「めちゃくちゃその企業を褒めていた」「自分の意見を一切言わず、全部相手に同調していた」という学生は、むしろ不気味に思われることもある。
社員も、ただヨイショしてくる学生よりも、「あ、自分で考えてるな」「ちゃんとこの企業を比較してるんだな」と思える人に信頼を置く。誠実なスタンスと、適度な主張と、素直な姿勢のバランスが取れている学生こそ、印象に残る存在になる。
選考につながるOB訪問に変えるための戦略
会う人の選び方が、情報の質を決める
OB訪問が選考に影響するかどうかは、「誰に会うか」でかなり変わる。仮に同じ企業に勤めていても、人事部と現場社員では持っている情報が異なるし、評価権限を持つ人かどうかで、伝わる影響力も違う。
以下のような観点で選ぶと、選考との接点が生まれやすい。
自分の志望職種・配属先に近い部署の社員
→ 実際の仕事との相性を確かめられる/リアルな配属後の話が聞ける
人事部や採用プロジェクトに関与している社員
→ 選考の流れ・見られているポイントについてのヒントが得やすい
大学のOB・OGで学生側の立場を理解してくれる人
→ 話しやすさ・深掘りしやすさが高まりやすい
加えて、すでにSNSやOBOG紹介制度などで紹介されている“紹介可能な社員”の中でも、「話を聞いた学生の評価が高かった人」は狙い目だ。複数人に話を聞いた先輩から「この人に会った方がいいよ」と紹介してもらえる場合、その人は学生対応が慣れていて好意的である可能性が高い。
質問の内容で印象は大きく変わる
「その人にしか答えられない質問」を用意する
誰にでも聞けるような一般的な質問は、印象に残りづらい。一方で、その人の経歴・担当職種・立場をもとにした質問をすれば、「ちゃんと調べてきたな」「他と違うな」という感覚を持ってもらえる。
例を挙げると、
「〇〇部署にいらっしゃると伺ったのですが、その中でも特に大変だと感じる業務はどのような部分ですか?」
「3年目ということですが、1年目と比べて、仕事への向き合い方に変化はありましたか?」
「〇〇大学からこの会社を選ばれた理由は、他にどんな選択肢と迷われた結果だったのでしょうか?」
など、相手の立場や背景に根ざした具体的な質問は、会話の深さにも直結する。
逆に、「御社の強みは何ですか?」「やりがいは何ですか?」といった汎用的な質問は、OBも数十回聞かれてうんざりしていることがある。“この学生はちゃんと自分を見て質問している”という感覚を与えることが重要だ。
OB訪問の印象を選考に繋げる行動とは
訪問後のフォローが、見えない評価を引き寄せる
OB訪問で好印象を残しても、終了後に音沙汰がないと、関係性はすぐに途切れる。一方、印象的なフォローメールを送ることで、「気になる学生」として社内で話題に上がる可能性も出てくる。
理想的なフォローは、以下の3要素を含むと良い。
感謝の言葉(話してもらった内容に対して具体的に)
印象に残ったエピソードや、自分の行動にどう活かすか
次のアクション(選考でお会いできるよう頑張ります、など)
特に、話した内容に対して「私も〇〇を軸に考えてみたいと思いました」「△△という視点がとても響きました」と書くと、相手にも“伝わっていたこと”が実感されて記憶に残る。
メールの文面一つで、社内チャットに「今日この学生からこんな丁寧なメールが来た」と共有されることも実際にある。地味に見えて、訪問後のフォローが選考に繋がるターニングポイントになることは少なくない。
発言だけでなく、非言語の印象も見られている
「姿勢・表情・目線」も選考の延長線上で判断される
就活生が想像する以上に、OB訪問では見た目や態度も見られている。面接ほど堅苦しくはないが、それでも社会人としての常識や雰囲気が見られている場であることは間違いない。
たとえば、
話すときに目を見て話せているか
相手の話をうなずきながら聞いているか
姿勢がだらしなくないか
時間に余裕をもって到着しているか
名刺やノートなど、最低限の準備をしているか
こうした小さな積み重ねが、「ちゃんとした学生だな」という信頼感につながる。これは特別な能力ではなく、意識と準備で誰にでも身につけられるポイントである。
まとめ:OB訪問を“選考の一部”として設計する視点を持つ
就活において、OB訪問は「やらなければならないもの」でもなければ、「絶対に評価に直結する」ものでもない。しかし、設計と実行次第で、選考に繋がる“強力な一手”にもなるし、ただの時間の浪費にもなる。
この違いは、OB訪問を就活の一環として「自分が主導する選考行動」として捉えられているかどうかにかかっている。
会う人を戦略的に選ぶ
目的と質問を明確に持つ
会話を通じて価値観の接点を見出す
丁寧なフォローを通じて信頼関係を築く
これらを意識すれば、OB訪問は単なる情報収集ではなく、「企業側に選ばれる場」にもなり得る。
就活においては、エントリーや面接のような“正式な選考”だけが評価ポイントではない。“選考外の接点”をいかに質の高いものにするかが、第一志望内定に繋がる差となる。その第一歩が、設計されたOB訪問だ。無意味な訪問を卒業し、自分の未来を形づくる一歩として活用してほしい。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます